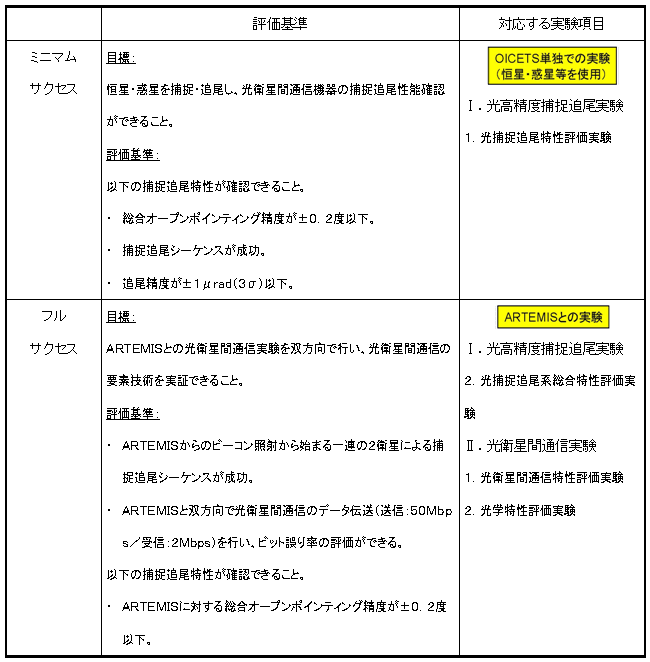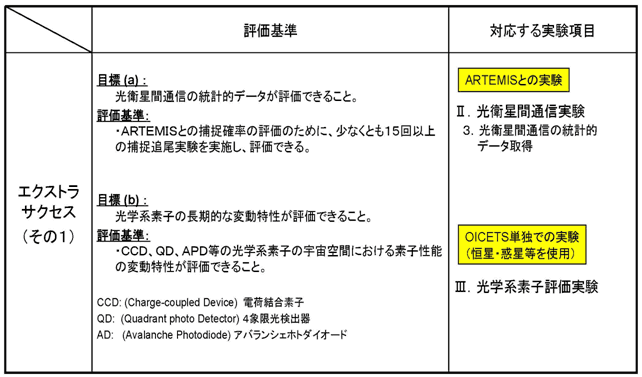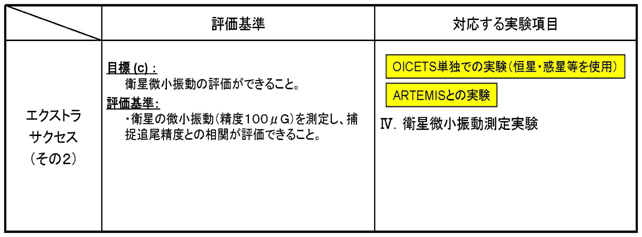別紙2
| 平成4年7月 | 平成5年度からの開発研究移行 |
| 平成5年8月 | 実験装置等の開発着手 |
| 平成6年7月 | 平成7年度からの開発移行 |
| 平成8年8月 | 打上げの延期(平成10年から平成12年へ) |
| 平成11年8月 | 打上げの延期(平成12年から平成13年へ) |
| 平成13年8月 | 当面打上げ見合わせ |
| 平成14年8月 | 開発計画の妥当性等の審議継続 |
| 平成15年7月 | 打上げ計画変更(平成17年打上げへ) |
| 平成16年12月 | 打上げロケットの決定 |
| 平成17年1月 | 進捗状況の確認 |
| 平成17年3月 | サクセスクライテリアの設定 |
将来の衛星間通信システムに有望な光通信技術について、欧州宇宙機関(ESA(イサ))との国際協力により、同機関の静止衛星ARTEMIS(アルテミス)との間で、捕捉追尾を中心とした要素技術の軌道上実験を行う光衛星間通信実験衛星を平成9年度頃にJ−![]() ロケットで打ち上げることを目標に開発研究に着手したい。
ロケットで打ち上げることを目標に開発研究に着手したい。
周回衛星搭載の光衛星間通信機器等に関する技術を開発し宇宙空間において実験・実証を行うため、平成9年度ころにJ−Iロケットにより打ち上げることを目標に、光衛星間通信実験用研究開発衛星の開発研究を行う。
周回衛星搭載の光衛星間通信の基礎的技術を宇宙で実験・実証するため、光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))をJ−1ロケットにより、平成9年度に打ち上げることを目標に実験装置等の開発に着手したい。
光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))については、引き続き開発研究が進められることになっているので、本件OICETS(オイセッツ)を用いた通信実験に関する地上実験装置等について、その整備を行うことは妥当である。
衛星間通信システムに有効な光通信技術について、捕捉追尾を中心とした要素技術の軌道上実験を欧州宇宙機関(ESA(イサ))の静止技術衛星(ARTEMIS(アルテミス))との間で行うため、平成10年度にJ−![]() ロケットにより高度約500キロメートルの略円軌道に打ち上げることを目標に開発に着手したい。
ロケットにより高度約500キロメートルの略円軌道に打ち上げることを目標に開発に着手したい。
(注)(参考)
光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))の開発については、郵政省からも要望が提出された。
光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))の打上げ年度の変更
光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))については、J−![]() ロケットにより、平成10年度に打ち上げることを目標に開発を行ってきたが、実験相手となる欧州宇宙機関(ESA(イサ))の先端型データ中継技術衛星(ARTEMIS(アルテミス))の打上げ時期延期を受け、打上げ年度を平成12年度に変更して、引き続き開発を進めたい。
ロケットにより、平成10年度に打ち上げることを目標に開発を行ってきたが、実験相手となる欧州宇宙機関(ESA(イサ))の先端型データ中継技術衛星(ARTEMIS(アルテミス))の打上げ時期延期を受け、打上げ年度を平成12年度に変更して、引き続き開発を進めたい。
実験相手となるESA(イサ)のARTEMIS(アルテミス)の打上げが延期されることとなったことから、打上げ年度を平成12年度に変更して、引き続き開発を進めることは妥当である。
技術試験衛星![]() 型(ETS−
型(ETS−![]() )の軌道上の不具合を反映し、データ中継技術衛星(DRTS−W)に使用されているスラスタを打上げ前に交換する。このため、DRTS−W及び民生部品・コンポーネント実証衛星(MDS−1)の打上げは約6ヶ月遅延する。これに伴い、射点整備及び追跡管制の都合等を考慮し、後続の光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))の打上げを確実に行うため、J−1ロケット2号機によるOICETS(オイセッツ)の打上げ年度を平成12年度から平成13年度に変更したい。
)の軌道上の不具合を反映し、データ中継技術衛星(DRTS−W)に使用されているスラスタを打上げ前に交換する。このため、DRTS−W及び民生部品・コンポーネント実証衛星(MDS−1)の打上げは約6ヶ月遅延する。これに伴い、射点整備及び追跡管制の都合等を考慮し、後続の光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))の打上げを確実に行うため、J−1ロケット2号機によるOICETS(オイセッツ)の打上げ年度を平成12年度から平成13年度に変更したい。
光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))の打上げ年度の変更は、データ中継技術衛星(DRTS−W)及びミッション実証衛星1号(MDS−1)の打上げが平成12年冬期に延期されることによるものであり、射点設備整備期間や追跡管制の対応を考慮すると、本衛星の打上げ年度を平成12年度から平成13年度に変更することは妥当である。
(略)…光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))を打ち上げる計画であったが、共同で実験を行う欧州宇宙機関(ESA(イサ))の先端型データ中継技術衛星(ARTEMIS(アルテミス))の軌道上機能確認遅延等のため、当面、打上げを見合わせる…(略)
衛星間通信実験の相手衛星(ESA(イサ)のARTEMIS(アルテミス))の打上げトラブルに伴い、OICETS(オイセッツ)の打上げを見合わせていたが、その後の対策処置によりARTEMIS(アルテミス)が平成15年度には所定の軌道に達する見通しが得られたため、宇宙開発事業団は、平成17年度の打上げを目指して準備を再開することを求めている。そのため、今後、当初の意義、目的が失われていないかの確認、打上げロケットを含めた計画の妥当性等について審議を継続する。
衛星間通信実験の相手側衛星であるESA(イサ)の先端型データ中継技術衛星(以下、「ARTEMIS(アルテミス)」という)の打上げトラブルに伴い、光衛星間通信実験衛星(OICETS(オイセッツ))の打上げを見合わせていたが、その後の対策処置によりARTEMIS(アルテミス)が静止軌道に投入されたため、NASDA(ナスダ)は、平成17年度の打上げを目指して準備を再開することを提案している。
本プロジェクトの評価にあたっては、平成14年度の宇宙開発委員会での審議における指摘を踏まえ、当初の意義・目的が失われていないかの確認を行った。その結果、大容量衛星間通信の実現を目指して光衛星間通信技術の要素技術実証を行うことの意義は、観測衛星等のデータ伝送要求の増加の傾向にも鑑みて、現時点でも失われていないと判断される。通信機器としての大幅な小型・軽量化や低消費電力化などの技術向上は、将来の衛星システムにとっても有効であると考えられる。
リスク管理の観点から、通信実験相手であるARTEMIS(アルテミス)の状況を適時適切に確認し、必要に応じて本プロジェクトの計画に反映することが必要である。ARTEMIS(アルテミス)の光通信機器の設計寿命が平成18年7月となっていることから、衛星間通信実験衛星を実施して目標とする成果を得るために、平成17年度に打上げを行い、必要な実験期間を確保することは適切と考えられる。一方、成果を適切に確保するためには、実験期間の確保が重要であり、想定する打上げ時期を適切に維持できるよう、プロジェクト管理及びリスク管理が着実に実施される必要がある。
打上げロケットについては、打上げ目標年度に向けてNASDA(ナスダ)が適切なロケットを選定していくことから、選定が完了した時点で、計画・評価部会にて打上げ計画に関する確認を行う。
これらの結果、本プロジェクトについて、平成17年度の打上げを目指して準備を再開することは適切であると判断される。
打上げロケット及び打上げ計画については、打上げ後の実験計画を明確にした上で、その適切な実施時期を確保するとともに、打上げに向けて衛星とロケットのインタフェースに係る技術検討を確実に実施するために必要な期間を確保するために、遅滞無く確定する必要がある。
以上により、OICETS(オイセッツ)については、ドニエプルロケットにより17年度夏頃打ち上げることとし、必要な準備作業を行うこととしたい。
なお、今後、推進部会にて所要の確認を受けることとする。
上記のとおり、平成16年12月にOICETS(オイセッツ)の打上げロケットが決定したことから、平成17年夏期の打上げまでに、衛星とロケットのインタフェースに係る技術的な検討を確実に実施するために必要な期間を確保することができた。
また、ARTEMIS(アルテミス)の光通信機器の設計寿命が平成18年7月となっていることに対して、OICETS(オイセッツ)の打上げが計画通り平成17年夏期に行われれば、少なくとも9ヶ月間の軌道上での実験期間が確保されることとなり、所期の成果を適切に確保することができると期待される。
これらのことによって、将来の宇宙における伝送データ量の増大に対応するため、宇宙空間における光通信技術の開発を行うという本プロジェクトの目的が達成されると考えられることから、OICETS(オイセッツ)の打上げ計画は妥当と判断される。
なお、JAXA(ジャクサ)は、ARTEMIS(アルテミス)及びドニエプルロケットを含めたプロジェクト全体の管理及びリスク管理について、今後とも引き続き十分配慮すべきである。
以下に示すサクセスクライテリアについて了解された。