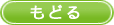動燃改革の基本的方向
平成9年8月1日
動燃改革検討委員会
- 認識の視点
- 我が国と原子力
- 動燃への負託
- 動燃の出発における潜在的困難
- 状況の変化と顕在化する困難
(1) 先駆者の消失
(2) 経済のグローバリゼーション
(3) 急速な技術進歩
- 問題の構造
- 動燃改革の枠組み
- 経営不在の詳細
(1) 安全確保と危機管理の不備
(2) 閉鎖性
(3) 事業の肥大化
- デザインの基本
- 新たな経営の確立
(1) 事業目標の設定
(2) 経営者の選定
(3) 組織の基本原理
- 新組織に想定される体制
(1) 開発領域の限定
(2) 安全確保と危機管理の体制
(3) 社会に開かれた体制
(4) 専門性の均衡と研究者の拡がり
第1章 改革の具体化の方針
- 経営の刷新
(1) 新法人の事業目標の明確化
(2) 新法人が行う経営の機能強化
(3) 職員の意識改革
(4) 明確な経営理念の確立と組織への浸透
(5) 新法人の運営に関する科学技術庁の役割
- 新法人の事業
(1) 動燃の現行事業の分類
(2) 新法人で実施すべき事業
(3) 事業の整理縮小
(4) 事業を進めるに当たっての配慮事項
- 安全確保の機能強化
(1) 運転管理体制の強化
(2) 安全確保の基盤整備
(3) 危機管理
- 社会に開かれた体制
(1) 広報・情報公開
(2) 開かれた研究開発体制
(3) 地域社会との共生
<付記>
○ 少数意見
○ 委員による個別調査結果
<付録>
○ 「動燃改革検討委員会」の開催について
○ 審議経過
<参考>(別冊)
○ コンサルタントによる調査結果
動燃改革検討委員会(以下「本委員会」という。)の目的は、動燃に与えられた使命を達成するための最適組織を提案することにある。その場合、動燃に与えられた使命そのものの改変は、本委員会の目的に含まれない。しかし、含まれはしないが、その使命を絶対不変の前提条件として検討を進めるわけではないことを注意しておく。それは、最適組織提案の過程で、現在の状況、すなわち技術的能力、経済的条件、社会的状況などに関して、我が国が現在置かれている状況は、避けることのできない強い条件であり、そのもとで、どんな組織をもってしても動燃に与えられた使命が達成できないことになれば、自ずと論理的帰結として、使命そのものの改変を提案せざるを得ない、という意味である。すなわち検討の論理的帰結としてはあり得るが、使命について論じることを課題とはしない、という立場をとる。
本委員会においては、今回の事故を通じて何が明らかにされたのかを認識し、その認識に従って動燃固有の問題を検討し、それを解決するものとしての組織を提案し、その提案を現実化するための問題群を指摘、分析する。
- 認識の視点
今回の問題は、平成7年12月8日の「もんじゅ」の事故及び平成9年3月11日のアスファルト固化処理施設の事故に関するものであるが、事故そのものの重大さに加え、事故の原因の中に看過し得ない深刻な問題が潜在していることが、事故の性質および事故処理において見られた諸問題を通じて明らかになって来たという重大な事実があり、この両者が問題の大きさを示している。
従って問題対処には二つの方向がある。第一は再び事故を起こさぬために緊急に対策を立てることである。そして第二は、事故の原因を本質的に除去することである。両者は本来同じ問題の二つの面であるが、現実の対策としては異なる内容を持つ。ここでは、第二の事故原因の除去を中心として論じるが、第一の問題についても具体的な改革案において言及する予定である。 - 我が国と原子力
動燃に与えられた使命は、原子力基本法第7条の規定に基づき、将来のエネルギー源として新しい原子力エネルギー技術を開発することにある。将来のエネルギーとは、資源枯渇、地球環境劣化等の、既に人類が遭遇し、今後数十年の間に悪化が更に進むことの予測がある中で、その悪化を阻止するための一つの可能な選択肢としてのエネルギーという意味である。
この立場で「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(原子力委員会)は書かれており、最初の1956年の長期計画の発表以後数年毎に改定されつつ、現在の1994年版に到るまで、この立場は一貫している。そこには、日本のように、高度な技術に支えられた高い生活水準を達成しながら、一方でそれを作動させるためのエネルギー資源を決定的に欠く、という特徴的な問題を持つ国が、その保有する高度な技術を用いて将来のエネルギーを開発することの必然性が主張されている。
この立場が、数十年に亘って認められてきたことは、我が国の国民がその方針を支持していることを意味するのであり、その開発の主役として、動燃は国民の負託を受けているのである。
この負託の意味をより深く認識しておくことが必要である。そのためにエネルギー問題が日本国内に止まるものでなく、世界全体の問題であることを考える必要がある。まず、世界においても、原子力は可能な選択肢として認知されていると言ってよいであろう。すなわち、世界におけるエネルギー確保は、人類生存のための必要事項であり、その一つの可能性を持つものとして原子力が位置付けられている。その結果、新しい原子力技術の開発とは、人類のエネルギー安全保障、というよりは我々の未来、およびこれから生まれて来る人類のための保険、という意味をもつことになる。ところが、どんな未来技術も成功率100%、すなわちリスクゼロということは論理的に言えないのであるから、保険の安全性を高めるには複数の未来技術の開発計画(オプション)を人類全体としては持つべきであり、それは既に検討されていると言ってよい。
その中で、何故日本が原子力を人類の複数のオプションの中から選んで担当するのかという点を明確にしておくことが必要である。我が国には、原子物理学をはじめ各界に優れた研究者が多数おり、高度経済成長を支えた高度な産業技術が蓄積され、プラント安全技術に十分な歴史を持ち、社会的セキュリティが高いなどの利点がある。そしてまた、我が国はエネルギー源をほとんど持たないが故に、人類のためと同時に日本の国としてもエネルギー安全保障を必要としているという事情がある。すなわち、原子力エネルギー開発に必要な条件の多くを満たすと共に、その意義が日本にとって極めて大きく、同時にそれが人類の目的とも調和するところに、人類のオプションとしての新しい原子力開発を我が国が分担することの必然性があるのである。 - 動燃への負託
このように、我が国にとってのエネルギー安全保障であると同時に、より広く世界の人類にとって、特に未来の人々にとっての保険の意味を持つが故に国際貢献にもなると考えることによって、原子力長期計画を理解することができる。そしてこのことが、動燃に対する負託の内容を決定するものなのである。
動燃に与えられた、国民の負託としての使命は、従って未来の原子力エネルギー技術の開発を国から受注したことに止まるものではない。前述のように、優れた研究者の存在は教育と基礎研究の歴史的帰結であり、戦後の産業技術の高度化も、工学技術系の教育と、産業における生産性向上の成果であり、そしてまた安全技術も数々の経験を経て確立した貴重な技術的資産なのである。そしてもちろん、社会的セキュリティも、全ての人々に配慮する我が国の社会的風習を背景として生み出された、またと得難い社会的資産である。そして、これらの存在があればこそ、世界のエネルギー開発のオプションとしての新しい原子力開発を選択することの必然性があったのであり、いわば現在に到る我が国の努力の積重ねの上に可能になるという意味で、日本人のアイデンティティを表現し得るものとして人々の大きな期待が込められた負託であったと言える。しかも、当時の風潮から当然推定されることであるが、期待の力点は世界に負けない自主技術の開発という点にあったのであり、それはエネルギー安全保障であることを超えて、日本のアイデンティティ確立の意味を持つものであった。
このように、明日の人類に視点を定めた国際貢献と日本のエネルギー安全保障とを目標としながら、日本が誇り得る人材、技術、経済等の資源を投入して新しい原子力技術を、自主技術として確立すること、それが日本が一流国になるための一つの道であることを信じながら、動燃は設立された。これが、いわば動燃の初心であると言ってよいであろう。
以下に述べるように、現在における動燃の問題は、動燃を取巻く状勢の変化が原因であって、動燃自身の変質によるのではない。従って初心に返ればよい、というような指摘は解決にならない。むしろ、初心からの離脱が必要なことなのであり、そのためには多くの要因についての検討が必要である。 - 動燃の出発における潜在的困難
国民の負託を受けて、1967年に設立された動燃は、新型の炉の開発と核燃料サイクルの実現に向けて出発する。そして我が国の産業の進展と歩調を合わせながら、基礎研究、開発そして実用化を同時に進行させるのである。これは多くの産業部門と同じく、欧米の諸研究、技術を学習し導入しつつ行われたものであって、研究や開発にめざましいものがあったが、その出発は外来のものに頼っていた。
しかし、動燃の目標は高速増殖炉、核燃料サイクルなどに関わる自主技術の開発である。1967年当時は、あらゆる産業において、我が国の要素技術、システム技術ともに世界一流とは言えなかった。それを少なくとも同等のものとすることによって、すべてを日本製で作ること、それが自主技術と呼ばれるものである。すなわち動燃は、基礎研究、開発、実用化という性格を異にする業務を、炉と燃料という、これも領域を異にする対象を相手に行なう。そして目標は、技術の国産化であったと言えるであろう。
このことは、動燃が設立当初から困難な問題を潜在させていたことを意味する。すなわち、第一に基礎研究、開発、実用化の段階を直列に配置した構造を持つが、この三者は思考様式も作業形態も違い、成果の評価基準も全く異なる。このような異種の空間を統合することについての困難さである。
第二は、炉建設と燃料製造という、背景学問、要素技術、手法などの全く異なる領域を並存した組織になっていることである。これらの領域間には、共通言語が必ずしもなく、ここには、その方法を改めて固有のものとして創出しなければならぬ困難さがある。
この結果、発展段階と領域との両面における異種性により、二次元的に異種の性格を持つ作業空間が動燃組織の中に混在することとなった。しかも目標は核燃料サイクルという閉じた製品を作る自主技術を開発することである。ここでは、これら異種空間を統合する方法論が本質的に必要なはずだった。
しかし、その必要性は顕在化せぬままに、各空間は独自の展開を遂げていく。そのとき統合の方法を持たぬままに、相互に矛盾が生じなかったのは、欧米に先駆的経験が存在したからである。要素技術の進展の方向を見失ったとき、本来ならばそれを再発見するのは技術間の均衡である。しかし、追従者の場合、その均衡に配慮するよりも先駆者の成功例を取り込む方が容易に確実な結果が得られる。それ自体を決して責める必要はない。しかし、そこでは全体を通して均衡を計画する視点はなく、従ってその方法は育たない。 - 状況の変化と顕在化する困難
動燃設置後現在に到る30年間に、動燃をとりまく情勢には多くの変化があった。その変化の中に、潜在する困難さを顕在させるものがあった。それを以下に述べよう。
(1) 先駆者の消失
最も劇的な変化は、軽水炉を超える原子力(核分裂)技術開発において、それまで先導的であった諸国が相次いで撤退したことである。その結果、我が国は学ぶべき先駆的成果のない分野で研究開発を行うこととなった。残った国はフランス、日本、ロシアなどだけである。また、この中で平和利用の原子力技術体系の完成を目指す唯一の非核兵器国としての日本の独自な立場もある。
このことは多面的な影響をもたらす。第一は前述した国の力を挙げての人類への国際貢献という意義が、ますます大きいものになったという点である。
しかし、一方、このような少数の国だけが競争状態にあるというのは技術開発という観点から見て正常とは言えない。これを是正する新しい提案が必要である。
第三が、先駆者もおらず、競争者も限られた国だけという状況下での研究開発は、我が国にとってほとんど初めて、特にこのような巨大プロジェクトでは経験がないという点で、これは動燃の出発時から見て、本質的な変化である。このとき前節に述べた潜在的問題が顕在化する。すなわち研究、開発、実用化という流れは、他に学ぶものがない以上、相互に学ぶ有機的な連携関係を構成するとともに、各部署に共通する安全確保、危機管理、社会性等を含めた自律的システムとして統合するべきである。しかし、事実はそうなっておらず、ここに非能率を生じるばかりでなく、各部が展開の方向を見失い、組織としての一体性を低下させることになる。(2) 経済のグローバリゼーション
東西の対立の解消と連動して、それ以前に始まった経済の地球化はさらに進行して行く。その結果、技術の地球化も起こる。これは経済、技術、企業において国境の存在が希薄になったことを意味している。このような中で、自主技術の意味が大幅な変更を迫られるのは当然である。
動燃の設立時、1967年においては、前述したように世界クラスの技術を持つことは我が国にとって夢であり、しかも保護貿易を容認する世界的雰囲気の中で、コストを気にせず自主技術を育て、その後に世界に打って出るのは一つの現実的な道であった。
しかし今、地球化の状況で、保護貿易などはあり得ず、メガコンペティションと言われる中で、あらゆる技術は競争力を持ってはじめて現実的存在となる状況が到来した。このことは、エネルギー技術でも例外ではあり得ない。
もちろん、新しい原子力技術は、現時点での競争力のみによって選択されるべきでなく、未来の人類のための保険という意味を持つことは前述した通りであり、このことは現在も正しい。しかし、現在、保険だからといってコストを無視してよいことにはならないという新しい状況がある。それは保険が真の保険であり得るためには、目標として競争力が重要な条件なのであり、これは研究、開発、実用化を通じて非常に大きい要件である。
すなわち今、設立当初の自主技術は、競争力のある技術と言い換えるべきであるが、その観点から見て現在の動燃の事業は不十分であると言わざるを得ない。(3) 急速な技術進歩
原子力が核分裂という固有の現象によってのみ実現可能であることは、今も昔も変わりがない。しかし、それが現実的な技術として利用されるのは、他の無数の技術が総合されたシステムとして核分裂を実現したときである。この30年間に、このような意味での広い技術の進歩には大きいものがあった。それは構造材料、制御技術、測定技術、自動化技術などの要素技術であり、また、シミュレーション技術、設計技術、製造技術、管理技術そして安全技術などの総合技術である。そしてまた、これらの技術の背後にある理論的発展も極めて大きいものがある。
これらは、厳しい市場競争や、失敗の経験や試行錯誤など、また異分野の協調や融合などによって、激しく変動しながら進歩している。そしてこれらを可能にしているのは、外界に開かれた研究開発の基本的態度である。
ところが、動燃においては、原子力の特殊性、すなわち核不拡散条約による秘密性要求や、事故に対する社会の敏感な反応などがあったことは認めるにしても、それ以上に当初の先進性の意識からの脱却が不十分なまま、広く産業技術の進歩とその接触を怠ってきたことは否めないであろう。この結果、動燃設立時に投入した技術的資産は急速に陳腐化したのである。 - 問題の構造
前述の分析により、現在の動燃は事業体として次のような課題を持っていることが理解される。それは、
・先例のない研究開発
・原子力であるが故の高い安全性
・競争力ある技術の供給
の三者の同時的実現である。これは決して容易なことではなく、この実現こそ前例のない課題である。この課題の困難さは、上記三者が、基本意識、方法などを異にする点にある。例えば、容易に理解されるように、先例のない研究開発では失敗をおそれない勇敢な精神が不可欠であり、安全性では失敗を最小化する細心さとともに、危機管理能力および社会性の向上が必要であり、競争力では全体的俯瞰による妥協というようなそれぞれ異なる精神構造を必要とする。しかも、それぞれの技術対象が、各段階を常時動いていくのであって、状況は非定常である。
現実に、濃縮、高速増殖炉、再処理、廃棄物処理処分などの核燃料サイクルの要素は、常時基礎研究から実用化までを移動している。このように、設立時から急速に変わる環境に置かれつつ、多様な意識や方法で推進すべき異なる領域の技術が、相互に深い関係を持つシステムとして統合する作業が動燃の行うべき作業、ということになる。
結論的に言って、動燃は二つの面で失敗している。それは、
・事故の防止とその後の対応の失敗
・コスト高のために技術を売れなかった
の二つである。そしてこの二者は、前節に述べた状況の変化に的確に対応しなかったことによる失敗であると位置付けられる。その内容は第2部以下で述べられるが、ここではそれが何故できなかったかを問題とする。
状況への対応とは、仕事内容の変化に伴う組織及び課題の変更、世界情勢の変化に伴う経済性追求への移動、安全技術等に関する産業界の進歩の開かれた導入などである。これが、何故できなかったか。それは一口に言えば、それを行う視点が存在しなかったから、と言うことになる。それは経営の不在である。
ここで特記しておくべきことは、日本の多くの組織で、この経営の不在現象が起こっていることである。国の行政組織、大学、そして企業にすらみられる現象である。これは、組織の構成員は十分に組織のために働く意識と意欲を持っているが、しかし視点は自分の置かれた位置における仕事に限定される。全体を俯瞰する視点を名目的な経営者が持つが、しかし組織全体を動かしているのは構成員の行動の総和である。すなわち、組織全体の行動決定者は特定できず、従って真の責任は不明となる。この状況は、組織としての行動の裁量権者と責任者が不明、あるいはずれているという現象である。
実はこのような状況は、目標が外に見えるものとして与えられているとき、極めて効率的に作動する装置となり得る。我が国の高度経済成長を成功させたのはこの装置であり、全員参加の集団主義と言われるものはその代表であろう。
しかし、この装置は、日本の様々な部分で破綻を来している。それは、外に見える目標がなくなったからであり、そこに独自の整合的な計画が立てられなければならぬ状況が現出したからである。このように整合的な目標の設定を、それぞれ固有の、組織の中で部分をなす構成員の視点によっては、たとえ総和を求めたとしても実現することはできない。この本質的不可能性の状況は、極めて根深いものであり、改変するには大きな努力を必要とする。
動燃がこうした状況の下で先に述べた困難な課題を追求してきたことが、今日の動燃の問題を生んだ大きな要因をなしていることを理解する必要がある。すなわち、変化に適応すべき計画を立てる俯瞰的な目を持つ経営者が、動燃において存在しなかったか、あるいは存在しても、十分な裁量を持って行動することが不可能であったということである。これは、日本全体が高度成長を通じて効率的に作動した装置を捨てることができないでいるという中で、動燃もまた例外でなかったことを意味している。言い換えれば、動燃の問題が解決できないとすれば、日本の将来は無いという問題の構造がここにある。
第1章 問題点の整理
- 動燃改革の枠組み
第1部で述べた基本認識において、事故を引き起こすに到った動燃の持つ問題点を指摘した。それは、日本の状況を背景とする大きな負託を国民から受け、それに相応しい投資によって高い技術を獲得しながら、事故を起こしただけでなくその対応を誤り、また経済的な競争力を十分につけることに失敗したのは、たとえ動燃の基本的使命は不変であるとしても、世界情勢の変化、日本の国際的位置の変化、技術の急速な進歩などにより、その実現すべき目標が大幅に変動したにも拘らず、それに適応すべく、目標や戦略の改変を達成することができなかった、という問題であった。そしてこの問題を起こした要因として、責任主体の拡散、経営目標の曖昧化、管理の硬直化、惰性的な運営などが指摘されたのである。これらの要因は、一言で言えば経営の不在である。動燃における管理運営の本筋から言えば、国と経営陣の間の緊張感に富む協調によって、国の要請すなわち国民の負託と、動燃固有の技術的能力によって動機付けられた開発意欲とが、適正な均衡を保ちつつ技術的展開を見せる、と言う経営がなければなるまい。しかし、事実はそうでなく、緊張感のないもたれ合いの状況を生み、結果として経営は消失した。そのことは、事故などの突発事故に対処するための主体的判断ができなかっただけでなく、そのとき自己を、地元に対して表現することにすら失敗したことに、象徴的に表わされている。
従って、動燃の改革においては、動燃に与えられた使命を実現するのに相応しい経営を確立することを、改革の軸に置くべきものであることは明らかである。 - 経営不在の詳細
経営の不在は、特定の目標を持つ組織を、その目標そのものや、目標達成のための条件の実現に向けて、組織全体を合目的的に動機付ける俯瞰的な視点を欠落させる。既に述べたように、先行者が居て、それに追随する場合にこの欠落は潜在的問題に止まるが、自らが先行者となった場合、問題が顕在化する。動燃に見られた問題は、以下のように整理される。
(1) 安全確保と危機管理の不備
動燃は、その設立当初より高度な研究開発と徹底した安全確保という、重要な技術的課題をその任務として持っていた。その両立は、他の組織には見られぬ特徴的なものであるから、先行者となったときは自らその道を探らなければならない。一口に言えば、この両立とは、与えられた資源を、新技術の開発と安全とに最適に配分する経営であり、またそれを実現する厳密な管理ということになろう。
しかし現実には、研究開発への偏重が見られ、安全への配分は不足していたと見られる。それは、両者への費用の配分のみならず、理念的にも、安全の達成に対する評価が必ずしも高くなく、従って人員配置、昇進等において安全を達成するために十分な運営が行われていたとは言い難い。また、施設の面でも、維持管理に人員、費用とも十分な投資を行っていたとは言えない面がある。このことは、過去の知識の保存管理、事故情報伝達の基準作成、通報体制、広報体制の整備、事故の分析とその教訓の反映などにおける不完全さとして露呈した。
一方、他産業における防災は多くの困難な経験を通じて高度な方法、技術を達成してきている。ところが動燃はこれらを学んだとはとても言えない。そもそも技術の進歩は一般的に言って、失敗を通じて行われることが多いのである。しかし、現在、原子力関連安全技術に関しては、失敗は許されないと考えられているため、保守的となって進歩が遅いのは同情に値することは確かであるが、逆に、であればこそ、他産業の一般防災の進歩を積極的に学び、本来、失敗をしたとしても、それが事故につながらないような安全対策をたてることが必要だったのである。原子力の安全性が高いのは保守的だからであり、数値上それが高いから他の技術を学ぶ必要がないとするのは、安全技術上の大きな錯誤と言わざるを得ない。
また、経営の視点は、異質な性格を持ちながらそれぞれ重要さを持つ、研究開発部門と施設運転部門との役割分担を、領域別に、さらに技術の進歩の状況により、常時精微に明確化しておく必要があった。これは度々述べるように二面性を持つ動燃の管理には必須のことである。しかし、運転計画の設定、運転の実施などの例に見られたように、この役割分担は明確でなく、従って、責任関係も不明確であったと言わざるを得ない。(2) 閉鎖性
動燃が社会に対して閉鎖的であると指摘されている。このことは、二重の意味で問題となる。第一は、動燃への国民の負託についての感受性を失ってしまうことである。基本認識で述べたように、この負託は変動し進化してきたのであった。従って、それに対し、常に高い感受性を持ち続けることが肝要である。この感受性の維持のために、また経営の視点が不可欠なのである。研究や運転を行うものは、その課題の目標が困難であればあるほど、従ってその解決が有意義であればあるほど、少なくともその課題の解決に没頭している間は外界が見えない。そしてそれは許されなければならぬ。しかし多くの作業の集積として動燃という組織が存在するなら、全体としては常に社会に開かれて居なければならず、そのとき流入する動燃への負託を受け止めるのは経営するものの責任であり、その負託に現実に応えるべく、研究、運転を企画立案し、それを個々の研究者と運転者が実現すべく資源を配分することが経営そのものであるはずである。
この負託は、一般の人々からを中心とし、同時に直接のユーザーとしての電力産業、潜在的な技術の提供者としての一般産業などを広く含むものであろう。とすれば、閉鎖的であることは、動燃が自らの進む道を見失い、効率的な努力の投入が不可能となり、結果的には安全においても競争力においても不十分なものとならざるを得ないのであって、ここに経営不在の大きな陥穽を見るのである。
第二は、発信に関わることである。これは第一として述べた感受性と同質の能力であるとすら言える。それは動燃の組織としての使命に関し、常に公表し、理解を求め、結果として外界の反応を得ることによって、正当に外界を感受できるからであり、それこそが最も正当な感受であろう。従って、公表し理解を求めることは、単なるサービスではあり得ず、負託によって存在する組織が自ら存在するための条件である。そしてここにも、個々の動燃研究者が研究発表し、技術者が専門家に開発結果を説明し、あるいは青少年のために教育的見学を計画することなどでは決して達成できない、本質的公開が経営者の視点によってのみ成し得るものとして存在している。それは、他に類のない専門性の高い事業であるからとか、秘密保持を義務付けられている、などを公開を拒む理由として持ち出すことが決して許されない本質的公開である。一口でいえば、それは動燃の目標に関する表明である。目標は、新しい原子力エネルギーという理念的なものに止まるのでなく、長期的エネルギー政策の中で、現時点では開発がどのレベルにあるのか、次の解決すべき問題は何か、そこにどんな技術的困難さが予想されるか、その克服のプログラムは何か、どんな分野の協力が他産業から必要か、そしてこれらにはどれくらいの人材や資金の投入が必要であり、また時間はどれ位かかるのか、そして出来得れば将来のエネルギー開発の他のオプションとの相対的位置付けについてなどのものであり、これらを常時メッセージとして発信していなければならぬ。
この際覚悟すべきことは、これらは厳しい自己評価、そしておそらく適正な外部評価を得て初めて可能になるということである。言い換えれば正しい評価が必要、ということである。その評価は、研究、運転の当事者達の目前の作業を遂行する熱のある目によっては不可能であり、できるだけ冷静な、ということは研究者や運転者にとって暖かい目による判断が必要である。
この点を考えるとき、事故隠しの不思議に言及せざるを得ない。研究者や運転者が全力を挙げて努力した過程で事故が発生した時、それは技術の、あるいは組織の隠されていた欠点についての情報であり、組織全体としては進歩のための、得難い貴重なデータである。それを以後根絶するための措置が、事故の認知を契機として取られることになる。すでに述べたように、失敗の極小化を要請されている保守的な原子力関連技術で、事故が万一生起した時、事故の生起そのものが重大であると同時に、そこに重要な情報が含まれていることをも、また認識する必要がある。
しかし、現実に起きたのが事故隠しであったのは何故か。この、事故の極小化の要請には、もう一つ別の面が含まれている。それは事故を起こすことは悪である、という面である。これは否定すべくもない判断であることをまず認めよう。その上で、悪であるからそれを起こしたものに罰を、少なくとも観念の上で罰を与えるという方向へ踏み出すとき、事故を起こしたものには低い評価が与えられることになり、研究や作業の環境は少なくともその結果として良くはならないであろう。
これは、事故を起こさないような細心さを要請するものとして、その有効性を認知する人が居るかもしれない。しかし、それは動燃のような、目標を持った組織の中での研究者や運転者に対しては当てはまらない。事故に潜在する重要な情報に注目すること無しに、単に罰することで処理しようというような眼は、これらの人にとって冷静な眼とはならず、冷酷な眼となり、組織の中に不信感を生むだけである。そして、前述したように、組織内不信感を生むに止まらず、結果的に事故の持つ重要情報を散逸させたという意味で責任は重いのであり、事実、それは組織に対する社会の信頼を失墜させてしまった。このことは、報告義務違反を問われた者が罰せられたからといって、決して減じることのない組織の責任なのであり、従って事故を起こした当事者とは別の経営上の責任が独立に存在すると考えることが必要なのである。(3) 事業の肥大化
経営の不在が事業の肥大化を生む。これは公的機関に屡々観察される、かなり一般的な現象である。その理由は容易に理解できる。組織全体を俯瞰的に観る目が曇っているか、あるいはその目を持つものの与えられた裁量権やその行使が過小の時、組織が動いて行く方向は、組織を構成する要素、すなわち部分組織の意欲に従って行われる動きの総和として決められる。特記すべきは、我が国の活動が、経済を中心として拡大していた時期においては、特に活発な部分組織が独特のプロセスによって成長するが、他も微増あるいは一定に止まるにしても縮小されることはない。この全般的拡大期というのは組織にとっては幸せな時期で、組織の構成要素は拡大か、そうでなくてもせいぜい一定不変であるから、全要素とも幸せで、結果的に組織変更に伴う経営の負担はないに等しい。そして、これは組織全体の肥大化を生む。
動燃も例外ではなかった。これが民間企業における事業の拡大ならば、そのこと自体歓迎される面もないわけではなかったが、基本認識で述べたようなエネルギー問題を取りまく環境の変化の中で、この肥大化は動燃の存在をより困難なものにしたことは間違いない。すなわち、業務や組織の適正な管理が困難となり、縦割り硬直化を生み、結果として事業の水平展開を妨げて競争力を向上できず、また事故防止に進歩が見られなかった。また長期展望なしの肥大化は、組織としての主体的意志を喪失せしめ、モラルの向上を阻害した。
このことは、動燃が高度成長時代の安易な肥大型経営に流されていたことを意味する。多くの場合、私企業ですらも、この高度成長期の肥大化の後遺症に悩まされたが、それから離脱したのは私企業の場合「リストラ」であり、それを行ったのは強力な経営である。
その中心は、スクラップアンドビルドであり、この場合、スクラップの対象となる構成要素が存在することが、肥大型経営と異なる。この場合の経営には強力なリーダーシップを必要とし、もしそれが弱い場合は構成要素の「既得権益」という自己保存的欲望に経営が負けることになる。
組織を構成する要素としての部分組織が自己保存を主張するのは、経営のないところではそれに換わるものとして有効である。しかし、動燃の置かれた位置は、状況の変化に計画的に、しかも的確に対応していくことが求められていたのであり、肥大型経営が有効に作動する余地はなかった。従って、スクラップや外部移管を含む強力な経営が必要だったのに、部分組織の自己保存欲に経営は敗北したのであり、ここにも経営の不在による失敗が、明らかに存在していると考えるべきであろう。
- デザインの基本
人類の将来のエネルギーについて我が国が分担するオプションの実現という国民の負託を実現するための最適な組織(以下「新組織」という。)を提案することが必要であり、ここではその基本的な輪郭を示す。新組織の目標は、必要な安全確保を条件として、競争力を持つエネルギー源としての閉じた核燃料サイクルをできるだけ速やかに実現することである。
この新組織のデザインを行うに当たって、与えられる資源の最大のものは、動燃に蓄積された技術およびノウハウである。それは、先例のない課題についての研究能力と研究成果であり、高い安全性を確保する運転管理能力と実績である。
新組織は、これらの資源を中心としつつ、しかし同時に国の内外、産業分野を問わず入手可能な人材や技術などの資源を可能な限り利用しつつ、目標実現のために最適な構成を持つものとする。
上述の目標は、新組織を取り巻く状況の変化および目標そのものの達成過程の進行に従って変動する。この変動に適応しつつ、目標達成のための最適性を常に保持する戦略を維持するために、新組織には強力な経営が必要不可欠である。
この場合の「経営」とは、広い意味での「経営」であり、将来のエネルギー確保についての国民の負託を現実化するために新組織に対して委託を行う国と、平和利用を精神とする固有の計画を立案する原子力委員会と、この両者に対して裁量権と責任との明確な分担を設定された新組織に導入される経営体との、三者により構成される。
この「経営」を構成するこれら三者は、目標実現のための全責任を負う。その中で、新組織の経営体は、国によって与えられた研究、開発、運転管理、営業などの資源、すなわち与えられた定員、施設、設備、予算の範囲において、目標達成のための組織の改変、施設および設備の計画と設置、予算の執行について、最大限の裁量を持つべきである。原子力委員会の長期計画を実現するための中心的存在である新組織における経営体は、このような裁量権が付与されると同時にその行使が義務付けられる。
従って三者のうち原子力委員会は長期計画などに述べられる計画の立案を使命とし、国はその立案の社会的根拠の設定およびその明示を使命とすると同時に、長期計画実現のための社会的基盤の整備および新組織への投資の大きさを決定する裁量と責任を持つ。そして新組織の経営体は、長期計画を目標とし、国によって与えられる資源の最適利用によって目標を実現するための方法の策定およびその執行についての裁量と権限を持つ、という役割分担が、デザインの基本的な構造となる。 - 新たな経営の確立
国および原子力委員会との関連において明確に設定された裁量権を持つ新組織に導入される経営は、以下のような条件を満たすものでなければならない。
(1) 事業目標の設定
既に述べられたように、新組織は明確な使命の負託を受けて設置されるべきものであるから、その事業目標は明確に設定され表現されていなければならない。しかもそれは、開発の進行と新組織をとりまく状勢の変動によって常に変化するものであるから、設定された目標を、社会のそれぞれの部分を代表する者によって常時評価し、変更するものでなければならない。この点は国および原子力委員会についても同様であり、従って変更は総合的なものである。
(2) 経営者の選定
新組織に与えられた使命が、先例のない研究開発と高度な安全性を満たす運転管理の多領域に亘る総合的なものであることを考えれば、経営者は事業に関する十分な専門的経験と知識、複雑な構成の組織を管理するための経験と知識、社会情勢についての時代に応じた知識等に裏打ちされた、洞察力と判断力、そして決断力を有する者でなければならない。その能力は、組織の改変、柔軟な運営、最適配置を可能にする人事管理、対外的な説明責任などのために使われる。この実現は、一人の個人によっては困難と考えられ、従って経営体は個人ではなく、経営組織であろう。この経営組織は、自己評価によって絶えず自己変革すると同時に、外部評価も必要である。とくに外部評価は、国の委託および原子力委員会の長期計画との適合性および地元との協調性を評価し、その乖離を未然に防ぐことに力点を置くべきである。
(3) 組織の基本原理
新組織の基本は国によって構想されるが、その改変は新組織に導入される経営体の裁量に委ねられる。新組織はそれに与えられた開発領域ごとの研究開発と運転管理との部門からなり、各部門は研究者、技術者、運転者、管理者などにより構成される。各部門は固有の使命を持ち、その実現のための業務を行うものであるが、その使命を定めるのは新組織全体を俯瞰する経営体であって、部門自身ではない。各部門、あるいは部門を構成する職員は、自らに割り当てられた使命を、研究、運転、管理などにおいて、創意に基づく計画とその実施によって実現する。この業務は新組織固有のものであり、例えば研究者は、大学研究者の業務とかなり異なる。大学研究者の場合は、使命については概念的な大枠が与えられているのみであって、その計画については大学研究者は大学の固有自治に基づく裁量により自らが立てる。一方、新組織の場合は、内容が明確に定められた国民の負託によって存立しているのであるから、研究者に与えられる使命は概念的なものに止まらず、目標達成のために経営体が中心となって定めた計画の実施を分担するものとして位置付けられており、計画における裁量は目標設定を含まず、目標実現の手段の設定に始まるものである。
ここで強調すべきことは、自ら研究目標を定める研究者に最も高い評価を与えるとする誤った風潮についてである。このような大学に見られる自由研究者と、高い使命を持つ組織の管理下で業務を遂行する研究者とは、その存在理由を異にするのであって、見かけ上の自由度などからその価値を比較すべきものではない。両者は独立であり、等しい価値を持つ。おそらく同一研究者が、自らの研究過程に従って、これら二つの型の研究者の間を行き来することもあり得るし、またそれは歓迎すべきことである。
同様に、研究者と運転者において、研究者に高い価値があるとする全く誤った俗的感覚をも指摘しておく必要があろう。高度な使命を持つ技術的開発組織において、研究者と運転者とは車の両輪であって対等である。従って両者は組織としての使命の実現への貢献について等しく評価されるべきであり、それに応じた昇任の道も等しく準備されるべきであり、管理への移行も同等の機会が与えられなければならぬ。むしろ、社会一般の評価機会を勘案すれば、一部の研究者は任期制として社会の評価を受ける機会を拡大し、運転者は組織内部の評価によって内部の昇進の道を安定的に定めると考える方が妥当とすら言えるのかもしれない。 - 新組織に想定される体制
(1) 開発領域の限定
前述のような条件の下に導入された経営体を持つ新組織には、それが遂行するべき使命、すなわち事業目的が必然的に与えられる。それは、我が国が分担するエネルギーオプションの実現の中心的役割を果たす新組織に与えられる使命である。
第一に、その事業は公共性の高いものでなければならない。既に述べたように、核燃料サイクルの開発は、全ての人類にとって重大な関心事であり、我が国がそれを分担することは国際的にも我が国自身にとっても意義があるとすれば、その開発は公共性が高いものと言えよう。しかも、第二に、この開発の事業は経済性から言えば、極めてリスクの大きいものと言わなければならぬ。このことは、そもそも核燃料サイクルを、将来に亘る人類生存のために可能なオプションとして定めるという動機の中に必然的に含意されていたと言うべきである。従って、核燃料サイクル実現のための技術開発は公共性が高く、しかもその開発は基本的に国が負担するべきもの、という結論が導かれる。しかし、既に述べたように、核燃料サイクルの実現には、いくつかの異質の専門的知識に裏付けされた開発領域があって、現時点でそれぞれが実用という目標から等しい距離にいるわけではない。すなわち開発領域毎に、目標に対する完成度に差がある。従って、もし目標を達成した開発領域があれば、それは国の負担において開発することの根拠が希薄になったと言うべきである。そこで開発領域の完成度、すなわち開発レベルを次のように分類する。レベル0:原理的可能性が発見されているが、実用化の可能性は不明なもの。
レベル1:基礎研究によって実用化の可能性があると判断されたが、完成までには多くの開発研究を必要としていて、実用の時期、経済性等について明言できないもの。
レベル2:実用への道が見えていて、どこに資源を投入すれば実用化可能であるかがかなりの確度で言えるもの。従って、経済性も推定できるもの。
レベル3:技術的実用という点ではほとんど完成しており、部分修正によって経済性向上が期待されるもの。
レベル4:開発研究が十分に完成、または完成しつつあるもの。
a.経済性配慮が行われており、市場における競争力があるもの。
b.経済性がなく、市場での競争力が期待できないもの。これは概略的な分類であるが、このような分類があるとき、どれが公共性の高い事業を行う新組織に相応しいかについて述べる。
レベル0:公共性はあるが、明確な目標の下で経営を行う新組織には馴染まず、別の研究組織で行う。
レベル1:新組織に相応しい。新組織の中で長期的かつ重点的に行われるものと位置付けられる。
レベル2:新組織に相応しい。高度な管理の下で遂行されるものとする。
レベル3:ユーザーへの技術支援、ユーザーとの共同研究などを考慮し、遂行されるものとする。
レベル4a:民間に移管する。
レベル4b:市場において競争力のない技術は、一般に改良程度では競争力はつかない。改めて基礎研究によって革新的部分を加える必要があるので、別の基礎研究所へ移管するか、廃止する。各研究、開発領域は、一般にレベルの低い方から高い方へと移動する。原則的にその移動は連続的であるが、そうでないこともあり得る。すなわち、他の競合技術の登場により、急に経済性を失う場合もあるからである。従って、新組織の経営体は、各開発領域についてレベルを常に監視しつつ、対応していくことが求められる。
移管の方法には多様なものがあろうが、人材、施設、方法などの、それぞれあるいは総合的な移転があり得る。その他民間に対する技術支援事業等も考えるべきである。
なお、今後民間への移管が行われたときも、全体としての核燃料サイクルというシステムは存在することを決して無視することは許されない。サイクルの一部が民間に移管されたり、あるいは外国製の技術で置き換わったりしたとき、サイクルは国家的事業、民間事業を越え、しかも国境を越えた世界的な広がりを持つことになる。そのとき、サイクル全体を俯瞰しつつ、その中での要素技術の状態を判断し、開発推進の方向を決めるのは、国、原子力委員会、新組織の経営体の共同作業によるべきである。(2) 安全確保と危機管理の体制
新組織の経営体が安全確保の体制を築き運用することになるが、その基本的方向は以下のようなものになるであろう。
運転管理に関しては研究開発偏重を排し、運転管理部門と研究開発部門とを独立に運営し、特に運転管理部門に陽を当ててその向上の方策を明確にする。
また、施設維持管理、人員配置管理等、安全に直接関係するところは品質保証の考え方を徹底し、またそのための部署を置き、全組織に安全の意識を徹底する任務を持たせるべきである。さらに、事故の原因等をきちんと把握、分析し、改善策を講ずる等、過去の事故の教訓を安全対策に適切に反映することが必要である。
危機管理体制においては、一般防災の知見を全面的に導入し、地域と連携一体化した管理体制を、規則の定めを越えて人的組織、連絡装置などの導入を図る。特に緊急医療体制を確立することは必須条件である。(3) 社会に開かれた体制
新組織は地元との共生を経営の基本の一つに据えるべきである。当然広報体制を充実し、例えば経営体の構成員一人を広報専任とすることは有効であろう。情報公開は徹底する。この際公開した方が自らの能力がよりよく発揮できるという意識を育てることが必要である。それを育てる方法は、本来ゆっくりそのような雰囲気を醸成するのが上手な経営というものであろうが、この際は強制しかない。特に事故における報告はどんな些細なものでも無視することは絶対許さず、隠した場合は厳重に対処する。その上で、報告された事故の原因究明と対策を的確にとる。この実現により、報告することの意義が組織として有用であることが自然に理解され、次第に報告の強制など不要になるだろう。
一方、外部との協調はより積極化する必要がある。民間との活発な人事交流はもちろんのこと、大学等他機関との共同研究を積極的に実施するための、特定の研究者制度などを導入すべきである。
核燃料サイクルの開発を推進する国が少なくなった現在、国際共同研究を国レベルで計画することが望ましい。とくにフランスとの共同研究を企画することが必要であり、一方他の諸国の専門家の半恒久的招聘等、新組織は核燃料サイクル開発の世界的拠点としての責務を果たすべきであろう。(4) 専門性の均衡と研究者の拡がり
核燃料サイクルを構成する各領域は、原子物理学、材料学、制御学、機械工学などの力点に、それぞれ差がある。しかし、核燃料サイクル全体を貫く安全性や経済性を考える時、それぞれの分野が安全について固有の方法論を持っていることから言って、各方法の利点を総合するという意味で、各領域とも、広い専門分野の人材が均衡よく配置されているのが望ましい。その結果、専門分野を広く擁する多くの大学へと人材の裾野が拡がり、大学における原子力研究を活性化し、その結果人材交流等も盛んになることが期待される。この裾野の広さは、一つの技術の成功に不可欠であることを銘記すべきである。
第1章 改革の具体化の方針
第2部の改革のデザインで述べた新組織として、動燃の現在の事業を抜本的に見直し、部分的に解消、または移管し、必要と考えられる部分で再出発させるとの方針の下に、動燃を改組し、新たな特殊法人(以下「新法人」という。)を組織する。すなわち、動燃は解体的に再出発するものとする。
新法人は、国民から負託された使命として、原子力の平和利用を堅持しつつ、核燃料サイクルの確立に向け、明確に設定された目標の下に、長期的な観点から実用化を目指したプロジェクト指向型の研究開発を遂行する。
また、新法人は、動燃に蓄積された人材・技術・ノウハウ等を最大限に活用しつつ、安全性と社会性の確保を条件とし、強いリーダーシップの下に、明確な裁量権と責任を持った新たな経営体制・組織で運営される。新法人を構成する全ての役員、職員には、強い意識改革が必要である。新たな経営体制・組織の確立は必要条件に過ぎない。その体制・組織のもとで作業を遂行する者は、分担すべき作業の意義と責任に対して、従来、我が国の組織を特徴付けていた曖昧さと決別し、それに明確な輪郭を与える新しい世界の創出が義務付けられていることを強く認識することが不可欠であり、それが新法人が成功するための十分条件を構成すると言ってよい。その実現のためには、制度の改変に加え、多くの努力が必要である。
改革は可能な限り早期に実現する必要があるが、新法人への改組までの間においても、動燃は、安全対策の強化、情報公開の徹底等、対応が可能なものについては順次改革を実行していく。その際、動燃は自らの責務を十分認識するとともに、安全確保を大前提に、業務を着実に遂行する。
動燃の度重なる事故により原子力施設のある地域住民をはじめとした国民一般に対し、原子力に対する不信不安を惹起したことの根源的責任は、動燃のみならず、それを指導監督するとする科学技術庁、および動燃の使命を決定する原子力委員会も等しく負うべきことは当然である。この三者が責任を負うべきことは明らかであるが、それぞれの持つ裁量が明確な輪郭を与えられていないために、責任の輪郭も不明となり、従って取るべき行動も明解に定められない。このことは、今回の改革をどうするかの難しさの原因を成すのみならず、今回の一連の事故および処理の不備の根源的な原因を成すと考えられる。しかし、本委員会の使命は、動燃にかかわるものであり、ここでは、動燃の改革に不可避的に関連して来る場合においてのみ原子力委員会や科学技術庁について言及するものとするが、当然原子力委員会および科学技術庁も、それぞれ本件に関して何らかの反省の上に立って対応がなされるものと本委員会は期待するのみならず要請もする。その成果が得られた時点で、本提案の修正が必要となるのであれば、当然それを受け入れるものであることは、「まえがき」で述べたことの論理的対偶として自明のことである。
以下に、新法人への改組の要点を提案する。この提案の具体化については、「あとがき」で述べるように、追加的な措置を含め、専門的、実務的な検討に委ねることとする。なお、ここでの提案事項のうち、新法人への改組までの間においても対応が可能なものについては、順次、実行に移していくことが必要である。
- 経営の刷新
(1) 新法人の事業目標の明確化
新法人の基本的な事業方針は、長期計画を中心とする各種の原子力委員会決定で定められる。これら長期計画等の決定を受けて、より具体的な5年程度の期間をカバーする事業目標を、関係者の意見を踏まえ、科学技術庁と協議の上、新法人において別途定める。
新法人の定める事業目標は、これと実施結果との比較によって新法人の経営の妥当性を判断していくこととなるため、科学技術庁や新法人の関係者だけでなく、第三者にも客観的に評価しうるものとする。
また、新法人を取り巻く状況は常に変動していることや、新法人において事業を進めていくうちに事業目標を変更していく必要が出てくることも十分に考えられるため、新法人の経営者はこれらの状況変化を十分に把握し、適切なタイミング、例えば毎年度見直していく。
一方、科学技術庁は、新法人の業務遂行状況及び目標達成状況を十分に把握し、状況変化等に応じて、長期計画の見直しを原子力委員会に要望するなどの柔軟な措置を講じる。また、それを受け、原子力委員会において、適切な対応がとられることが期待される。(2) 新法人が行う経営の機能強化
新法人においては、理事長及び理事からなる経営体に付与された明確な裁量権と責任についての自覚に基づき、強いリーダーシップの下で組織が運営されることが必要である。このため、以下に示す改革により、経営機能を抜本的に強化することとし、早急にその具体化の作業を進める。
-
1) 裁量権の拡大と行使
新法人の経営機能を強化するため、経営体にできる限りの裁量権を付与し、手続き面等での科学技術庁の関与を極力減少させる。理事会及びこれを代表する理事長は、裁量権が付与されていることの責任を十分に認識し、事業目標の達成に向けて強力なリーダーシップとイニシアチブを持ってこれを行使する。
また、新法人においては、理事長の裁量の下、組織の改変、人事管理、経理面において経営に柔軟性を確保する。
ここで言う裁量とは、実質的なものでなければならない。すなわち、事業目標の達成のための経営の成功のために最適な任務の配分にかかわる裁量である。この配分の詳細については十分な精査ののちに行うべきであろうが、以下のような側面は、この時点で強調しておいてよいであろう。つまり、与えられた開発項目を均衡に配慮しつつ総合的に実現していく責務は新法人にあり、状況の変化に適切に対応しつつ、自主的な判断の下に研究開発を遂行する。新法人が殆ど国の資金により運営される研究開発主体の特殊法人である以上、毎会計年度の人員、施設・設備、予算の基本的な部分については、国会及び政府の予算システムの枠内で決定されていくことはやむを得ないが、その枠内でこれらの詳細な計画と配分について、新法人が出来る限りの裁量を持つべきである。その際、毎会計年度の予算システムの過程で、的確な予算要求を行うべき義務を新法人が有することを認識するとともに、技術内容を知らないものが新法人の裁量に不必要に関与することを断固排除する決意を持つことが極めて重要である。2) 理事会メンバーの人選
柔軟で視野の広い経営体制を確立するため、非常勤理事を含めた理事会のメンバーは、従来の構成にとらわれず、幅広い分野から人材を登用する。
すなわち、国際的貢献を軸として、国民の負託に応えつつ、与えられた開発項目と資源の枠のもとでの経営に必要な能力を十分に覆うために、科学技術の専門と経験を有するもの、競争力向上の経営についての専門と経験を有するもの、国際貢献と国民の負託について確固たる方針を有するものなどが理事会を構成することとなろう。しかも、人材の登用に当たっては、新法人の事業目標達成に献身的に努力するものであることを登用の最大の条件とする。また、その構成は、新法人と特定の利害関係のある者や関係省庁からの出向者が大半を占めることなどは適当ではない。3) 経営の外部評価
国民、国の政策、社会等との乖離を未然に防ぐため、新法人においては、自己評価による自己変革とともに、経営に第三者による外部評価の機能を導入する。外部評価の結果は、理事会に報告されるとともに、必要に応じて科学技術庁や原子力委員会に報告される。4) 組織管理の強化
動燃においては、本社機能の肥大化、各事業部門間の縦割り弊害、各部署の責任と権限の不明確等組織上の問題が存在している。新法人においては、より効率的で責任体制が明確な組織を構築するため、本社機能と事業所機能を抜本的に見直し、事業所横断的な機能を充実させるなど新たな組織に刷新する。5) 人事制度の刷新
新法人においては、職員の職務に対する意識、意欲の向上とともに、人材の適材適所を図るため、研究者、技術者、運転員等の業務の特性に配慮しつつ、人事評価や処遇を見直し、人事制度を刷新する。
その際留意すべきことがある。既に新法人は基礎研究から競争的開発まで幅広い範囲を覆うという特徴的でしかもむずかしい業務内容を持つことを指摘しているが、それは固有の人事制度を要請しているのである。すなわち研究者は、すでに世界的に拡がる流動性の中で常に十分な能力と最適の意図を持つものが採用され、処遇されるべきであり、一方技術者は、製造業との間で流動性を創出する方策を立て、それに従って流動的な採用を実現すべきであり、一方運転員は安定的な昇進を約束された体系に置かれる。従って人事考課は、研究者は外部の同種研究者群による評価、技術者は内部技術者による評価、運転員は管理者の評価を参考としつつ、理事会の責任において定めるものであり、一元的にはならないことを知るべきである。(3) 職員の意識改革
新法人が動燃の職員を引継ぎ、新たな組織として再出発するに当たっては、理事長の明確な責任の下に、職員全体の意識改革を図ることが極めて重要である。
意識改革の基本は、役員においても職員においても、自ら分担する作業の輪郭を明確にすること、その輪郭の中では十全の裁量を持ち、従って完全な責任を担うことである。それに加え、それを第三者に明快な説明をすべく常時準備しておくことが必要である。恐らく、従来の日本の組織の習慣から言ってそれは容易なことではない。しかし、その実現は本質的なことであり、是非実現されるべきである。また、新法人に求められる意識改革とは、我が国の多くの部分の意識改革と並行して行われたときに、真に有効性を発揮する面があり、この実現のプログラムを我が国として早急にたてる必要がある。このような総合政策を土台とした上で、新法人の目標の明示と、その反映としての評価の原則とを明示する作業を開始する必要がある。
これらの点を踏まえ、以下のとおり、新法人の経営の基本として、職員の意識改革に最大限の努力をすることが必要である。-
1) 職員の裁量と業務分担の明確化
意識改革の実現のためには、理事会が新法人の作業の全体図を各構成員の裁量を積み上げた形として明示することが出発点となろう。これは、理事会の最初の仕事であり、早急に行うべきである。2) 目標の共有化
意識改革において、すべての構成員に必要なのは、新法人の目標を共通的に理解することである。各人の分担が、截然と分離されるのと並行して、目標意識の共通化がその分離を統合するのである。すなわち、それは、人類の将来におけるエネルギー確保のために、他にないオプションを担うという地球的課題である。各構成員が、行動の基盤として、そのことに誇りを持つことができるような組織とすることが必要である。3) 業績の評価とキャリアパス
新法人で行われる作業の評価は、通常の研究評価と同一ではあり得ない。例えば研究者の研究実績が、査読つき研究論文の数で評価される方式は適用すべきではない。十年かかってプラントが完成したとき、業績はそのプラントそのものと、その過程で得られた数々の知見である。その中には、通常の査読つき論文になるものも一部はあろう。しかし、目標から言って、本当の業績は、競争力ある新技術の完成である。これは、論文の形式から解放されたドキュメントとして広く公開されることが期待され、新法人は自らの業績を社会に広く評価されるためにも、積極的な開示に努めるべきである。また、社会は、こうしたドキュメントに対し、数多くの論文に匹敵するものとして高い評価を与えるべきである。その上で、このような実績を持つものが、大学教員として、あるいは企業の経営者、技術者として歓迎されるようなキャリアパスが創出されるべきであり、そのためには一般企業、大学も偏狭な人事政策を改めることが期待される。4) 人事交流による開放性の確保
新法人の開放性を確保するため、異分野の組織・人材からの意識の触発の機会を充実させ、民間、他機関及び海外との双方向の人事交流を活発に実施する。また、組織内における人事的な停滞性を回避するため、部門間の人事異動を活発化させる。5) 研修等による革新的な風土の形成
国民からの負託に対する意識を向上させるとともに、社会環境への順応性を高めるため、外部での研修等を含め、自己革新を可能とする意欲の醸成や学習機能強化のための各種研修制度や社会科学セミナー等を充実させることにより、個々の明確な問題意識を醸成し、自己革新や組織改革を可能とさせる風土を形成する。(4) 明確な経営理念の確立と組織への浸透
新法人の組織運営に当たっては、改革の趣旨及び時々の状勢変化も踏まえ、経営理念を確立し、組織に浸透させることが極めて重要である。このため、理事長は、経営理念を明確化し、全職員への分かりやすい形での浸透を図る。その際、安全性と社会性を前提条件としつつ、特に、現場重視、コスト意識、民間や関係機関との連携強化等新たな経営理念として必要と考えられるものを積極的に取り入れていくことが重要である。
(5) 新法人の運営に関する科学技術庁の役割
以下に示すとおり、新法人の業務遂行については、基本的に自らの裁量で行うこととし、科学技術庁は、その業務の結果について厳正な評価・監査を行うことを基本とする。その際、科学技術庁は、このような新法人の指導監督の考え方に一貫性を確保する。
ここで指導監督という表現について言及しておく。指導とか監督というと、より多く学んだもの、より豊富な経験を持つものが、そうでないものに教えたり、助言したりすることを一般に意味するが、ここで用いられる「指導監督」は、そのような内容を意味するものでは全くないということに注意すべきである。従って、指導するのは偉い人という含意はなく、科学技術庁は新法人に対して、偉い人という見方があったとすればそれは全く払拭されるべきである。
ここで言う指導監督とは、国の資金を使って実行される新法人に対して、国民の負託を受けて向き合うということである。そして当然のことながら、次のような二面性があろう。すなわち、科学技術庁は、現場としての新法人が最大の効率で資源を利用できるような環境を設定するためのサービスを行うとともに、また国民の血と汗の結晶である税金から賄われる国の資金を使っているという意味で、この資金が無駄な形で使われていないかを常に国民に代わって監視していると考えるべきである。-
1) 新法人の事業目標の尊重
科学技術庁は、新法人の定めた事業目標を尊重し、新法人と協議しつつ、毎事業年度の予算・定員の確保に努める。その際、科学技術庁は、新法人の業務現場を十分に把握した上で、安全確保、資金・人員の効率的運用、事業のスクラップアンドビルドを徹底するとともに、新法人を社会に開かれた体制とするよう留意する。2) 科学技術庁による業務結果の評価・監査
科学技術庁は、新法人の業務の実施結果について、現場の状況を十分に把握した上で、厳正に評価・監査を行い、その結果、必要と判断する場合には、新法人に対して是正措置を求める。 - 新法人の事業
(1) 動燃の現行事業の分類
動燃の現行事業を第2部の改革のデザインで述べた分類に当てはめ、大別すると次表のような分類が考えられる。
レベル0 ・フロンティア研究の一部 レベル1 ・フロンティア研究の一部
・先進的核燃料サイクル技術開発レベル2 ・高速増殖炉開発及びそれに関連する核燃料サイクル技術開発
・高レベル放射性廃棄物処理処分の研究開発レベル3 ・軽水炉再処理研究開発 レベル4a ・ウラン濃縮研究開発
・海外ウラン探鉱レベル4b ・新型転換炉開発 (2) 新法人で実施すべき事業
世界における潮流と先駆者たる新法人の役割を踏まえつつ、第2部に描かれた新法人の存在意義、ビジョンに照らし合わせ、新法人が実施すべき事業を整理すると次のとおりである。
-
1) 先進的核燃料サイクル技術開発等
レベル1に分類される事業は、実用化の可能性はあるが、その完成に多くの研究開発を必要とするものであり、新法人において長期的かつ重点的に進めるべき事業である。レベル1に分類されるものとして、先進的核燃料サイクル技術開発とフロンティア研究の一部等、後述の中核的事業に関連する目的の明確な基盤技術研究については、新法人において実施されることが適当である。その際、大学、原研等関係機関との共同研究の積極的推進に配慮する。2) 新法人の基本となる研究開発
レベル2に分類される事業は、実用化の確度が高く、経済性の推定も可能であり、新法人において高度な管理下で遂行されるべき事業である。この分類に従い、次の2つの事業を新法人の中核的事業として位置付けることが適当である。・高速増殖炉開発及びそれに関連する核燃料サイクル技術開発
・高レベル放射性廃棄物処理処分の研究開発高速増殖炉開発及びそれに関連する核燃料サイクル技術開発は、将来的に核燃料サイクルの中核を成す研究開発であり、我が国の将来、さらには、人類の未来を見通したグローバルなエネルギー安全保障の確保に資する極めて公共性の高い研究開発であることから、新法人においては、その研究開発を着実に推進していく。その際、高速増殖原型炉「もんじゅ」を含む我が国の高速増殖炉の将来のあり方に関しては、現在、原子力委員会「高速増殖炉懇談会」で審議が行われているところであり、その審議結果、及び「財政構造改革の推進について(平成9年6月3日閣議決定)」を踏まえつつ、適切な対応をとる。
また、高レベル放射性廃棄物処理処分は、整合性のある原子力開発利用の観点から残された最重要課題として位置付けられており、新法人は、中核推進機関として、その研究開発を関係機関と協力しつつ着実に推進していく。3) 軽水炉再処理研究開発
レベル3に分類される事業は、実用化という面ではほぼ完成しているが、部分的に修正することにより経済性の向上が期待されるものであり、ユーザーへの技術支援や共同研究に考慮して新法人で遂行すべきものである。軽水炉再処理研究開発については、当面、このレベル3に位置付けられる。東海再処理工場では、当面電気事業者からの契約による役務や、新型転換炉「ふげん」等からの使用済燃料の再処理等を実施するとともに、現在建設中の六ヶ所再処理工場の運転要員の養成訓練にも役立てる。六ヶ所再処理工場が安定的に操業を実施する段階となれば、軽水炉再処理研究開発自体はレベル4aとなるが、その段階における東海再処理工場の役割として、レベル2である高速炉燃料再処理等の技術開発を行う施設としての活用を検討する。(3) 事業の整理縮小
動燃の事業のうち、以下に示すものは、新法人の事業としては、基本的に廃止を含め整理縮小するものとする。
-
1) 他の研究機関への移管
レベル0に位置付けられるフロンティア研究の一部については、基本的に原研等へ移管、または廃止する。2) 民間への技術移転
レベル4aに位置付けられるウラン濃縮研究開発については、動燃の技術を基に、事業化が進められていることから、新法人として、技術、人材面等で協力しつつ、民間に技術移転する。また、動燃人形峠事業所のウラン濃縮原型プラントについては、立地地元自治体等とも協議し、適切な過渡期間をおいて運転を停止し、濃縮機器の廃棄技術の研究に活用する。
同様に、レベル4aに位置付けられる海外ウラン探鉱については、基本的に民間活動に委ねることとし、現在の鉱区の権益については、外国、共同事業者等に配慮しつつ、適当な過渡期間をおいて、民間等に移管するか、または廃止する。3) 撤退事業
レベル4bに位置付けられる新型転換炉開発については、その役割が終了しつつあることから、基本的に撤退する。「ふげん」については、立地地元自治体等とも協議し、適切な過渡期間をおいて運転を停止し、廃炉研究に活用する。(4) 事業を進めるに当たっての配慮事項
新法人におけるこれらの事業の実施、または事業の整理縮小に当たっては、以下の点に留意する必要がある。
-
1) コスト意識の定着
新法人の事業は、実用化を目標として推進されることから、事業の成果が可能な限り経済性を持つことが重要であり、そのため、事業実施の各段階で、電気事業者、メーカー等外部専門家を交えてコスト評価を実施するなどにより、コスト意識の定着を図る。2) 技術移転
新法人の行った事業の成果を円滑に技術移転していくためには、電気事業者をはじめとする関係者との緊密な協力関係を構築していく必要がある。このため、事業実施の初期段階において、関係者間で技術移転についての考え方を整理しておくとともに、事業の進展に応じてこれを見直す。
また、技術の移転に当たっては、当然のことながら受け手側で十分な安全確保が図られることが移転の前提となる。3) 事業の整理計画
整理縮小する事業については、地元自治体をはじめとする関係者と十分協議し、計画的かつ円滑に撤収していくための整理計画を動燃が早急に作成し、新法人に引き継ぐ。 - 安全確保の機能強化
(1) 運転管理体制の強化
新法人の安全確保を万全とするため、以下のとおり、組織面、人事面等から安全確保のための体制の刷新を図る。
-
1) 運転管理部門の独立
動燃の組織において研究開発偏重の傾向があったことを踏まえ、新法人においては、プラントの安全な運転管理を徹底させるため、運転管理部門を組織として独立させ、役割分担を明確にして、万全な体制で施設を運転する。2) 運転管理部門への民間能力の活用
新法人の施設の運転管理に広く人材を糾合し、万全な安全確保を図るため、民間との積極的な人事交流を通じ、運転管理に民間能力を活用する。その際、外部からの出向者の処遇に十分配慮するとともに、新法人の職員を民間プラントの運転現場に派遣するなど活発な人事交流を実施する。3) 請負会社との関係の改善
運転保守部門における新法人の職員と請負作業員との関係を改善し、一層の安全確保を図るため、新法人の職員と請負作業員との責任関係を明確にするとともに、請負作業員への十分な情報提供等により、職員と請負作業員とが一体感を持って仕事に従事できるような環境を整える。その際、各施設ごとに請負作業員の規模の適正化に配慮する。4) 運転員等の処遇改善
運転員や保守業務従事者が意欲と誇りを持って業務に従事することが安全確保の重要な条件であることに鑑み、電気事業者の原子力発電プラント運転員等の処遇を参考として、適切な改善を図る。5) 教育・訓練の徹底
過去の教訓を適切に活用しつつ、実災害等への対応が確実になされるよう、職員、請負作業員を問わず、運転・保守従事者全体に対して、安全管理と危機管理の徹底した実践的な教育・訓練を実施するとともに、その結果を安全確保のための体制、マニュアル、その後の教育・訓練等に反映させる。(2) 安全確保の基盤整備
以下のとおり、新法人において、安全確保を支えるハード・ソフト両面からの十分な基盤を整備するとともに、科学技術庁においても安全監視体制を強化する。
-
1) 施設・設備のメンテナンス
施設・設備の老朽化への対応のため、現在動燃において実施されている「もんじゅ」の安全総点検や必要に応じ主要施設について安全性一斉点検を実施し、その評価結果を踏まえ、施設・設備の着実なメンテナンスを実施する。また、安全確保上重要な設備、装置に対しては、最新かつ信頼性の高い技術を積極的に活用する。2) 安全確保支援部門の確立
組織横断的な安全確保を強化するため、安全確保支援部門を外部人材も含めた専門的で優秀な人材を結集して組織し、安全確保対策の事業所間の水平展開、事業所横断的な安全確保や安全面での点検評価の実施、マニュアル整備のための指針の作成、要員の教育・訓練の実施、全社レベルでの安全品質保証活動等を実施する。3) 一般防災への視点の強化
今般の一連の事故は、危険物、可燃物等の取扱いや消火確認等一般防災に対する認識不足が大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、放射線防護等の原子力に固有な安全対策に加え、一般防災の考え方をマニュアルに取入れるとともに、化学プラントの事故例等を含め、一般防災を十分に考慮したデータベース等を整備する。また、外部専門家の招聘等により、一般防災への対応を強化する。4) 事故教訓の学習と反映
安全確保に向けて細心の注意を払うことは当然であるが、常日頃より、明らかになっていない技術や組織に隠された問題を究明し、一層の安全確保に努めるため、各種の実験から得られたデータはもちろんのこと、各事業所内で生じた軽微なものを含む種々の事故例、民間や海外を含めた他機関における事故例等を徹底的に研究するとともに、その結果を整理・蓄積し、安全確保対策や教育・訓練及びマニュアルに反映させる。5) 第三者的な安全評価の実施
科学技術庁は、新法人の安全確保に対する努力を支援するため、非原子力分野を含む安全分野の専門家チームによる第三者的な安全評価を実施する。(3) 危機管理
日常の安全確保対策を通じ、事故の未然防止を図ることは基本であるが、事故が起こった場合に備え、事前に対応策を確立しておくことが極めて重要である。このため、新法人においては、以下のとおり、万全な危機管理体制を確立する。
-
1) 事故時の動員体制の整備
事故時の迅速な動員体制を確保するため、予め、各事業所や施設ごとに緊急時に対応すべき要員を指名し、これらの要員に対し、抜き打ち形式等により、実災害等に即応しうる訓練を徹底して実施する。2) 危機管理マニュアルの整備
事故時の対応と事故後の対応はおのずと異なるものであり、また、特に、役員、関係部署の職員、動員された職員等の役割分担も事故対応の極めて重要な要素であることから、事故自体への対応とその後の推移に応じた対応要員の行動を明確化し、十分な連絡体制を確立するなど、適切な事故対応マニュアルを整備する。3) 緊急時対応のための施設・設備の整備
事故時に直ちに対応体制を確立し機能させるため、各事業所や施設ごとに、緊急時にセンターとなる施設を予め整備するとともに、的確な事故情報の伝達等をなし得るよう、テレビ会議システム等の設備を整備し、緊急時情報システムを構築する。 - 社会に開かれた体制
(1) 広報・情報公開
新法人が社会に対して開かれた体制となるには、事業目標や活動状況について常に公表し、国民の理解を求めるとともに、外界の反応を得ることが不可欠である。従って、新法人による広報や情報公開は、単なる対外的なサービスではなく、組織自らが存在するための条件であり、情報の発信に対する社会からのフィードバックを得て、適切に状況の変化に対応することが重要であり、以下のとおり、広報・情報公開の強化を図る。
-
1) 広報の強化
的確かつ質の高い広報の実現には専門性が要求されることから、外部での研修や訓練に参加すること等により、広報の専門家を育成・確保するとともに、外部専門家を活用するなど人材面から広報体制を強化する。また、渉外、広報、報道対応等対外的な機能を再検討し、広報関連部門を統合するなど広報の一元化を図る。さらに、インターネット等を活用した高度な情報通信機能の導入を図るなど設備を含めた広報のための基盤を整備するとともに、外部の関係機関との連携を図りつつ、より効果的な広報活動を実施する。2) 情報公開の徹底
極力個人の判断が関与しない明確な情報公開の基準を設定するとともに、公開情報の内容を簡単かつビジュアルにするなど国民にとって極力理解しやすいものとする。また、所要のインフラを整備し、平時、事故時を問わず適時・的確かつ信頼性の高い情報公開を実施し、組織として高度な透明性を確保するとともに、研究開発の成果の積極的発信に努める。(2) 開かれた研究開発体制
核燃料サイクルの研究開発は、総合的な技術体系を必要とするものであり、新法人においては、広く国内外の各専門分野の人材を結集し、均衡よく配置された体制で研究開発を進めるとともに、国際貢献等を積極的に推進し、核燃料サイクルの世界的拠点となることを目指し、以下のとおり、開かれた研究開発体制を確立する。-
1) 他分野の技術成果の活用
原子力開発利用は従来より総合技術体系として推進されてきたが、情報通信技術等、最近の他分野での技術開発の進展には目覚ましいものがあり、これらの優れた技術成果を一層積極的に取り入れるよう努力する。2) 開発成果の社会への還元
社会に開かれた事業展開を図るため、新法人に蓄積された事業の成果に関し、原子力関連分野への活用を積極的に進めていくことは当然として、それ以外の幅広い分野への活用を促進する。3) 国際貢献・国際協力
新法人の技術、資産を活用し、積極的な国際貢献、国際協力を実施するため、新法人の成果をアジア諸国をはじめとする世界各国に積極的に発信するとともに、外国人研究者等の採用や招聘制度等の充実を図る。4) 任期付任用制度の導入
広く人材を糾合するため、国内外の研究者、技術者、安全管理の専門家等を一定期間職員として採用する任期付任用制度を導入する。5) 大学等との連携
我が国の研究ポテンシャルを結集した共同研究、共同開発の推進のため、大学、原研、産業界等の研究者、技術者に積極的に門戸を開放する。また、我が国の原子力開発にとって貴重な技術開発の場である新法人の施設を広く大学等に開放する。(3) 地域社会との共生
新法人は、原子力施設の立地地域の地方自治体、地域住民等の理解、支援がなければ、その事業遂行が不可能であることを十分に認識し、以下のとおり、地域社会との共生に努める。また、科学技術庁は、こうした新法人の活動を充実・強化するために以下の必要な措置をとる。
-
1) 本社の立地地域への設置
新法人は、立地地元重視の観点から、その本社を立地地域に置く。2) 地域社会に開かれた活動の推進
新法人は、事業所施設を積極的に地域住民に公開するとともに、地域が主催するイベント等に組織として積極的に参加し、また、役員、職員が地域に溶け込んで生活するなどにより、新法人に対する地域住民の理解を増進し、地域と共生する。3) 地域住民の信頼感の確立
新法人は、立地地域の住民が安心して暮らせるよう一層の努力を払う。例えば、放射線の環境への影響をより的確かつ積極的に公開することとし、地域の地方自治体及び地域住民に対し、サイト内の環境モニタリング・データをリアルタイムで通報、または表示するシステムの構築を検討する。また、あわせて、きめの細かい、速報性の高い事故情報の伝達システムの構築を図る。4) 原子力防災の強化
科学技術庁は、地域全体の連携を考慮し、事故時に備え、政府(安全規制当局、防災関係機関等)、地方自治体、原子力事業者、医療関係機関等の責任、役割分担について、法制度面を含めて検討を行い、その明確化を図るとともに、その役割に応じた防災活動のための基盤を整備する。また、避難、防災の目安となるような事故想定を明確化し、一般防災の教訓の反映に留意しつつ、効果的な訓練を実施する。5) 地域との連携強化
科学技術庁は、地域との連携の一層の強化を図るため、地域に職員を常駐させるとともに、関係地方自治体との人事交流を積極的に実施する。さらに、事故時において、関係地方自治体等と遅延なく連絡ができるよう24時間通報連絡体制を整備する。また、適切な対応をしうる専門家を現地に迅速に派遣するとともに、危機管理オペレーション機能を整備する。
本委員会は、1997年4月18日に第1回を始めてから、6回の会を重ね、報告書をまとめるに到った。本委員会の使命は、この報告書の提出によって基本的には終了するものと考える。しかし、この3部からなる報告書は、第1部「動燃改革の基本認識」、第2部「動燃改革の基本的考え方」、第3部「改革の実現に向けて」と、その結論は理念的なものから現実的なものへと進展してはいるが、現実的で具体的な改革案の提出には到っていない。それは、開発技術対象やその作業、管理などの業務の詳細について、また実際の業務の現行法規との関連などの詳細については、委員の専門や時間的制約などからいって言及することが出来なかったからである。しかし、改革の基本的方向については、あいまいなところをほとんど残さず規定し得た。そこで、この報告書に基づいて具体的改革案を作成する新法人への改革のための作業部会を本委員会とは別に設置して、作業を遂行するのがよいと考える。
従って、ここに作業部会の設置を別紙のとおり提案する。また、この作業部会の作業の報告を受け、本報告書の内容、改革の基本的方向に沿って、具体的改革案が作られているかどうかを確認しつつ助言することによって、本委員会の使命を全うするため、本委員会は作業部会がその使命を終えるまで存続させることを、あわせて提案する。
(別紙)
動燃改革検討委員会の報告書を踏まえ、動燃の改革の推進と新法人への改組の具体化を図るため、関係各界の協力を得て、作業部会を以下のとおり科学技術庁に設置する。
- 任務
新法人の経営、組織・人事、安全強化、開かれた体制整備など新法人の具体的組織体制及びその実施すべき事業の計画などの具体化の作業を行う。 - 構成
作業部会は、学識経験者を部会長とし、科学技術庁、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所及び電気事業者など各界のしかるべき者を構成員とする。 - 進め方
作業部会に実務者からなるタスクフォースを置き、動燃改革検討委員会の報告書を踏まえ、所要の個別事項について調査検討を行う。
<付 記>
| *当委員会では、少数意見についても報告書本文とは別に付記することが、審議の中で確認されており、それに基づき提出された少数意見が付記1である。 *当委員会では、委員会での審議に資するため、委員の発意による個別調査が適宜実施され、その結果は委員会に報告された。付記2は、個別調査を行った委員による結果報告の際の資料である。 |
(付記1)
<少数意見>
岸田 純之助
- 改革の提案
(1) 日本原子力研究所と動力炉・核燃料開発事業団の大部分とを合わせた新組織を作る。名称は日本原子力研究所とする。
その中に、1)基礎研究局、2)核分裂応用技術研究開発局、3)核融合応用技術研究開発局−いずれも仮称−を置く。次の(2)項に基く動燃は、2)の中に所属する。
新組織の運営に当たっては、それぞれ広い範囲に分散した施設を持っていることもあり、これまでより、これらの活動を独立性の高いものにする。(2) 動燃は解体し、その大部分は上記(1)の新研究所に吸収する。
現在の動燃所属の機関のうち、ウラン採鉱、ウラン濃縮などは、一定の準備期間の後民営化される。「ふげん」も一定期間後廃棄される。再処理施設は、六カ所村で建設中のものが本格的に稼働するまでは、引き続き操業される。 - 提案の理由
(1) 67年の動燃発足後 l0年目の77年4月7日に、再処理以降の、原子力技術後半部の技術体系開発を目的としている動燃にとって、極めて大きな情勢変化が起こった。カーター米大統領が、1)商業用再処理の無期延期、2)高速増殖炉(FBR )計画のスローダウン、3)軍事転用のおそれのない核燃料サイクルの研究促進、4)内外の需要を満たすよう米国の濃縮ウランの増産、5)他国への核燃料供給保証のための国内立法、6)濃縮・再処理の禁輸措置の継続、7)平和利用と核拡散防止を両立させる国際的な枠組み作りについて各国との協議続行、という7項目の原子力新政策を発表、同月末「77年核不拡散法」の特別教書を上下両院に送った。つづいて翌月、INFCE(国際核燃料サイクル評価)の各国間討議を提案した。
こうした米国の強い意向に押されて高速炉開発から撤退する国が相次ぎ、結局、日本を含む数カ国だけが、原子力平和利用技術体系の完成に努力する使命を担う国となった。(2) 更に、80年代に入って地球環境問題への関心が高まり、原子力についても、ウラン資源を出来るだけ十分に活用し、廃棄物の地球への負荷も軽減する、いわば、文字通りの意味での平和利用技術体系開発が求められるようになった。 94年6月決定の「原子力開発利用長期計画」で正式のプログラムとして採用された「先進的核燃料リサイクル技術の研究開発」が、それに応えるものである。
実はこれは、(1)項のカーター提案の3)、「軍事転用のおそれのない核燃料サイクルの研究促進」にも適合する計画である。使用済み燃料に含まれるPu以外の核分裂性物質(マイナー・アクチニド)も取り出して高速炉の燃料とするから、その結果、核不拡散性が高まる。長半減期の物質が燃料として使われるから、高レベル廃棄物の環境への負荷も格段に改善される。
この「原子力長計」の決定と前後して、米国アルゴンヌで80年代からこれと同様な思想のもとに研究開発が進められていたIFR(Integral Fast Reactor)への政府予算支出が停止された。つまり、この分野で日本は唯一の重要な責務を自らに課した国になった。(3) これらの事実は、核分裂を利用する原子力平和利用技術の全体系を完成するための、世界の研究センターともいうべき役割を、日本の国立研究機関が果たさねばならなくなったことを示している。
特に(2) 項の研究開発には、核兵器開発のためのPu抽出装置から発展した、これまで核保有国で利用していた再処理施設とは、方式の大きく異なる再処理技術の開発が必要であり、また高速炉用の燃料も金属燃料あるいは窒化物燃料の開発が要請される。つまりは、未踏の技術領域の開拓が不可欠なのである。純粋な基礎研究から開発の段階までを一貫した、この領域の研究者、技術者を結集した研究開発体制が緊要になっていることを痛感させる。
「原子力長計」が「先進的核燃料リサイクル技術の研究開発」の項で「動燃・原研において必要な試験施設・設備の整備を進めるとともに、試験炉の必要性についても検討していく」と、二つの機関の協力体制を予想しているのは、そうした認識に立っているからだといえよう。研究開発の各段階、「研究」「探索的開発」「試作開発」「製作開発」「実用開発」を一貫して進めていく組織の確立を急がなければならない。
今回の動燃事故あるいは不祥事で直面することになった”危機”を、人材の総結集のための、天の与えた「機会」と受けとめたいのである。 - いくつかの補足
(1) 「原子力長計」では、「先進的核燃料リサイクル技術の研究開発」の進め方について、「今後の具体的展開については、原子力委員会の核燃料リサイクル専門部会において早急に検討を進めることとする」と述べていた。 94年末その最初の会合が開かれ、第1分科会(従来からの高速炉計画の具体策の立案)、第2分科会(先進的核燃料リサイクル研究開発計画の立案)設置を決めた。部会が発足して1年にもならないところで「もんじゅ」事故が起こった。その後この部会は開かれることなく今日に至っている。残念なことだと思う。
(2) 動燃改革検討委員会報告に基づき新設される新組織は、プロジェクト開発の色彩の強いものになると予想される。基礎研究からの積み上げに大きく依存することになる「先進的リサイクル」の研究開発は、むしろ原研を中心に進める方がいいのではないかと考える。
(付記2)
<委員による個別調査結果>
(東海事業所調査を踏まえて)
久 米 均
- 管理者の意識について
1) 自分の立場での論理が強すぎないか。
・第2回の改革検討委員会において資料第2-5号(動燃事業団の業務とその実績−総括表)により動燃の業務の実績の説明が行われたが、動燃で何が開発されたかの説明に終始し、それが我が国の電力事業にどのように貢献しているか、電力側からどのように評価されているかの説明がなかった。顧客不在の開発が行われているとの印象が強く残った。
・5月14日に東海事業所を訪問し、品質管理の状況調査するための懇談を行ったが、その際調査に必要な資料の提出をお願いしたところ、資料の所在場所が懇談の場所から遠いということで提出を渋られた。懇談場所を設定したのは当方ではなく動燃側である。
・改善提案が活発に行われているとの説明を受けた。提案件数は作業者一人当たり年3件とのことであった。これは決して悪い数字ではないが、活発に行われているというレベルではない。一般の民間企業で提案が活発に行われていると云えるのは一人当たり月1〜3件以上の場合である。2) こう在るべきだの論理が強い。事実をそのまま素直に受取めるという態度が必要ではないだろうか。
東海事業所の燃料再処理工程の分析管理室に多くの警報装置が設置されているが、警報装置が作動した場合に、その原因が不明であることはないとのことであった。本当にそうであろうか。管理者は実態を把握しているのだろうか。
複雑なシステム製品においては品質不具合が発生しても、原因調査のために不具合の再確認を行おうとすると、その不具合が発生しないということが少なくない。「再現せず不良」の原因解析をどのように行うかは現在の品質管理の技術的課題で多くの企業でその克服に努力が払われている。
事実を事実として受け止めていく謙虚さが必要ではないだろうか。異常警報が動作すればその原因はすべて分かる筈、消火器が働けば火は消える筈、室内は負圧に設定されているから放射性物質は拡散しない筈など、頭の中での論理が強すぎると、事実はこうある筈だということになり、事実が捩曲げられ、虚偽が発生し、進歩が停止する。
現場、現物での確認が品質管理の第一歩である。 - 管理の方法について
1) 目で見る管理による情報の共有化
工程異常に対する処置はその都度行われており、その状況は担当者、課長レベルまでは把握されているように思われる。しかし、工程異常の内容についての統計的解析が行われていないことは、状況対応の管理であり、事故の未然防止に対する体系的アプローチが充分でないことを示唆する。パレート分析、管理図、時系的グラフなどによる目に見える管理の導入を行い、作業者、管理者が情報を共有化することが必要である。現在のような体制で部門の長はどのようにして現場の状況を把握しているのであろうか。2) 率先垂範
組織の長は自ら率先垂範するのではなく、問題があれば受けて対処するというマネジメントの体質があるように思われる。待ちの姿勢では現場を充分に掌握することが難しく、緊急時の対応力が弱くなる。各部門の長は積極的に現場を把握し、その管理レベルの向上をはかっていくことが必要である。3) 変更管理
完成度の高い作業ではその管理の重点は
作業者の教育・訓練
設備の保全
変更管理
発生した異常の原因究明と再発防止
の4つである。この中で変更管理の体制が弱いように思われる。改善あるいは変更の内容によって班長、課長、部長、工場長の誰が承認するか、変更結果の副次的影響の評価をどのように行うかを明確にし、変更管理体制を確立することが必要である。不用意な改善・変更が大きなトラブルを招いた例は極めて多い。
(インタビュー調査に基づく所見)
| 野中郁次郎(動燃改革検討委員会委員) 鎌田伸一(防衛大学校) 梅本勝博(北陸先端科学技術大学院大学) |
- インタビュー調査の概要
以下のスケジュールで4回に亘るインタビュー調査を実施し、動燃事業団の経営・組織改革に関わる情報を聴取した。第1回:4月25日(於:一橋大学)
本社経営改革本部関係者3名より動燃事業団の概要に関する説明を受け、インタビューでの聴取事項及びスケジュールにつき調整を行った。第2回:5月2日(於:動燃本社)
各部門の技術者11名より担当部門のミッションに関する説明を受け、他部門との連携、民間への技術移転の可能性、経営改革への認識などにつき質疑を行った。第3回:5月9日(於:動燃本社)
本社経営改革本部、技術協力部等の関係者4名よりFBRの意義と他の技術的オプション(小型炉等)に関する説明を受け、また動燃内部で昭和62年に策定された「中長期事業計画」に関する説明を求めた。第4回:6月12日(於:動燃本社)
昭和62年「中長期事業計画」の策定に携わった関係者3名より、策定時の問題意識およびその後の実施状況につき聴取した。 - 所感
動燃側からの説明では個々の部門のミッションに関する説明に多くの時間が割かれたが、われわれの質疑は、そのミッションを運用する組織の側面に向けられた。その際、可能な限り動燃関係者としての利害を離れた現状認識を聴取できる問題に焦点を絞り、様々な角度からの仮説を投げかけ、それに対する判断ないし意見を求めるという方法でインタビューを進めた。(1)技術者の意識から窺える問題点
われわれの面接した技術者の間では、その担当部門によって差異はあるものの、概して以下のような認識が共有されていたと思われる。1) 動燃における基礎研究は実用化研究と並行して行うことによって効果的に推進できる。
2)研究に必要な知識は、しばしばルーティンな仕事の中で蓄積される。
3)動燃においては特定の事業目標に関わる問題解決に寄与することが研究者の任務であって、その点が主に論文によって成果を問われる他の機関(例えば原研)とは異なる。
4)リスクを伴う研究開発のミッションと、放射能を絶対に出してはならないという危機管理の間で、常にダブルバインド(二重拘束)の状況に立たされている。技術者らは研究開発の効率の側面から1)の点をかなり重視しており、今回の組織改革によって部門間の相互作用が阻害される可能性への危惧も見受けられる。他方、動燃全体としては部門間の相互作用を統合的に管理する視点が欠けている(この点は部門間での計画的な人事交流が少ないことや、プロジェクト管理が一般に縦割り組織で行われていることなどに端的に反映されている)ため、各部門が部分均衡的な解を求める傾向にある。
3) に象徴されるような動燃の「軍隊組織的」な体質は、日本における原子力開発の前線を担っているというプライドを技術者に持たせる一方で、個々の技術者の個性を重視する人材育成を困難にしている側面も見られる。技術者の間からは、しばしば明確なビジョンないしシナリオが提示されることや、強いリーダーシップへの待望の声も聞こえてきたが、それが動燃の中から出現することが始めから断念されている点に、むしろ本質的な問題があると思われる。
概して、今日の動燃の技術者らは、自らの担当する研究開発の将来に夢を持ち難い状況に置かれている。この問題は、昭和62年「中長期事業計画」が動燃内部で策定された当時から、団法改正の焦点の一つであった研究テーマ発掘等における裁量権の確保が、今日に至るも実現されていないことに根ざしている。
4) に関連する問題として、運転部門における危機管理のみならず、研究部門の危機管理に対してもTQC的な発想で対処する傾向が指摘できる。本来、研究開発は不確実な領域を確実なものに転化する活動であり、当初の予想ないし仮説通りにいかないというリスクを抱え込んでいることなどから、TQC的発想に基づく管理には馴染まない性質を有している。それにも関わらず、動燃の研究開発がとかくTQC的な視点からの批判にさらされてきたことは、研究開発における動燃のミッションの定義が曖昧であることに起因している。(2)組織特性
動燃には、特殊法人であることから、以下のような組織特性がみられる。1)ドメインの空間的特性:産学官の狭間にあるスキ間組織である。
2)ドメインの時間的特性:プロジェクト志向で、時限付きの性格を持つ。
但し、そのプロジェクトの時間的スパンは極めて長く、機能部門ごとの縦割り組織で管理されているという特質を持つ。)1) の特性から、動燃の事業には多様なステークホルダー(利害関係者)が関わっているため、組織外部との調整機能を担うトップ・リーダーの役割が、とりわけ重要となる。
また、2)の特性から、環境の変化に応じてプロジェクトのスクラップ・アンド・ビルドにかかる経営判断を行い、縦割り組織を統合する強いリーダーシップが必要となる。
しかし、近年の動燃は、このような機能を担うトップ・リーダーが不在ないし経営トップとしてのリーダーシップを発揮し難い状態にあった。 - 若干の提言
(1)研究開発型組織としてのミッションの再定義
動燃事業団の役割は極めて多岐に亘っているため、本来ナショナル・プロジェクトとして行うべきミッションは何かという観点から、組織目標を再定義する必要が認められる。組織改革の基本的な方向としては、「高速増殖炉及び新型転換炉並びに核原料物質及び核燃料物質に関する」研究開発までを行う中核機関としての性格を明確にし、この枠を超える事業については、すでに技術移転が進んでいる部分に限らず、民間部門へ移管することが望ましい。
(高度に政策的なレベルでの危機管理を要請するプルトニウム燃料加工、および超長期的な視点からの管理を要請する高レベル放射性廃棄物処分は、本質的に民間部門による運営に馴染まず、移管の対象からは除外すべきであろう。)
ただし、この方向で組織改革を進めるに当たっては、以下の点に十分な配慮を行う必要がある。(2)強いリーダーシップと裁量権の確保
組織改革は単に外圧的に行うだけではなく、改革に向けた自己組織性が機能するような環境を作り出す必要がある。このため、再定義された動燃のミッションにおいては、従来以上に裁量権を持たせ、強力なリーダーシップが機能する余地を設けるべきである。
強力なリーダーシップは、既述のように、多様なステークホルダーとの間での調整機能、プロジェクトの統合機能を担う上でも重要である。(3)技術者集団としての特性を活かすための組織改革
動燃は「多量の核物質と高レベルの放射性物質を取り扱ってきた経験を有する技術者集団」であり、その特性を国の知的資産として活かすことを改革の指針として、教育訓練システムを含む人事制度の見直しなどを行うべきである。(4)ミッション間の相互作用への配慮
研究開発のプロセスにおいては、基礎研究と実用化のための技術開発がパラレルに進められることによって、ミッション間で有用な情報交換が行われる場合がある。そのような重複的なプロセスが不可欠な技術課題については、実用化の目途が立ったミッションを機械的に切り離して民間部門に移管することが、かえってプロジェクトのリードタイムを遅延させたり、知識ベースの活用を阻害する場合もある。したがって、民間移管の対象となる業務については、それが研究開発と密接な相互作用を持つものであるかいなかを、予め検討しておく必要がある。
また、民間移管の対象となる部門の保有する施設設備については、研究設備として有効利用すべき余地があるかどうかを検討する必要がある。(5)アウトソーシング(外部委託)等の見直し
動燃として行うべき研究開発については、基本的に組織内部で行うことによって知識、経験を蓄積していくことが肝要であり、そのために必要な予算措置および人材の確保はむしろ積極的に講ずるべきである。適切な予算と内部人材のバランスを欠くことによって、本来組織内部で行うべき業務が作業委託によって賄われたり、出向に依存する構造になると、それは動燃のミッションを再び曖昧にする原因ともなる。
(今回事故の発生した施設がいずれも作業委託比率ないし出向依存度の高い部門にあったことが事故原因の組織論的側面に関連したものであるかどうかは、現時点では判断できないが、留意すべき論点である。)(6)研究開発成果の公開および技術移転の促進
研究開発型組織としての動燃の成果については、対外的な公表、開示のための活動を一層充実させ、広く国内外からの研究評価を受けるようにするべきである。
このことは、動燃の扱う先端技術の中から、民間部門における技術開発への応用が可能な分野を抽出する上でも、一つの端緒となるであろう。すでに若干のケースが複合材料分野の技術などでは見られたとは言え、先端分野における民間への技術移転は、動燃の知的資産を活用していく上での今後の大きな課題であり、そのために必要な制度上、予算上の措置を講ずるべきである。
なお、研究開発をめぐる国際協力については、上記の観点からもさらに推進されることが望ましい。(7)社会科学的な視点の導入
既述のように動燃の改革は研究開発型組織としてのミッションをより明確にする方向で検討すべきであるが、その際、緊急時における情報公開のあり方を含む危機管理や、原子力に関する国民的合意形成についての社会科学的な研究も、動燃の研究課題の一環として自主的に行うことが期待される。危機管理等に関連する(失敗も含めた)動燃の経験から、国家・社会が学習すべき教訓は少なくない。付記:原研との統合案に関するコメント
組織改革の基本的な方向に関する意見を集約した結果によると、「現存の事業を抜本的に見直し、部分的に解消、移管し、残った部分で動燃を再出発」および「原研と動燃の大部分を統合」という対立する二つの案が提起されている。
後者の案には、かつて原研で行われていたFBRの研究が動燃に移管された経緯などを振り返ると、原子炉の研究から開発までを一貫して進める体制の確立という観点からみて合理的な要素も含まれている。
しかしながら、われわれが動燃関係者に対して行ったこれまでのインタビューの結果から判断する限り、基礎研究を主なミッションとする原研と、新型の炉等の開発までをミッションとする動燃の間には、組織文化の上で大きな隔たりがあり、両者を有機的に統合することは事実上困難であると思われる。
例えば、動燃の基礎的研究課題は既存の燃料施設等との連携の下で効率的に運営されてきた側面があり、これを切り離して研究部門のみを一つの部局の下に統合することが果たして知識の結集につながるのかどうかには多くの疑問が残る。
また、両者におけるミッションの差異は、研究者の主要なアウトプットに対する認識の差異(原研では学術論文等、動燃では個別の事業目標に関わる問題解決)にも端的に反映されている。
こうした組織文化的側面の融合も含めた有機的な再編が不可能であるならば、両者の統合は、現在の動燃において組織改革の焦点とされるべき課題の解決に逆行する現象を生む可能性もある。すなわち、それは組織の単なる肥大化をもたらすことにより、
1) 研究開発における目標、ミッションの定義を曖昧にし、
2) 組織運営における柔軟かつ迅速な意思決定を阻害し、
3) 一貫した研究評価システムの導入を困難にする
といった現象に帰結するかも知れない。
これまでの原子力政策の文脈の中で動燃の知的資産を最大限に活用することを組織改革の指針とするならば、原研との統合案に伴う以上のようなリスクは大きすぎるのであり、より現実的な改革案として、現状の事業を抜本的に見直した上で動燃を再出発させる途を選択すべきであると思われる。
現地調査報告
矢野 浩一郎
調査日 :平成9年5月19日
調査対象:動燃事業団東海事業所、東海村及び茨城県
- 動燃事業団東海事業所
説明者 :所長・副所長・安全管理部長ほか
調査事項:アスファルト固化処理施設を中心とする安全管理体制について○ 聞きしにまさる大規模な施設。新しい技術の研究開発とあわせて半ば経常化した業務を含め、組織も複雑巨大化。原子力利用の発達とともに膨張してきたものであるが、約3000人の従事者のうち過半数は協力会社等との作業請負契約に基づく技術員により業務が処理されている。
○ 事故が発生したアスファルト固化処理施設についてみれば、その運転体制は1班7〜8人の4班編成による3交代制であるが、各班のチーフ(班長)は「嘱託」であり、チーフ(班長)を除く作業メンバーは全て「作業請負契約」に基づく技術員であり、各班全体を通じての統括責任者のみが正規職員を以て充てられている。形式上は事業団の責任による業務処理であっても実質的には業務委託に近い状態と言えよう。
○ 業務全体の膨張に伴う必要な人員の確保が困難であったことから、このような作業請負契約による技術員への依存が大きくなったのであろうが、そのため、原子力施設としての核心になる業務部門についてはできるだけ正規職員を配置し、放射性廃液処理というような周辺部分の業務については作業請負契約に依存するという結果になっているものと思われる。これら技術員にはもちろん熟練者も含まれているのだろうが、しかし、このような周辺部分の業務を含めて特に現場の責任と能力を重視する姿勢を組織全体に行きわたらせるという意識が薄かったという印象を受ける。
○ 事故発生の原因となった廃液処理設備の稼働条件の変更も、実験室での実験でなく、危険物質を扱う実機を用いての実験的処理である以上、より細心の管理上の注意を以て行われるべきであるにもかかわらず、あのような事故に至ったのは、現場の責任体制への配慮が不足していたことを意味する。
○ 動燃事業団は、原子力に関するに日本最大の知識技術集団であるだけに、核物質の防護や放射能への警戒規制などの安全管理の面には、高度の知識技術による細心の注意が払われているが、しかし、一方で危険物・可燃物という一般の化学物質をも多量に扱う化学工場としての安全管理に関する意識及び知識技術の徹底が甚だ不十分であるという印象が強い。
爆発事故の直接の原因となった火災発生に際して1分間の注水をもって消火完了とした不徹底さは、基礎的な消火活動の知識技術を欠くものである。処理設備開発の初期の段階では、完全消火に8分間の注水を要するということも実験を通じて示されていたようであるが、その後このような消火活動のノウハウの実践的継承も行われていなかったことになる。
また、事故の再発防止のために最も大切な事故原因の調査に手間取っているのは、事故発生後の対応の不手際や事実隠しなどの非常識な行動に起因するところが大きいが、これも危険物を扱う化学工場としては絶対に必要な防災上の心構えと基礎的知識を欠くことによるものと言わざるを得ない。○ 自衛消防組織は、全体を統括する消防班長(1名)の下に1班8名(チーフは副班長)の3班で編成され、消防車・化学消防車各1台を有する。メンバーは専任ではなく、本来業務との兼任である。訓練は月2回程度。村内の水害に際し出動した経験もあり、村当局から感謝状を受けているが、今回の事故に際しては午前の火災時には呼集・出動は行われていない。夜の爆発の際は、呼集は行われ待機したが出動はしなかった。
○ 廃液処理施設の建物の構造については、放射能の封じ込めという面では必要な配慮がなされているが、爆発により窓ガラスや扉が破壊されたことからみて、爆圧に耐え得る設計にはなっていない。事業所側の説明によれば、そのような爆発事故は未然に防止するという前提に立っており、いわば盲点を突かれたとのこと。
○ 事業所の説明によれば、安全管理に関する教育・訓練は年間を通じて数多く実施されており、また安全管理を含めた業務改善についての職場の小グループ活動なども行われている。にもかかわらず、今回のような事故及びその処理をめぐってさまざまな問題を引き起こしたのは、それらの教育・訓練・活動が内部の世界に閉じこもっており、化学工場の安全管理に関する最新の知識技術の吸収など外の世界に目を向ける積極的姿勢が足りなかったため、緊張感や真剣さに欠けるところがあったことによるものではないか。それは事業団そのものの閉鎖的性格に起因するものとの印象を受ける。
- 東海村
説明者 :村長・企画総務部長・消防署長
調査事項:事故発生時の情報連絡体制等について○ 今回の事故発生に際し、地域住民の安全確保の責任を持つ村当局として最も困惑し、不満が強かったのは、事故の内容や規模、その及ぼす影響等についての迅速かつ正確な情報が容易につかめず、住民の安全を護るための態勢の取りようがなかったということである。
東海村としては、事業所と役場の間の電話連絡では到底事足りずと見て、消防車を急きょ現場に出動させ、指揮者が直接情報を集め、状況を把握して備付けの無線電話で直接役場へ連絡しようとしたが、混乱する現場の中で結局思うように行かなかったとのこと。○ 県、所在町村および隣接市町村と事業所との間に締結されている原子力安全協定によれば、原子力施設にかかわる異常事態や事故の発生については、事業所側から村への報告連絡が行われることとなっており、平成元年度以降の報告件数は、事業所側の記録によれば、異常事態の発生が年間1〜4件、事故・故障等が平成6年度の7件を除いては年間1〜2件で、いずれも大事には至らない軽微なものであったが、今回のような相当規模の事故の発生に際して、安全協定の最も大事な部分である迅速的確な情報連絡に関する取り決めがその機能を果たさなかったこととなる。
○ 事業所と消防機関との関係は、毎年の合同訓練と年1〜2回の教育訓練への消防職員の派遣のほかは、消防機関が事業所の業務管理に関与することはほとんどない。東海村消防機関にとって動燃事業団等の原子力施設はあまりにも巨大過ぎ、頼りにするのは結局、原子力安全協定による迅速的確な連絡通報であり、今回の経験にかえりみ、政府の責任ある機動的・即時的情報連絡体制を整備して欲しいとの要望があった。
○ また、動燃事業団の改革に際しては、東海村の経済や雇用の面での原子力関係のシェアの大きさ、国家政策に協力してきた地元の立場に十分配慮して欲しいとの要望があった。
- 茨城県
説明者 :生活環境部長、同参事、原子力安全対策課長、消防防災課長ほか
調査事項:今回の事故に対する県としての所感・安全対策に関する考え方等について○ 今回の事故は、放射性物質を扱う化学工場の安全管理体制の欠陥という点で県民に大きなショックを与えたが、その大きな要因は、初期情報の混乱にあった。放射能という不可視的なものを対象にするだけに、地域社会として敏速に対応するために、政府の機動的常設チームによる情報の一元的管理についての体制の整備が求められる。
○ 日本における原子力利用発祥の地として、茨城県では昭和38年から地域防災計画の中に原子力防災計画を策定するなど、原子力防災対策に力を入れてきた。現在の安全対策は、原子力安全委員会の指針など、国の指導の下に行われているが、もっと国が主体的・積極的姿勢を発揮して欲しい。
○ そのためには、原子力防災に関する特別措置法の制定によって、国・県・市町村の役割分担を明確化し、また安全協定についても法的根拠を置いて地域社会に対する事業者の責任を開かれた形ではっきりさせる必要があるのではないか。
○ 県としても、原子力対策所管部門と消防防災所管部門との連携の緊密化、国の原子力担当機関との人事交流などにより原子力防災対策の充実を図っていく。
<付 録>
(付録1)
平成9年4月11日
科学技術庁
- 開催の趣旨
一昨年のもんじゅ事故に続き、先月、東海再処理施設アスファルト固化処理施設で、火災爆発事故を引き起こした動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)の体質及び組織・体制について、徹底的に第三者的なチェックを行い、抜本的な改革を図る必要がある。
このため、動燃の組織・経営管理、情報伝達・広報、施設の管理、危機管理体制等の業務の現状全般について、聖域を設けず見直しを行い、動燃改革についての考え方のとりまとめを行うこととし、以下のとおり「動燃改革検討委員会」(以下「委員会」という。)を開催する。 - 調査検討事項
(1)業務の抜本的な見直し(下請け問題を含む)
(2)設備の保守点検の進め方と老朽化対応
(3)本社業務と現場業務の適切化と連携強化
(4)職員のモラルと能力の向上と体質の改善
(5)事故時等の緊急時における対応の見直し
(6)周辺地方自治体との連絡通報体制整備
(7)その他 - 構成員
別紙のとおり。 - その他
委員会は、公開で行う。
(別紙)
| 座長 | 吉川 弘之 | 前東京大学総長 |
| 今井 通子 | 医師・登山家 | |
| 岸田 純之助 | (財)日本総合研究所名誉会長 | |
| 久米 均 | 中央大学理工学部経営システム工学科教授 日本工業標準調査会ISO部会部会長 元日本品質管理学会会長 |
|
| 那須 翔 |
(社)経済団体連合会副会長 |
|
|
野中 郁次郎 |
北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科長 一橋大学イノベーション研究センター教授 組織学会会長 |
|
|
古川 昌彦 |
(社)経済団体連合会副会長 化学工学会会長 |
|
|
矢野 浩一郎 |
市町村職員中央研修所学長 元消防庁長官 |
|
|
吉澤 康雄 |
東京大学名誉教授(医学部) |
(敬称略)
(付録2)
第1回(平成9年4月18日(金))
(1)動燃改革検討委員会の開催について
(2)動燃事業団の経営の現状と課題
(3)動燃改革に関する主な論点について
(4)自由討議
(5)動燃改革検討委員会の今後の進め方
(6)その他
第2回(平成9年5月12日(月))
(1)事故報告
(2)今後の検討項目の整理
(3)核燃料サイクルと動燃の事業
(4)動燃事業団における管理運営体制について
(5)その他
第3回(平成9年6月6日(金))
(1)委員及びコンサルタントによる調査状況報告について
(2)動燃改革の基本的方向性について
(3)その他
第4回(平成9年6月17日(火))
(1)委員及びコンサルタントによる調査の報告について
(2)動燃改革の基本的方向について
(3)その他
第5回(平成9年7月7日(月))
(1)コンサルタントによる調査の報告について
(2)動燃改革検討委員会報告書(素案)について
(3)その他
第6回(平成9年7月30日(水))
(1)動燃改革検討委員会報告書(案)について
(2)その他