課題番号:2001
高知大学理学部
南海地震震源域のセグメント構造と長中期的発生予測
南海地震のような巨大地震の場合は破壊域が一様に形成されるとは考えにくく、マルチプルショックとして何回かに分かれて破壊が進行すると考えたほうが妥当であろうし、既にこのことを示唆する論文も公表されている。現在入手できる観測データに基づき想定したセグメント構造に種々の点からアプローチを行い、南海地震のマルチプルショックの可能性を求める。また、フィリピン海プレートの沈み込み口である南海トラフの形状が単純であるのに対し、マントル最上部地震の震源分布の傾斜方向や走向は、紀伊半島、紀伊水道、四国東部、四国西部では大きく異なっている。このような複雑な震源分布とセグメント構造とを対比させて将来の南海地震の発生機構の手がかりを得る。これまでの結果およびこれらの特徴を考慮して到達目標を以下に列挙する。
(平成18年度の計画の位置付け):平成18年度は5ヵ年の到達目標のうち、第1項目の南海地震震源域のセグメント構造についてb値などによる区分けが可能かどうか更に検討する。第2項目のS波スプリッティング解析により時間変動成分検出の可能性を検討し、コーダQについては19年度以降に行う。引き続いて第2項目の地震活動度の時間変化に基づいて次の南海地震発生に至る過程を推測する。
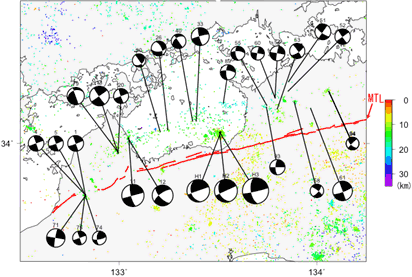 |
| 図1 |
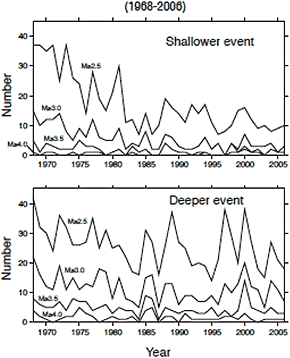 |
| 図2 |
木村昌三・久保篤規・川谷和夫(高知大学理学部)
金沢大学自然科学研究科、平松良浩