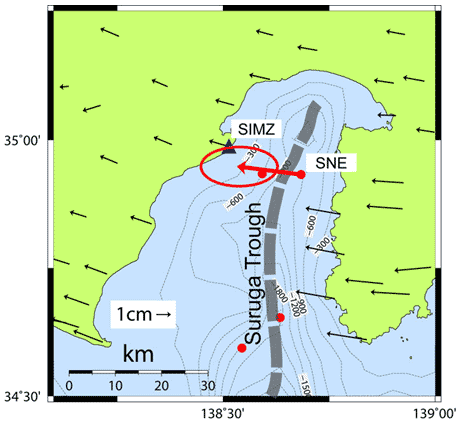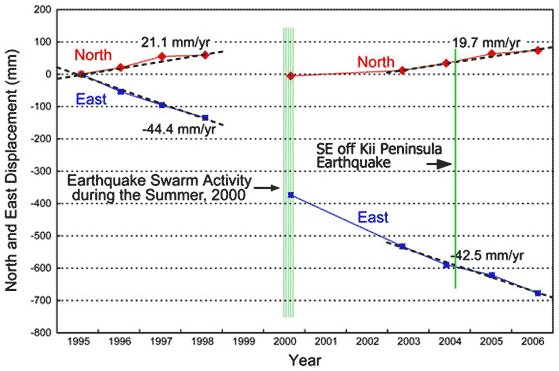(2)研究課題(または観測項目)名
東海地域でのプレート収束速度・カップリングのモニタリング
(5)本課題の平成16年度からの5ヵ年の到達目標と、それに対する平成18年度実施計画の位置付け
本研究課題では,駿河トラフでのプレートの収束速度やカップリング状態のモニタリングを行うために,以下の新たな地殻変動観測を行う
- 1)海底地殻変動観測
駿河湾内に4カ所(既設の3カ所を含む),御前崎沖に2カ所からなる海底地殻変動観測網(海底局網)を構築する.それぞれの海底局について年間3回程度のくり返し観測を実施し,5年間で駿河トラフでの詳細な変位速度場を明らかにする.
- 2)リアルタイム・キネマティックGPS観測
御前崎,浜名期,三河湾に新たにGPS観測点を設け,10キロメートル程度の基線でRTK観測を行う.これは,名古屋大学で約20年間続けていた光波測距をGPSに置き換えたもので,RTK観測により時間分解能を上げることができる.
- 3)銭洲岩礁および神津島でのGPSキャンペーン観測
駿河トラフでの収束速度を議論する上で,最近その存在が示唆されている伊豆マイクロプレートを無視できない.そこで,銭洲岩礁と神津島で初年度から年2回のGPS観測を行い,銭洲リッジ周辺におけるプレート収束速度を実測し,5年間の観測結果から伊豆マイクロプレートが駿河トラフでのプレート収束速度に与える影響を評価する.
(6)平成18年度実施計画の概要
- 1)海底地殻変動観測
海底局位置決定精度を向上させるとともに,御前崎沖に2カ所からなる海底地殻変動観測網(海底局網)を構築する.
- 2)リアルタイム・キネマティックGPS観測
御前崎,浜名期,三河湾に新たにGPS観測点を設け,10キロメートル程度の基線でキネマティック観測を開始する.
- 3)銭洲岩礁および神津島でのGPSキャンペーン観測
銭洲岩礁と神津島で年1〜2回のGPS観測を行う.
(7)平成18年度成果の概要
- 1)海底地殻変動観測
駿河湾内での海底地殻変動観測の結果,図1のように,年間約3cm/yr(センチメートル毎年)の変位速度の観測に成功した.なお,図1は,GEONETの彦根を固定したときの変位ベクトルで,陸上の変位ベクトルは,国土地理院GEONEによる2005年6月15日から2週間の座標平均と2006年7月15日から2週間の座標平均との差である.
駿河湾内での観測に集中したため,御前崎沖への海底局網設置は見送った.
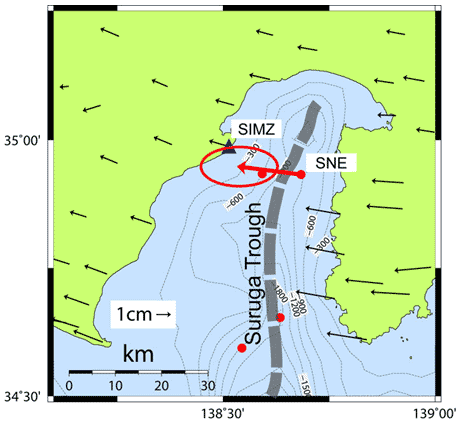 |
| 図1 駿河湾観測点における変位ベクトル(彦根固定) |
- 2)リアルタイム・キネマティックGPS観測
観測網の設置を行う前に,RTK測位の精度評価実験を年度内に実施する.
- 3)銭洲岩礁および神津島でのGPSキャンペーン観測
2006年6月に銭洲岩礁にて臨時GPS観測を行った.過去の解析結果も考慮すると,銭洲岩礁の変位速度は,西向きに43mm/yr(ミリメートル毎年),北向きに19.7mm/yr(ミリメートル毎年)となる(図2).また,南伊豆-銭洲間に10^-7毎年程度の短縮が認められるが,この間にDeformation Frontの存在を支持するものではなく,西伊豆-南伊豆-銭洲の動きは1枚のブロックの運動で表現可能である.
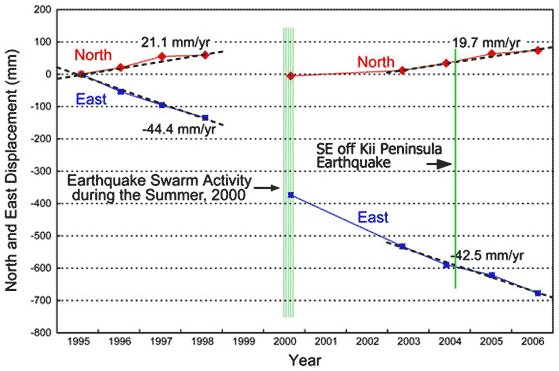 |
| 図2 銭洲岩礁における変位ベクトル.田部井ほか[2006]による. |
(8)平成18年度の成果に関連の深いもので、平成18年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)
(9)実施機関の参加者氏名または部署等名
田所敬一,木股文昭,安藤雅孝,宮島力雄,奥田 隆
他機関との共同研究の有無
高知大学理学部 田部井隆雄
東海大学海洋研究所:佐柳敬造,長尾年恭