課題番号:1603
東京工業大学理工学研究科,火山流体研究センター
全磁力経年変化からみた地殻応力蓄積過程
なし
中長期的には、これまでの基礎研究から得られた成果をさらに発展させ、全磁力観測から日本列島全域における応力変化をモニターする体制を構築する必要があると考えている。ただし、これを大学のみで行うことは難しく、できれば地震調査研究推進本部の基盤的調査観測に準じる観測項目として、例えば国土地理院などが実施することが望ましい。平成18年度はこれまで行ってきた観測研究を継続し、全磁力変化の推移を調べるとともに、群発地震との関連、応力蓄積との関連などを調べた。
これまで同様に、伊豆半島北東部における全磁力観測を継続する。テレメータシステムの改良をさらに進めた。
伊豆半島北東部において、京大防災研究所、東大地震研究所、気象庁柿岡地磁気観測所と共同して、プロトン磁力計による地磁気全磁力値の連続観測を継続して実施した。
図1に伊豆半島北東部における全磁力観測点を示す。観測点(OIS)でこれまで大きな地点差の減少変化が観測されてきた。
図2に2000年から2006年末までの期間の、菅引(SGH)を基準とした各観測点での地点差の5日平均値の変化をしめす。観測点OSNは、図1に示されていないが、気象庁柿岡地磁気観測所による観測点OISの北約1キロメートルに位置する観測点である。伊東東方沖では2006年4月に小規模な群発的な活動が見られたが、その地震活動終結後、OISでの一時的な増加傾向が見られたが2006年末には元の値に戻っている。OSNでも地震活動前後に2nT(ナノテスラ)程度の急激な減少が見られるが、これは、人工的な擾乱の影響である。ABD、YKWでの減少傾向見られる。
観測開始の1989年9月から2007年2月上旬までの、観測点OIS、ABD、および、YKWでの5日平均によるKWNを基準とした全磁力地点差の変化を図3に示す。OISで見られた大きな変化は、上述した変化が見られるほかは、ここ1999年以降は、ほぼ停滞しているといえる。
2観測点での伏角、偏角の大きな違いによる地点差変化の見かけ上の変化を補正する目的で、観測点のセンサー位置で、簡易伏角計による伏角計測を実施した。
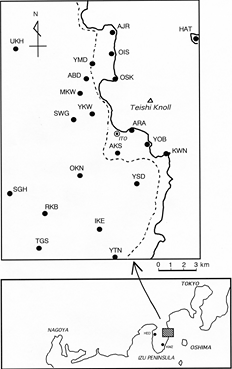 |
| 図1:伊豆半島東部の伊東周辺の全磁力観測点分布 |
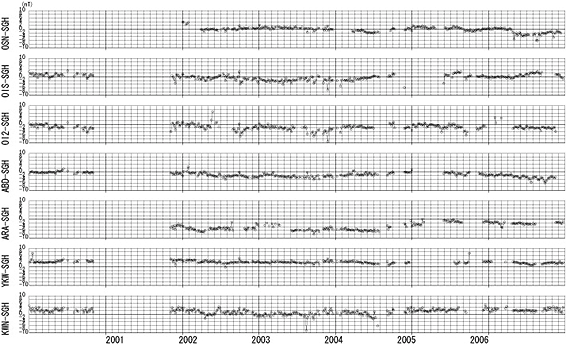 |
| 図2:2000年から2006年末までの期間の、菅引(SGH)を基準とした各観測点での地点差の5日平均値の変化。 |
なし
本蔵義守、小川康雄
有
京都大学防災研究所、東京大学地震研究所、気象庁柿岡地磁気観測所との共同研究(5名)