課題番号:1101
弘前大学理工学部
日本列島の短波長不均質構造と応力分布
本課題では、日本列島規模での構造的不均質と応力分布に関する知見を得ることを5ヶ年の到達目標とする。定常地震観測網で観測される地震波形データを基に地震波散乱強度の空間分布を推定し、速度構造よりも短波長の不均質構造の分布を明らかにする。一方、地殻構造に比して不足している地殻応力の分布に関する情報を得るため、応力テンソル・地表での歪分布・地震活動度それぞれの時空間変化の関係を調査する。
18年度においては、新潟県中越地震の余震観測データを用いて、波形インバージョンから震源メカニズム解を推定し、臨時観測点を展開した震源域北部付近におけるメカニズム解の詳細な分布を得る。それを震源分布、地震波速度構造、地形・地質構造等と比較し、メカニズム解の分布がどのような要因に影響を受けているのかを検討する。また、全国の機関の合同観測として実施されている歪集中帯合同観測のテレメータ観測を継続するとともに、そのデータを用いた震源メカニズム解の決定を行い、中部地方及び歪集中帯におけるメカニズム解の空間分布の特徴把握を行う。それを中越地域での結果と比較し、メカニズム解の分布と不均質構造との関係を検討する。18年度の計画は、応力分布に関する知見を得るという5ヶ年の到達目標に対し、実質的なデータを得るという内容である。
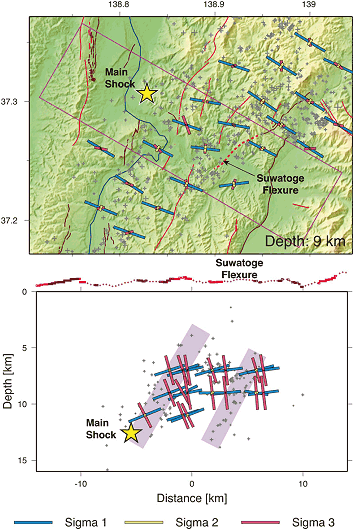 |
| 図1 本震を含む領域における応力テンソルの分布。青・黄・赤の太い棒は、それぞれ最大、中間、最小主応力を表す。平面図は深さ8〜10キロメートルにおけるテンソルを地表に、断面図は平面図の黒線の枠内のテンソルを南西方向から鉛直面に投影したもの。黄色い星印は本震、灰色の十字は統合データの震央、紫色の線は余震列を表す。 |
小菅正裕・村田和則・渡辺和俊・佐藤魂夫・佐藤勝人
データの統合は中越地震の臨時観測を実施した機関との共同研究。