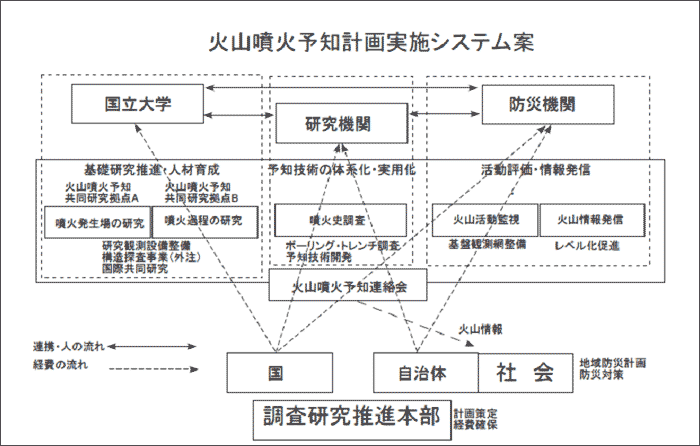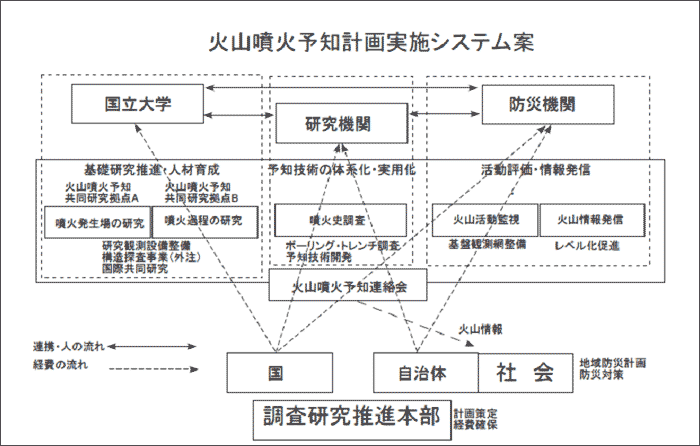《その他》
(実施状況等レビュー結果及び外部評価結果を踏まえ、今後の考え方や取組み等についてご意見をお願いします。特に、外部評価で指摘された下記の項目について、どのように反映していくべきかなどについてご意見をお願いします。)
- ● 法人化後、全く設備費が措置されないために、機器の老朽化が急速に進んでいる。このため、現状の定常的観測を維持するのが困難になってきている。地震予知・火山噴火予知研究では、気象庁・防災科研・国土地理院等の業務機関とは違った視点で大学が行っている研究的観測による成果がその推進に大きな役割を果たしており、それを支える基礎的観測網の維持経費の措置方法を何らかの形で実現しないと、将来的に高品質データの供給、およびそれに基づいた研究の進展が停滞・後退することは確実であり、次期計画においてこれに対する対応策が望まれる。
- ● 秋田大学の地震予知・火山噴火予知研究の基本的な方針は、秋田・東北地域で観測を行い、地域に密着した研究を行うことである。その上で全国的な共同観測に関しても積極的に現地の研究観測作業に参加し、支援を行う方針である。
- ● 火山噴火予知計画では火山体浅部の構造解明に取り組んできた。その結果、雲仙岳では反射法の導入による火道の検出、浅間山では電磁気探査と総合しマグマに関連した構造の検出に成功している。しかし、今後、火山体におけるマグマ蓄積過程を解明するには、地震学分野だけでなく、総合的な観測を高分解能で実施することが重要である。しかも、マグマ蓄積過程の時間変化までを対象として、3〜5年の長期にわたる継続的な観測が重要である。
日本列島で二つぐらいの火山を長期にわたり、集中的な高精度で連続的な観測を研究機関の連携として取り組むことにより、マグマ蓄積過程と噴火ポテンシャルの評価が可能と考える。
本研究計画の評価は,国内外の有識者を集めた外部評価委員会を組織して行うべきである.国際的な基準に基づいた成果の評価が行えるだけでなく,日本の優れた研究成果を国外に向けてアピールする機会ともなる。
- ● 近畿地方中北部では2003年頃から地震活動の低下、GPSによるひずみ速度の変化、地殻変動連続観測の異常などが見いだされ、これらの変化に注意して観測研究を継続している。この地域は新潟-神戸ひずみ集中帯に属している。また、南海トラフの巨大地震の前に地震活動の活発化が懸念されている地域でもある。今後、このような場所において一歩進んだ観測研究を推進することが重要である。近年続発する大地震の際や、跡津川断層帯においては、全国の大学等による大規模な地震、GPSおよび電磁気探査等が実施され、大地震発生域の特性が明らかになってきた。それ以前には出来なかった高密度観測点による調査により成果が上がったわけであり、このような高密度観測を、今後さらに重点的に推進することが重要であると考えられる。
- ● 地震と火山の分野の理解は国の責務であり、世界のトップランナーを目指す
我が国は、大地震のリスクがある地域に人口が集中し、なおかつ高度な経済活動が営まれているという、主要先進国中でも特異な状況にある。ひとたび大地震が発生し、防災・減災の対策が正しくとられていなければ、地震時に国民の生命・財産が失われるだけでなく、国家経済自体も回復困難な打撃を被ることになる。G8構成国において、かつてその首都が地震によって壊滅的な被害を受けた国はなく、今後の危険性においてもまた同じである。大地震の発生は避けられない。火山についても、日本と比較しうるリスクがあるとすればG8構成国中にはイタリアくらいのものである。そのような国であるからこそ、日本は世界においても最も地震と火山のことをよく理解し、正しくそれに立ち向かうようにすることは、国としての責務である。また、そのような観点から、地震と火山に関する学問分野は非常に重要なものであるといえる。ゆえに、この分野において、日本は、世界の最先端を目指し、世界に発信できるようになるべきであると考える。
- ● 海域は陸域に比べデータの蓄積は極めて少ない。これからの観測研究では、海域の調査もより重要になると考える。
- ● 骨子案の中で「1.地殻活動のモニタリングと予測シミュレーションのための観測研究の推進」とあるが、「1地震および火山活動のモニタリング」がよいのではないか?。
理由:「地殻活動」はあまりに広義であり、受け取り方に幅があり、一般になじみが薄いと思う。本計画の実施計画の最初の大項目としては「地震」、「火山噴火」を使ったほうが良いのではないか。なお、予測シミュレーションの実施内容は大項目2がよいのではないか?
なお、地震と火山噴火の計画を一本化するのであれば、本計画の冒頭で、地震予知と火山噴火予知の基本的戦略、基本的考え方を、一本化することを含めて、これまでの経緯と合わせて、明確に述べる必要がある。予測シミュレーション・データ同化などが地震予知の基本的戦略であるなら、この部分で記述するほうが適当であるように思う。
- ● 火山は担い手が現実に確保できるのでしょうか?もっと純粋科学としてなら大丈夫でしょうが。
- ● 地震調査研究推進本部の設置および基盤的観測の構築によって地震予知研究が大きく進展したことにかんがみれば、建議の議論の枠を越えているとは思うが、火山噴火予知実研に向けて国家としての取り組みを強化するため、火山噴火予知調査研究推進本部が設置され、基盤的観測の整備がなされることが必要と考える。
- ● 情報の効果的伝達の手段としてメデイアを活用すべきである。それぞれの機関では、それぞれ工夫して国民への情報公開、情報伝達を行っているが、国民の側から見れば、それらの情報や解説などはまとめて発信してもらうほうが理解しやすい。メデイアに載せる経費も、予知研究計画の予算に限らず、従来各機関がそれぞれに行ってきた情報公開予算の一部を出して一括する。一元化情報の発信と予算の一括のために協議会か何らかの機構を作って活動することが望ましい。この協議会/機構の延長には「地震・火山庁」を見据えるべきである。
- ● 自治体と共同でのNPO立ち上げを除き、上記のような新規の事業を行うためには、予知事業費の大幅増額あるいは新規予算の獲得が不可欠である。予知研究が通常の学術研究と異なり、安全・安心な社会を実現するための国家的・社会的に重要な課題に対応した研究であるので、研究者の自由な発想に基づく研究を実現するための科学研究費補助金の獲得に期待するのではなく、科学技術振興調整費や研究機関に研究委託が可能な新規予算の獲得を想定する必要があろう。
- ● 前回の火山のレビューを拝見し、よくレビューがなされていると思ったが、仕上がった文書は一般の人が読むには難しく、目的以外での活用が難しいと思った。文書の作成にはとても多くの時間を費やすので、例えば国民や防災担当者にも読めるような文書にすれば、費やした時間がもっと活きると思う。
- ● これまで火山噴火予知計画の建議は、ボトムアップ方式で起草されてきたため関連する大学、研究機関、防災機関が経費と人材の枠内で可能な整備計画を立案し取りまとめられてきた。このため、十分な経費と人員の確保ができず、多くの活火山(北方領土、海底火山を除いた活火山の50パーセント以上)の監視観測網が未整備のまま取り残されてきた。また、大学が主体的に進めてきた火山学および火山噴火予知の基礎となる火山体の構造探査も9火山に留まり、火山噴火の中長期予測に必要な噴火履歴調査も十分に行われていない。
火山噴火予知計画の実施体制についても、同様の方針で起草され、火山噴火予知シンポジウムなどで機械あるたびに提案され続けてきた抜本的な体制の改革については言及されていない。
このように、発足から33年が経過した火山噴火予知計画は多くの問題を抱えており、次期以後の火山噴火予知計画を推進するためには、計画推進の裏づけとなる法律を整備して、抜本的な体制の再構築が必要不可欠である。以下に今後の火山噴火予知を推進する新たな体制についての私案を提案する。
大学は、現在の全国共同利用研究所を整備して二つの共同研究拠点を構築し、新たな予知手法の開発や、火山噴火発生場(構造)および噴火発生過程などの基礎研究を推進する。共同研究拠点は国際共同研究の拠点としても機能し、また研究者の育成をはかる。噴火予知に関係する研究機関は、第7次計画の建議でもうたわれている予知技術の体系化・実用化を図るとともに、近い将来発生が予想される大規模噴火に備え、ボーリング・トレンチ調査等による詳細な噴火履歴の解明プロジェクトを新たに展開する。併せて、防災機関は火山監視強化のため大学、研究機関と協力して未整備の火山を含め高密度・高精度・多項目の火山基盤観測網を整備し、的確な情報を社会に発信する。
大学の基礎研究および観測研究設備の更新・新設、研究機関が行う予知技術の体系化・実用化研究およびプロジェクト調査研究、防災機関が行う基盤観測網の整備に必要な高額経費は国および自治体が分担する。尚、経費には、停滞している若手研究者の雇用の拡大を図り、将来を担う博士課程の学生増につなげるために人件費も含める。また、大学の必要経費は共同研究拠点に委託費として配分する。
また、具体的な整備計画は、今後15年以内、すなわち噴火予知計画発足から50年以内に完了することを目指す。このためには、気象庁が主体となる火山の基盤観測網は少なくとも年に5火山を整備し、大学が主体として推進する火山体の構造探査は年に3〜4火山で実施する。また、研究機関が進める噴火履歴調査プロジェクトも年に3火山程度実施する。
この新たなシステムによる火山噴火予知計画の実現は、日本の噴火災害の軽減のみならず、火山学および火山噴火予知において世界をリードする(図参照)。
このシステムは、各大学や省庁の縦割り行政の弊害がぬぐいきれないため、15年以内に基礎研究、観測研究、防災・情報発信が一体となった組織に移行することが望ましい。