- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資源調査分科会 > 資源調査分科会(第20回) 配付資料 > 資料2 水資源の統合管理の概念整理
資料2 水資源の統合管理の概念整理
東京大学名誉教授
社団法人 資源協会 会長
高橋 裕
1.背景
1970 年代以降、国際社会の環境問題に対する関心が高まり、1977 年に国連で初めての水会議が開催された。また1987
年には「持続可能な開発」を世界に提言した「環境と開発に関する世界委員会(通称ブルトラント委員会)」の報告書の中で、水問題が国際的な問題として取り上げられた。
その後1992
年にアイルランドのダブリンにおいて水と環境について広く議論が行われ、統合的水資源管理についての原則が示された。これを受けて同年6
月にブラジルで開催された地球サミットでは、その成果文書に「淡水資源の確保」として1章が設けられ、水資源を統合的に管理することの必要性が盛り込まれた。(「アジェンダ21」第18
章)。
2000年3月の第2回世界水フォーラムに向けて、世界水パートナーシップ(※)が「統合的水資源管理」に関する詳細な報告書をまとめ、ハーグ閣僚宣言の中に盛り込まれた。
※ Global
Water Partnership
水資源管理に関わる各国政府、公的機関、企業、専門家組織等のネットワーク組織として、世界銀行、UNDP(国連開発計画)等により1996年に設立された組織。
2.概念
(定義)
統合的水資源管理とは、水資源、土地資源、その他の関連する資源の調和的な開発及び管理を促進するためのプロセスであり、その結果もたらされる経済的、社会的な福祉の最大化を図りつつ、同時に決定的に重要な生態系の持続可能性を確保するもの。
(統合の概念)
統合には、人と自然との関わりにおいて、自然系と人間社会の二つの基本的なカテゴリーが考えられる。時間的・空間的な状況に応じた適切な統合を行うことにより、より良い戦略や計画、管理技術の開発を実現することができる。
1) 技術的統合(自然系)
1.淡水域と沿岸域の統合
淡水地域と沿岸域を一つの連続体として捉えた統合管理が必要である。淡水システムは沿岸域における環境条件の決定因子であり、沿岸域を考慮した淡水資源の管理が必要である。
2.土地と水の統合
大気、土壌、植生、地表水、地下水などの土地資源の各要素は、水文循環によって互いに連結していることから、水は全ての生態系を特徴づける根本的な決定因子である。土地利用や植生被覆は水の流れと水質に大きく影響する。このため、流域・集水域という自然系に着目して土地と水を統合的に管理する手法が有効であり、これは水量と水質の関係や上・下流域の利害関係を一体的に取り扱う観点からも重要である。
3.総合的な水収支管理
植物の光合成や蒸発散作用により失われる水は、現在管理対象になっていない。これらの水を、例えば、灌漑用に使う場合は一度限りの利用しかできないが、河川水等を家庭用や工業用に使う場合は再利用も可能である。今後は、降雨や土壌水を河川水等とともに統合的に管理することにより、効率的な水利用と生態系の保全を図る必要がある。
4.地表水と地下水の統合
地下水は水文循環により地表水と連結している。現在、世界の人口の多くは地下水に依存しており、また化学肥料の使用と汚染の拡大は地下水の水質に重大な影響を与えている。このような地下水を地表水とともに、量的、質的に一体的な管理を行う必要がある。
5.水量と水質の管理の統合
水資源管理においては、水質と水量の問題を同時に扱う必要がある。上流での水質汚染は下流での有効利用水量を制限する。逆に河川流量の低下は水質環境を規定する。水質管理は統合的水資源管理の重要な要素である。
6.上流域と下流域の統合
上流の様々な活動により、下流の受ける影響は大きい。上流において、過度に水が消費されたり水質が汚染されたりすると、下流における利用が阻害される。このため、上・下流一体となった流域全体での計画と紛争解決のためのメカニズム等が必要となる。
2) 政策的統合(人間社会)
水資源管理には、関連する各部門の政策的な統合が必要であり、その内容は以下のとおり。
1.水資源管理の経済的把握
持続可能な水資源管理にかかるコストを経済的に把握し、これを生産や消費のパターンに組み込んでいくための適切なメカニズムが必要である。
2.政策決定の統合
政策間の統合に当たっては、以下の点に留意する。
- インフレの危険性、費用負担のバランス、マクロ経済成長への影響等を慎重に考慮
- 下流域への影響と自然環境への影響(外部費用)を把握し、費用対便益の観点から決定
- 予防原則の適用
3.構造的統合
水資源関連の政策では、省庁から地方自治体、地域共同体などの協同による意思決定が必要であり、このため、参加型アプローチを基本とした、構造的枠組みが求められる。
参加型アプローチにおいては、常にコンセンサスが得られる訳ではないので、紛争解決のメカニズムも必要である。
現場の意思決定においては、トップダウンとボトムアップの適切なバランスが重要であるが、権限を委譲する際に最適なレベルは一様ではない。農家が適切な意思決定単位になる場合もあれば、国際流域のような空間的に規模が大きい場合は、国家間の調整メカニズムが必要になる。
4.水利用と排水管理の統合
水は再利用可能な資源であり、還流により利用可能な資源量が増加する。このために、経済的・社会的・行政的なシステムにおいて、排水管理を水利用に統合した仕組みをつくる必要がある。
3.手法
統合的水資源管理には、次の三つの相互補完的な政策手法が考えられる。
- 政策環境の条件整備:政策、法制度、情報基盤の整備
- 構造政策:各行政レベルや多様な関係者の役割分担、対象エリアの特定、能力開発等
- 管理手法:確立された法制度の指導、実施を効率的に推進するための措置
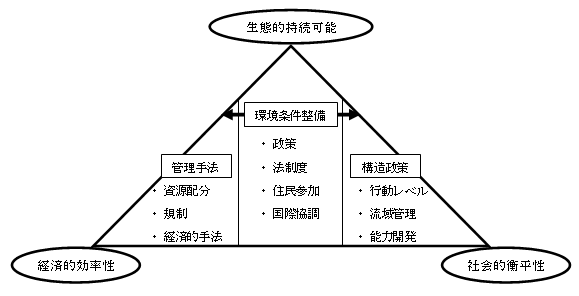
4.流域管理組織
自然系における河川流域と行政区域は一致しない。どちらを統合的水資源管理の単位とするかは、地域の実情によるべきである。水文循環の特性を考えれば、水資源計画は流域単位でたてるべきであるが、管理主体としての組織を流域におく場合は、「需要あっての開発」の原則に従い、地元の受け入れ態勢が整っている場合にのみ設置すべきである。また、行政区界が流域単位の管理に障害となる場合もあるが、流域管理組織が水資源管理を行うには、関係行政機関の協力が不可欠である。
流域管理組織の形態には、水利権の調整や料金徴収などを行う実施機関としての性格を持つものから、行政に対する助言だけを目的にするものなど幅広くみられるが、重要な機能として、調整・統合機能、合意形成機能、財政機能、国際機能(国際河川の共同管理)が挙げられる。
5.我が国における水資源の統合管理の必要性
(災害対応のための統合管理)
- 戦後から高度成長までの約30年間、活発な開発が、それぞれの分野ごとに実施され、日本の経済発展、庶民の生活水準向上に成功したが、全国各地の土地利用の急激な変化は、都市水害はもとより、流域開発による洪水流出の変化により水害の質的変化をもたらした。
- 元来、水利用は、地表水、地下水、各種の水利用を統一的管理のもと、水と土地という自然との共生の理念のもと行うのが理想である。高度成長期までは各個別の水利用開発は、それぞれの部分に関する限り効率的であった。しかし、無秩序な開発による水循環の不健全化、生態系の破壊が、1980年代から顕在するようになり、それを護るためにも水、土地という自然の管理を統合する必然性が高まって来た。
- 各地に発生した開発事業反対運動、あるいは自然再生運動の高まりは、自然界のリズムが各地域ごとに乱れていることの顕れの一端であり、自然管理の統合化を求める叫びでもあった。(1997年の河川法改正による自然環境の整備と保全、2002年の自然再生推進法、1995年の生物多様性国家戦略、同じく2002年の新・生物多様性国家戦略など)
- 自然再生事業は釧路湿原を皮切りに全国では19地域で始められているが、その対象地域は、森林、草原、里山、河川、湖沼、湿原、干潟、サンゴ礁などさまざまであり、多様な生態系を有し、事業遂行は容易でない。そのための科学的方法も技術的手段も模索段階とさえいえる。これら事業は環境省、農林水産省、国土交通省がそれぞれ関わり、その統一的手法による省際的提携が強く求められている。
- 今後のわが国の統合的管理で憂慮されるのは、いずれ来るであろう大災害(大地震、火山爆発、大水害など)、及び着実に進行する恐れのある生態系の破壊とそれによってもたらされる悪影響である。
- わが国の過去の災害史を顧みれば、1世紀に1~2度は大震災、火山大噴火、そしてさらに頻度の高い大水害を経験している。阪神・淡路大震災では、単に防災条件の不備に止まらず、都市計画を含む統合的計画及び管理ができていなかった。統合的自然管理の必要性は敗戦直後から指摘されてはいたが、このような大災害の際にもっとも明確にその弱点が明示される。阪神・淡路大震災の教訓は、ビルや各種インフラの耐震計画はもとより、いかに都市及び防災計画に統合的管理体制をとれるか否かにかかっている。しかも21世紀が進むにつれ、気候変動と少子高齢化による自然及び社会条件の急変に対し、土地、水などの自然管理の在り方が問われている。
(気候変動等へ対応としての統合管理)
- 今後の国土に関わる統合的管理を考える場合、最も重要な変化要因は、気候変動と人口動向である。それへの適切な対応なくして、統合的管理の実を挙げることはできない。
- 地球シミュレーターでは、“降水量”と“豪雨の頻度”について予測している。降水量に関しては、2071~2100年の平均と、1971~2000年の平均を比較して“バランス型社会A1Bシナリオ”では地球規模で6.4%増、日本の夏では19%増となっている。
- 日本の夏に降水量が増えるのは、熱帯域の太平洋の温度上昇に伴う、日本列島の南側が高気圧偏差となって、湿暖な空気が日本列島に大量にもたらされるからと予測されている。さらには、日本の北側も高気圧偏差となり、梅雨前線の北上を妨げるためと考えられている。日本の夏の豪雨頻度も平均的に上昇すると予測され、降水量の増加のみならず、大気中の水蒸気量の増加のためと推定されている。これによって、日本においては洪水などによる豪雨災害の危険度が高まる。
- 現在の日本の治水計画では、特に重要な河川は200年確率洪水に耐えることを目標に事業が進められている。続いて河川重要度に応じて、150年、100年、80年確率洪水に対する安全を求めて計画が推進されている。しかし、例えば従来の100年洪水が約30年洪水となり、それに応じて治水事業計画を拡大することは、財政的にも、治水戦略としても現実的でない。従って、21世紀の進行とともに気候変動が進むと予想される状況に鑑み、治水戦略を転換せざるを得ない。
- 具体的には、人口密集地域は、従来のハード方式に頼りつつも、地域内での情報伝達、警報システムの完備に基づく、避難対策の整備が切望される。河川上流域の特に峡谷部、山間部などの人口過疎化の進行地域では、一般に高齢化が進んでいるので、従来の河川整備よりはむしろ、住民の避難対策に重点を移すべきである。河川中下流部では地域の事情は多様であるが、沿川に低湿地、沼沢地などが存在すれば、それらを長期的には洪水調節地的に土地利用を変換したい。さらには休耕田、耕作放置地なども、土地を選んで洪水氾濫を積極的に許容できるよう、治水もしくは環境の観点からの土地利用を計画すべきである。
- 気候変動による水資源への影響もまた重大である。その顕著な例として、日本においては降雪量の減少による被害を強調しなければならない。地球規模では北極と南極の山岳氷河と積雪での著しい減少は、IPCCの第4次評価報告書でも自信を以って強調している。日本列島でも既に降雪の減少は明瞭に進行している。
- 降雪の減少は、融雪水の河川への影響に関して、憂慮すべき事態の発生が予想される。日本の雪国における水田も発電水力ダムも豊富な積雪とそれから流出する融雪出水に多くを頼りとしている。只見川水系や北陸の黒部ダムなどはその典型例であり、集水域の積雪量が減少すれば、融雪流量は減少し、気温上昇とも相まって、融雪の大部分は春先に集中する。そのため夏期には渇水が頻発する。従来の流出パターンで運営してきた水位操作は狂い、発電効率も落ちる。
- また、海面上昇も、27,800kmもの長い海岸線を有するわが国にとって、由々しき問題である。IPCC第4次報告書に基づき、同報告の執筆者でもある三村信男茨城大学教授によれば、今世紀末に海面は18~59cm上昇すると予測している。30cmの上昇で、日本の砂浜面積は56.6%失われるという。
- わが国は有史以来初めて人口減少時代を迎えている。それを今後の土地利用計画にどのように適合させるかは、国土計画の重大課題である。しかし、これを防災面に実現させるためには省際的協力は不可欠であり、防災行政が開発及び土地利用計画と一体になった強力な防災と開発行政の一元化が強く望まれる。
(国土保全のための統合管理)
- 21世紀が前世紀と決定的に異なる条件は、気候変動、少子高齢化であり、わが国においては気候変動が、人口減少、首都圏南部への人口集中、農山漁村及び河川上流部の極端な過疎化・空洞化を伴って発生する。第1次産業人口のさらなる減少は、農林漁業の産業としての危機のみならず、わが国土管理の仕組み、方法における発想の転換、旧来の管理の改革を迫っている。地方の小都市や農山漁村は、今後貧困と公共サービスの劣化が重なり、かつ防災力も弱まる。沿岸域、河川上流部に限らず、これら災害に脆弱な地域への対策は容易ではないが、新しい着想に基づく土地の統合管理が求められている。
- 農林漁業の人口減、極端な高齢化は、わが国土の3分の2を占める森林経営、及び水田経営にとって重大である。森林、水田は決して木材や米の工場ではなく、国土防衛の意義が重要だからである。第1次産業の衰退は、国土保全の危機であるとの思想に基づいて統合的自然管理の体制を整えるべきである。農林漁業は、生産効率の面で工業とは到底競争できない。EC諸国で近年考えられているように、第1次産業は国土基盤形成産業として位置づけ、土地資源を守る業として扱うべきである。それを可能にする強力な省際的機関、学問と研究部門も学際的協力を必然とするために、従来の枠を破る組織替えが欠かせない。
- わが国の国土経営、自然管理は、戦後60年余、目まぐるしく変化してきたそれぞれの局面打開に追われ通しであり、いわば対症療法的対応に終始し、確たる自然観に基づいた国土保全、国土経営思想が欠如していたのである。今こそ、強力な統合的管理を目ざす国土思想を構築し、来るべき国土の危機に備えるべきである。
- 例えば、水田農業は古来水循環のにない手として重要な役割を果たしてきている。水稲生育期の湛水栽培は、地下水を涵養し補給している。出水時における水田は、一時的ながら、出水調整、洪水貯留の機能を持っている。水田が水循環に適合しているのは、減反の対象となった水田の周辺で、地下水位の下がっている例が多いことでも明らかである。兵庫県豊岡におけるコウノトリの放鳥成功の影には、県の但馬県民局豊岡土地改良事務所などの貴重な努力がある。コウノトリの餌として、かつては水田の蛙やドジョウの存在があった。この土地改良事務所では農薬禁止はもとよりのこと、水田へ魚を持ち上げる魚道を設け、放鳥成功の一役をになっている。水田は日本列島の自然界の水循環に良く適合した土地利用を維持し、生態系保持にも役立ってきたことを評価すべきである。
- さらに農村の農業用水路は、かつては、用水路の水を飲料や家事用水、防火用水にも利用されていた。従って、用水路の水質や水路維持に留意し、その管理も行き届いていた。そこで、農村を流れる水路の醸し出す風景は、一幅の絵画たり得たのである。農業用水路は現代的表現を借りれば、多目的水路であった。しかし、かつての農民にとっては水路が多目的であるとの感覚は無かったに違いない。行政から見れば多目的といえば費用振分けを考えた途端に、この話は立ち消えになる。個々の目的を明瞭に分けられず、ましてやそれぞれを数量化できないし、それは無意味である。つまり、藩政時代以来の農業用水路は、人間と自然との付き合いの場であり、数量化して効率向上を目ざす、という自然科学的思考論理以前の、人間と自然との関係である。近年のコトバでいえば、“自然との共生”であり、それは生態系の一角を占めている自然との触れ合いの在り方が問われるテーマである。農業用水路をめぐる“自然との共生”の状況は、農村に水道が普及し、近代的消防施設が整い、農村の日常生活が都市化されるにつれ、一変した。農村は生活の効率化、合理化という都市化と引きかえに、自然との協調、融合を犠牲にしてしまったのである。こうして、全国の多くの農村で農業用水路は見る影もなく荒れ果てている。都市生活化に伴って、多くの用水路は下水路と化し、水質は汚れ水路の維持管理も滞る例が多く、かつての水路を要とする田園風景は見られなくなった。農業用水路の近代化はコンクリートの三面張り水路となり一刻も早く用水を運ぶための施設となり、流速を高めた流水は、一旦子供が落ちると危険であるので柵をめぐらしている。農業用水路は、用水を効率良く運ぶことに特化したのである。米の生産機能と経済効率を高めるためには、それが水路の近代化であった。近代化は“自然との共生”という数量化しにくい抽象的概念を捨て去ったのである。たとえ“多目的水路”を認識したとしても、それは水路が農民と自然との付き合いの路として育ててきた“地域”の水路であることが忘れ去られた証拠である。そもそも農民の意識が都市化し、農業は自然との共生の場であるより以前に、再び新たな価値観で、水田を米生産の場としてしか認識させない農政が続いている。
- 第1次産業は、自然、土地資源を基盤とする産業であり、水田が米の生産現場であり、森林が木材の生産工場という認識では将来は暗い。まず生産以前に“自然との共生”概念が先行しない限り、その発展は覚束無い。農林地は国家財産として、土地資源としての地位を与えるべきである。水田はわが国が所有する広大な湿地である。個々の水田の、生態的健全性、社会的健全性、経済的健全性から評価するシステムを考えたい。
6.我が国における水資源の統合管理の課題
(水環境問題、水利用の多面化等、新たな課題の出現)
- 水資源とその利用をめぐる情勢は、第2次大戦以後、目まぐるしく変転してきた。戦争直後の大水害頻発時代(1945~59)は治水投資に重点が置かれ、それに続く水資源不足時代(1960~72)は、水資源開発、具体的にはダム建設謳歌時代であった。これに対応する活発な河川事業は、その所期の目的は達したが、河川にとっては深刻な重荷となり、それは河川環境の復元を目ざす河川事業への要求となり、河川法にも“河川環境の整備と保全(1997)”が明記された(1973~97)。
- 農業用水、工業用水、都市用水とも建設から維持管理の時代に入り、水質に関しては次々と発見される新化学物質の対応に追われている。かつて、水資源の開発、そしてその利用はそれぞれの所管官庁によって、ともかくそれぞれが能力を発揮し、共存共栄してきたといえる。しかし、近年は省際的課題が続出し、それに応ずる水行政システムができていない。水を全水利体系からみると不能率、あるいは不備が出現している。
- 健全な水環境が行政面で注目されるようになったのは、1990年代後半、治水技術の革新に関わる数々の提案が当時の建設省、国土庁、環境庁において発表されたことによっている。河川技術の革新は、行政面では1990年の建設省による“多自然型川づくり”に始まる。それは河川技術が河川との共生を認識する契機となった。
- 一般住民サイドの河川事業改革の声を代表したのが、1994年完成の長良川河口堰反対運動であった。反対のおもな理由は、堰建設による河川環境破壊、水資源のさらなる開発の不要などであったが、この反対は当時のマス・コミの支援下、想像以上の盛り上りを見せ、社会問題と化した。
- 90年代は、上述のように、上下水道、治水、利水、水環境ごとに新たな課題が続出し、しかもそれらが重なり合って、その解決への道は、古くから主張されていた水の統合的管理の再来であった。しかもより強力に次代の動きを洞察した上での統合的管理である。
- 水利用における農業用水、工業用水、都市上水(生活用水及び都市活動用水)の特に渇水時における調整に関しては依然として解決すべき課題を残している。従来のようにダム開発を主軸とした河川開発には今後大きな期待をかけられないが、下水処理水の再利用、雨水などとの共存の在り方については、まさに統合的管理の対象である。
(河川と下水道の統合)
- 河川と下水道の関係は、前世紀の高度成長期からしばしば指摘されていた。特に人口密集都市の豪雨排水は複数の行政が担当している。本来は都市計画の在り方に関わる課題であるが、ここでは河川と下水道との関係についてのみ触れる。気候変動によって近年時間雨量100mmを越える豪雨が必ずしも特異現象ではなくなってきた。かつて多くの都市では時間雨量50mmが10年確率豪雨で、それに耐える排水が目標であった。時間雨量100mmに対して安全な排水もしくは治水対策を考えるには、従来の発想では、到底解決不可能である。河川事業と下水道事業との権限争い以前の問題である。かつて洪水処理をめぐって、河川と下水道が裁判の場で争ったことがあり、以後両者の話し合いは或程度進んだが、現在問われている気候変動に関わる難問は、発想の転換によらなければ解決できない。都市河川の氾濫、地下室での(東京や福岡での)水死事故の発生は、偶発的、局所的ではなく、基本的には都市計画の問題であるとともに、都市河川、下水道行政の在り方を問う問題である。
(上・下水道の統合)
- 下水処理水の再利用が進行しつつあり、本来の水道水源との役割分担、さらには徐々に普及しつつある雨水利用、その管理は水資源政策としては明確に位置づけられていない。
- 一方、上下水道民営化が国際的に重要話題となっている。水源水質の新たな課題、水源の多様化に対する国家としての水戦略が問われている。
- 政府及び地方自治体は、上下水道事業の民営化の場合、公共性を確保できる制度と組織を設けるなど、企業利益に振り回されない強力な措置を講ずるべきである。
(流域管理組織の設立)
- 水の統合的管理は、可能な限り流域圏単位で行われるのが望ましい。特に上水道と下水道事業の統合推進を優先的に検討したい。政府及び地方自治体は、治水、上下水道、水源からの取水と排水を通じて流域及び関連隣接流域における健全な水循環の持続可能性を保障する。そのために基礎的調査を関連機関が実質的に協議できる仕組みを早急に構築すべきである。上述水関連の各部局が実質的に統合的管理できる新たな組織を創り、各部局の代表が、協議できるようにする。
(水基本法の制定)
- これら管理を実施するためには、水関連のすべての法をしばる水基本法等の制定によって、気候変動と水問題の国際化という新たな状況に対処することを検討すべきである。
(水・エネルギー・食料の一元管理)
- わが国の食料自給率はカロリーベースで39%にまで落ち込んでおり、それ自体重大課題であるが、水の仮想水(virtual water)問題と深く関連している。わが国が仮想水としての年間輸入量は、沖大幹教授の試算によれば、その量は約744億m3であり、わが国の2004年の年間水使用量(農業用水552億m3、生活用水162億m3、工業用水121億m3、合計835億m3)の約90%にも相当する莫大な量である(平成19年版 日本の水資源、国交省水資源部より)。わが国が外国(特に米国、カナダ、オーストラリア)から輸入している牛肉は仮想水を増加させている。輸入牛肉が食卓に上がるまでに、膨大な飼料を必要とし、その飼料育成に大量の水を要するためである。
- 水が生産されるまでには、時には大量のエネルギーを使う。ダム開発、浄水、配水、処理過程を含め、水の開発、運搬、利用、排水すべての過程でのトータルエネルギーとコストを計量し、その相互比較から、将来の水生産、送水、排水の在り方を検討すべきである。CO2削減問題が脚光を浴びるなか、個々の部分でのCO2削減は議論され、いくたの提案があるが、水システムのエネルギーの在り方をエネルギー・フローの観点から検討すべきであり、そのための水に関わる統合的管理手法が問われている。
- 食料とエネルギーの関係は、エネルギー対策としてのバイオ燃料が食料価格を釣り上げている。食料生産とバイオ燃料の密接な関係は、それぞれを生産する水のコスト、その輸出入価格に関わり、現段階では見通しは不透明である。
- このように、水、エネルギー、食料はそれぞれは密接不可分の関係にあり、水の将来構想を練るに際してその一部のみに注目してはならない。個々のテーマごとに需給計画を作成するのではなく、3者が協議して共通理念のもとに、トータル・システムでの最適解を見出し、それに基づく管理体制を構築するのが望ましい。
(以上)
お問合せ先
科学技術・学術政策局政策課資源室
-- 登録:平成21年以前 --