資料6−4
平成19年12月11日
文部科学省
科学技術・学術戦略官付
(推進調整担当)
科学技術振興調整費においては、従来より中間評価及び事後評価を実施してきたが、一昨年改定された「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成17年3月29日 内閣総理大臣決定)、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成17年9月26日 文部科学大臣決定)の中で、研究開発施策、研究開発課題等においては、終了後、一定の時間を経過してから、副次的効果を含め、研究開発の直接の成果(アウトプット)から生み出された効果・効用(アウトカム)や波及効果(インパクト)を確認することも、評価の在り方や制度運用の見直しに当たって有用であるとの観点から、追跡評価の一層の定着・充実を図ることが求められている。
アウトカムやインパクトといった観点については、これまでも中間評価や事後評価において評価項目の一つとして評価を行ってきているが、これらの観点は、中長期的な視点から遡及的に評価を行うことにより、より精緻な、より質の高い評価が行えると考えられるため、中間・事後評価では必ずしも十分でなかった点を補うものとして、新たに追跡評価の仕組みを導入することとし、科学技術振興調整費のプログラム・オフィサー(PO)により、平成17年度から試行的に実施している。
本年度については、17、18年度に実施した「総合研究」プログラムにおける追跡評価の経験を踏まえ、「総合研究」以外のプログラムについて、昨年を上回る規模で追跡評価を実施した。
その際、実施課題のアウトカムやインパクトの把握に際しては、プログラムの設計に即した調査設計となるよう留意した。
また、追跡評価の結果として、単なる個別課題のアウトカムやインパクトの評価のみならず、評価対象プログラムが果たした役割や成果を明らかにするとともに、今後のプログラム設計に関する改善事項を分析・提案するよう努めた。
追跡評価の結果については、科学技術振興調整費の制度運用に活かしていくこととする。
平成19年度においては、昨年・一昨年に実施した「総合研究」以外のプログラムについて実施した。
具体的には、事後評価から5年程度が経過している課題が最も多く、また、「総合研究」のプログラム趣旨が大きく異なる、「知的基盤整備」、「流動促進研究」の2プログラムを対象とした(各プログラムの調査対象課題は別添1を参照)。
先端的・独創的な研究開発を積極的に推進するためには、研究者の研究開発活動を安定的かつ効果的に支える知的基盤を総合的に整備することが極めて重要。このため、知的基盤に関する研究開発を推進することにより、我が国の知的基盤の整備を加速し、もって我が国の研究環境の向上を図る。
平成9年〜平成12年
5年以内
1年につき2億円程度
研究者の創造性の発揮に基礎を置いた柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を整備するためには、研究者の流動化を促進させることが必要。任期付研究員が成果を上げることが可能となるよう必要な経費を措置することにより、国立試験研究機関における研究者の流動的かつ独創的な研究活動を推進することを目的とする。
平成9年〜平成12年
3年〜5年
1年につき15百万円程度
追跡評価の実施に際しては、各プログラムの設計に即した調査となるよう、プログラム毎に調査方法を定めることとし、具体的には以下のとおり実施した。
本プログラムの追跡評価の実施に際しては、優れた取組がなされた結果として課題終了時に各研究機関に整備された知的基盤が、その後どのようなアウトカムやインパクトを生み出しているのかについて分析する必要がある。
また、課題毎に整備された知的基盤の性質(研究用材料の開発、計測・分析手法等の標準化、計測・分析ツールの開発、情報のデータベース化 等)や研究領域が異なることから、実施課題毎に、詳細な分析・評価を行う必要がある。
このため、本プログラムに関する追跡評価については、以下の手順・内容にて実施した。
本プログラムの追跡評価の実施に際しては、国立試験研究機関が本プログラムで任期付研究員を採用した結果として、国立試験研究機関にどのようなアウトカムやインパクトを与えているのか(具体的には、研究者の流動的かつ独創的な研究活動が推進されたのかどうか)を調査・分析する必要がある。
その際には、任期付研究員のリーダーシップや協調性、周辺環境等の外部要因から影響を受けることが想定されることから、個々の任期付研究者による研究成果の優劣にはこだわらず、むしろ、可能な限り多くの課題を対象とし、また、統計的手法によって総合的に分析することが妥当と思われる。
このため、本プログラムに関する追跡評価については、以下の手順・内容にて実施した。
追跡評価は、科学技術振興調整費のPOが実施した。調査の実施に際しては、各POが有する知見を最大限に活かしつつ、各POの知見等をとりまとめて総合的に分析を行う、「総括担当PO」を配置することにより、体系的な調査・分析を実施した。
| 9月中旬 | 事前調査の実施 |
| 10月上旬 | アンケート調査表の作成 |
| 10月中旬 | アンケート調査表の送付(研究代表者、主な研究担当者、研究運営委員会委員) |
| 10月下旬 | アンケート調査表の回収 |
| 11月上旬 | インタビュー調査の実施(研究代表者、外部有識者等) |
| 11月中旬 | 取りまとめ |
独立行政法人産業技術総合研究所の開発した「一次時間周波数標準器」が、その後、世界レベルである2,000万年に1秒の誤差まで精度を高めている等、調査を行ったほぼすべての対象について、その後も知的基盤として発展している。
具体例:
なお、「1.国際的先進材料の実用化を促進するための基盤構築に関する研究」においては、課題実施期間終了後に担当機関の予算の十分な確保ができず、新規関連分野の分析手法の標準化が進まない等の状況も見られ、国内外から更なる貢献が求められている。科学技術の進歩に伴って、知的基盤を継続的に整備することが重要である。
独立行政法人理化学研究所が開発した世界最高性能の中性子散乱装置は、我が国発の新技術として国際的に高く評価され、英国、仏国との共同研究として実証研究が進められている等、本プログラムで整備されたほぼすべての知的基盤に対し、国内外から高い評価を受けている。
具体例:
独立行政法人理化学研究所の開発した「超精密非球面加工技術」を活用することにより、世界一のマーケットシェアを占める加工機が開発される等、本プログラムで整備された知的基盤の活用によって、高い成果が得られている。
具体例:
以上のように、本プログラムで整備された知的基盤が、その後も継続的に発展しつつ活用され、第二期科学技術基本計画で定める「知的基盤」の4つの領域(研究用材料、計量標準、計測方法・機器、データベース)で、それぞれ高い成果を残している。しかしながら一部の取組においては、その後の予算確保が十分ではなく、関連する分野の分析手法の標準化が進まない等の状況も見られ、国内外から更なる貢献が求められているものもみられる。科学技術の進歩に伴い、整備した基盤の更なる発展が重要であり、知的基盤の継続的な整備が重要である。
今回の調査対象課題は、いずれも事後評価で高い評価を得ているものであるが、上述のとおり、その後も順調に活用・発展されており、事後評価の結果も妥当であると考えられる。本プログラムは高い成果を上げており、今後とも整備された知的基盤の有効活用が望まれる。なお、時間標準や、標準物質などの科学・産業技術の基盤となる知的基盤に関しては、その精度の向上と運営の維持のために継続的な取組が必要である。このように終了後も継続して発展させる必要のある知的基盤に関しては、公募時に振興調整費による支援終了後においても継続して知的基盤を発展させることを求める等、プログラムの設計時に継続性を担保できる仕組みを設けることも重要と考えられる。
| 10月上中旬 | 調査票の作成 |
| 10月下旬 | 実施機関、本プログラムで雇用された任期付研究員(以下「調整費の任期付研究員」)及び当時のその上司への調査表の送付と回収 |
| 11月上中旬 | 分析、ヒアリング等追加調査の実施 |
| 11月中下旬 | 取りまとめ |
課題が実施された国立試験研究機関(旧国研を含む)13機関、課題を実施した調整費の任期付研究員68名、その当時の上司68名を対象にアンケート調査を行った。回収されたアンケート数は機関12(92パーセント、内1機関は1部分のみに回答)、調整費の任期付研究員53(78パーセント)、上司49(72パーセント)であった。
本プログラム実施前(平成8年以前)には殆ど見られなかった任期付研究員であるが、回答が寄せられた11機関において、本プログラムの開始年(平成9年)に研究員総数(常勤)比で平均約0.6パーセント、実施課題の取り組みが概ね終了した年(平成16年)には平均11パーセント弱に達し、任期付研究員数は平成9年以降急速に増加した。
| 表1.「流動促進研究」プログラム参加研究機関における研究員数と任期付研究員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成9年と平成16年の比較)
|
新規採用研究員の採用形態は、本プログラム開始の年(平成9年)には回答が寄せられた12機関の合計において、定年制職員としての採用が91名に対して、任期付での採用は21名と少ない人数であった。一方実施課題の取り組みが概ね終了した年(平成16年)には、定年制職員としての採用が55名、任期付での採用は182名と、平成9年の採用比率とは逆転して任期付での採用が一般的となった。
さらに、回答が寄せられた12機関中11機関より、「任期付研究員制度が研究員新規採用の一般的形態として、あるいはその一部として定着した」との回答が寄せられた。
本設問に回答のあった9機関中6機関が「任期付研究員数の増加に有効」あるいは「まずまず有効」であったと回答し、他3機関も「多少の効果があった」と回答した。
また調整費の任期付研究員、上司共にその6割強が「有効」あるいは「まずまず有効」と答え、「効果が無かった」との回答は2割弱であった。機関、調整費の任期付研究員、上司のいずれも5割以上が「有効」或いは「まずまず有効」と回答しており、本プログラムは、任期付研究員数の増加に効果があったものと考えられる。
| 表2.任期付研究員数増加に対する効果 | ||||||||||||||||||||||||
(パーセント)
|
本プログラムの任期付任用制度定着への寄与についても半数の機関が「寄与した」あるいは「まずまず寄与した」と回答し、残る半数が「多少の寄与が認められた」として、「寄与が無かった」とした機関は認められなかった。
| 表3.任期付研究員数増加に向けて効果が認められた点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(パーセント、複数回答可)
|
機関の多くが、本プログラム実施が任期付研究員採用のきっかけとなったと回答し、任期付き研究員の認知度を高めたとの回答も多く示された。調整費の任期付研究員、そしてその上司も共に、本プログラムが任期付研究員の認知度を高めた点を高く評価している。アンケートでは、採用数を高めることにつながったとの回答が多く、任期付研究員採用のきっかけ又は、動機となったとの回答も続いて多く認められた。また、本プログラムに参加することを目指し任期付研究員に応募して採択された研究者も見られ、任期付研究員応募者の増加にもつながったことがアンケートに示されている。
任期付研究員制度は、科学技術基本計画(平成8年7月2日閣議決定)に基づき、研究開発システムの整備の一環として政策的に推進されたものであるが、本「流動促進研究」プログラムで雇用された任期付研究員は、その国立試験研究機関で始めて雇用された任期付研究員であったケースが多い。
このため、科学技術振興調整費による任期付研究員の雇用に伴い、任期付研究員の評価制度や、再任用制度、処遇など人事制度の改訂・改革が試みられ、採用される任期付研究員数の拡大に伴って、そうした人事制度改革がさらに具体化・定着したことも、ヒアリングにて伺われた。この意味では本プログラムは各機関において任期付任用制度が定着する過程において、一定の役割を果たしたものと考えられる。
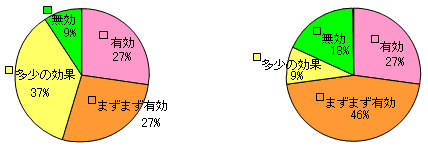 図1.人事制度改革に対する任期付研究員採用の効果(実施機関回答より) |
| 左:調整費の任期付研究員による効果、右:本プログラム以外で雇用された任期付研究員をも含む、任期付研究員一般の採用による効果) |
機関、調整費の任期付研究員の7割、そして上司の9割が、本プログラムの実施が研究成果等の創出に有効であったことを示し、その理由として論文発表等研究成果向上に有効であったこと、研究レベルが向上したこと、成果発表機運が高まったことを挙げている。
10機関中6機関が「有効」または「まずまず有効」と回答し、残る4機関も「多少の効果があった」と回答した。調整費の任期付研究員とその上司による評価はさらに高く、いずれも8割強が「有効」または「まずまず有効」と回答した。その理由として、大多数が「研究レベルの向上」、「成果が得られたこと」そして「成果発表機運の高まり」を挙げている。
「課題を実施した調整費の任期付研究員の成長に有効であったかと」の問いにも、同様の回答が得られており、実際に調整費の任期付研究員の約半数が「課題終了後国内の学会で注目されるようになった」とし、「国内国外との共同研究が増えた」との回答も目立ち、「国際学会で注目されるようになった」との回答も2割強認められた。
このようにアンケートにおいて、本プログラム実施は若手研究者の育成に有効であったとの回答が多い。また、その要因として、「調整費の任期付研究員に対して相当規模の研究費が支給されたことが、その育成に寄与した」との回答が多く寄せられた。
外部研究機関(所属研究機関以外の大学や他研究機関)との交流促進に関しては、回答を寄せた10機関中5機関が「有効」または「まずまず有効」と回答、4機関が「多少の効果あり」と回答し、上司も5割強が「有効」または「まずまず有効」と回答した。有効であった点として、「外部研究者との討議の機会の増加」、また「共同研究増加につながったこと」が挙げられ、本プログラムが外部研究機関との交流促進に有効であったとの回答が多い。
本プログラムが研究員の流動化につながったかについては、表4に示されるように、「多少の効果」とする回答が最も多く示され、「有効」あるいは「まずまず有効」とする意見と「無効」とする意見が拮抗して、その効果は明瞭に示されていない。
| 表4.研究員の流動化に有効であったか | ||||||||||||||||||||
(パーセント)
|
「有効」との回答では任期付研究員制度導入により主として任期付研究員の雇用や任期満了に伴う研究員の異動を評価し、「無効」との回答においては「任期満了後再任用されるケースが多かった」、「対象となる任期付研究員が少ない」とする回答が見られた。
また、アンケートに寄せられた関連コメントにおいて、「受け皿としてのポストが限られるために流動化が促進されない」との声が複数寄せられた。
本調査において、「独創的研究の創出」、「機関内の交流促進」、「研究機関の国際化」についてもアンケート項目に含め、その効果を分析したが、明確な方向は得られなかった。