本文へ
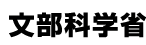
(2)「重要課題解決型研究等の推進」公募要領
1 目的
国民のニーズに対応する国家的、社会的に重要な政策課題であって、単独の府省では対処が困難であり、政府として速やかに取り組むべき課題について、産学官の複数の研究機関による総合的な推進体制の下で、具体的な達成目標を設定し、研究開発を推進する。また、科学技術政策に必要な調査研究を実施する。
2 対象とする課題
(1)重要課題解決型研究
 知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現
知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現
(課題1−1) 科学技術情報の国際的流通促進に関する研究開発
アジア諸国には様々な分野において各国言語で記述された科学技術文献が存在する。アジア諸国における科学技術の発展及びアジア諸国の知見も活かした我が国の国際競争力の強化のためには、工学だけでなく人文科学の知見も活用して、科学技術情報の広範な流通及び母国語によって閲覧できることが必要である。このため、現実社会の大量の科学技術文献を対象にする言語翻訳の基盤技術として、文献データベースの構築、科学技術用語辞書の整備、言語翻訳技術の向上等の多言語翻訳のほか、英語を介しない個々の母国語での検索及び実証システムの研究開発を行う。
(課題1−2) 地下構造の統合化データベースの構築
様々な目的の調査・研究によって得られた地下構造データは国民共有の国家財産であるにもかかわらず、これまで統合、共有化が十分図られていない。安全・安心な社会の実現に向けた研究開発に資するためにはこれら知的資産の統合、共有、利活用の促進が必要である。このため、大学、研究機関、地方自治体等に散在する大量の地下構造データの有機的な統合を図り、地震防災対策等の具体的研究ニーズに対して利用が可能な統合化データベースシステムを構築する。
 国際競争力があり持続的発展ができる国の実現
国際競争力があり持続的発展ができる国の実現
(課題2−1) デジタルコンテンツ創造等のための研究開発
映画、音楽、アニメ、ゲームソフトをはじめとする我が国の強みであるコンテンツの国際競争力確保のため、技術革新の進展に即応したCG等の映像技術、ブロードバンドにおける流通技術等を活かした高品質なデジタルコンテンツの制作・流通等が円滑に図られるよう、それに必要な先端的な技術に関する研究開発を行う。その際、内容に応じ標準化が必要なものについては、研究開発と一体的に進める。
(課題2−2) 持続可能な流域圏環境管理技術の開発
人口減少時代を迎え、持続可能な社会の構築に向け、都市構造・国土構造を見直す必要性が高まっている。流域圏は、森林・農村・河川・都市等の要素を含み、環境管理を行うべき基本区分となり得るものである。流域圏の環境管理を実現するためには、地域住民・地方自治体・関係各省等の協力の下、流域圏の将来の在り方を検討する環境アセスメント技術の確立により、流域圏の将来の在り方を明確にすることが必要である。このため、物質循環や生物生態系等のメカニズムを考慮した影響評価技術を用いて、あらゆる視点からの幅広い流域圏利用の在り方に対し総合的に評価できるアセスメント技術の実証的研究を行う。
 安心・安全で質の高い生活のできる国の実現
安心・安全で質の高い生活のできる国の実現
(課題3−1) 国民の健康障害に関する研究開発
生活環境や労働環境に依存して不特定の国民の健康に脅威を与え得る疾患のうち、現在発症機序が不明で有効な対処方法のない疾患について、早期にその脅威を低減・除去するために、発症機序の解明を進めるとともに、早期診断や治療に関する技術の開発に結びつく研究を実施する。その際、研究開発の迅速な展開のために臨床情報等の共有を図るとともに、統一的な基準のもとでの診断法・治療法の開発を目指す。
(課題3−2) 情報セキュリティに資する研究開発
情報通信技術を取り巻く状況は急速に変化しており、最近では、携帯電話へのコンピュータウイルス攻撃や情報家電を踏み台にしたネットワーク攻撃のように多様で広範囲な脅威が新たに顕在化してきている。また、電子マネー機能を有する携帯電話端末やタグによる小学生の登下校管理のように新たな情報通信の利活用の形態が出現している。こうした中で、悪意ある脅威としてのサイバー攻撃等によって、情報通信インフラが中断され社会生活・経済活動に深刻な影響を与えるおそれがあるため、安定な情報通信サービスの提供、個人認証及び個人情報の保護が重要な課題である。これらの課題への対策及び新たに発生する問題の予測・予防の方策について、情報通信の安全性・信頼性向上に資する研究開発を行う。
(課題3−3) 国際テロ・犯罪からの安全を確保する先端科学技術研究
国際社会におけるテロ発生の危険性とその対策の緊要性は高い。国民生活、社会経済の安全・安心を脅かす国際テロ・犯罪対策においては、情報収集・分析、水際対策など未然防止とあわせて、万一の事態発生における人命救助と被害拡大防止に備えておくことが肝要である。このため、テロ発生時の初動対処に活用可能な、化学剤及び生物剤の現場検知、除去技術について、実証的な研究開発を行う。
(課題3−4) 減災対策技術の研究開発
人工的な国土環境の改変に伴う土砂災害、海岸浸食、地盤沈下等は近年社会的な問題となっている。国土環境の保全・再生の観点による対策とともに、これらの環境変化に伴って地震・津波等に対する被害の増大が懸念されているため、減災の観点からの対策が必要とされている。このため、有効な減災対策と国土環境保全に資することを目的として、地域の自治体・企業等と連携を行い、先端技術を活用して、減災対策の実証的な研究開発を行う。
(課題3−5) 人工降雨を中心とした渇水対策に関する研究
地球温暖化に伴う気候変動により、豪雨や少雨といった極端な気象現象が今後頻発するとの見込みが指摘されているため、少雨等に伴う渇水対策の新たな取組として、人工降雨技術の研究開発を行う。人工降雨技術を用いた渇水対策としては、冬季の雪雲を対象として山岳地に積雪の形で確保する方法が効果的と考えられるため、直接観測による雲の内部構造・降水機構の解明、人工降雨に適した雲の観測・判別手法の開発、人工降雨実験によるシーディング効果の評価等を中心とした実証的研究を行う。また、降水予測技術の精度の向上、及びそれと連動した渇水緩和のための水資源管理技術の研究開発を行う。
(2)科学技術政策に必要な調査研究
(課題1) ライフサイエンスやナノテクノロジー等の先端科学技術が社会に与える影響の調査研究
ライフサイエンス推進において、生命倫理は避けて通れない課題である。我が国では、ヒト胚の取扱いの基本的考え方が示されているが、関連する国際的な政策の動向や再生医療を巡る研究開発動向の把握は引き続き重要である。また、欧米等において、エンハンスメント(運動能力増進等の増進的介入)など、新たな生命倫理の課題も取りあげられつつある。こうした状況への対応に必要な情報を収集するため、国際的な政策や研究開発の動向の把握、及び国民の問題意識の調査等の調査研究を推進する。
ナノテクノロジーは、IT、ライフサイエンス、環境・エネルギー、医薬・バイオ等様々な分野で次世代産業を担う新科学・技術として大きな期待を担っているが、その半面、予測しない環境・健康影響等の負の側面について懸念する報告があり、こうした漠然とした社会不安が産業化の障壁となっている。このため、今後のナノテクノロジーの健全な発展を促進するため、ナノ材料の健康や環境影響、倫理や法律、ナノテクノロジーの標準化やテクノロジーアセスメントの在り方等、社会受容高度化のための調査研究を府省横断の産学官の協力体制で行う。
(課題2) 統合・代替医療の科学的評価手法の調査研究
いわゆる西洋医学以外の漢方、鍼灸、整体などの療法やこれらを西洋医学と統合した療法について、その有効性を科学的に評価する普遍的手法を開発する。これに基づき有効性を認められたものについては、統合・代替医療として投薬や手術などの過剰な実施を防止し、患者の選択の幅を広げ、保険財政の負担軽減につながるため、そうした統合・代替医療の在り方について基礎的な調査研究を行う。
3 対象機関
(1)重要課題解決型研究
大学、国公立試験研究機関、独立行政法人、民間等の研究機関その他研究能力を有する国内の機関すべてを対象とする。
ただし、産学官の複数の研究機関を結集するなど総合的な推進体制を構築するほか、研究を総括し、課題全体に係る責任を有する機関(以下「責任機関」という。)及び責任機関に所属し課題全体に係る責任を有する者(以下「研究代表者」という。)を設定することとする。このとき、研究代表者は研究遂行上の実質的な代表者であることとし、単に組織の代表者を形式的にその任につけてはならないこととする。なお、明確な目的意識の下で効率的かつ効果的に研究開発を推進する観点から、1課題当たりの参画機関は真に必要な機関に絞ることとし、原則として5機関程度とする。
(2)科学技術政策に必要な調査研究
大学、国公立試験研究機関、独立行政法人、民間等の研究機関その他研究能力を有する国内の機関すべてを対象とする。
ただし、調査研究の中核となる機関(以下「中核機関」という。)及び中核機関に所属し課題全体に係る責任を有する者(以下「研究代表者」という。)を設定することとする。
4 実施期間
(1)重要課題解決型研究
原則3年間とする。ただし、特に必要と認められる場合には、5年間を限度とする。
実施期間が3年を超えるものについては、業務開始後3年目に中間評価を行い、中間評価の結果に応じて、計画の変更、業務の中止等の見直しを行う。なお、中間評価においては、3年目までの目標が達成できているかどうかについて確認した上で業務継続の可否を決めることとし、優れた成果が挙げられていないものについては、原則として業務を中止することとする。
(2)科学技術政策に必要な調査研究
原則1年間とする。ただし、特に必要と認められる場合には、2年間を限度とする。
5 費用
- (1)課題の実施に必要な経費については、文部科学省から(他府省所管の国立試験研究機関等の機関・組織については所管府省を経由して)支給する。
本プログラムにおいて使用できる費目の種類は、原則として別表2に示すものとする。
- (2)1課題当たりの経費は、以下のとおりとする。
 重要課題解決型研究は、原則として年間1〜2億円(間接経費を含む。)とする(真に必要とする金額を要求する提案を重視する。)。
重要課題解決型研究は、原則として年間1〜2億円(間接経費を含む。)とする(真に必要とする金額を要求する提案を重視する。)。 科学技術政策に必要な調査研究については、年間3千万円程度(間接経費を含む。)とする。
科学技術政策に必要な調査研究については、年間3千万円程度(間接経費を含む。)とする。
6 提案書類等
(1)重要課題解決型研究
提案書類は、様式2−1から2−9によるものとする。本プログラムによる課題の実施を希望する研究機関は、責任機関及び研究代表者を決定する。責任機関及び研究代表者は参画する産学官の機関(以下、「参画機関」とする。)と調整し、研究終了時(3年間を超えて実施する場合は研究中間時及び研究終了時)の「具体的な達成目標」(以下「ミッションステートメント」とする。)を作成した上で、上記の様式に必要事項を記入し、責任機関から科学技術振興機構に提出することとする。
(2)科学技術政策に必要な調査研究
提案書類は、様式2−1から2−9によるものとする。本プログラムによる課題の実施を希望する研究機関は、中核機関及び研究代表者を決めた上で、上記の様式に必要事項を記入し、中核機関から科学技術振興機構に提出することとする。
7 実施課題の選定
- (1)選定に係る審査は、外部有識者からなるワーキンググループにおいて、提出された提案書類による書類審査及び研究代表者からのヒアリングの二段階審査により行い、その審査結果をもとに、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術振興調整費審査部会(以下「審査部会」という。)における審議を経て選定する。
- (2)選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。
 重要課題解決型研究
重要課題解決型研究
- ア 研究等の内容
- 「知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現」、「国際競争力があり持続的発展ができる国の実現」又は「安心・安全で質の高い生活のできる国の実現」のいずれかに直接結びつく内容であるか。また、社会的・経済的波及効果が高い研究成果が期待できる内容であるか。
- 十分な準備に基づいた戦略的な構想であるか。
- 特定府省の行政ニーズに閉じた研究内容になっていないか。
- 科学技術振興調整費により行う必要性は明確か。また、責任機関及び参画機関が運営費交付金等で行うべき内容と明確に切り分けができるものか。
- 研究内容、研究手法(アウトリーチ活動を含む。)は適切であるか。
- イ 研究等の必要性
- 国家的・社会的ニーズが高く、国際的な協調や国際競争の観点から重要であり、早急に対応すべき課題であるか。
- 新たに対応を取ることが、近年特に必要とされている課題であるか。
- ウ 計画の妥当性
- ミッションステートメントが具体的かつ明確に定められているか。また、ミッションステートメントの水準は、実施期間、参加する機関のポテンシャルから見て適正か。
- 当該研究に投入される費用と得られる研究成果とのバランス(費用対効果)は適切か。特に、得られる成果に対して費用が過大になっていないか。
- 研究計画には実施内容に即したアウトリーチ活動が明確に盛り込まれているか。
- エ 実施体制
- 研究代表者の適性(参加する各機関を束ねて課題を推進するポテンシャル)は十分であるか。また、途中で交代することを前提としていないか。
- 課題を実施する上で、適切な機関が産学官から参加しているか(重要な機関が抜け落ちていないか。)。また、研究機関があまりに多く参加するために1機関当たりの研究費が細分化され、効率的な研究が阻害されるような体制となっていないか(参画機関は真に必要な機関に絞ることとし、原則として5機関程度とする。)。
- 参加するそれぞれの機関の役割が明確であり、かつ、機関間が有機的に連携し、一体的な取組が行われる課題か。
- 各参画機関における当該課題に関連するこれまでの実績は十分か。
- 研究終了後も、引き続き総合的な体制の下で実用化等に向けた必要な取組が進められる体制になっているか。また、知的基盤整備等の成果については、自立的に維持、運営、発展できる体制になっているか。
 科学技術政策に必要な調査研究
科学技術政策に必要な調査研究
- ア 調査能力の妥当性
- 調査研究を行うために必要な知識、ノウハウを持った研究者等により適切に実施体制が構成されているか。
- イ 検討体制
- グループとしての意見を集約し得る体制となっているか(特定の意見に偏らない体制となっているか。)。
- ウ 実施計画の妥当性
- 科学技術政策にとって重要な結果が期待できる計画となっているか。
- 計画における調査・分析方法は妥当なものであるか。
- エ 社会との関連性
- 社会にとって有意義な結果が期待できる計画となっているか。
- 調査によって得られる結果は社会への貢献度が高いと期待されるものか。
- 社会ニーズを十分に反映した計画となっているか。
- オ 調査終了後の展開
- 調査結果を今後の政策に反映させる仕組み、手法等が明確であるか。
- 調査結果による波及効果が十分に大きいと期待できるか。
- (3)選定に当たっては、審査部会等の意見を踏まえ、計画の修正を求めることがある。
- (4)審査結果は、審査終了後、提案書類に記された事務連絡先に通知する。なお、ヒアリングを実施する提案の研究代表者に対しては、ヒアリングの日時、場所等を事務連絡先に通知する。
8 業務の実施
- (1)選定された責任機関又は中核機関は、提案書類の研究実施計画に即し、参画機関ごとの年次計画及びこれに対応した経費の積算(以下「計画書等」という。)を取りまとめ、調整の上、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出する。なお、これらについては、調整の結果、修正を求めることがある。
- (2)重要課題解決型研究については、責任機関は、ミッションステートメントを科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出する。なお、本プログラムを開始するまでの間、選定時における審査部会等の意見を踏まえ、修正を求めることがある。
- (3)業務開始後のミッションステートメントの変更、実施機関の追加は原則として認められないが、変更等しなければならない事情が生じた場合は、科学技術振興機構を通じて文部科学省の確認を得ることとする。
- (4)文部科学省は、提出された計画書等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、国の機関・組織については示達(文部科学省以外の府省が所管する機関・組織については所管府省に移替えの上、示達)、その他については委託により業務の実施に必要な経費を配分する。
また、文部科学省は、当該機関に対し、研究費等の直接経費の30パーセントに相当する額を間接経費として配分する。
なお、委託する場合については、「科学技術振興調整費委託業務事務処理要領」に基づき委託契約を締結するものとする。
- (5)重要課題解決型研究については、責任機関は、研究代表者のイニシアティブの下、当該研究課題の円滑な推進を図るため、研究の厳密な運営管理に必要な連絡調整を行う研究運営委員会を採択後速やかに設置する。研究運営委員会は、研究代表者を長とし、各参画機関から選任される責任者、外部の有識者、当該研究に関係する府省の担当官等で構成され、責任機関が適宜開催するものとする。その際、文部科学省及び科学技術振興調整費プログラムオフィサーが、必要に応じこれに参画するとともに、現地調査等の実施などにより進捗状況を把握し、必要に応じ助言を行う。
- (6)参画機関は、計画書等に基づき業務を実施するほか、毎年度、研究の進捗状況及び経費の使用実績に関する報告書(以下「報告書等」という。)を作成し、責任機関又は中核機関に提出する。責任機関又は中核機関は、各参画機関から提出された当該年度の報告書等を(「重要課題解決型研究」にあっては、研究代表者の下、研究運営委員会での議論等を経て、調整の上)取りまとめ、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出する。
- (7)重要課題解決型研究については、責任機関は、研究期間終了後(3年間を超えて実施する場合は研究開始後3年目及び研究期間終了後)、速やかに各参画機関からの成果報告書を取りまとめ、調整の上、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出する。提出された成果報告書は、文部科学省から科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会(以下「評価部会」という。)に報告する。
評価部会は、成果報告書をもとに事後評価を行う(3年間を超えて実施する場合は研究開始後3年目に中間評価を実施する。)。評価に当たっては、必要に応じて研究代表者等からヒアリングを行うこととする。なお、成果報告書及び評価部会による評価結果は、文部科学省が公表するとともに、文部科学省から総合科学技術会議に報告する。
また、科学技術政策に必要な調査研究については、中核機関は、研究期間終了後、速やかに各参画機関からの成果報告書を取りまとめ、調整の上、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出する。提出された成果報告書は文部科学省が公表するとともに、文部科学省から科学技術・学術審議会及び総合科学技術会議へ報告する。
- (8)重要課題解決型研究については、毎年度、直接経費のうち概ね3パーセントに相当する経費をアウトリーチ活動(注1)に充当し、国民・社会に対してわかりやすくその研究の科学的、政策的意義について説明し、理解・受容を求めるよう努めることとする。特に初年度は、一般国民向けの公開シンポジウムを主催し、実施する研究計画をわかりやすく説明することとする。なお、アウトリーチ活動についても中間評価及び事後評価の対象とする。
- (9)ここに定めるもののほか、業務の実施に当たっては、文部科学省が別途定める実施要綱に従うこととする。
- (注1) 本プログラムにおけるアウトリーチ活動とは、単にシンポジウムでの成果発表やパンフレット等の作成ではなく、例えば、
 中学や高校に研究者が出向いて、生徒に対して研究内容やその成果が社会に与える影響についてわかりやすく説明する(出前レクチャー)、
中学や高校に研究者が出向いて、生徒に対して研究内容やその成果が社会に与える影響についてわかりやすく説明する(出前レクチャー)、 一般国民を対象とした公開セミナー等の場において実験のデモンストレーション等を行い、科学的原理の説明と研究の内容・成果について理解を求める、などの取組を想定している。また、ただ単に知識や情報を国民に発信するというものではなく、研究者等と国民が互いに対話しながら、国民のニーズを研究者等が共有するためのコミュニケーション活動を指す。
一般国民を対象とした公開セミナー等の場において実験のデモンストレーション等を行い、科学的原理の説明と研究の内容・成果について理解を求める、などの取組を想定している。また、ただ単に知識や情報を国民に発信するというものではなく、研究者等と国民が互いに対話しながら、国民のニーズを研究者等が共有するためのコミュニケーション活動を指す。
- (参考)平成16年度科学技術白書より抜粋
特に、科学者等のアウトリーチ活動と言った場合、「研究所・科学館・博物館の外に出て行う単なる出張サービス的な活動ではなく、科学者等のグループの外にいる国民に影響を与える、国民の心を動かす活動」であると認識することが重要である。ただ単に知識や情報を国民に発信するというのではなく、国民との双方向的な対話を通じて、科学者等は国民のニーズを共有するとともに、科学技術に対する国民の疑問や不安を認識する必要がある。一方、このような活動を通じて、国民は科学者等の夢や希望に共感することができる。こうして、科学者等と国民が互いに対話しながら信頼を醸成していくことが、アウトリーチ活動の意義であると考えられる。