- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 科学技術・学術審議会 > 資料3‐2 地球上の生命を育む水のすばらしさの更なる認識と新たな発見を目指して > 第2章 水の需給の動向
第2章 水の需給の動向
1 水循環予測
(要旨)
一般的に言って、水資源の特徴としては、次の三つが重要である。
- 循環型、持続的な資源である
- 他の物質資源に比べて重さや体積当たりの単価が安い
- 必要な時に必要な場所に必要な質の水でなければ価値が無い
「価格が安い」という特徴は、「貯蔵したり運搬したりするコストが相対的に高くなる」ということにつながり、結果として必要な時に必要な場所に存在する水でないと水資源としては価値が下がる。「水が足りない」ということは「水という物質が足りない」ということではなく、「安価な淡水が足りない」ということである。
日本の水資源使用量は、生活用水に国民1人当たり1年間に約130m3、工業用水の淡水補給量が1人当たりに換算して約110m3、そして農業用水が約460m3で、合計約700m3になる。一般に、先進国では1人当たり年間1000m3の水資源が必要だとされるが、我が国は大量の農畜産物を輸入しているため、結果として国内の水資源消費量が相対的に低く抑えられている。農畜産物を輸入することは、あたかも水を輸入しているのと同じである、という意味で、そうした農畜産物のことを水資源的観点からvirtual waterと呼ぶことがある。ここでは、「間接水」と訳す。
日本の「間接水」の輸入量は全部で年間約744億m3にものぼり、国民1人当たりにすると年間約600m3に相当する。国内で利用している水資源量700m3と併せると合計1,300m3となり、先進国としてはやや多目の水資源の利用量となる。
このように日本人は生活を支えている水資源の半分近くを海外に依存している。それが健全な経済活動に基づいていて、また、開発途上国等に環境負荷をかけていないとしても、利用可能な水資源量は時間的な変動も激しく、世界の水資源需給がどういう状態にあるかを常に気にかけておく必要があると考えられる。
世界の水資源は、年間約40,000km3が最大限利用可能であるが、ある推計によれば、農業用水に2,500km3、工業用水に750km3、生活用水に350km3、そして貯水池からの蒸発として200km3の合計3,800km3を毎年利用しており、最大利用可能量の約10パーセントを20世紀の終り頃には人類は利用していたと考えられている。
水の利用可能量に対する水の利用量の比を「水ストレス比」と呼び、これが40パーセントを越えている場合には、「水ストレスが高い状況下に置かれている」という目安となる。
人口増加、気候変動、そして経済発展に伴う水消費需要の増大を考慮して、2050年の水ストレス比を算定すると、アメリカ中西部、中近東、インドパキスタン国境~インダス川流域、中国北部の河北平原等でこの比が高い。この分布の概要は1995年の状況と大差なく、現在水ストレス比が高い地域が将来的にも高い、という将来展望となる。
2050年の世界人口のうち、何人がどの程度の水ストレス比の値に分類される地域に住むことになるかについて、1 人口増加のみを考慮した場合、2 気候変動も考慮した場合、更に3 1人当たりの取水量の増加も考慮した場合を比べてみると、40パーセント以上の高い水ストレスにさらされる人口は、現状の推定値14億人に対して、1 人口増加のみを考慮すると2050年には90パーセント増加するのに対し、2 気候変動を考慮すると現状に比べて74パーセントの増加に留まると推定される。更に3 1人当たりの取水量の増加も考慮すると、79パーセントの増加となり、将来の水需給の逼迫を考える場合には第一義的にはやはり人口増加が問題であることがわかる。
この水ストレス比の1995年に対する2050年の推計結果の比を見ると、アフリカを中心として中近東へかけての地域で水ストレス比が大きく増大すると見込まれる。これは、現在も充分に水資源を利用することができていない地域で、更に水を多く使わざるを得ない状況になるということである。現状のまま放置すればそうした発展途上地域において水需給バランスが崩れる可能性がある。それを回避するためには、そうした国々での貧困問題に取り組み、経済成長を促し、社会基盤施設の整備や効率の良い統合的な水資源マネジメントの仕組みを構築することを、現在から準備し始める必要があるだろう。
サステイナブル・デベロップメントという言葉は、持続的開発、あるいは持続的発展と訳され、あたかも開発や発展をし続けることが重要であるかのような印象を受けるが、その本来の趣旨は、おそらくサステイナビリティ・デベロップメント、すなわち、社会に持続性を構築することなのではないだろうか。
グローバルな統合的水資源マネジメントのためにも、世界の水循環、水利用に関して、日本がもっと興味を持ち、必要に応じて適切なアクションを起すことが必要であろう。
1 水循環予測 ― グローバルな水循環予測と世界の水資源 総合地球環境学研究所助教授 沖 大幹
1-1 地球上の水と水資源
水の惑星とも呼ばれる地球であるが、地球表層における水の総重量は地球全体のわずかに0.02パーセント程度でしかなく、地球は水の惑星というよりは、水に覆われた惑星である。
さて、地球上に存在する水のうち、水資源として利用可能な水はどれだけであろうか。ある水の利用が人間社会に何らかの価値や便益をもたらす場合、その水は単なる物質ではなく経済財、すなわち、水資源、として呼ばれることになる。従って、水としてどんなに多量に存在していても、利用にあたっての経済的な価値が低いとみなされる場合には、その水は水資源としては存在しないのと同じである。したがって、水資源を考える際には、自然界における水の存在や循環とともに、常にそれを使う人間側の需要、何にどの様に利用するためどのくらい必要なのか、もあわせて考える必要がある。
一般に水資源といった場合、まずは飲み水を思い浮かべられることが多いが、資源としての水は
- 農業生産のための灌漑や排水(農業用水)
- 工業製品生産のための工業用水
- 都市等における生活用水
- 水力発電などのエネルギー生産
- 舟運・漁業・景観のための水面・低水維持
- 水生生態系と沿岸域の海水保全
などの目的に利用される。
海水を飲み水や生活用水、農業用水として用いるためには多大なエネルギーとコストをかけて塩分濃度を低くする必要があるため、河川水や地下水等の淡水が利用しやすい状況では、通常水資源とはみなされない。氷河や雪氷も、その大半が南極やグリーンランド等、水を必要とする人間社会から離れたところに存在するので、通常はわざわざ人為的に輸送して融かしてまで水資源として利用されることはない。地下水は全体では2,300万km3存在するとされるが、このうち地表に近く水資源として比較的利用しやすい深度百メートルまでの地下水は氷河に覆われていない全陸地合わせて約360万km3程である。これに淡水の湖沼の水、約10万km3等を加えても380万km3にもならない。次節でも紹介する通り、20世紀の終り頃には、世界全体で年間3,800km3の水資源を利用していたと算定されている。すると、現在のペースで水資源を使っていると、ちょうど千年位で淡水資源を使いきってしまうのだろうか。
もちろんこの計算は間違っている。石油や石炭の様に地下から掘り出して利用(燃焼)したら物質が変化してしまい再利用はできない化石燃料などとは異なり、通常の水資源の利用では、物質としての水はほとんど失われることはない。蒸発してなくなったかのように見えても、それは液体の水が気体の水蒸気に相変化しただけで、やがて降水(雨や雪)として大気から再び海や陸に降り注ぐ。現実には、水資源の利用の大半は、こうした水文循環の一部を人間社会に導くことによって行われており、地下水に比べて汚染されやすいという欠点はあるものの、標高の高い地域への降水の位置エネルギーを利用することにより、安価に輸送配分が可能な河川水が良く利用される。
毎年約12万km3程度の降水が陸上に到達し、そのうち約2/3は土壌表面からの蒸発や植物の葉からの蒸散によって大気へ戻り、残りの年間約4万km3の水が河川を通じて陸から海へ流れ出ている。ある瞬間に河川河道内に存在する水の量は観測値に基づいて平均約2,000km3程度であると算定されているので、河川水は平均して年間約20回入れ替わっていることになる。通常はこの全世界で約4万km3という量が、自然界で最大利用可能な水資源量だとみなされている。
実際には、地下水に関しても、通常利用されているのは水文循環に組み込まれた地下水で、人間によって汲み上げられてなかったとしたら湧水となって河川を通じてやがては海へ流れるか、あるいは地下水のまま海底から湧出する水であると考えられ、前者は上記約四万km3に含まれることになる。海に湧出する地下水量に関する測定例は少なく世界的な推定値もばらつきが大きいが、多くとも河川流出量のせいぜい10パーセント程度であると考えられている。
なお、現在の水文循環には組み込まれていないか、あるいは循環速度がきわめて遅く、取水によって低下した地下水面(あるいは地下水の圧力)の回復に数百年といった長期間を要するような地下水は化石水と呼ばれ、その利用は持続的ではない。しかし、一般的に言って、水資源の特徴としては、次の三つが重要である。
- 循環型、持続的な資源である
- 他の物質資源に比べて重さや体積あたりの単価が安い
- 必要な時に必要な場所に必要な質の水でなければ価値が無い
水文循環の原動力は元をただせば太陽からの放射エネルギーであり、これによって蒸発散する際に淡水化され、海水や汚れた水も淡水資源として利用可能になる。標高の高いところへの降水は位置エネルギーを持つので動力を使わずとも輸送配分できるし発電を行うこともでき様になる。したがって、時間あたり利用可能な量には上限があり、その値の年々の変動も少なくはないものの、太陽エネルギーが適正に供給される限り、水は持続的に資源として利用可能である、ということになる。循環型である、ということは必ずしも無尽蔵であるということを意味しない。なぜなら、ある時間内に利用可能な水の量には上限があり、それ以上は利用できないからである。また、化石水(fossile water)と呼ばれる涵養されていない地下水は鉱物資源と同様に利用し続けるとやがては失くなってしまう。
二点目の水の価格に関して、ミネラルウオーター等、瓶入りで小売りされる水は1リットルあたり100円から200円位なのでガソリンよりも高い、という言い方もされるが、瓶入りの水が水資源利用全体に占める割合は無視できるほどであり例外的に高価なのである。蛇口をひねって出てくる上水道の水は世界的には1m3(千リットル)でおおよそ1ドル程度、日本では一般家庭の平均的支払い価格が1m3あたり約140円であり、瓶入りの水は水道水の約千倍の値段に相当していることがわかる。ちなみに日本の上水道の給水原価は180円となっていて、家庭に対しては逆ざやとなっている。
水質基準が緩い工業用水道に関してはさらに安く、約25円/m3となっている。家畜の飼料として使われる大豆油の絞りかす(大豆ミール)が安い時でも一トンあたり1万円以上、価格低下で回収率低下がリサイクル促進上の問題ともなっている古紙でも5,000円/t以上、安い鉄屑でも3,000円/t、等という価格に比べると、ちょうど1tに相当する1m3で200円程度の水が、いかに安いか、という実感がわくのではないだろうか。
価格が安いという水資源の特徴は、貯蔵したり運搬したりするコストが相対的に高くなる、ということにつながり、結果として必要な時に必要な場所に存在する水でないと、水資源としては価値が下がる、という第3点目の特徴につながる。逆に言うと、だからこそダム貯水池の用にスケールメリットを生かした貯留施設や、パイプラインの様に安価な貯留、輸送手段が模索され、利用されているのである。人間が利用しない、という観点からは河口から海へ流れ出る水は無駄であるという考え方もできるが、本来そうなってしまう水を貯めて必要なときに使える様にするということは、水資源を産み出している、と考えて良いことになる。逆に、森林土壌や水田の様に大量の水を蓄えることが可能であっても、必要な時に人間が利用できる様にコントロールできなければ、水資源としては存在しないのと同じだということになる。同様に、必要な質が確保されていない水も資源としては価値がないため、量の消費を伴わなくても質の悪化は水資源の消費であることになる。
その他の水資源創出の手段としては、下水や産業排水等の再生利用、雨水貯留、海水の淡水化等が実際に利用されているが、日本では全部合わせても、河川水や地下水利用の一パーセントにも満たない。しかし、アラブ首長国連邦の様に自然に循環している淡水水資源が少なく、かつエネルギーコストが相対的に安い国では、取水量の20パーセント近くを海水の淡水化でまかなっている例もある。逆に言えば、タンカーやパイプラインでの輸送、あるいは海水の淡水化など、コストをかければ淡水を得ることは可能なのであり、水が足りない、ということは水という物質が足りないということではなく、安価な淡水が足りない、という事だと考える必要がある。
また、雲の種類に応じてヨウ化銀やドライアイス粒子を散布し、降水を増強しようといういわゆる人工降雨の試みが、水資源開発の一貫として行われている例が21世紀になってからも世界的には存在する。しかし、日本では1960年代に精力的に研究が行われた結果、降水量を増やす効果は平均して約五パーセント程度である、という結論が得られており、既存の雲からの降水量を増やすことはできても、晴天時に新たに雲を形成させることはできないためまさに必要な時に必要なだけ水資源を生成できず、さらにコストと便益との関係も明瞭ではないため、現業での積極的な運用はなされていない。
1-2 日本の水資源利用の現状
では、それらの水資源は何の目的にどの様に使われているのだろうか(土地・水資源局,2002)。水資源というとまずは飲み水を思い浮かべる人が多いだろう。しかし、尿や発汗、呼気に含まれる水蒸気等、体から排出される水分量から算定された人間1人1日当たりに必要な水分の量は2~3リットル程度だとされ、しかも、食物に含まれる水分や、食物を分解(代謝)する際に生じる水分が合わせて約1リットル程度あるので、液体として飲む水分はせいぜい2リットル/日、年間1m3足らずと水資源量としては少量で済む。逆に言うと、だからこそ、仮に飲む水すべてを瓶詰めミネラルウオーターにしたとしても年間1人当たり10万円程度にしかならないので、大金持ちでなくても水道水の千倍以上の値段の瓶詰水を飲み続けられる、というわけである。
日本では降水量が年間約1.7mでそのうち0.7m分位が蒸発散で失われて結局水深1m分が河川水や地下水となって水資源として利用可能であるという目安になっている。すなわち、日本では1m2の土地に降った雨から蒸発散で失われた後の残りの分だけで、人1人が1年間に飲む水の量が確保できるという計算になる。
これに対し、家庭や都会の事業所、公園等で使われる生活用水は、平均して日本人1人1日あたり320リットル、配水経路でのロス等を含めて年間130m2程度、日本全体で年間約160億m3になる。家庭内で消費されているのはこのうち250リットル/人/日(東京都の例)とされ、残りはホテルやデパート等の大規模施設等で消費されている。この内、家庭では風呂、トイレ、炊事、洗濯等にほぼ1/4ずつ使い、洗面その他に利用される水の量は全体の10パーセントにも満たない。昭和30年代には日本人1人1日あたり約半分の生活用水利用量であったのが現在の様に1人1日あたり320リットルも使うようになったのは、上水道や下水道整備率の向上や生活水準の向上に伴う変化、すなわち、銭湯から内風呂へ、汲取式から水洗式トイレへ、全自動洗濯機の普及、といった変化による影響である。
ここで、これら生活用水への用途を考えると、水を使うのは主に洗浄のためだ、という点に気づくだろう。風呂は体を洗うため、トイレでは便器を洗うため、炊事では主に食材や食器を洗ったりするため、洗濯では衣類を洗うため、そして洗面では歯を磨いたり手や顔を洗ったりするために水を使うのである。そういう意味では飲み水も、汗を出して体温を調節する以外に体内の不要物を排出するために必要だという見方もできる。つまり、生活のために水を使うのは水に汚れを運んでもらうために他ならない。時に「水をきれいに使いましょう」という標語を目にすることがあるが、極端に言えば、水を汚さなければ水資源的には使っていないのと同じである、とも言える。逆に、水を使って汚したとしても、きれいにすればまた水資源として利用可能になる、というわけである。
日本人の場合、飲み水の約百倍の生活用水を使用していることになり、1年間に利用する水資源量を確保するためには、1人あたり約100m2の土地が必要だということになる。これは、1万人/km2人口密度に対応し、東京都の人工密集市街地が概ねこの程度の人口密度となっている。したがって、都会では、そこに降った雨のうち、蒸発で失われる分はしょうがないにしても、残りをすべて使える様にしなければ自分達の住んでいる領域の水資源では暮らしの水を賄えない、ということになる。
日本における工業用水の使用量は年間560億m3程度であるとされるが、これは淡水の利用のみで、これ以外に海水の利用が150億m3程度ある。しかし、工業排水の水質規制が強化徹底されるに従い、工場内で再利用されるいわゆる「回収利用」が進み、現在では回収率は80パーセント近くにもなっていて、河川や地下水等からの取水量(淡水補給量)は年間120億m3程度と、実際に工場内で利用されている淡水の1/4~1/5で済んでいる。
これに対し、日本の農業用水の使用量は年間580億m3程度と推計されており、日本全体の水資源使用量約900億m3の2/3を占め、その農業用水の9割以上が水田灌漑用水として利用されている。そうした水田に引かれた水は、蒸発したり稲によって蒸散したりして失われる部分もあるものの、浸透して地下水を涵養したり、河川へ還流したりする分もあり、農業用水として取水された水がすべて消費されるわけではない。しかし、この点に関しては生活用水や工業用水に関しても同様の側面がある。下水処理場や排水処理された水は再び水域へ還流し、放流先が海ではなく川であれば、下流で再び浄化して利用されているわけであり、農業用水に限らず、生活用水や工業用水等も含めて、ここで上げた数字は水資源の取水量として理解される必要がある。日本では、農業用水はほとんど河川から取水されるため、表流水からの取水が全体の8割以上を占めているが、生活用水や工業用水などの都市用水では地下水からの取水が1/4程度を占め、世界的にみても、特に飲み水等に関しては地下水からの取水に依存する割合が高くなる。
また、減反調整している分を含めて日本の水田面積は約270万ha程度あるので、面積あたり約2m3、降水量と同様の水柱換算で2,000mmの水が水田で毎年利用されていることになる。この2,000mmという値は、小麦やとうもろこし等他の穀物に比較してかなり大きいが、湛水させて栽培するのは、単に稲を生育させるためだけではなく、他の雑草の繁茂を抑えたり、温度変化を小さくしたりという管理上の目的もあるとされるので、稲という植物の水効率が悪いということを必ずしも意味しない。何度も述べているように、日本の場合降水量のうち水資源として利用できるのは水柱高にして1m分なので、水田面積当たり2m3の水資源を灌漑取水するためには、水田の上流には、その水田の少なくとも2倍の面積の水源涵養域が必要だ、ということになる。
農業用水に関して、土地改良区費等、日本の農家の水利費負担額は10aあたり8,000円程度である。水田の面積あたり2m3の水資源利用量から算定すると、農家が直接負担している水の利用料金は4円/m3程度となる。生活用水に比べて数十分の一というこの価格は、世界的にみても妥当な値である。工業用水に比べてもさらに安い理由としては、農業用水に利用する水は基本的には浄水処理を必要としないことや、低エネルギー負荷の輸送配分システムが古くから整備されていること、水路のメインテナンスや配分等に関して農家が労働力提供という形で実質的にかなりの対価を支払っていると見做せること、などがあげられる。農業用水には年間5億m3の畜産用水を含み、全国で年間約50億m3程度利用されている養魚用水は含まれない。
その他の水資源の利用としては、発電がある。日本では全発電量に占める水力発電の割合が10パーセントを切るなどエネルギー供給の主要ソースではなくなったものの、国際的にみると、今後開発の余地を残しているいわゆる包蔵水力エネルギー量は発展途上国を中心としてまだまだ多いと言われている。水力発電は水の重力エネルギーのみを用いて水質にほとんど変化をもたらさないため、生活用水や工業用水、農業用水等への利用を考えると水力発電は水資源を消費していないという見方もできる。しかし、その重力エネルギーは、本来ダム貯水池に堆積する土砂を下流へ運ぶために使われるはずだったとも考えられ、貯留容量の減少や下流域への土砂供給の減少に伴う河底低下や海岸決壊等を考えると、水力発電は何のデメリットももたらしていないということはできない。やはり人間が自然界に何らかの働き掛けを行って便益を引き出す際には、普通は何らかの負の影響があると考える方が良いだろう。
また、水の温度を利用する水資源の利用として、消雪パイプ用水に約4億m3足らずが年間利用されていて、その85パーセントが温度の一定している地下水を利用している。また、雪を排出するための流雪溝に流すための水として消雪パイプ用水よりも多い年間約7億m3足らずの水が利用されている。
その他、舟運、漁業、景観・レクリエーションのためにも水面、水体が確保されている必要があり、さらには水生生態系、沿岸域の生態系保全を念頭に置いた河川水量、良好な水質の確保が広い意味での水資源の開発とマネジメントの目標であると考えるのが現在の趨勢である。すると、それらの個々の目的に沿う流量を確保するために、他の用途、例えば生活用水の取水量が制限を受けるとすれば、例えば、生態系(の保全)も水資源を使用している、と言う風に考えねばならないことになる。水資源はその循環の一部を利用するのみで、石油や石炭の様な化石燃料とは異なり、基本的に水を使ったからといって水が失われることはない。しかし、その水を他の用途に利用することが妨げられるのであれば、それは水資源を使っているということになるのである。すなわち、排他的な水の利用こそが、水資源を利用することに他ならない、ということになる。
1-3 間接的な水の利用
さて、前節で紹介した通り、日本の水資源使用量は、生活用水に国民1人あたり1年間に約130m3、工業用水の淡水補給量が1人あたりに換算して約110m3、そして農業用水が約460m3で、合計約700m3になる。しかし、一般に、先進国では1人あたり年間1,000m3の水資源が必要だとされる。この差は何に起因するのであろうか。日本は世界に先駆けて節水を心掛けているのであろうか。
グローバルにみても、水資源のもっとも大口のユーザは農業である。逆に言うと、農業製品は水資源を多量に投入してできた産物である、ということができる。実は日本は、先進国にしては珍しく大量の農畜産物を輸入ばかりしており、このため、結果として国内の水資源消費量が相対的に低く抑えられているのである。すなわち、農畜産物を輸入することは、あたかも水を輸入しているのと同じである、という意味で、そうした農畜産物のことを水資源的観点からvirtual waterと呼ぶことがある。仮想水と直訳される場合もあるが、他国の水資源を、農畜産物の輸入を通じて間接的に消費することから、ここでは間接水と訳すことにする。
間接水は、ロンドン大学のトニー・アラン教授が、1990年代の始め頃に考えついた概念である。彼は、人口1人あたりの利用水資源可能量が非常に少ない中東に於いて、水をめぐる争いが、想定されるほどには深刻ではないのはなぜか、を説明するツールとして間接水の概念にたどり着いた。すなわち、中東の産油国等で生活水準も高く、それを維持するには多量の水資源が必要であると考えられる国でも、実際の水資源の使用量は少ない。それは、水を相対的に大量に必要とする農産物を自国で生産せず、他国からの輸入によって賄っているために、生活水準的には自国の水資源は不足していても、結果的には水の需給バランスが満たされているからだ、つまり、それらの国では石油を売って間接水を買っている様なものだ、というわけである。
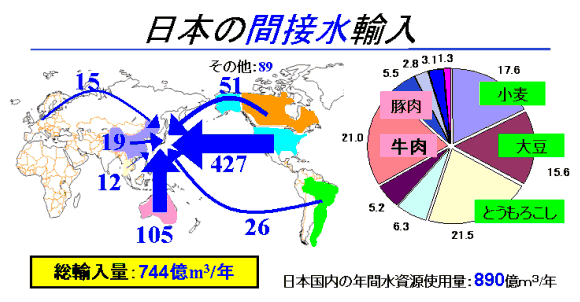
図1:日本が1年間に輸入しているヴァーチャルウオーター(間接水)。日本が輸入している穀物、肉類、工業製品を生産するのにどの程度の水資源が必要であるか、に関して2000年頃の輸入統計に基づいて算定。
では、そうした間接水の輸出入の実態はどの程度なのであろうか。間接水の輸出入を算定するには、米1t、とか、小麦1tを生産するのに必要な水の量、水消費原単位、をまず知る必要がある。水消費原単位の算定には様々な手法が考えられ、また、値も人によってまちまちであるが、平均的な栽培期間とその間の平均的な蒸発散量を仮定し、面積当たりの収量を知ることによって算定することができる。この場合、河川に流れる水を使うという狭義の水資源ではなく、植物が蒸発させることも水資源の利用である、という広義の水資源の利用の定義となっている点に注意されたい。
その様にして筆者の研究グループで過去の数字を再検討したところ、可食部に対する重量比で米の場合には約6,000倍、小麦では約2,900倍、大豆では2,400倍、とうもろこしでは1,000倍の水が必要である、と算定されている。すなわち、1kgの白米を得るためには、実は6m3もの水資源が投入されているということになる。ちなみに、蒸散量のうち実際に光合成によって固定される水分は約0.1パーセント程度であるとされ、植物が蒸発散によって消費する水も、実際には根から養分などを葉へ運ぶ媒体としての役割が強い。また、葉の温度が上がりすぎないように調整するためにも蒸散が役立っている。
従来は、例えば小麦の場合、重量比で約1,000倍の水資源が必要である、という風に仮定して議論が進められることも多かった。ここで示している値はこの1,000倍という値よりもかなり多目であるが、それは、従来の値の方が、可食部の重さあたりで換算していなかったのかも知れないし、灌漑水量のみを水資源の利用だとして間接的水消費算定に組み込んだのかも知れない。また、先進国で単収が多い地域を基準とすると、水資源消費原単位は低めに見積もられる。そうした不確実性があるので、以下の推定値に関しても、オーダーがそのくらいである、という有効数字1桁程度の信頼性であり、今後数値が大きく変る可能性がある、という風に受け止めていただきたい。
さて、間接水の概念は穀物のみならず、畜産製品にも拡大して考えることができる。家畜の飼育に投入される飼料の内訳、飼育期間、そして屠殺後の歩留率等を考慮し、飼料中の穀物等の水消費原単位を利用すると、穀物の場合と同様に精肉に対する重量比で、鶏肉では4,000倍、豚肉では6,100倍、そして牛肉では約22,000~25,000倍もの水資源が投入されているとみなす必要があるという結果となった。一般に、生活水準の向上に伴い、肉類によるカロリー摂取割合が増える傾向にあることが知られ、そうした肉食への移行は水資源需要の増加に直結していることになる。なお、ここで利用した飼料の配合や飼育期間等は日本での値なので、いわば、輸入している畜産物を日本で得ようとしたら、その飼料用穀物を生産するのにどのくらいの水資源がより必要であったか、という数字に相当している。牛肉の水消費原単位が大きくなる理由は、牛は豚や鶏に比べて飼育期間が長く、また、1日あたりに必要な飼料の量も多いにも関わらず、得られる肉の量がそれほどには多くない、という牛のカロリー換算効率の悪さに起因している。
さらに、工業製品の生産にも水資源は利用されており、工業製品の輸出入にあたっても、間接水がやり取りされていると考えることができる。工業用水統計には、各産業別の出荷額あたりの水資源使用量が示されており、例えば、紙パルプ製造業では出荷額1億円に対し約45,000m3、繊維工業では出荷額1億円あたり約25,000m3の水資源が淡水供給量として利用されているという値が得られる。ここで、こうした算定では、そこでの製造に関わる水資源使用量だけで、原材料の生産に関わる水資源使用量が考慮されていない点に注意が必要である。
1996~98年の農畜産物輸入量、ならびに1998年の工業製品輸出入量の統計に対してこうして得られた水資源消費原単位を適用し、世界のどの国や地域からどの程度の間接水を輸入していることになるかを示したのが図-1である。工業製品に関しては総輸出量が16億m3と、総輸入量の10億m3を上回っているが、図-1には、その差ではなく、輸入量そのものを加えている。水資源消費原単位が大きいこともあって、牛肉の輸入が間接水の輸入には支配的な要因として効いており、アメリカ、オーストラリア、カナダ等が間接水の主要輸入元となっている。穀物として輸入されている大豆やとうもろこしも、大豆油の絞りかすや、とうもろこしそのものが日本では概ね飼料用として消費されるので、ある意味では間接水の輸入は、肉として輸入するか、穀物として輸入してから肉にするか、の違いはあるにせよ、畜産製品、特に国内での牛肉の消費のために引き起こされているとも言える。
日本の間接水の輸入量は全部で年間約744億m3にものぼり、国民一人あたりにすると年間約600m3に相当する。国内で利用している水資源量700m3と併せると合計1,300m3となり、先進国としてはやや多目の水資源の利用量となる。ただし、日本の場合には、中東の様に水資源が不足しているから間接水を輸入しているというよりは、そうした(飼料用)穀物の生産に必要な土地面積が足りないために海外に依存している、という側面が強い。
また、農畜産物や工業製品の生産には、水と土地だけではなく、労働力も投入されている。そして、工業製品の原材料や、人一人が生存するために必要な水資源量を考えるには、結局、産業連関表を用いたライフサイクルアセスメント的な手法を援用して、水に関するライフサイクルアセスメント、すなわち、各産業やセクターにどのくらいの水資源が投入されて、最終的にどこで消費されたか、をマクロに追い掛ける必要があると考えられる。こうした研究は現在手がけられ始めたところであり、社会のどの分野でどのくらい間接的に水を使用している事になるのかが、今後、徐々に明らかになっていくものと期待される。
1-4 グローバルな水需給の現状と将来
前節で示された様に、日本人は生活を支えている水資源の半分近くを海外に依存している。それが健全な経済活動に基づいていて、また、途上国等に環境負荷をかけていないとしても、利用可能な水資源量は時間的な変動も激しく、世界の水資源需給がどういう状態にあるかを常に気にかけておく必要があると考えられる。
では、世界の水資源は現在どの様な状況にあり、今後どの様に推移すると考えられるのだろうか。まず、現状の水供給サイドに関しては、本章の最初に述べた通り、年間約40,000km3の水が世界全体としては最大限利用可能である。これに対し、人間活動に起因する水資源の利用量は、ロシアのシクロマノフ博士等が1995年に対して推計した結果によると、農業用水に2,500km3、工業用水に750km3、生活用水に350km3、そして貯水池からの蒸発として200km3の合計3,800km3を毎年利用しているという。すなわち、最大利用可能量の約10パーセントを二十世紀の終り頃には人類は利用していたことになる。
ちなみに、日本は約380km3の最大利用可能水資源量のうち、約90km3を国内で一年間に利用しているので、最大利用可能水資源量の25パーセント程度まで利用開発をすでに進めている、ということになる。水ストレスのアセスメントを行う際には、この利用可能量に対する水利用量の比(水ストレス比RWS)が指標として用いられることも多く、RWSが40パーセントを越えている場合には、水ストレスが高い状況下に置かれている、という目安として用いられる。確かに、水ストレス比RWSが大きいということは、利用可能な水資源に対して相対的に多量の水を利用しているということであり、時間的な変動が激しい水資源の利用が安定しにくい、あるいは寡雨・渇水に対する柔軟性に欠ける、という懸念が示唆される。
しかし、別の見方をすると、水ストレス比RWSが大きいということは、不安定な水資源供給を平準化して効率よく利用するための各種社会基盤、利用システムが整っている状態であるともいえる。そこで、将来の水需給アセスメントの結果を吟味する場合には、水利用比等の水ストレス指標そのものだけではなく、その水ストレス指標(例えばRWSの現状からの変化にも着目する必要があると考えられる点に注意が必要である。他によく利用される水ストレス指標としては、一人あたり年間利用可能水資源量があり、これが500m3よりも少ない場合、高水ストレス下にあるとされる。この場合でも、間接水の輸入によって水需給が緩和されているとか、水が少なくて済む穀物を食べる食文化や生活水をほとんど使わない生活スタイルが伝統となっている、等の要因も考えられるので、一律に水ストレスを分類するのではなく、将来予測における現状からの変化の大きさを問題とすべきであろう。
発展途上国においては、現在でも水不足による貧困、不衛生状態、病気等に悩む地域があり、さらに
- 人口の増加
- 生活レベルの向上
- 都市化の進展
等により今後しばらくは水需給の更なる悪化が予想されている。人口の増加は食糧となる穀物の需要を増大させ、生活レベルの向上に伴う飼料用穀物等の間接消費の増加がさらに穀物需要の増加をもたらすことが懸念されている。
1-5 グローバルな水需給の将来推計
世界の水需給の将来予測を考えるには、当然の事ながら、水供給側と水需要側の両側面を考慮する必要があるが、供給側の変化が語られることは少なかった。例えば世界水フォーラム等に水資源需給の基礎資料を提供しているShiklomanov(Shiklomanov, 2000)では、水資源供給(自然)側の変化として考えられる気候変動に関しては不確実性が大きく、地球温暖化の影響が顕在化するのも21世紀後半以降であろうからという理由で、自然の水循環は変化しないものとして将来に関する世界水資源アセスメントがなされている。
これに対し、Vörösmarty等(Vörösmarty et al. , 2000)では、カナダの気候モデルによる推定値に基づき、1985年に対する2025年の降水量と気温の変化を利用して水収支モデルから河川流量変化を推定し、需給バランスの変化が調べられている。その結果によると、気候変動のみを考慮した場合、グローバル平均での水資源需給比(需要量/水資源賦存量)は4パーセント増大してより逼迫する、という結果になるのに対し、人口増加と経済成長に伴う需要増大のみを考慮すると水資源需給比は50パーセントの増大、両者を考慮すると61パーセントの増大という結果が示されている。すなわち、2025年を想定すると気候変動よりも人口増大や経済成長がグローバルな水需給に及ぼす影響の方が大きい、ということになる。
しかしながら、人口増加や経済成長に伴う将来の水需給の逼迫は現在すでに水ストレスが生じている主に発展途上国で深刻であるのに対し、地球温暖化等の気候変動は先進国・途上国を問わず水資源需給に影響を及ぼす可能性があり、世界平均で考えて気候変動による水需給変動が相対的に小さいからといって看過することはできない。また、気候変動に関する政府間パネル(IPPC;International Panel on Climate Change)による将来予測が複数の気候モデルの結果に基づいて議論された様に、グローバルな水資源需給の将来予測には、複数の研究グループが推定値を提出し、それらの結果の吟味を行うことが不確実性の見積もりや、信頼性の担保のためには不可欠であると考えられる。
利用可能な水資源量については、気候変動、特に地球温暖化に伴う水循環への影響を考える必要がある。温度上昇の直接的な影響としては、
- 融雪促進による河川流況パターンの変化
- 氷河・氷床の融解に伴う河川流量の一時的な増加
- 農作物育成暦の変化による水需要期の変化
- 水需要原単位(人口あたりの量)の増加
- 水温の変化(上昇)に伴う水質の変化(悪化)、生態系への影響
- 損失量(蒸発散量)の増加
間接的な影響としては
- 降雨変動パターン(豪雨・寡雨)の変化と、それに伴う河川の洪水流量、渇水流量の変化
等が懸念されている。このうち、量的にもっとも影響が大きくほぼ確実なのは中高緯度で融雪水が重要な水資源となっている地域であろう。日本のみならずアメリカに関しても温暖化が水資源に与える影響として積雪量の減少と冬季の流量の増加、夏季の土壌水分量や水資源賦存量の減少が深刻であると予想されている。
温度に関してはほぼすべての研究グループの温暖化予測結果でも高緯度地方を中心として地表面気温の上昇が予測されているが、降水量の変化に関しては、年平均値の増減分布に関する予測もまちまちで、洪水や渇水に関わる様な極値と呼ばれる極端な値に関してははっきりとした科学的な合意はできていないのが現状である。二十世紀の終り頃から、大洪水や大渇水などの異常気象がある度に地球温暖化との関連が語られるが、科学的にはっきりとした関連が示されるのは、二十一世紀の終り頃になってからだろうと思われる。また、実際に将来の水需給アセスメントを行った研究成果において、高い水ストレス指標下に置かれることになる人口の推計に及ぼす地球温暖化の影響は、需要側の変化に比べて二割程度と副次的であることが示されており、グローバルに考えると、地球温暖化の影響はそんなに深刻ではないとも言える。しかし、先進国においては、人口増やさらなる生活水準の向上に伴う生活用水使用量の増大、工業用水の増大などがあまり見込まれず、需要側に大きな将来変化が考えられないため、将来の水需給アセスメントに対する気候変動の影響が相対的に大きくなり、よりきめの細かい将来の気候変動予測が重要である。
これに対し、途上国を中心とした地域で深刻な水需要の変化をもたらすのが人口の増加である。二十世紀後半の食糧増産は耕地面積の拡大ではなく主に灌漑面積の拡大と肥料投入量の増強、品種改良等によって実現されてきたため、人口増加に伴う食糧需要の増大により、灌漑用水需要のさらなる増大が見込まれる。すでに述べてきたように、水資源の消費量としては農業生産用が最も多いので、水不足が生じると、飲み水が足りなくなって喉が乾いて苦しむのではなく、食糧が不足気味になって飢饉に陥る恐れがある、という事になる。もちろん、途上国でも都市に集中すると思われる人口が必要とする生活用水をいかに確保するか、また、今後まだまだ伸びが期待される途上国での工業用水をいかに確保するか、という点も考えねばならない。さらに、地球温暖化が生じた場合には、農作物育成歴が変化することによる水需要期のすれ、現在でも暑い夏の方が生活用水需要は多いことから温度上昇に起因する生活用水需要の増大、水温上昇による水質悪化に伴う有効に利用できる水資源量の減少等も懸念される。
こうした中で、人口増加、気候変動、そして経済発展に伴う水消費需要の増大を考慮して、2050年の水ストレス比RWSを算定した結果を図-2に示す(沖ほか、2002)。
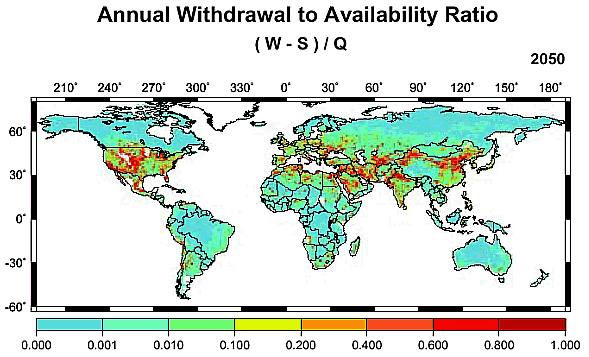
図2:2050年の水ストレス比RWSのグローバルな分布。最大限利用可能な循環淡水資源量に対する取水量の比であり、この値が0.4よりも大きい場合水ストレスが高い状態にあるとされる。
自然系の水資源賦存量の将来推定に関しては、東京大学気候システム研究センターならびに国立環境研究所が開発している大気大循環モデル(GCM)による二酸化炭素倍増時の数値実験結果を利用した。これはほぼ2050年頃の状況に対応すると考えられる。気候予測結果を水資源賦存量推定に応用する方法としては、
- GCMの河川流出量予測値をそのまま利用する
- GCMの降水量や気温等の予測値を陸面水文植生モデルなどに与えて、水(プラスエネルギー)収支を算定して利用する
- GCMの河川流出量算定値に関して現状に対するシミュレーションと将来に対するシミュレーションの変化を、現状に対する信頼のおける河川流出量算定値に対して勘案して利用する
- 同様にGCM内の将来に対する変化量を現状の降水量や気温に対して勘案し、オフラインシミュレーションによって将来の河川流出量を算定して利用する
等が考えられる。現状では、GCMによる現在の気候条件に対するシミュレーションが降水量の絶対値に関しては必ずしも完全ではないので、ここでは3に従い、GCMにおける河川流出量の現状シミュレーションと将来予測の差を、観測値に基づいて算定した河川流出量に上乗せすることによって将来の河川流出量とし、グローバルな河道流下モデルを利用して将来の河川流量を求めた。
一方で、需要側に関しては、次の様なシナリオを設定した。まず、人口に関しては国連の中位推計にしたがって増加すること、また、農業用水取水量は人口増加に比例して増加するとした。これは、過去1960年頃から1990年にかけての灌漑面積と人口増加がほぼ対応していることに依拠していて、今後さらにきめ細かく推計する必要がある点である。また、単位灌漑面積当たりの灌漑取水量も変化しないと仮定した。生活用水、工業用水の水需要原単位の増加については、既存の将来推計を利用した。工業用水に関しては高橋等(高橋ほか、2002)の水使用効率改善係数に加えて、GDPの増加に伴い工業用水取水量が伸びることを考慮した。
図-2を見ると、アメリカ中西部、中近東、インドパキスタン国境~インダス川流域、中国北部の河北平原等でこの比が高くなっていることが分かる。しかし、実はこの分布の概要は1995年に対するアセスメントと大差なく、現在水ストレス比が高い地域が将来的にも高い、という将来展望なのである。それは、基本的に現在水ストレスがかかっている地域で、将来的により深刻な状況が想定される、ということではあるが、基本的には過去のトレンドに基づいて将来推計を行った本研究の限界でもある。
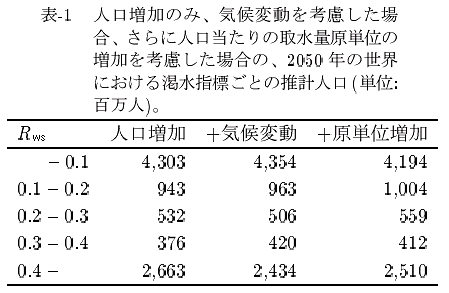
しかしながら、2050年の世界人口のうちの何人がどの程度の水ストレス比RWSの値に分類される地域に住むことになるか、を、人口増加のみを考慮した場合、気候変動も考慮した場合、さらに取水量原単位の増加も考慮した場合を比べてみると(表-1)、RWS>0.4の高い水ストレスにさらされる人口は、現状に対する推定値14億人に対して、人口増加のみを考慮すると2050年には90パーセント増加するのに対し、気候変動を考慮すると現状に比べて74パーセントの増加に留まると推定される。さらに取水量原単位の増加も考慮すると、79パーセントの増加となり、将来の水需給の逼迫を考える場合には第一義的にはやはり人口増加が問題であることがわかる。
Vörösmarty等(Vörösmarty et al., 2000)も人口増加が主要因であるという結論的には同様であるが、彼らの結果では気候変動はグローバルな水需給をより逼迫させているのに対し、本研究で用いた温暖化時の水循環予測結果では、現状で水需給が逼迫している領域で降水量が増加し、グローバルに見ても降水量は増加しており、流量も増加して水需給を緩和させる結果となっている。
IPCC第3次レポート(Houghton et al., 2001)によると、21世紀の間に全球平均降水量は増加するだろうとされており、おそらくは全体としてみると地球温暖化の影響で水資源需給は緩和される方向にあると思われるが、個々の水問題は地域的であり、例えば中国でも、平均して降水量が増加しても、それが北部の黄河流域であるのか、南部地域であるのかで水需給に及ぼす影響は大きく異なってくる。したがって、そうしたきめ細かい空間的な違いをきちんと表現できるような数値モデルの解像度で、将来の水循環がどう変化するのかを的確に推計できる様にすることが極めて重要であると考えられる。
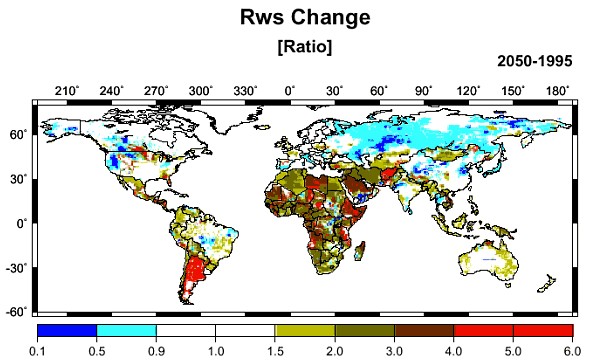
図3:1995年に対する2050年の水ストレス比の増減比
しかし、この水ストレス比RWSが現状に対してどの程度増減するか、という1995年に対する2050年の推計結果の比をとったのが図-3である。アフリカを中心として中近東へかけての地域で水ストレス比が大きく増大することが見て取る。これは、現在充分に水資源を利用していない、別の見方をすれば、現在も充分に水資源を利用することができていない地域で、さらに水を多く使わざるを得ない状況になるということである。水もバーチャルウオーターも低い方ではなくお金のある方に流れる、と言われる通り、現状のまま放置しておけばそうした発展途上地域において水需給バランスが崩れる可能性がある。それを回避するためには、そうした国々での貧困問題に取り組み、経済成長を促し、社会基盤施設の整備や効率の良い統合的な水資源マネジメントの仕組みを構築することを、現在から準備し始める必要があるだろう。
サステイナブル・デベロップメントという言葉は、持続的開発、あるいは持続的発展と訳され、あたかも開発や発展をし続けることが重要であるかのような印象を受けるが、その本来の趣旨は、おそらくサステイナビリティ・デベロップメント、すなわち、社会に持続性を構築することなのではないだろうか。水資源に関しては、二十一世紀半ばに予想される食糧需要増大に伴う灌漑水量の増大に対して、必要な地域に間接水を交易や援助を通じて輸送することを含めてなんとか乗り切れば、後は人口の伸びも鈍化し、生態系への水資源の確保も含めて、うまくバランスをとって水資源を上手に利用し続けられるのではないかと筆者は期待している。そうしたグローバルな統合的水資源マネジメントのためにも、世界の水循環、水利用に関して、日本がもっと興味を持ち、必要に応じて適切なアクションを起すことが必要であろう。
1-6 おわりに
この様に懸念される気候変動と世界の水危機問題に対し、学問的な取り組みが期待されるのは次の点である(沖、 2001)。
- 過去と現在に関して信頼のおけるグローバルな水循環情報を提供すること
- 集中豪雨の様な激しい大気に関する準実時間予測や、エルニーニョやラニーニャ等に伴う季節~数年スケールの気候の自然変動の予測に関する精度を向上すること
- 地球温暖化等の気候変化時における水循環の信頼のおける予測を提供すること
- どれだけの水が人間にとって現在利用可能であり将来それがどうなるのか、という点に関する定量的な推定
- 現在ならびに将来の水需要を満たす水供給を確保するためにはどの様な施策を取れば良いのかという選択肢の提示
- 仮想的な水の輸出入や間接消費の実態把握と「水資源安全保障」の枠組みの提示
これらのうち、最初の3つは、従来の自然科学やエンジニアリングの枠組みで充分推進可能な課題である。しかし、後の3つに関しては、技術レベルに加えて人間行動や生活文化、社会の法制度や体制等の現状の的確な把握と将来予測が必要であり、多分野の学際的な連携なしには解決が不可能である。
(参考文献)
Houghton, J., Y. Ding, D. Griggs, M. Noguer, P. van der Linden, X. Dai, K. Maskell and C. J. (eds.), 2001: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
高橋 潔、松岡 譲、島田 洋子、嶋村 亮、2002:気候変動下での地球規模の水資源評価と渇水対策戦略評価のためのモデル開発.第8回地球環境シンポジウム講演集、8、175-180
沖 大幹、安形 康、鼎 信次郎、虫明 功臣、猿橋 崇央、2002:気候変動を考慮したグローバルな水資源需給の将来.第6回水資源に関するシンポジウム論文集、6、649-554
Shiklomanov, I. A., 2000: Assessment of Water Resources and Water Availability in the World. UNESCO, Paris, France.
土地・水資源局水資源部、2002:日本の水資源.水資源白書、国土交通省、平成14年度版.
Vörösmarty, C. J., P.Green, J. Salisbury and R. B. Lammers, 2000: Global Water Resources: Vulnerability from Climate Change and Population Growth. Science, 289, 284-288.
沖 大幹、2001:世界の水資源と地球環境学、学術月報、51、1044-1048.
Taikan Oki, Yasushi Agata, Shinjiro Kanae, Takao Saruhashi, Dawen Yang, and Katumi Musiake:Global Assessment of Current Water Resources using Total Runoff Integrating Pathways, Hydrol. Sci. J., 46, 983-996, 2001.
2 水の需給
(要旨)
地球上の大気は、赤道上で暖められて上昇し、極地で冷却されて下降するが、地球の自転の影響でこの循環が3つに別れ、更に、これが1年を周期として少しずつ南北に移動すると解釈できる。その影響で、ある国では雨季が来る。また、反対に別の国では乾季が訪れる。この大気循環の機構が、降雨の場所的な偏在が出る一つの要因である。これに加えて、山脈・海流の影響などで偏在がさらに生じる。日本は年間1700~1800mmで、世界平均の約2倍であるが、日本は人間が多いため1人当たりではそれほど多くはない。水の時間的な偏在に関しては、雨期と乾期の存在が重要である。1年中雨が降る日本のような国は、それほど多いわけではない。また、乾燥地域でも最大の降雨のピークは低くない。
将来の水需給に関するモデルの一つであるPODIUMモデルによると現在の世界での総取水量3,800km3が2025年には4,300~5,200km3に増加し(13~37パーセントの増加)、世界人口の約半分が水ストレスの強い地域に住むことになる。
需要の面から考えると、人口の増加と所得水準の向上による嗜好の蛋白質への変化の影響により、将来の食料の必要量は21世紀中頃までに2倍になると予測されている。食料の増産にもっとも有効でなくてはならないのが、農業用水である。農業用水は世界の水需要の約7割を占めるが、これが食料増産のために、現在の17パーセントの増加が必要とされる。供給の面から考えると、これだけの水の需要の増加をまかなうため、ダムをつくるのが有効な方法であるが、現在のダムの建設状況から判断して、将来の大幅な供給増には限界がある。
現在、農業用水の利用効率が低いと言われており、その対策として、農民の自発的な参加によって水を管理する、それも、水路などの施設の建設段階から参加し、水の重要性についての認識を深めてもらうことがよいと言われている。
また、現在、開発途上国などで政府により水が無料で配られていることが水の無駄な使用を引き起こしているとし、水を経済財として位置づけ、市場原理による水資源配分の最適化を図ろうとする考えがある。これについては、それでは最も貧しい人々から水を取り上げることになる等の幾つかの問題点が指摘されており、現在いろいろなところで議論が行われている。
更に、水が少ない国は、少ない水で付加価値の高い作物を作って輸出し、その代金で水のたくさんある国の穀物を輸入すればよい。これは、仮想の水を輸入していることになる、という考え方がある。これは、貿易障壁は撤廃するべきであるという主張とつながり、WTOにおける議論と関係してくる。WTOにおいて、日本は、農業用水は環境を守るためにも、農村社会を育てるためにも大変役立っていると主張している。
特に、水田は大変に生物の生態系をはぐくむ。また、農業用水は、農村の生活のいろいろな面で多面的に役立っている、ということが重要視されている。
更に、開発途上国への援助については、「等身大の技術」であることが重要であり、現地で必要な技術開発には、先進国とは別の発想が必要で、開発途上国独特の技術の開発も必要である
将来的な水資源の需給の調整は、政策によって決せられるところが大きい。したがって、政策の提言が重要であり、その提言には、今まで以上に、より緊密な文系と理系の協力が必要である。水の将来予測においても、降雨の予測とかを含む供給の予測は理系の仕事である一方、需要の中で大きな部分を占める食料関係の予測は経済分野の方々の仕事である。この両者の協調をとりつけて、文系と理系との真の意味での融合を図ることが重要である。
2 水の需給 ― 偏在と対応の諸相 日本大学生物資源科学部教授 中村 良太
筆者の専門は、大学においては、農学部で「地域環境工学」と呼ばれている。が、これは最近の名前で、もともとは、農業工学科の中の「農業土木」であった。農業と土木と、その両方を兼ねあわせたところである。このような立場から、水の偏在と需給について述べる。
最初に、「水」という言葉の使い方について考える。土木工学の方で扱う水は、ここでは「水資源」という言葉であらわされるのがよいのではないか。この委員会でほかの委員がご担当になる、たとえば機能水なども「水」であるが、それと土木関係者が考える「水」は、そのとらえ方の角度が異なる。
更に細かく言えば、同じ土木系であっても、官庁で言う「水資源」と、我々研究者の言う「水資源」は、少し異なる。水資源は英語ではwater resourcesであるが、国際的にはこのwater resourcesには、洪水の問題も含まれる。日本でも研究者の間では一般的に、このような広い使い方は許容される。
日本でも官庁においては、水資源はもっと狭い意味に解釈される。一般に、土木的な「水」の範囲は、洪水の問題と、水を上水道や工業・農業のための用水として使用する問題とに大分けされる。官庁においては、この用水として使用する水をさして「水資源」と呼び、洪水の話はこれに含まれない。諸官庁の間の仕事の分担も、これにしたがっていると思われる。
この委員会では、この土木系でいう「水」を、研究者的な広い用法で「水資源」と言うほうが、機能水とかそういう物理的な水との違いが明らかに分かってよいのではないか。
筆者に課された題は「水の需給」ということである。大体同じ話を沖委員が土木系として扱われているので、重複するところは省略して、基礎的な事項の中で、筆者がとくに興味を持って面白いと感じていることの要点を、かいつまんで述べる。
2-1 水資源の偏在
(1)降雨をもたらす大気循環の構造
地球上の大気の循環については、R. K. Linsleyが引用するRosbyの説明が筆者にとっては、分かりやすく、面白かった。それは、大気が赤道上で暖められて上昇し、極地で冷却されて下降するという循環が基本であるとするものである。図1の左の部分は、もし地球が回転しなかったら起こるであろうこの大気の循環の模様である。すなわち、地球上の大気の層を考えると、極地はでは大気が沈みこみ、赤道では上昇気流が起こる。それで一つの循環が起こる。
ところが、地球は自転をしているので、その影響でこの循環が三つに分かれる。その説明が図1の右の図である。三つの内の中央の循環は、連行流のために、赤道側では沈み込み、局地側では上昇をするように循環する。各循環の境目で上から空気が落ちてくるところは高気圧で、雨が降らない。下から上に空気が上がるところは低気圧となって、雨が降る。このような循環が横にいくつも連なってチューブとなり、帯となって地球を取り巻いている。高気圧の帯のところが、砂漠が多くなる。低気圧の帯のところがいわゆるモンスーン帯とか梅雨の線となる。
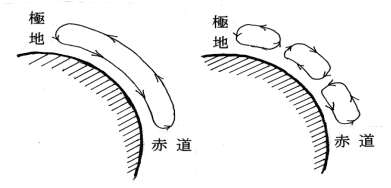
図1.Linsleyの大気の循環の説明
(左側が自転の影響がないとき、右側が自転の影響があるとき)
以上に加えて、これが一年を周期として、少しずつ南北に移動する。北半球で夏になると、太陽の直角方向の変化から、一番暖かいところが北へ寄る。そうすると、低気圧の雨が降るところも順に北にずれる。その影響で、ある国では雨季が来る。また、反対に乾季が訪れる国もある。これが降雨の偏在をもたらす大気循環の基本である。
(2)場所的偏在
上で述べた大気循環の機構が、降雨の場所的な偏在が出る一つの要因である。上記の循環構造に加えて、山脈・海流の影響などで偏在がさらに生じる。
その結果として、世界各地の降水量の中で日本はどうであろうか。図2に示すところで、上にはインドネシアの年間2600ミリとか、フィリピンとかニュージーランドで雨が多いところがある。少ないところでは、エジプトなどは大変少ない。日本はこの図で見ると、世界での平均は年間970mmに対し、日本は1700~1800mmで、約2倍で、図の降水量が多い方から全体の1/3の辺にある。
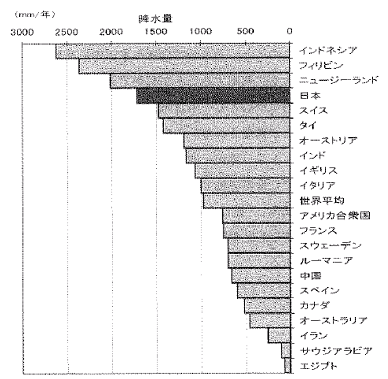
図2.世界各地の降水量 (国土交通省刊 平成13年版「日本の水資源」による)
それでは、日本は大変に水資源に恵まれているかという問題がある。仮に人口割で1人当たりの水資源量を調べてみたのが図3である。この中で日本は、人口が多いので1人当たりにすると、そんなに多くはない。したがって、まだまだ水資源の開発が必要だとも考えられる。
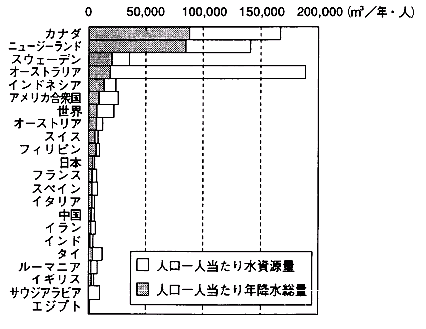
図3.人口一人当たり年降水総量・水資源量
(国土交通省刊、平成13年版「日本の水資源」による)
(3)時間的な偏在
時間的な偏在について、私の興味を引く点を2点ほど述べる。それは、雨季と乾季の存在と、乾燥地域でも最大の降雨のピークは低くないこと、である。これらについて、以下に述べる。
第1点は、雨季と乾季の存在である。日本では雨季と乾季の別があまりなく、他の国々と比較すると、かなり1年中一様に雨が降る。このような国は、それほど多いわけではない。とくにアジアにおいては、かなり珍しい。アジアでも台湾の中ほどまでは大体日本と同様であるが、それを過ぎるにしたがって、雨季と乾季の別がはっきりする。乾季と雨季の差が大きいところでは、乾季は降雨の量が局端に少なくなるため、草も枯れて、あたり一面の風景が茶色になる。そういう強い乾季は日本ではない。その結果、我々は雨季と乾季に対してはややセンスが鈍いところがある。余談であるが、インドネシアは赤道に近くて1年中気温が高いため、インドネシア語で秋や冬はない。そのかわりにあるのが、雨季と乾季という言葉である点は興味深い。
第2点として、いわゆる乾燥地域でも、降雨の頻度は下がるが、降雨のピーク値は意外に高いような印象を持つ。乾燥地域でも、最大降雨のピークはそう低くならないことがある。あまり知られていないが、砂漠でも洪水がある。筆者の経験でも、以前サハラ砂漠に出かけて、30年に一度という大雨が降った後に出合ったことがある。また、砂漠の中にある都市ラスべガスで洪水に出合ったこともある。このような特殊な気候の性状によって、砂漠特有の生態系を作り出している。
図4はパリとバンコックの月別雨量で、30年間の平均である。バンコックでは多く降る月と少なく降る月の差が大きいが、パリは量は少ないが、1年じゅう均等によく降る。バンコックでは、雨期の多量の降雨を用いての水田農業に適し、パリでは畑作による文化が発達したのには、やはりこういう雨の降り方の影響という一面もあるのではないかと感じられる。
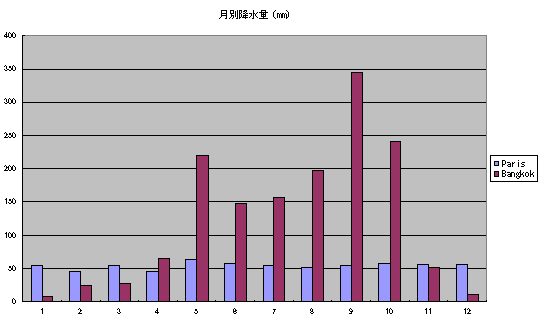
図4.パリとバンコクの月別雨量(30年間の平均値)
2-2 水資源の需給
(1)全体の見通しとモデル解析の現況
概況を見ると、前章でも触れられたが、水資源の使用量について、ごく概略をいえば、現在の世界での取水量は3,800km3、そのうち農業用水が70パーセント、工業用水が20パーセント、飲料水が10パーセントを使用しているといわれている。
もう少し細かく言えば、この現在の水需要が将来どうなるかについての予測が必要となる。将来の水需給に関するモデルは種々行われている。一例としてPODIUMモデルによる2025年での予測をについて、考察する。(PODIUMはスリランカにある国際機関のIWMIすなわちInternational Water Management Instituteで作成されたものである)。PODIUMモデルの内容は、降水量をベースとする水の供給量予測部分と、食料の需要予測部分からなるモデルである。いろいろな要素が絡む、大変複雑なモデルで、雨の予測、食料の需要量および供給量の予測が含まれる。
この内容では、将来も食料問題が大変な問題で、そちらから解決しないと、なかなか水の需要もわからないということが表されている。これによると現在の世界での総取水量3,800km3が2025年には4,300~5,200km3に増加し(13~37パーセントの増加)、世界人口の約半分が水ストレスの強い地域に住むことになる。農業用水については、現在の17パーセントの増加が必要とされる。
図5は、PODIUMモデルによる2025年の需給関係の世界分布の検討の結果であるが、色が濃いほど水が足りないということが出ている。
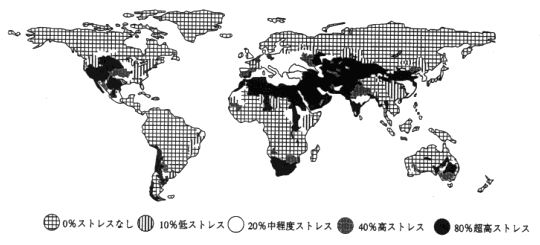
図5.PODIUMモデルによる2025年の世界の水ストレス分布予測
(世界水ビジョン委員会刊、世界水ビジョンより)
このようなモデルによる解析おいて、以下に述べるような、幾つかの問題点が存在する。
まず、これだけの水の需要の増加をまかなうためには、2025年までにどうやって水の供給量を引き上げるかという問題がある。現在、世界各地で河川の水はそれほど余裕があるわけではないという印象があり、とすると、ダムをつくるのが、有効な方法と考えられる。
たとえば、バンコックなどで、雨季の水をダムにためておいて、乾季のところで流す。それによって穀物を作れば、バンコックなどは気候が温暖であるから、年に何回か作物がつくれる。乾季の水をダムで補えば、年に3回、4回と米の収穫ができ、食料問題の解決にきわめて大きな貢献がなされることになる。
水需給のさらに細かな場所的な偏在の問題がある。このレポートを元にした世界水フォーラムのビジョン・レポートでは、先進国では水の使い方の効率化が進んで、水の需要は減少するだろう、途上国で需要がふえるということを言っている。将来、世界で水需要が増大して大変だろうとよく言われるが、横並びで全部大変かというと、そうではないという意見もあるということである。日本においても、流域によってはまだ水資源の不足が続こうが、長期的に見れば、日本全土で一様に不足するとはいい難い一面があるように思われる。
これらのPODIUMの解析は国単位で行ったわけである。国単位だと例えば中国を一まとめに扱っているが、中国の北は水がなくて、南は水が多いとかいう水の偏在は扱えていない。それをもう少し細かく切って解析する作業が、ICIDおよびIWMIで進められている。しかし、細分した地域内のGDPなどの経済指標、地域間相互の水・食料の輸送量、その他の量など、必ずしも流域単位での統計量は得られない。国によっては、国内のデータを外国に出すことに必ずしも協力的ではなく、あるいは国によってはそもそもデータの存在しない国もあり、解析を困難なものにしていると考えられる。
筆者の専門の農業の側から見る、全体的な水需給予測の問題点としては、一番大口の農業用水の需要がどうなるかの予測がかなり困難であることを問題点として指摘したい。いうまでもなく、農業用水は今のところ世界の水資源の70パーセントを使っている、もっとも大口の需要である。全農地の中で、潅漑されている農地は17パーセントであるが、そこからの生産は全体の40パーセントを占めており、潅漑は食料生産において、もっとも重要な働きをする。
農業用水を考えるには、供給側と需要側の二つの面の、どちら側から考えるかということがある。供給はどれだけ可能かというのが、第一の面である。これから考えると、現在のダムの建設状況から判断して、将来の大幅な供給増には限界があるという面がある。
他方、需要の面から考えると、将来の食料問題についての関連を考える必要がある。食料の必要量は21世紀中頃までに2倍になると予測される。この原因には、人口の増加と所得水準の向上による嗜好の蛋白質への変化の影響の2種類が含まれる。いわゆる未来予測で、人口の伸びは将来予想の中でも比較的確かなものである。21世紀の後半には、世界人口が100億近くになるといわれている。これが一つの需要増加の原因である。
嗜好の変化について考えれば、開発途上国の人の生活レベルが向上すると、蛋白質の需要が増加することがある。蛋白質の需要が増すと、食料の必要量は大きく増加する。それはたとえば、
牛肉1キログラムをつくるには穀物11キログラム
豚肉1キログラムをつくるには穀物7キログラム
鶏肉1キログラムをつくるには穀物4キログラム
がいる、などということがいわれていることによる。図6は、川島による一人あたりのGNPと蛋白質消費量との関係である。このように蛋白質の需要は、きわめて生活レベルの向上と関係が深い。日本においては、食料の59パーセント(カロリー・ベース)というきわめて多量のものを輸入しているが、これは国民の蛋白質の摂取量の割合が増加したことが原因として大きい。これについては、カロリーの総摂取量が不変と仮定すると、日本国民全体が一日に米を一口よけいに食べる毎に、食料自給率は1パーセント増加するとも、さらには国民全体が朝食を和食にすれば食料自給率は数十パーセント増加する、という表現がなされている。将来の需要の変化には、国家の価格政策、経済生長割合も関連し、複雑な問題となる。今後の解析においては、これらの各要素の実状を取り入れた分析を、さらに積み重ねる必要がある。
(注:章末に、図7として、農業用水の部分のPODIUMモデルの構造の概略を示す)
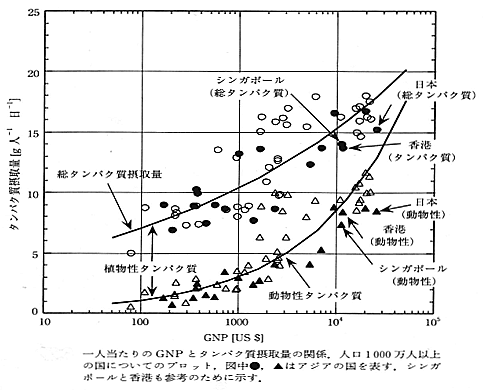
図6.一人当たりのGNPとタンパク質摂取量の関係(川島による)
(2)農業用水に関する最近の幾つかのトピックス
ア 農業用水の効率向上(農民参加による水管理)
農業用水に関する話題となる問題点であるが、農業用水の利用効率が低い(ときとして利用効率が60パーセントを下回るときもある)と一般に言われている。それをどうするかという話である。現在潅漑分野で主に言われているのは、水の管理を農民の自発的な参加によって行うようにするのがよい、ということである。それも、水路などの施設ができてから参加をうながしても、うまく行かず、施設の建設段階から参加をしてもらって、水の重要性についての認識を深めてもらうのがよい、ということになっている。このような点から、日本の「土地改良区」という農民の水管理組織は、世界における一つの模範的な例であると考えられている。
イ Water Pricing
現在、開発途上国などでは水は政府が供給するものとして、無料で配られているところも多い。これが水の節約意欲を失わせ、水の無駄な使用を引き起こしているという考え方がある。この背後には、後に述べるように、水を経済財として位置づけ、市場原理による水資源配分の最適化を計ろうとする考えがある。この考えについては、それではもっとも貧しい人々から水を取り上げることになる、等の幾つかの問題点が指摘などされて、種々の反論があり、現在いろいろなところで議論が行われている。
ウ 「仮想の水」と貿易
水が少ない国が、無理をして穀物などの水をたくさん必要とする作物を作る必要はない。少ない水で付加価値の高い作物を作り、それを輸出して穀物をその代金で水のたくさんある国の穀物を輸入すればよい。これは、仮想の水を輸入していることになる、という考え方がある。これが前章で述べられた「仮想の水の貿易の話」である。ただし、この仮想の水貿易が、よいことなのだということになると、世界での貿易障壁は撤廃すべきである、という主張とつながり、WTOにおける議論と関係してくる。WTOにおける日本としての主張には、農業用水は環境を守るためにも大変役立っている、それから農村社会を育てるためにも大変役立っているということがある点には、注意を要する。
エ 農業用水と環境との調和(用水の多面的機能)
今、日本がこのような国際社会で言っているのは、特に水田は大変に生物の生態系をはぐくむ。水の底まで太陽が通る浅い水は、生態系に大変好適である。それだけでなく、農業用水は、農村の生活のいろいろな面(防火、消流雪、景観・親水など)で多面的に役立っている、ということが重要視されている。
オ 等身大の技術の必要性
少し以前であるが、途上国への援助について「等身大の技術」ということが盛んに言われたことがある。たとえば、日本からパソコンを援助で提供したが、現地では1日に10回も停電があり、使い物にならなかった、というたぐいのことをいましめる意味である。筆者も、現地人に、「いろいろな先進技術を用いた機材よりも、大きな体育館のような建物がほしい。そこで農民を集めて、手工芸品の作り方を教えるのがもっとも有効だ」、と言われたことがある。水資源関係でも、鉄製品が泥棒にねらわれる国では、先進国で用いられるような鉄製の施設などを野外でそのまま使うことには、問題があるかもしれない。筆者の印象では、現地で必要な技術開発には、先進国とは別の発想が必要で、途上国独特の技術の開発も必要である。
2-3 水資源の将来の需給の調整と科学技術一般
(1)水資源計画における理系と文系の人々協力の必要性
水資源の将来の需給の調整に関する計画は、政府機関の政策によって決せられるところが大きい。すなわち、政策の提言の必要性が存在する。これについて、理系の研究者である筆者がどのような印象を持つかについて、言及する。
一般的にここ数十年、たとえば、人工衛星、原子力開発など、世界で多数の大型の科学技術プロジェクトが行われてきている。水資源開発プロジェクトは、そのような大型プロジェクトの一つと、位置付けられる。
このような科学技術プロジェクトの計画立案は、理系の人々が主となってなされること多い。が、プロジェクトが大型化するにしたがって、国の政策レベルでの論議が必要となる。ふつう、政策の議論では、文系の人々が主要な働きをする。それは、文系、とくに経済学あるいは法学の分野の相当部分は、学問の目的自体が政策提言であることによる。このような分野の文系の専門家は、若いときからそれに携わっている、いわば政策提言の専門家である。しかし、最近の大型化した科学技術プロジェクトを含む政策を論じるには、理系の知識が必要となる。さらに環境問題が重要となっている昨今、生態学などの知識も必要となる。このような原因から、大型科学技術プロジェクトに関する政策立案には、文系と理系の人々の協力が必要とされていると言える。
これらの事情を、とくに水資源開発の場合について、筆者のような理系の側からの視点で見てみる。水資源については、実際の開発作業、すなわち河川にどのくらいの水量が存在するかの測定、水路を作ること、ダムの建設などは、いずれもエンジニアリング分野の仕事である。そのため従来、主として理系の分野の人々によって建設の計画も扱われ、その基礎となる学問も開発されてきていた。
しかし最近では、理系の人々の間でも、水に関する経済面からの議論が、世界的にさかんになされるようになった。たとえば、水に関するすべてのセクターの人々を集めての大規模な会議「世界水フォーラム」の第2回は、2000年にオランダで開かれた。その折に、議論の一つの中心となったのは、水を経済財として扱かうという考え方であった。さらに、幾つもの国際的な組織、たとえば、国際潅漑排水会議(ICID)、国際水パートナーシップ(GWP)、世界銀行などで行われている議論の中でも、水の経済財化に関する内容が最近は多く含まれている。このように、水資源を論じる際に、最近では経済は重要な要素と考えられている。
なぜ、このように経済の議論が重要性を増すようになったかを、次に細かく見てみる。その原因は第一には、世界の各地で、水資源の水量不足が起こる機会がふえたこと、第二には、科学技術の進歩にともなって水資源の開発プロジェクトの投資規模が増加し、後で述べるように水の量以外のいろいろな要素において、他のセクターとの競合が起こるようになったことである。以下にこれらの二つの要素について、もう少し説明をする。
第一の水量についてであるが、水は、空気のように潤沢にあってだれでも他人に影響をあたえず自由に使用できて売買の価格がつかない「自由財」と、総量が限られていて使用するのに値段がつくいわゆる「経済財」との間を、いろいろと千変万化する。
水資源はかつては、きわめて自由財的なものであった。日本の場合を例にとっても、ふだんは河川の水が比較的多量で水資源に恵まれており、それほど水不足を感じることもない。すなわち水は自由財的である。とくに洪水にでもなれば、水は価格がないというより、むしろ水は迷惑なもので、負の値を持つ場合すらある自由財である。しかし、最近では水資源の使用量が増え、その上、いったん旱魃がおとずれ、水不足になれば、個々の水使用に制限が生じる。すなわち、きわめて経済財的になる。たとえば日本においては、あらかじめ旱魃にそなえてダムの中の水の一定容量を確保しておくためには、ダムの建設時には相応の建設費用を分担しなければならない。世界においても、各国での経済規模の拡大にともなって、都市用水の需要が増大して、農業用水などとの分野間の水利用の競合から、ますます水資源問題が深刻になるため、各地で水が経済財として扱われるという要素を強めてきた。
第二の水量以外の要素についての競合であるが、上に述べたように、近年技術的な進歩のために、水資源に関するプロジェクトが大規模かつ多数なされるようになってきて、水以外の各種資源についても他分野との競合が起こることがある。各種資源の中には、国家による投資の予算資源も含まれよう。国土計画とかかわる面がある。その地方の将来の水資源需要をどのように見込むかには、その地方の将来の産業計画、人口政策、都市計画が関連するからである。最近では、水質、生態を含む環境問題との関わりも重要である。
以上二つの場合、いずれも資源の配分の問題と考えることができる。上で述べた第一の場合は、狭い意味での水資源そのものであり、第二の場合はもっと広い意味での資源である。さらに前者について追加すれば、水不足が頻発するようになれば、どれだけの水を上・工・農業のどの部門に配分するかが問題とされる。第二の中の環境などとの関わりについては、最近では経済学の分野においても、公共経済学あるいは環境経済学として、経済学の分野で取り扱われるように、一種の環境資源をめぐる競合としての接近も計られている。
経済学の専門家がこれらの問題を扱えば、これは両方ともに、一種の資源の分配の問題である。これについて、最近いわれるのは、水の価格を定めて、市場原理によって分配をすると、もっとも水資源の有効な利用が達成されるという考え方である。この方向から論じれば、水資源問題は経済学的な問題として、経済学の分野で検討されることが、適当なことになる。
もちろん、第一近似としての市場原理の存在は無視できない。しかし、アダム・スミス以降、自由市場経済の欠点を克服して国がどのような政策をとるべきかを論じているのが、一般経済学の主要論点であるように、我々外部の理系の者からは見える。例えば宇沢弘文などのいう社会共通資本なども必ずしも市場原理のみで配分はできない。日本のみならず世界各地で行われるダム建設についての反対運動など見るように、単なる環境資源の配分に関する経済学の問題の範囲を超えて、政治あるいは社会の問題の様相を呈する。このように、社会の広い範囲におよぶ問題の解決には、ことさらに、理系と文系の人々の協力による学問の構築が将来必要とされると考えられる。
以上の議論は、水資源の開発についてのものであったが、このようなことは、一般の大型科学技術開発の開発全体にもいえることである。筆者はかって、米国のNASA(ナサ)の関係者が、人工衛星の打ち上げの必要性に関して米国議会などを説得をする苦労話を読んだ記憶がある。この場合、米国の国威発揚の経済効果などまで含めての定量的な評価などに苦心がなされて新しい手法の開発がなされていて、水資源開発と同様の要素があり、興味深かった記憶がある。
(2)理系と文系の協力の今後
近年他のいろいろな分野でも、大型の科学技術のプロジェクトは行われている。しかし、水資源の分野は、その中でもとくに歴史が古い。長大な水路やダムを作る水資源開発プロジェクトは、元来大型のものが多いからである。大正、明治、江戸時代以前はもとより、第二次大戦後ほどなく行われた愛知用水の事業は、世界銀行の借款を得ての近代的な大型総合的水資源開発として、最初のものであった。それ以後、各地でダムを作っての水資源開発が行われるようになる。このような、大事業は、日本だけでなく世界的にも、エジプトのアスワン・ダムなどを始めとして、各地に治水・農業用水の事業が行われてきた。これらの計画がなされるそのたびに、国の政策レベルにおいて開発の是非が議論され、その中で、事業の妥当性を説明する必要が生じていたに違いない。さらに最近では、プロジェクトに関する計画決定に透明性と説明性が必要とされる。説明性の中には、経済効果の議論が含まれる。
上に述べたような事情から、水資源開発に携わる理系の人々の間において、このような経済などの知識を入れたアプローチに対する必要性は、古くから感じられていた。たとえば20年ほど以前から、理系の人々によって、「計画学」というジャンルを作られて来た。とくにコンピュータの発達期において、コンピュータによって経済効果を最大にするような政策を立案する可能性に期待が寄せられ、この分野で幾多の研究が行われた。しかし、現在では、かってほどの隆盛は見られないように感じられる。その原因は、筆者の私見であるが、いかにコンピュータが進歩しても、現実社会ははるかにそれより複雑であり、それに対しての扱いには限界があったことであろう。
とくに水資源開発技術においては、社会のいろいろな他分野との関わりが強い。たとえば衛星の打ち上げなら、打ち上げ基地を柵でかこえば、そこは技術者のみの隔絶した社会が生じるが、水の場合は、そこに住民がおり、社会・環境・食料・貿易などとの関わりが、際だって強くなる。このために、文系と理系の協力による学問の構築がもっとも早くから必要になったが、現在にいたっても、それがやや未成熟である点は否めない。
これから先は、筆者の個人的な印象である。政策の提言の基礎としては、科学技術の「政策提言学」がさらに文系と理系のバランスの上で発展することが必要である。いままで、理系の側のいくつかの水資源に関する学会や委員会では、上に見られた文系との協力の必要性から、種々、文系の人々を招いて意見の調整を計ろうとする試みが多くあった。しかし、そのいずれも、大成功して発展を続けているようには見えない。たとえば、国際潅漑排水会議(ICID)は、潅漑排水を主目的とするほとんど唯一の国際組織で主としてエンジニアが多く参加しているが、ここでは、1990年代の組織改革において、社会経済などの重要性に着目して、とくに「社会・経済と政策についてのワーキング・グループ」を作った。しかし、ごく最近に至るまでその活動は限られており、文系の人々の参加は少ない。日本においても、1990年代に水文・水資源学会が発足したが、その当初から、限られた理事の中に一人は文系の理事を選任するなどして、文系の人々の参加を求めることを試みたが、現在まで、文系の人々の参加は限られている。
具体的な水の将来予測においても、上で見たように、降雨の予測などを含む供給の予測は理系の仕事である一方、潅漑の基本となる食料需給関係の予測は経済分野の仕事である。この両者の関係を十分につけることが必要である。このような必要性は、水資源以外のいろいろな分野の大型科学技術プロジェクト一般についても、言われているであろう。しかし、とくにこのことについて歴史の古い水資源分野の経験からいえば、この試みは、簡単には成功しない。今後の文系・理系の協力関係の内容は、単に文系と理系が単に会合で同席するレベルではなく、一歩を進めて文系と理系との真の意味での融合が計られることが必要であろう。
(参考文献)
1)R. K .Linsley, et al., Applied hydrology, McGraw Hill, 1949
2)川島 博之、21世紀における世界の食料生産、安井 至編著、21世紀の環境予測と対策、丸善、2000
3)国土交通省土地・水資源局水資源部、日本の水資源、2001
4)世界水ビジョン川と水委員会、世界水ビジョン、山海堂、2001
5)D. N. Tiwari, A. Dinar, Prospects of irrigated agriculture, Agriculture and Rural Development Department, Water Team, The World Bank, Oct. 2002
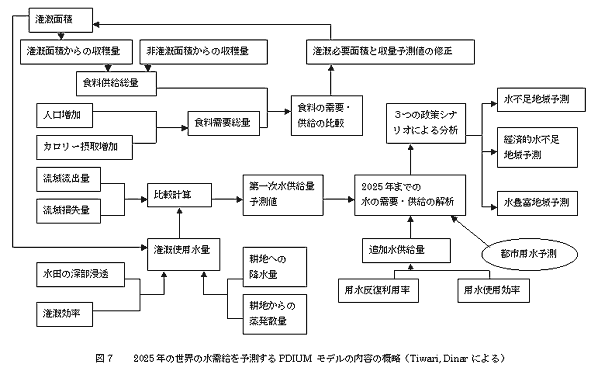
お問合せ先
科学技術・学術政策局政策課
-- 登録:平成21年以前 --