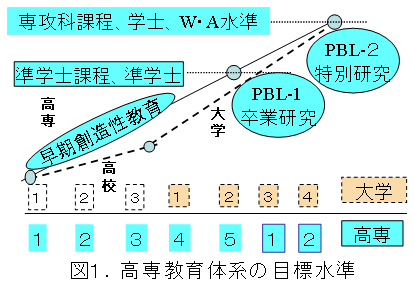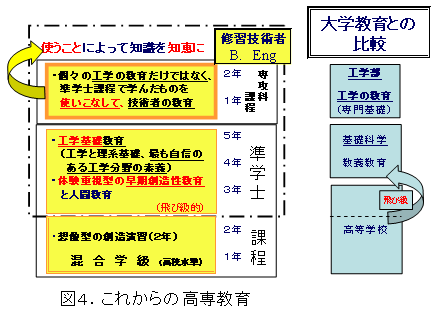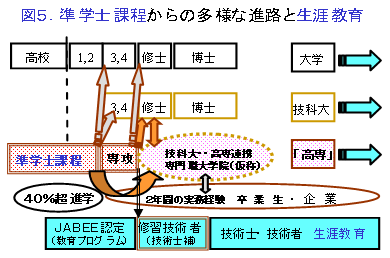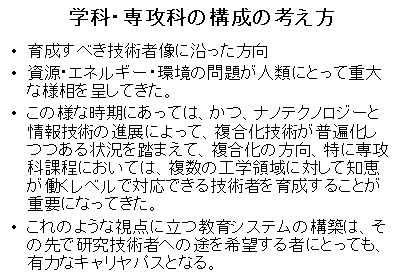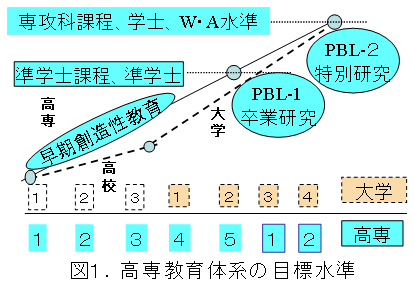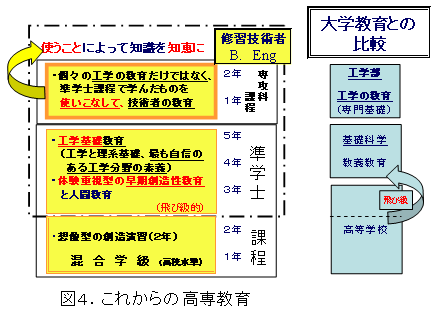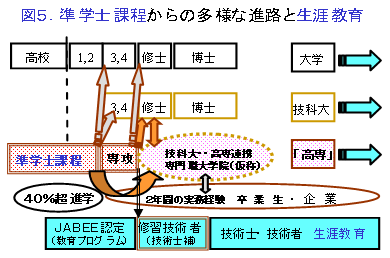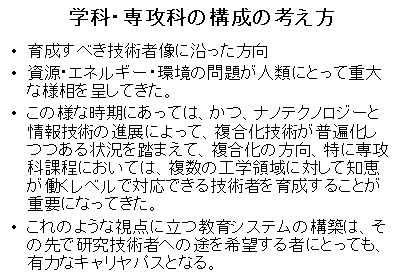2. 歴史を振り返って
#理由1:大学審議会:平成3年2月答申の受け止め方
- 答申の方向での投資がなされなかったし、国家レベルの施策も立てられなかった。即ち、本格的に新しい分野への展開を実施するに際しては、その在り方を考える中核人材の集団が必要。それなりの人材の投入と準備期間とが必要。加えて、それを実現するための初期投資と維持発展させる予算措置も必要。それらがなされなかったということが基本的な要因。
- この答申が、高専側からは「総合高専」創設への提案とは受け止められなかった。
- 当時、高専側、社会の側共に切迫したニーズを持っていなかった。
このため、
- A.高専設置から法人化の前までの状況
- 高専側:高専を「専科大学」とし、教育だけでなく研究が出来るような大学並みの学校に転換することを要望する
- 中教審側:「高専制度は曲がり角に来ているのではないか」、高専について継続的に審議する
- B.法人化の際
- 旧国専協における検討:次のような課題整理があったと記憶している。
- a.設置基準の大綱化のもとで、高専設置当時の趣旨や工業高専、電波工業高専、商船高専の名前にとらわれずに、工学分野以外に展開するのがよいのか、
- b.科学技術創造立国の国是に基づき、ものづくり基本法の趣旨に則って、大学の低学年教育、短大教育、専門学校教育との棲み分けを明確にしながら、実践的な工学・技術の担い手として、生涯継続教育の中の15才から5ないし7年間の年齢層の若者を対象とした人材育成のさらなる質の向上をめざすのがよいのか。
- 旧国専協の意見の大勢は、b.の方向であった。
- 国立高専は、技術者教育の国際相互承認(ワシントンアコード)への取組によって、卒業生達のステータスと確約の場の確保に向けて努力した。
- 国際的に通用する単位の数え方(中教審平成17年1月:平成18年設置基準改正)の改正へ
#理由2.高専としての入口と出口への不安
- 工業系分野は比較的安定した需要あり、実績もあることから現状を維持。
その際、社会的ニーズを把握しながら学科の改組等、適宜対応 ただ、学科増まで踏み切る余裕はなし(高レベルを維持したままの定員確保に自信なし)。
- 商船分野は出口に不安、養った専門能力を生かせる就職先の確保が不十分 → 志願者減 → 入学者のレベルの低下
- 農業分野は大学や専門学校でも人気薄(国策として農業振興不十分 → 若者に将来的な不安あり)→ 就職先に不安あり → 学科新設に踏み切れず(地域によっては、農業高校と農業短大とを核として農業高専を創る可能性について検討したところもあった。)
#理由3.新分野への対応の在り方について
- 分野を考えるに当たって、特定の分野に特化した技術者養成の問題点を工夫すること。例えば、「環境工学」という学科を作ったとしても、それだけで就職できるとは期待できない。土木技術、機械技術、化学工学をマスターして、さらに環境に関する理解が深い、のでないと企業は雇用してくれない。とくに、医工学系の技術者については、本質的に電気電子工学、機械工学、化学などの技術・知識が求められる。高専レベルの卒業生を求めるのなら、むしろ電気電子、機械、化学などの卒業生を雇用して医工学方面に伸ばしていただくのがより適切。
- この考え方は、融合複合工学分野について、高専専攻科が目指す人物像と整合する。即ち、「最も得意とする技術分野の基礎的素養を持ち(本科の教育)、複眼的視野と総合的対応能力を持つ技術者」
#理由4.高専教育の曲がり角論の事例とそれへの対応・現状認識
ある事例が提示した新分野対応の高専経営を止めることとなった理由:
- (注1)高学歴指向と少子化の進展に伴い進路決定時期が高年齢化する中で、理工科離れもあって高専志願者すうが減少傾向にある。
- (注2)本科卒業後の進学者の増加は、実践的技術者の輩出を本旨とする高専は、過渡的な教育機関としての性格を強めつつある。
上記の見解((注1),(注2))に対しては:
- 生涯学習・生涯教育の視点の理解が重要
- 高専教育を完成教育としてではなく、心身の発達速度が最も急激で、それに伴う感受性が最も高い年代の青少年を主対象にした生涯継続教育の大切な一過程の教育と位置づけることが重要な視点。
- 実践的なものづくり人材育成は、生涯にわたる中堅的技術者の育成ではない(高級技術者の育成とは解されにくい)。専門的職業の入口の方向性だけを示すものであって、生涯的目標ではない。このことを国民にデータを基にして説明し、理解が得られる努力をすべきである。
(国立高専機構の作成した卒業生達の活躍状況に関する出版物等は有用であろう)
- 人材育成における学校種の棲み分け(大学・短大・高専・専門学校等)が、高専外(大学・短大・専門学校)からも容認されることが望まれる。
- 総合大学等では、創造性についての意見にまとまりが見えない。高専では、実践的ものづくりを通して、“教育のできる創造性”の三つの基本「基礎学力」、「応用力」「段取り力」(ハーバード大学のビジネススクールの例)を重点として教育実績を上げてきた(中堅技術者からスタートして指導者経営者に育った高専卒の比率は他の学校種と較べても高いと言える)ことは、重要な社会的成果と見なせる。
3.これから 持続可能な社会の形成に向けた技術分野を担当する技術者
持続可能性、環境問題、1次産業と技術、安心・安全確保の技術ニーズ等、広範な分野に亘るニーズに対応する新たな総合高専の視点は、今後大いに検討する価値がある。
その際、次の視点を重視することを期待
- 15歳から専門職業人としての道を志す、その中学卒業時点での上位者を主体とする学生達は、我が国の技術者としての人的資源としては極めて重要な意味をもつ。
- 国際競争を考えた時に開発技術は基礎研究とともに生命線になると考える。それを支えるのは工学教育主体の大学では難しく、体験教育を多種取り入れている高専教育の特色と実績がその役割を果たすことを示している。
- 科学技術立国を国是とする我が国は、高専教育に本格的に投資する価値がある。
*高専教育の現状に関する参考資料:これまでのこの委員会での審議の流れから
1.体験重視型の早期創造性教育
高専は、地域の中学校から上位の学生を集めて、頭脳の柔らかい15歳から学士水準まで、物理学と数学を基軸とする理工系一貫教育を通して、体験重視型の創造性涵養教育を行っている。即ち、座学で得た知識を使ってみる体験機会の多い教育システムであり、その成果をペーパーテストで評価しにくい能力、例えば創意工夫する能力、知識を複合化して必要に即して使いこなす能力など、技術者が働く場面で必要とされる能力が身につくように工夫されている。
我が国でこの種の教育が可能な唯一の高等教育機関である。創意工夫の能力を涵養しようとするとき、創造体験を持つ教員の存在と学齢の若さは望ましい条件である(学生の資質と優れた教員)。
2.科学的知識に裏打ちされた知的技能と体験を通して体で覚えた知識(身体知)の涵養
準学士課程では、体験重視型の早期創造性教育と共に、自然科学と個別の専門工学のリテラシー教育(学問体系の基礎基本を中心とした体系的な教育と自学自習の習慣)を徹底する。技術者として必要最小限度の手ほどきであり、後は実社会に出てからの実践経験を経て技術者に育っていく。
一方、専攻科課程では、「科学的知識に裏打ちされた知的技能」をしっかり身につけるために、社会との共同教育体験を含む融合・複合的なカリキュラムで、知識の使いこなしによって深いレベルでその本質を理解し、未知の領域で遭遇する技術的課題の問題点を見抜き、それを解決していける技術者の育成を目指す。複眼的視野で技術の目利きが出来る技術者である。
3.キャリヤパスとしての視点
高専は、準学士課程(通称:本科)の教育からスタートした歴史的経緯があるため、その本科生の就職者数が約60パーセントであるというと、高専は本来の目的とする技術者を育ててないのではないかと言われることが多い。しかし、高専は準学士課程の教育を中核として最も大切にしてきたし、今後ともそれを変えるつもりはない。本科生の卒業後のキャリヤパスが如何なるものであろうとも、高専は本来の目的を100パーセント達成しているのであって、直ちに企業で仕事に就こうが、さらに高度の教育を経てから職業に就こうが、結果的に90パーセント以上の学生が技術者への道を歩んでいる。JABEEは「技術者教育」を認定しているのであって、「工学教育」を認定しているものではない。さらに、博士課程に進むものも大歓迎であって、欧米先進国では、技術界のリーダーの多くが「技術士を持った博士」を標準としていることをも視野に入れている
(以下の図は、平成19年4月25日(水曜日)開催の本委員会で使用したものである)