| (1) |
職の種類
法令上の定めはなく各大学が定めており、一般には |
| |
 |
教授(Professor) |
|
 |
上級教員
(Senior Staff) |
 |
学術スタッフ |
 |
上級講師(Senior Lecturer) |
|
 |
 |
| |
 |
 |
 |
 |
このうち、業績の優れた一部の者を
準教授(Reader)とする場合もある。 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
|
|
 |
 |
Lecturer(講師) |
|
|
 |
| |
が置かれており、その他、研究者(Researcher)等の教育研究職が存在。
なお、新しい大学(1990年代に、かつてのポリテクや高等教育カレッジから昇格したもの)では、主任講師(Principal
Lecturer)が置かれている。 |
|
| |
| |
(参考)教員の構成(2001年) |
| |
| 地 位 |
合 計 |
教 授 |
上級講師 |
講 師 |
その他 |
人 数
(構成比) |
143,150人
(100%) |
13,810人
(9.6%) |
24,630人
(17.2%) |
50,140人
(35.0%) |
54,570人
(38.1%) |
| フルタイム教員 |
119,900人 |
12,825人 |
22,720人 |
41,490人 |
42,865人 |
|
| |
| (出典: |
HESA Reference volume Resources of higher education institutions 2001) |
|
|
| (2) |
任用形態 |
| |
雇用期間は、期限付きの雇用と定年までの雇用に大別され、特に、定年までの雇用の場合には、定年まで解雇されない権利として「テニュア」(academic
tenure 終身在職権)が付与。
|
| |
| |
(参考)教員の契約形態別割合(2000年)(単位:フルタイム換算数) |
| |
| 地 位 |
講師以上 |
講師未満 |
その他 |
計 |
| 終 身 |
期限付 |
終 身 |
期限付 |
人数
(構成比) |
64,012人
(63%) |
9,553人
(9%) |
1,485人
(1%) |
25,010人
(25%) |
1,286人
(1%) |
101,346人
(100%) |
|
| |
(注)一部医学系教員等を含まない。
出典:HEFCE Academic staff : trends and projections 2002 |
|
| (3) |
採用・資格 |
| |
 |
教授、及び講師のポストは公募されるのが一般。上級講師は内部からの昇格者が多い。 |
 |
採用や昇進は、一般に研究業績が重視されるとされるが、各大学の具体的な選考基準が公表されることはあまりない。 |
|
| (1) |
職の種類
法令(教育法典)上、大学の常勤教員は、基本的に、 |
| |
 |
教授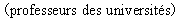 |
 |
|
| |
|
|
教育研究職(enseignants-chercheurs) |
 |
助教授 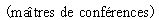 |
 |
|
とされている。
このほかの常勤の大学教員としては、大学病院センター(CHU)教員が存在。なお、1986年に講師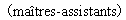 ・助手(assistants)は廃止され、現職者のみ存在。 ・助手(assistants)は廃止され、現職者のみ存在。
また、非常勤の大学教員として、非常勤教育研究補佐員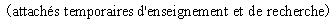 、学生指導員(monitorat)が存在。 、学生指導員(monitorat)が存在。
|
| (2) |
職務内容 |
| |
| ○ |
教育法典上に規程。教授の職務は「カリキュラム、学生進路指導、教育組織の立案について主たる責任を負う」とされている。(助教授の職務に関する個別の定めはない。) |
| ○ |
教授・助教授身分規程(1984年6月6日付け政令第84-431号)では、教育に関しては、講義と演習のうち講義は主に教授が担当することになっており、研究に関しては教授が研究室の責任者となると定められている。 |
| ○ |
博士論文指導教官となる資格は教授のみに与えられている。 |
|
| |
| |
(参考)教員の構成(1999年) |
| |
| 地 位 |
合 計 |
教 授 |
助教授 |
助 手 |
CHU教員 |
人 数
(構成比) |
53,124人
(100%) |
17,536人
(33.0%) |
30,053人
(56.6%) |
1,417人
(2.7%) |
4,118人
(7.8%) |
|
|
| (3) |
任用形態 |
| |
 |
大学はすべて国立で、常勤の大学教員は正規公務員の身分を有する。 |
 |
教授、助教授ともに、いわゆる終身雇用であり、任用後は65歳の定年まで身分保障。 |
 |
助教授は、最初の1年間は試補助教授として採用。試補期間終了後、再度大学の審査を経て、大学の提案に基づき、国民教育大臣が、正式任命、試補延長(1年間)、試補採用前の職への留置、解雇のいずれかを決定する。 |
|
| (3) |
採用・資格
教授、助教授とも任用は公募。
|
| |
 |
教授
| ○ |
全国大学審議会が審査を経て作成する「教授職有資格者リスト」へ登録された者が、国民教育省令による公募に出願し、各大学が行う選考に合格した場合には、大統領によって任命。
|
| ○ |
「教授職有資格者リスト」への出願資格としては、基本的に次のとおり。
| ア. |
国家資格である「研究指導資格」又は相当の学位を有する者 |
| イ. |
過去8年間のうち5年間の専門分野における勤務経験を有する者 |
| ウ. |
常勤客員教員 |
| エ. |
教授に出向した公務員 |
| オ. |
教授と同等の研究員 |
|
|
 |
助教授
| ○ |
全国大学審議会が審査を経て作成する「助教授職有資格者リスト」へ登録された者が、国民教育省令による公募に出願し、各大学が行う選考に合格した場合には、国民教育大臣によって試補助教授として任命。(以下、上記の(3) 参照) 参照)
|
| ○ |
「助教授職有資格者リスト」への出願資格としては、基本的に次のとおり。
| ア. |
博士号、「研究指導者資格」又は相当の学位を有する者 |
| イ. |
過去6年間のうち3年間の専門分野における勤務経験を有する者 |
| ウ. |
常勤客員教員 |
| エ. |
助教授に出向した公務員 |
| オ. |
研究員 |
|
|
 |
非常勤教育研究補佐員
| ○ |
学長が採用。 |
| ○ |
出願資格は、概ね次のとおり。
| ア. |
博士号又は「研究指導者資格」の取得課程に在学する、又は高等教育教員採用試験受験の意思のある上級公務員(カテゴリーA 大卒) |
| イ. |
高等教育教員採用試験受験の意思のある1年以上の研究手当(研究奨励金)受給者 |
| ウ. |
外国大学に職を持つ外国人 |
| エ. |
博士号を有し、高等教育教員採用試験受験の意思のある学生指導員 |
| オ. |
1年以内に博士号取得見込みの学生 |
| カ. |
博士号又は「研究指導者資格」を有し、高等教育教員採用試験受験の意思のある者 |
|
|
 |
学生指導員
| ○ |
学長が採用し、教授、助教授(教育研究職)の指導の下で教育活動に従事。 |
| ○ |
出願資格は、概ね、高等教育教員を志望する研究手当(研究奨励金)受給学生。 |
|
|
| (1) |
職の種類 |
| |
 |
ドイツ全体に共通する高等教育の枠組みは、連邦法である高等教育大綱法(1975年制定)が定めており、同法に合わせて、各州が州高等教育法等の関連法令において詳細を定めている。高等教育大綱法(2002年改正)上、 |
| |
| ア. |
教授(Professor)、 |
 |
|
| |
|
|
高等教育機関の本務の教員(Hochschullehrer) |
| イ. |
準教授(Juniorprofessor) |
 |
|
とされている。
教授は、俸給表上、W2及びW3に別れており、準教授は俸給表上、W1とされている。
なお、旧制度においては、教授を俸給表上、C2、C3、C4(日本の講師、助教授、教授に相当)の3つの等級に分けていた。
|
 |
このほか、語学や実践的知識・技能の教育にあたる特別任務教員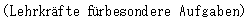 や、学部に所属し、専門的な知識や実践的な技能の教育を含む職務に従事する学術協力者(Wissenschaftlicher
Mitarbeiter)、芸術協力者 や、学部に所属し、専門的な知識や実践的な技能の教育を含む職務に従事する学術協力者(Wissenschaftlicher
Mitarbeiter)、芸術協力者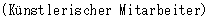 が存在。 が存在。
|
 |
なお、2002年の高等教育大綱法の改正により、準教授が新設される一方、従来の助手等(大学講師、上級助手、学術助手等)は廃止され、現職者のみ存在する。
|
|
| |
| |
(参考)教員の構成(1999年) |
| |
| 地 位 |
合 計 |
教 授 |
助手等 |
学術・芸術協力者 |
その他 |
人 数
(構成比) |
138,881人
(100%) |
24,205人
(17.4%) |
14,210人
(10.2%) |
96,162人
(69.2%) |
4,118人
(7.8%) |
|
| |
(注)学術・芸術協力者の4分の3は任期付きである。 |
|
| (2) |
教授、準教授の職務内容
教員の職務として規定されており、教授と準教授で分けて個別には規定されていない。 |
| |
 |
所属する高等教育機関に課された学術及び芸術、研究並びに継続教育に関する任務を、その専攻分野において、独立して遂行する |
 |
教員の本務には、学修改革及び学修相談に係る任務、高等教育機関の管理への参加、試験の実施等も含まれる |
 |
教員は、専攻分野に係る授業を行う義務を有する |
|
| (3) |
任用形態
高等教育機関は、ほとんどが州立であり、州立高等教育機関の教授及び準教授は、通常、州の公務員であり、公法上の勤務・忠誠関係にある官吏の身分である。学術協力者・芸術協力者も、通常、公務員であるが、官吏と私法上の労働契約に基づく雇員の場合がある。 |
| |
 |
教授は、通常、終身官吏として任用される。期限付官吏としての任用は、学生の急増期等の例外的な場合といわれている。 |
 |
準教授は、3年間の期限付官吏として任用され、さらに3年延長することができる。 |
|
| (4) |
採用・資格 |
| |
 |
教授
| ア. |
高等教育の修了 |
| イ. |
教育上の適性 |
| ウ. |
通常、学位論文(博士号)によって証明される学術上の特別な活動能力等 |
| エ. |
原則として、準教授としての勤務経験(準教授在職経験に代わり、外国あるいは大学以外での研究実績も認められている。) |
| ※ |
2002年の高等教育大綱法の改正により、従来、大学教授の採用条件となっていた「ハビリタツィオン(大学教授資格)」は廃止された。 |
|
 |
準教授
| ア. |
高等教育の修了 |
| イ. |
教育上の適性 |
| ウ. |
通常、学位論文(博士号)によって証明される特別な学術上の活動能力 |
| ※ |
学術協力者等としての勤務した場合、博士号取得期間と勤務期間の合計が6年(医学は9年)を越えてはならないとされている。連邦政府は準教授の採用年齢を33歳と見込んでいると言われている。 |
|
 |
学術協力者・芸術協力者
|
|