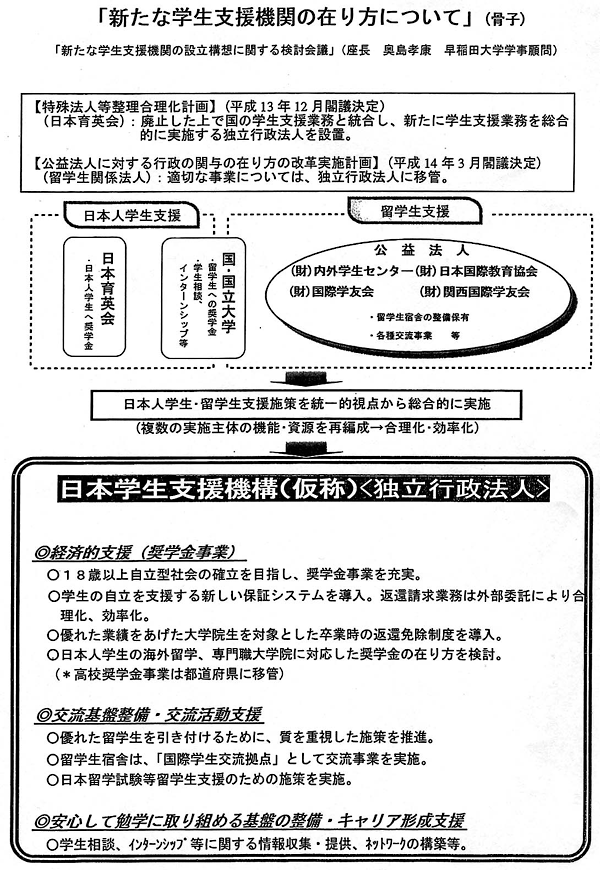
| ○ | 今後の学生支援は、日本人学生・留学生支援施策を統一的視点から展開。 |
| ○ | 現在実施主体が別個に複数分かれているが(日本育英会、留学生関係公益法人及び国)、今後は統一的な理念と実施方針の下に、機能・資源を再編成し、学生支援業務を総合的、合理的、効率的・効果的に実施できる機関を設置。 |
|
| ○ | 学生支援施策の充実に努め、大学等における教育の充実、国際交流の推進、教育の機会均等の確保等の実現を目的として設置。 |
| ○ | 国公私立大学等での学生支援業務をリード・サポートする中核機関。 |
| ○ | 各大学等に共通し共同実施が合理的、効率的・効果的な業務を実施する大学共同利用的な性格。 |
| ○ | 大学等、地域社会、産業界等との連携・協力。 |
|
| ○ | 独立行政法人として設置。役職員は非公務員型。 |
| ○ | 役職員は新機関の使命を十分理解し、国民・社会の期待に応えられるように全力で職務遂行。 |
| ○ | 経済的支援(奨学金事業)は、資金調達等を適切に行い得る機能、体制。 |
| ○ | 留学生にとって「顔の見える支援体制」とするため対応窓口をできるだけ一元化。留学生の特性に鑑みた別途の方策の措置、体制。 |
| ○ | 名称は、新機関の役割、機能を適切に表すものとして、例えば「日本学生支援機構」(仮称)などが適当。 |
|
| ○ | 学生に対する個別対応は、各大学が基本。 |
| ○ | 国の施策として実施すべき業務や施策推進のための支援措置の実施が求められる業務について実施。 |
| ○ | 教育の機会均等の確保と18歳以上自立型社会の実現を目指し、無利子・有利子奨学金を充実。 |
| ○ | 従来の人的保証に替えて又は加えて、学生の自立を支援する新しい機関保証のシステムのできるだけ速やかな導入が適当。 |
| ○ | 収支相償を基本に返還者の負担状況を勘案して、奨学金事業にふさわしい安定的な制度を設計。 |
| ○ | 返還請求業務については、外部委託による業務の合理化、効率化の徹底。 |
| ○ | 特定の職のみを返還免除することの不公平感、教育・研究職の処遇改善等による人材誘致効果の減少を理由に、現在の制度は廃止。 |
| ○ | 大学院進学のインセンティブの付与、大学院生の質的向上等の観点から、若手研究者を対象とした競争的資金の充実に加え、「優れた業績をあげた大学院生を対象とした卒業時の返還免除制度」の導入が適当。 |
| ○ | 現業的業務については、よりきめ細やかな支援体制を実現し、交流基盤整備・交流活動支援業務と一体的に実施。 |
| ○ | 日本人学生の海外留学が一層容易となるような奨学金の在り方や、法科大学院など専門職大学院制度を考慮した奨学金の在り方については、社会の変化や新たな需要を考慮して検討。
|
| ○ | 日本育英会で実施していた高校奨学金は、各都道府県が地域の特色を生かした事業を実施できるよう、関係省庁との連携の下に円滑な事業の移管方策を早急に検討。 |
| ○ | 優れた留学生を惹き付けるために質を重視した施策の推進。 |
| ○ | 留学生宿舎 ・主として国費外国人留学生を対象とした宿舎の整備保有。 ・「国際学生交流拠点」機能を持ち、交流事業を各拠点で体系的、継続的に実施。 |
| ○ | このほか、大学等間学生交流、留学情報の収集・提供、日本留学試験、帰国外国人留学生に対するフォローアップを実施。 |
| ○ | 学生相談、就職、インターンシップに関する全国的な情報収集・提供、全国ネットワークの構築等により大学等の個別の取組を支援。 |
| ○ | 各大学の転学(転部)に関する情報の収集提供、大学等での管理が行えない場合の学籍簿の管理の検討。 |
| ○ | 各大学等の学生担当教職員の研修や業務に必要な国内外での調査・研究。 |