| 参考資料1 |
(1)我が国の大学が、世界トップレベルの大学と伍して、教育及び研究の水準の向上や、世界をリードする創造的人材の育成をしていくためには、競争的環境を一層醸成し、国公私を通じた大学間の競い合いがより活発に行われることが重要。この一環として、第三者評価に基づく競争原理により、世界的な教育研究拠点の形成を重点的に支援し、国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを推進。 (2)主として研究上のポテンシャルの高い大学の教育研究拠点に対し、高度な人材育成機能も加味した重点的支援を実施。 (3)あらかじめ大学を選んだり、大学のランク付けを行うものではなく、大学からの申請に基づき、いわばピアレビューによる審査で選定。選定の結果は固定化せず、評価に応じて変動し得る仕組み。 (4)各大学の個性や特色の明確化が図られ、国公私を通じた競い合いにより、我が国の大学全体の水準向上や活性化につながることも期待。
学問分野構成など、基本的な仕組みの概要は以下のような方向。 ・分野構成 人文・社会科学から自然科学までの学問分野を10分野程度に構成し、分野別に申請を受け審査。 ・対象 大学院(博士課程)レベルの専攻等を対象(複数の専攻等の組み合わせや附置研究所等にも配慮)。 ・申請 どの専攻等を如何にして世界的な教育研究拠点に育成するかという学長のリーダーシップの下における大学としての戦略に基づき、学長から申請。 ・審査 学問分野別に、専門家・有識者等による客観的で公平・公正な第三者評価に基づき選定(審査委員会は省外に設置)。 ・審査の視点 教育研究活動実績及び将来構想等を基に、ポテンシャルの高さについて評価。 ・年次計画等 初年度は5分野を対象とすることを予定。1件当たり年間1〜5億円程度の支援を5年間程度予定。2年目に中間評価、期間終了時に事後評価を実施。
|
||||||||||||||||||||||
| 「世界的教育研究拠点の形成のための重点的支援」の骨格(案) |
・人文、社会科学から自然科学までの学問分野を下記の10分野に構成。 ・初年度は5分野を対象とし、各分野10〜30件(平均20件)程度(年間1〜5億円程度の支援)を選定(分野の特色、申請の状況等に応じ弾力的に対応)。 ・○は初年度、●は次年度の申請・選定を予定。
申請の取扱い ○分野構成と申請の関係については、各大学の構想に応じて弾力的に対応可能なものとする。 ・同一分野の申請について 同一分野に複数申請することも、複数専攻等を組み合わせて申請することも可。なお、大学としての戦略性の観点から複数の専攻等を有機的に組み合わせることに意義がある場合には、そのような組み合わせによって申請を行うことが期待される。 ・複数分野への申請について 1大学から(複合的な専攻の場合は1専攻から)複数の分野に申請することも可。また、一つの申請が複数の分野にまたがることも可(どの分野を主とするかは大学の希望を尊重)
(1)申請内容に係る教育研究活動の実績(当該申請内容に係る実績として大学が何を主眼としているかという観点に加え、下記の(参考)に例示するような指標を参考とする。) (2)当該大学の将来構想及びその実現のための計画(本経費の措置により、どのように世界的教育研究拠点の形成を目指すのか等) 注) 参考)(1)の教育研究活動の実績についての評価指標として考えられるものの例 ※あくまで例示であって、また、分野によって異なるものであり、一律に適用するものではない。具体的には、新たに組織される審査委員会において検討。 ※各分野特有の指標については、審査委員会において検討。
|
・この経費をどのように使うかの計画も含めて申請を行う。 ・補助金は学長にまとめて交付し、選定された専攻等において計画に基づき必要な 経費として使用。 (年度当たり1〜5億円程度。分野や専攻等の規模等に応じ弾力的に対応。)。
|
|||||||||||||||||||
・学問分野を10分野に分け、第1フェイズとして、2年計画で10分野をカバー。 ・初年度は5分野を対象とし、各分野10〜30件(平均20件)程度(年間1〜5 億円程度の支援)を選定(分野の特色、申請の状況等に応じ弾力的に対応)。 (イメージ) 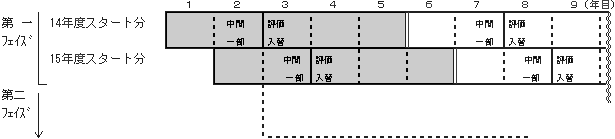
|
| 全体会議 | 各学問分野の関係者 産業界関係者、その他学識経験者等で構成 |
|
| 専門委員会 | 全体会議の委員が各専門委員会に分属するほか、各専門分野ごとに専門委員で構成 |
「世界的教育研究拠点の形成のための重点的支援」の当面のスケジュール(案)
(今後の状況如何により変更の可能性あり)
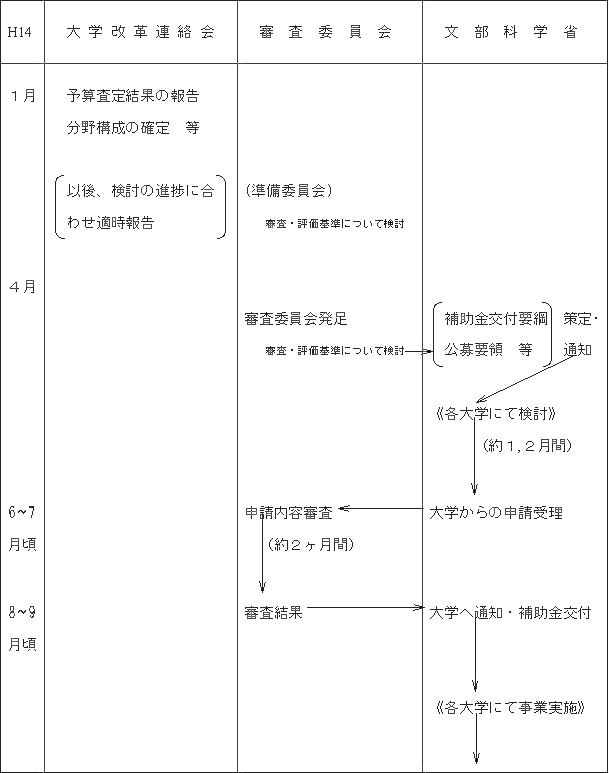
ページの先頭へ