- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 制度部会(第23回) 配付資料 > 資料3 ファカルティ・ディベロップメント関係参考資料 > 国立大学法人における教養教育に関する実態調査報告書-総括、FD関係抜粋-
国立大学法人における教養教育に関する実態調査報告書-総括、FD関係抜粋-
調査の目的と方法
(2)調査の方法と各設問の内容
本調査は「1.教養教育の実施体制」「2.教養教育の方法」の2つの設問で構成されている。
本調査は、全国の国立大学法人に対して実施し、1.については各大学から一つの回答を求め、2.については学部・分校等で教養教育を独立に実施している場合は独立単位ごとに回答を求めた。また、設問によっては、学長や教育担当副学長等でなければ回答できないものもあり、必要に応じてその方々に回答を依頼するよう求めた。
調査は、平成17年9月30日現在の状況に応じて回答を求めた。すべての回答は表計算ソフトに作成された回答フォーマットに入力する形式で集約された。
第1部調査結果
1.教養教育の実施体制について
(5)教養教育に関連ある教育研究施設(センター等)
表5‐1 教養教育に関連ある教育研究施設(センター等)
| 件数 | 比率 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 大学教育研究センター、高等教育研究センター等を設置している | 56 | 67.5 |
| 2 | 外国語センター、言語センター等を設置している | 22 | 26.5 |
| 3 | 保健体育研究センター等を設置している | 11 | 13.3 |
| 4 | 学生支援センター等を設置している | 25 | 30.1 |
| 5 | 国際センター、留学生センター等を設置している | 64 | 77.1 |
| 6 | アドミッションセンター、アドミッションオフィス等を設置している | 22 | 26.5 |
| 7 | 保健管理センター等を設置している | 78 | 94.0 |
| 8 | エクステンションセンター等を設置している | 18 | 21.7 |
| 9 | その他 | 25 | 30.1 |
本設問は、教養教育や大学教育全般、学生支援、高大連携等に関連のある大学内の教育研究施設の設置状況を問うたものである。83校から有効な回答が得られた。
1)大学教育研究センター、高等教育研究センター等の設置
まず、大学教育研究センター、高等教育研究センターの設置状況は56校(67.5パーセント)にのぼる。このうち、省令施設と明記されているものは15施設で、「高等教育機能開発総合センター」(北海道)、「高等教育研究センター」(名古屋)、「高等教育研究開発推進センター」(京都)、「高等教育研究開発センター」(広島)などの研究センターの流れをくむものと、「大学教育開発・支援センター」(金沢)、「大学教育総合センター」(鳥取)、「教育開発センター」(岡山)、「大学教育センター」(山口)、「大学教育機能開発センター」(長崎)等の比較的新しく、業務や業務研究を重視するもの、「教育工学開発センター」(東京工業)、「教育実践総合センター」(福岡教育)などの教育工学センターや教育実践研究指導センターの流れをくむものが見られる。また、学内措置として設置されたものには、「大学教育センター」(静岡)、「工学教育総合センター」(名古屋工業)、「高等教育創造開発センター」(三重)、「教育研究企画センター」(宮崎)、「教育開発センター」(愛媛)、「教育実践総合センター」(大阪教育)等、専任教員を置いている(と記述がある)ものが15施設ある。これらの施設は、工学センターや教育実践研究指導センター等の流れをくむものも見られるが、全学教育研究施設として、他の施設と連携しながら、教養教育の企画・実施・評価・調整やFD活動、高等教育研究などを行っている。
一方、「大学教育研究センター」(群馬)、「大学教育センター」(電気通信、琉球)など、学内措置として兼任教員のみで構成し、主に教養教育の企画・実施・調整などのための機能的組織として設立されたものも見られる他、「情報科学センター、地域共同研究センター」(京都工芸繊維、エクステンションセンターとして集計)、「地域連携センター」(鳴門教育、エクステンションセンターとして集計)、「地域・僻地医療教育実践センター」(旭川医科)、「学校教育総合研究センター」(上越教育)、「医療人育成教育研究センター」(滋賀医科)等、エクステンションセンターとして分類できるセンターや、部局や大学の特性に応じた特殊な目的のセンターを設置しているところも見受けられる。
なお、1999年の大学教育学会調査と比較すると、大学教育センター等を設置していた大学は16.7パーセントで、2005年の65.1パーセントは隔世の感がする。
2.教養教育の方法について
(15)教養教育の充実のための取り組みの状況
本設問では、各大学における教養教育の充実のための諸方策への取り組み状況をたずねた。1998年10月の大学審議会答申『21世紀の大学像と今後の改革方策について‐競争的環境の中で個性が輝く大学‐』(以下、「答申」)は、社会の高度化・複雑化等が進む中で、「主体的に変化に対応し、自ら将来の課題を探求し、その課題に対して幅広い視野から柔軟かつ総合的な判断を下すことのできる力」(課題探求能力)の育成が重要であるとの観点から、「学問のすそ野を広げ、様々な角度から物事を見ることができる能力や、自主的・総合的に考え、的確に判断する能力、豊かな人間性を養い、自分の知識や人生を社会との関係で位置づけることのできる人材を育てる」という教養教育の理念・目標を明示した上で、その実現のための改善改革の諸方策を具体的に例示していた。翌年の99年に、大学教育学会の委嘱により行われた「大学の教養教育に関する実態調査」(倉敷芸術科学大学教養学部「大学の教養教育に関する実態調査」委員会)が、その時点での「大学審議会答申」に対する各大学の取り組み状況を調査している。「答申」から7年余りが経過し、法人化も経た現在、国立大学の取り組み状況はどのように変化したのかを探るため、本設問はその際の調査の項目に一部修正変更を加えた以下に見る20項目について、「すでに実施済」「極めて容易」「やや容易」「やや困難」「極めて困難」の5段階からの選択回答でたずねた。
なお、本設問では、学部・分校等で教養教育を独立して実施している場合には当該学部・分校ごとの回答を求めているため、各大学での教養教育実施体制や組織のあり方・規模の多様性を反映して、結果的にほとんどの大規模総合大学からの全学としての単一の回答と、比較的中規模・小規模の複数学部を有する若干の大学からの学部ごとの回答および単科大学の分校ごとの回答とが混在することになり、83大学から合計96例の回答が寄せられた(一部、無回答があった項目は95例)。そこで、本設問に関しては、規模の大小やカテゴリーの相違にかかわらず、原則としてすべての回答を、それぞれが独立した教養教育実施の責任母体からの回答とみなして母数に加えることにした。ただし、同一大学の複数学部からの回答が20のすべての項目について全く同一である場合は、実質上同一の責任母体からの単一の回答とみなして、あえて重複してカウントすることはしなかった。その結果、母数は83大学からの88例(一部、無回答があった項目は87例)となった。その集計結果が表15‐1である。各項目ごとの回答の比率をグラフ化すると図15‐1のようになる。各項目に対する回答の比率を一覧表示すれば表15‐2の通りである。「すでに実施済」「極めて容易」「やや容易」の三者の合計を「実施は容易」、「やや困難」「極めて困難」の二者の合計を「実施は困難」として、それぞれの比率も加えて示した。以下の分析では、この二つの数値も併せて用いることにする。
表15‐1 教養教育の充実のための取り組み状況への回答
| すでに実施済 | 極めて容易 | やや容易 | やや困難 | 極めて困難 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理念・目標を実現するための全教員の意識改革 | 11 | 0 | 25 | 41 | 11 | 88 |
| 2 | 教養教育の全学的な実施・運営体制の整備 | 42 | 3 | 17 | 25 | 1 | 88 |
| 3 | 教養教育と専門教育の有機的連携の確保 | 32 | 0 | 26 | 26 | 4 | 88 |
| 4 | ボランティア活動等関連の授業科目開設 | 24 | 3 | 25 | 25 | 10 | 87 |
| 5 | インターンシップ等関連の授業科目開設 | 38 | 4 | 20 | 22 | 3 | 87 |
| 6 | キャリア教育等関連の授業科目開設 | 46 | 6 | 19 | 11 | 5 | 87 |
| 7 | 国際舞台で活躍できる能力の育成 | 15 | 4 | 21 | 43 | 5 | 88 |
| 8 | 単位制度の実質化(授業外学習時間の確保) | 14 | 1 | 21 | 41 | 11 | 88 |
| 9 | 厳格な成績評価の実施 | 21 | 3 | 28 | 33 | 3 | 88 |
| 10 | 履修指導の充実 | 37 | 4 | 34 | 13 | 0 | 88 |
| 11 | 履修科目登録の上限設定 | 46 | 11 | 13 | 13 | 4 | 87 |
| 12 | FD(ファカルティ・ディベロップメント)の実施 | 65 | 3 | 13 | 7 | 0 | 88 |
| 13 | シラバスの活用 | 57 | 3 | 22 | 6 | 0 | 88 |
| 14 | マルチメディアの効果的な活用 | 28 | 7 | 29 | 22 | 2 | 88 |
| 15 | 教育活動の評価の実施 | 35 | 4 | 23 | 21 | 5 | 88 |
| 16 | 優れた教育活動を行っている教員の顕彰 | 18 | 5 | 33 | 27 | 4 | 87 |
| 17 | 単位互換制度等の拡大 | 43 | 4 | 23 | 17 | 1 | 88 |
| 18 | 学長のリーダーシップを確立する組織運営体制の整備 | 48 | 4 | 25 | 10 | 1 | 88 |
| 19 | 自己点検・評価の充実 | 40 | 3 | 33 | 12 | 0 | 88 |
| 20 | 認証評価機関以外の第三者評価システムの導入 | 17 | 5 | 27 | 33 | 5 | 87 |
図15‐1 教養教育の充実のための取り組み状況の比率
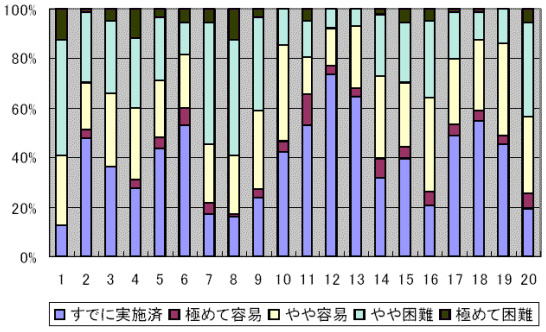
図15‐2 教養教育の充実のための取り組み状況の比率一覧
| 項目 | すでに実施済み | 極めて容易 | やや容易 | やや困難 | 極めて困難 | 実施は容易 | 実施は困難 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5パーセント | 0.0パーセント | 28.4パーセント | 46.6パーセント | 12.5パーセント | 40.9パーセント | 59.1パーセント |
| 2 | 47.7パーセント | 3.4パーセント | 19.3パーセント | 28.4パーセント | 1.1パーセント | 70.5パーセント | 29.5パーセント |
| 3 | 36.4パーセント | 0.0パーセント | 29.5パーセント | 29.5パーセント | 4.5パーセント | 65.9パーセント | 34.1パーセント |
| 4 | 27.6パーセント | 3.4パーセント | 28.7パーセント | 28.7パーセント | 11.5パーセント | 59.8パーセント | 40.2パーセント |
| 5 | 43.7パーセント | 4.6パーセント | 23.0パーセント | 25.3パーセント | 3.4パーセント | 71.3パーセント | 28.7パーセント |
| 6 | 52.9パーセント | 6.9パーセント | 21.8パーセント | 12.6パーセント | 5.7パーセント | 81.6パーセント | 18.4パーセント |
| 7 | 17.0パーセント | 4.5パーセント | 23.9パーセント | 48.9パーセント | 5.7パーセント | 45.5パーセント | 54.5パーセント |
| 8 | 15.9パーセント | 1.1パーセント | 23.9パーセント | 46.6パーセント | 12.5パーセント | 40.9パーセント | 59.1パーセント |
| 9 | 23.9パーセント | 3.4パーセント | 31.8パーセント | 37.5パーセント | 3.4パーセント | 59.1パーセント | 40.9パーセント |
| 10 | 42.0パーセント | 4.5パーセント | 38.6パーセント | 14.8パーセント | 0.0パーセント | 85.2パーセント | 14.8パーセント |
| 11 | 52.9パーセント | 12.6パーセント | 14.9パーセント | 14.9パーセント | 4.6パーセント | 80.5パーセント | 19.5パーセント |
| 12 | 73.9パーセント | 3.4パーセント | 14.8パーセント | 8.0パーセント | 0.0パーセント | 92.0パーセント | 8.0パーセント |
| 13 | 64.8パーセント | 3.4パーセント | 25.0パーセント | 6.8パーセント | 0.0パーセント | 93.2パーセント | 6.8パーセント |
| 14 | 31.8パーセント | 8.0パーセント | 33.0パーセント | 25.0パーセント | 2.3パーセント | 72.7パーセント | 27.3パーセント |
| 15 | 39.8パーセント | 4.5パーセント | 26.1パーセント | 23.9パーセント | 5.7パーセント | 70.5パーセント | 29.5パーセント |
| 16 | 20.7パーセント | 5.7パーセント | 37.9パーセント | 31.0パーセント | 4.6パーセント | 64.4パーセント | 35.6パーセント |
| 17 | 48.9パーセント | 4.5パーセント | 26.1パーセント | 19.3パーセント | 1.1パーセント | 79.5パーセント | 20.5パーセント |
| 18 | 54.5パーセント | 4.5パーセント | 28.4パーセント | 11.4パーセント | 1.1パーセント | 87.5パーセント | 12.5パーセント |
| 19 | 45.5パーセント | 3.4パーセント | 37.5パーセント | 13.6パーセント | 0.0パーセント | 86.4パーセント | 13.6パーセント |
| 20 | 19.5パーセント | 5.7パーセント | 31.0パーセント | 37.9パーセント | 5.7パーセント | 56.3パーセント | 43.7パーセント |
2)教養教育の全学的な実施・運営体制の整備
「教養教育の全学的な実施・運営体制の整備」については、実施率が47.7パーセントとほぼ半数弱が実施済との回答であったが、1999年の調査(57.9パーセント,N=57)と比較すると10ポイント減少している。実施を困難とする回答も22.8パーセントから29.5パーセントと増加している。これも、母数が異なることや、統合及び法人化を経たことによる状況の変化等が考えられるため、一概に後退したと決めつけることには慎重でなければならないが、少なくとも思うように前進してはいないということだけは確かであろう。
図15‐3 教養教育の全学的な実施・運営体制の整備への取り組み状況
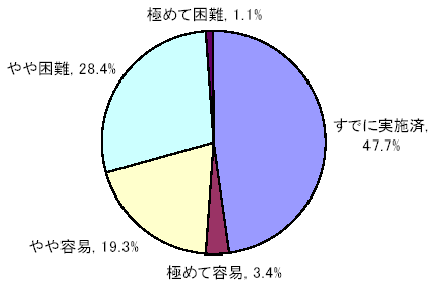
12)FD(ファカルティ・ディベロップメント)の実施
「FD(ファカルティ・ディベロップメント)の実施」については、73.9パーセントがすでに実施しているとの結果を得た。本設問20項目中では最高の実施率である。実施は困難とする回答の比率も8.0パーセントにすぎず、そのうち「極めて困難」の回答はなかった。1999年の実施率29.1パーセント、困難とする回答40.1パーセントと較べると隔世の感がある。FDに関しては、単なる実施の有無ではなく、むしろその内容や成果が問われる時代に入った、と言ってよいのではなかろうか。
図15‐13 FD(ファカルティ・ディベロップメント)の実施への取り組み状況
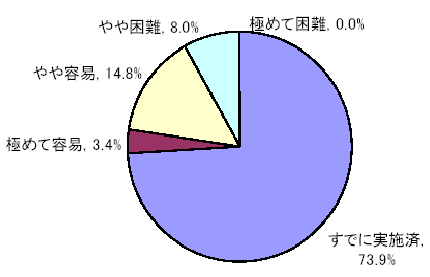
第2部総括
これまでの第1部1,2の考察を踏まえて、第2部では全体的に総括的な整理を試みた結果、教養教育の実施体制においても、教養教育の方法においても、現状にはさまざまな問題点や課題が山積していることが理解できる。ここでは、それぞれの項目毎に要約的な診断を行うことによって、現状の問題点や課題を具体的に指摘するとともに、それを踏まえて、教養教育に関する理念の確立や組織改革等に焦点を絞って、論点の整理を行うことにしたい。
1.教養教育の実施体制に関する現状と課題
(1)教養教育実施組織の類型
1)教養教育実施組織の諸類型への該当
専門教育と対峙した教養教育の主たる担当組織である「担当学部方式」、「教養部方式」、「機能的・実質的組織方式」、「各学部方式」の4類型の中では、「機能的・実質的組織方式」が増加しており、全類型の4分の3を占める半面、「担当学部方式」や「教養部方式」は減少の一途を辿っている事実が得られる。この結果、戦後半世紀にわたって教養教育を主導してきた教養部はもはやほとんど解体したことが判明する。
2)機能的・実質的組織方式の具体的組織形態
機能的・実質的組織方式に関して、調査した4類型(機能的、実質的、委員会専従、委員会兼担の各方式)ではどの方式を採用しているかを尋ねてみた結果、ほぼ均等に分かれた。この事実は、従来の教養部が機能的分化を遂げている実態を顕著に示しているとみなされる。さらにそのことは、「機能的組織方式」「実質的組織方式」として包括される類型が増加すると同時に、その内部の名称が多種多様に分化している事実を裏書きしている。
教養部解体と機能方式の定着に伴い、教養教育責任部局の分断化が進行し、しだいに先細りになる傾向が生じていると危惧されるのではあるまいか。この点を踏まえて、教養教育の再建を図るには、担当学部方式や教養部方式を強化するか、分断化した組織の再編成を図るかの選択が迫られるであろう。しかしながら、前者の方式の回復は解体化が持続している現状では実質的に困難となっているし、後者の場合は組織の多様化に拍車がかかっている現状では具体的な歯止め策が困難になっていると解される。したがって、このままで今後の事態が進行すれば、教養教育の一層の混迷と形骸化が進行するものと推察される。
(2)教養教育実施組織の事務組織
今回は、前回調査に比較して、独立事務組織の比率が下がり、特定学部事務部内や各学部事務との業務分担の比率が上がっているところに特徴が見出される。このことは、上で指摘した組織の分断化に連動すると解されるし、事務組織の現在の動きがこのまま推移すれば、教養教育の事務組織の責任所在は今後一層風化する畏れがあると言えるだろう。
(3)教養教育実施組織の調査研究部門・広報部門
「機能的・実質的組織方式」においては、調査研究部門を置くか、大学教育センター等と連携している形態が最多である。それに伴って、大学教育センター等の学内での比重が高まっていると観察できるが、大学教育センター等が本来期待された「自己研究装置」としての研究組織の性格を強化するよりも、教育実践組織の性格を色濃くする傾向が見られる。果たして、そのような方向へ向かうことは、この種のセンターにとって望ましいのか否か検討が必要な段階に来ている。
(4)全学的な教養教育担当教員集団
回答を寄せた国立大学の中には全学的な教養教育担当教員集団を組織している割合が多いことから、教養部解体に伴って、科目別担当教員集団を組織することの必要性が高まっていると考えられる。
(5)教養教育に関連ある教育研究施設(センター等)
1)大学教育研究センター、高等教育研究センター等の設置
前回(16.7パーセント)と比較すると、設置状況は半数以上(67.5パーセント)にのぼっており、この間に飛躍的に増加し、内容的に多様化が進行している。教育研究施設に関しては、研究センターよりも、教育センターや教育開発センターが増加する傾向を示している事実は、カリキュラム、評価、FDなどの実践的な課題を遂行することが当該センター組織に対して期待されているとみなされる。この種のセンターが教養教育の実施義務を付与される傾向が高まる半面、必ずしも十分な責任を付与されていない傾向が見られるのは、上述した責任部局の形骸化と通底する問題である。同時に大学教育研究センター等は、上でも指摘したが、本来の「自己研究装置」の性格を維持することとすぐ役立つ実践へ参画することの間で動揺する傾向が生じており、中途半端な役割の中でアイデンティティの拡散が生じているのではないかと観察される。
2)その他のセンター類(外国語センター、言語センター等/保健体育研究センター等/学生支援センター等/国際センター、留学生センター等/アドミッションセンター、アドミッションオフィス等/保健管理センター等/エクステンションセンター等/その他の施設)の設置
これらの各種センター類の設置においても、増加と多様化の実態が進行している。この種のセンター設置は、教養教育の内実が機能分化し、専門化することを通して、専門組織に分業化され、専門家に分担される動きが顕著になっている証左であると同時に、上記の組織的変化と連動して、責任部局が集中的に統合した取組みを行う、従来の教養部相当の拠点が成立しなくなっている現象を裏書きしていると解される。
(6)教養教育の学士課程教育内の位置づけ
教養教育を学士課程の全域を通じて実施する大学群と教養教育実施組織の実施時期に集中する大学群とが大半を占めている。上記の観察に関連づければ、組織的には双方ともに教養教育の強化よりも弱化の方向に作用する途上にあると観察される。学士課程内の教養教育の位置づけに関して、大学間に温度差がみられる事実は、教養教育と専門教育との有機的統合を図ることによって、教養教育の強化をもたらすとの所期の意図が十分に実現しているとは言えない現実を端的に反映するものではなかろうか。換言するならば、教養教育を学士課程教育の中でコア・カリキュラムや主専攻として担保する比重は、専門教育との統合や融合の名の下に次第に低下を来しているのではあるまいか。したがって、この事実は、教養教育を主軸に専門教育との協力を遂行するよりも、専門教育を主軸に教養教育を包摂する方向への動きに拍車がかけられていると読みとれる。
(7)教養教育の目標と学部・学科の教育目標及び学生の受入との関係
1)アドミッション・ポリシーの策定状況
大半の大学は、アドミッション・ポリシーを学部・学科の教育目的と整合的に策定している、と回答している。
2)グラデュエーション・ポリシー等の策的状況
調査結果では、教養教育の目的が明確に規定され、学部・学科の教育目標に反映している大学は増加していることが分かる。
目標に関する回答結果から、大学教育が目標設定とその目標達成を意識する観点に立脚して、入学と卒業のポリシーを定着させ始めている実態が把握できるが、果たしてそれらが首尾一貫して遂行され、インプットとアウトプットのみに留まらず、スループットとの連関の中で、効果的な教育が達成されているか、が問われる。そのことは本調査では尋ねておらず、したがって明確になっていないものの、教養教育の組織や機能が後退している事実と連関付けて観察した場合、大学教育の入口から出口までの一貫性と関連した教育効果がどの程度奏功しているかを吟味する観点が今後は一層問われるに違いない。
(8)法人化後の教養教育に向けられる予算及び人的資源の変化
1)教養教育に向けられる予算の変化状況
法人化後に教養教育の予算は減少した大学が約3割、しかも将来的には約7割が減少すると予想されている。今後厳しい予算の中で教養教育をいかに充実していくのかが重要な問題となっている。予算及び人的資源の変化に関する調査結果は、組織的に問題が露呈しているのに加え、予算的にも深刻な問題が露呈していると読める事実を帰結している。運営費交付金の減少をはじめ、大学予算が削減され、入学金、授業料、寄付金等の政府予算に依存しない、新たな予算の増加を自力で開拓する必要に迫られる近未来を想定すると、各大学の将来に対する不安は高まらざるを得ない。その影響が直接及ぶのは重点整備が期待される部分よりも、組織や機能の後退が進行しはじめている部分であることは容易に想像できるのではあるまいか。そのような観点から、調査結果を直視するならば、それはすでに後退を顕著に示している教養教育への容赦のない集中砲火であり、今後の不安をますます募らせる状態の到来を意味するのは自明であろう。
2)教養教育を担当する教員数の変化状況
教養教育を担当する常勤教員数が今後減少すると予想する大学は約半数に達している。
3)教養教育を担当する非常勤講師数の変化状況
今後の減少を予想している大学は9割近くに達しており、教養教育の非常勤講師の削減は今後ますます進行すると予想される。常勤、非常勤の両方が減少すると予測する大学が多いので、それを補足して教養教育の質的維持を行うには、人員削減をカリキュラムの質で補完する視点から、カリキュラムの見直しが不可欠の課題となる。
4)教養教育を担当する常勤講師の担当コマ数の変化状況
常勤担当コマ数は今後増加すると予想している。
5)教養教育を担当する非常勤講師の担当コマ数の変化状況
非常勤担当コマ数は今後ますます減少すると予想している。今後教養教育はスリム化し、残った常勤担当教員により多くのコマ数負担が集中する大学が増えると予想される。大多数の教員は教養教育の担当からはずれ、少数の専任に一任される傾向が顕著になりつつある。
6)教養教育を担当する部署における事務職員の変化状況
教養教育の担当事務職員数は6割の大学で今後減少していくと予想されている。
全体に、上述したように、教養教育の責任担当部局が縮小し、曖昧となり、分断化し、機能化する中で、従来では教養部という責任担当部局によって組織的かつ機能的に明確な性格を付与されていた教養教育は確実に形骸化し、風化する事態が進行していると観察できる。加えて、常勤教員、非常勤講師ともに減少傾向にあり、今後も減少した常勤教員にコマ数が集中する傾向が予想されているという事実が判明した。
こうして、教養教育は組織的な規模や人数などの量的側面では明らかに後退が加速する状況が出現していることは否定できないから、それを挽回するには、組織的には責任担当部局あるいは多少でもそれに近い部局の再建強化策が重要な課題となるとともに、それと連動した量的側面の立て直しは当面の課題である。しかしながら、予算縮小によって、組織や教員の縮小に追い打ちがかけられるとの予想が各大学では支配的空気になっており、教養教育の形骸化、空洞化、風化への歯止めや補強に対する無力感が着実に高進しており、今後も加速されそうな気配が窺われる。
(9)各大学の将来像
中教審答申「我が国の高等教育の将来像」(平成17年)で提言された7つの種別の中で、特に教養教育と密接な関係にある「総合的教養教育」の機能に比重を50パーセント以上置く大学は現在までのところ皆無であるという調査結果が得られた。大半の大学は、「世界的研究・教育拠点」、「高度専門職業人養成」、「幅広い職業人養成」、「特定の専門分野の教育研究」のいずれかに50パーセント以上の重点を置いている半面、「総合的教養教育」、「地域の生涯学習拠点」、「社会貢献」には重点を置いていない、という事実が判明した。この事実には、研究や専門職へ比重を置き、教育や教養教育、生涯教育へは比重を置かないという国立大学法人の実態が鮮明に窺えるのである。
このことは、中教審が描く構想とは異なって、教養教育を中心に行う「リベラル・アーツ型大学」を明確にめざした大学は、現在のところは存在しないという興味深い事実を示していることにほかならない。それに加えて、国立大学の約4分の1が教養教育を全く重視していないという俄には信じがたい事実も判明した。
このような現実は、上で観察した形骸化、空洞化、風化、無力化の方向が21世紀の大学像と無関係に進行しているのではなく、明らかに大学像と現実とは符合しながら進行していることを示唆すると解されるに違いない。そればかりではなく、今後、現在の後退する教養教育を再建し、充実させる方向に舵取りをするために、主体や拠点となるべき諸大学において極めて消極的な現実が横たわっている証拠がそこには厳然と存在するのである。これでは、教養教育の現状がすでに危惧すべき状態に置かれているばかりか、将来に対しても黄信号やむしろ赤信号が点灯しているというほかないだろう。
(10)教養教育の組織運営に関する問題点
前回の調査と比較すると、教員負担の偏りと全学的な調整や連絡の希薄化が進行していることが明らかになった。教養部の解体に伴い、「全学出動体制」を含め大学全体で教養教育に取組む体制や姿勢が重要な課題となったにもかかわらず、現実にはその体制や姿勢が確立されず崩壊する方向を辿り、しだいに一部教員へ負担が集中する傾向が生じ、さらには学内の教養教育に対する理念・目的・目標に関するコンセンサスが部局間において希薄化している事実が把握できる。回答結果は、担当教員自身は教養教育を軽視する傾向に歯止めがかかっているとする半面、その他の担当しない多くの教員は等閑視する傾向が生じているとしている。こうした調査結果には、一部教員に教養教育を一任して、多くの教員は教養教育よりも専門教育あるいは研究に専念したいという本音が透けて見える、と言って過言ではあるまい。
(11)検討課題
今後の検討課題としては、1.教養教育の充実、2.教養教育実施組織、3.教養教育の予算、4.教養教育の授業担当者、5.教養教育のカリキュラム、6.その他、などへの要望が多いことが分かる。1は教養教育の理念の共有が脆弱であること、2は実施責任組織が弱体であること、3は予算の削減が問題であること、4は授業担当者の偏り・不足、非常勤講師の削減などの問題を含むこと、等々、概して量的側面の改革課題となっていることが分かる。これに対して、特に5はカリキュラムの見直し・充実の問題、教養教育と専門教育のバランス・提携の問題を含み、質的側面の改革課題となっているのに加え、6では、FDの充実が課題となっている。こうして、ハード面、ソフト面の両方において検討を要すべき問題や課題が山積している実態が窺われる。
こうした結果を見る限り、教養教育の実態は良好な状態にあるとは決して読みとれない。理念、組織、人員、予算、内容等の全領域にわたって、再建のための再検討の必要性が焦眉の急を告げている現状が厳然と存在すると言わなければならない。
2.教養教育の方法に関する現状と課題
これまでの考察では、第1部の教養教育の実施体制に関する現状と課題を中心に、各項目に対する要点的な概略と分析を行なってきた。それに引き続き、以下の(12)から(18)までの項目は、第2部の教養教育の方法に関する現状と課題を中心に、やはり各項目に対する要点的な概略と分析を行なうものである。
(12)教養教育に関する卒業要件
1)卒業の要件となる教養教育に関する授業科目の単位数
平成10年以降、教養教育の単位数に変化なしとする大学が過半数(6割以上)を占めているものの、減少したとする回答が増加したとする回答を上回っていることから、減少傾向が進行しはじめていると観察できるのではあるまいか。教養教育の形骸化に歯止めをかけるには、単位数の多寡の動向は無視できない要因だろう。教養教育の遂行基盤のバロメータとなる単位数が増加するのではなく減少する事実がある以上、それを直視し、歯止めをかけ、補強する方策が必要であるはずである。
2)外国語科目の履修方法
英語を必修、第2外国語を選択必修とする大学の割合が多く、また文系と理系学部間に履修に関して差を設けていない、という事実が看取できる。
3)英語教育に関する達成目標の設定状況
達成目標を設定していない大学が圧倒的多数(8割)を占めている事実は、注目に値する。教養教育の単位数が減少する傾向に問題があると同時に、質的保証の観点から質的な到達目標が設定されることが課題となるにもかかわらず、現実には未だ殆ど設定されていないことは問題であり、改善を要するであろう。
(13)教養教育に関する授業科目
教養教育の授業科目に見られる特徴は次のようなものである。「学際的・総合的内容の講義科目」、「実験・実習など実験的教育」、「専門教育の入門・基礎科目」、「情報処理科目」、「心身の健康に関する科目」、「演習や体験学習を主体とするプロジェクト型科目」、「キャリア教育、職業意識啓発科目等」等の比重が概して高い。多くの大学が教養教育に専門教育の橋渡し的役割を付与していることも指摘できる。特色ある科目もかなり導入されている事実がみられる。
こうした動向には、教養教育と専門教育を学際的・総合的に統合する試みが次第に定着している事実が読み取れると同時に、教養教育の独自性が失われ、全体に専門教育の入門や基礎など、専門教育への導入の手段としてみなされる傾向も増加していると解される。
また、補習科目を約4割の大学が開設しており、学生の学力低下への対応が不可欠になっている実情が窺える。このことは、初年次教育、高大接続の必要性との連関で見た場合には当然の結果と解されるであろうが、その半面、大学が次第に「学校化」の一途を辿っている現象として捉えられるだろう。言うまでもなく、このことは「大学1年生」ではなく「高校4年生」現象が蔓延し、学習力や学力の大学への適応が欠如する学生層が増加する傾向にますます拍車がかけられている現実以上のなにものでもない、と解される。教育や研究が弱体化するのと比例して、本来ならば、高校までに達成されなければならない学習力や学力の解決が容赦なく大学へと持ち込まれる現象が着実に定着しつつある事実を示している。
こうして、ユニバーサル・アクセスが実質化の時代を迎える今後、学習者としての学生の重要性が浮上し、大学が学習者支援の立場を鮮明にする必要性が高まらざるを得ないと予想される。それと同時に、学生の学習や学修への参加が増大すると見込まれるし、学生同士の学修が増加することも予想されるが、調査結果を見る限りでは、「ピア・エデュケーション(学生同士が教え合うシステム)」はまだあまり導入されていない。
(14)新入生に対するオリエンテーション・プログラム
オリエンテーション・プログラムはほぼ全大学で導入されているとともに、その中味は、「教養ゼミ」、「基礎ゼミ」、「フレッシュマン・セミナー」など多様性が見られるのが特徴である。
1)新入生に対する指導教員の分担
多くの場合教員1人が10名程度の学生を担当している。大学が大衆化し、クラス人数が大人数化する現実の中で、いかにしてチューター制度、オフィス・アワー、少人数教育制度などを導入し、教員と学生のコミュニケーションを密接に保持し得るか否かは重要な課題である。学生10名程度に1人の指導教員を配置している事実は、こうした問題に多くの大学で苦慮している事実の一端が窺える結果であるとみなされる。
2)最も重視している点
履修指導は大半の大学が導入しており、これまでの観察からみても、当然予測できる実態を裏書きしている。
(15)教養教育の充実のための取組みの状況
1)理念・目標を実現するための全教員の意識改革
意識改革は実現されたとする回答比率(12.5パーセント)が前回調査の比率(16.4パーセント)より低く、今回の20項目の中で最低を示したのは意外な事実ではあるまいか。意識改革への動きは徐々に前向きになっているものの、このような依然として停滞する数字を読む限り、その背景には意識改革を阻む条件が厳然と横たわっている事実があると言わなければならず、一方ではそのような条件を排除することが重要な課題になるとともに、他方では教養教育を推進するためには全体には依然として意識改革が重要な課題であるとみなされる。
2)教養教育の全学的な実施・運営体制の整備
この項目への肯定的な回答が、前回と比較して10ポイントも減少している事実は、衝撃的であると言えるかもしれない。そこには、意識改革が停滞しているのに加え、実施・運営の体制そのものの整備の困難性が意識されている現状のあることを見逃せないであろう。改革の意識と体制とは相即の関係にあると推察すれば、意識の推進と体制の推進という双方の前向きな推進なくしては、現状の打開はおぼつかないと容易に考えられる。
3)教養教育と専門教育の有機的連携の確保
両者の有機的連携の確保は、前回より若干増加傾向にあることが判明した。しかし伸び悩みに注意すべきであろう。このことは、上記したように、教養教育と専門教育との連携がある程度展開した事実を示唆するが、同時に教養教育の独自性が徐々に失われている実態を裏書きすることを示唆するとも読めるであろう。
「知の再構築」やカリキュラムの再編成が実現されて、学際的かつ学融的な視点からの教養教育と専門教育の有機的な連携が実現するには、カリキュラム編成や教員の意識等の質的な側面との関係が重要な鍵を握っているのであるから、量的な側面の進展のみでは解決できない。その点、すでに考察したことを踏まえ、教養教育が前進よりもむしろ後退している現状を総合的に勘案すると、両者の質的な統合や融合は未だに程遠く、全体的には進捗状態が芳しくない実態に留まっている。
4)ボランティア活動等関連の授業科目開設
具体的に様々な科目の開設状態を検討してみると、多くの科目を開設し、相当の効果を上げていると回答した大学は少なくないことが分かる。ボランティア活動関連の授業科目開設は、まだ少ないにもかかわらず、前回と比較すると前進している。
5)インターンシップ等関連の授業科目開設
実施率(43.7パーセント)はボランティア科目開設に比べ高く、比較的順調である。
6)キャリア教育等関連の授業科目開設
半数以上(52.9パーセント)が実施しているように、1999年の中教審答申で提案された以降に急速に導入が進展したとみなされる。
一般的に、フリーターやニートが増加現象を辿る現実がある以上、それを阻止する方策は、人生全体を視界にいれたキャリア教育の充実に求める必要があるであろう。その意味では、日本におけるキャリア教育の従来の発展状態は必ずしも十分であったとは言えず、現在も今後の展開が期待される段階に留まっているとうほかない。その経緯や現状を考慮すると、曲がりなりにも、大学での取組みが進展しつつある事実は注目されてしかるべきであろう。
7)国際舞台で活躍できる能力の育成
この項目への回答を見ると、実施済み(17.0パーセント)がかなり低調であり、実施困難の割合も高い。前回と比較しても改善が見られないことから、今後、どのような対応をするかが問われる状態にある。グローバル化の進展は、大学教育への挑戦であり、従来のカリキュラムや指導体制では、国際舞台で活躍できる能力を育成するには無理があるに違いない。上述した教養教育のカリキュラムの開発や充実と密接に関係している事実を考慮すると、骨太の改革を必要としており、小手先の改革では通用しないであろう。その意味から、この項目は今後の取組みが期待される段階に留まっていると言わなければならないだろう。
8)単位制度の実質化(授業外学習時間の確保)
20項目中、意識改革に次いで低く、実施困難とする割合(59.1パーセント)も、同様に低い。前回と比較すると、実施率は多少上がっているが、単位制度の実質化が容易だとする割合は下がっている。単位制度の実質化は思ったよりも困難であることが次第に認識されてきていると読める傾向であろう。想えば、単位制度の形骸化は戦後、アメリカのシステムを導入したとき以来進行して現在に至った事実である。
この事実こそ、単位制度が日本的風土や土壌の中で骨抜きにされ、定着しなかった何よりの証拠であるとみなしてさしつかえあるまい。これを本来の単位制度に復元し、予習時間、授業時間、復習時間があいまって所定の単位が授与される仕組みを回復しない限り、教育の量的側面は達成されても、肝心の質的側面はなんら達成されたことにはなるまい。単位制の充実は、教育の質的保証の重要な柱である以上、きわめて立遅れた現状の迅速な改革が課題である。
9)厳格な成績評価の実施
前回より改善されているとはいえ、問題がないのではない。なぜなら、内容の吟味が不可欠な状態にあると言えるからである。厳格な成績評価は、厳格な単位制度の運用、それと関連したGPA制度や履修科目登録の上限設定=CAP制度の運用、等と密接に連関した教育過程の一環を形成している以上、他の運用が適切でこの運用のみが不適切という現象が生じることはあまり現実的であるとは言えないだろう。その点、他の運用と同様、多少の改善が見られるとしても、その内容は十分検討されるべき段階に留まっている。そこには、前回より改善されたとはいえ、依然として厳密な成績評価が十分行なわれているとは言えない現実が横たわっているのであり、それは日本の大学教育の質的保証が未だ不十分な状態に低迷していることを物語る証拠の一端を示しているというほかあるまい。
厳格な成績評価は、教育過程の仕上げの部分であることにかんがみ、教育目的・目標の設定、カリキュラムの編成、GPA制度、CAP制度、履修指導、教育指導のあり方、といった一連の過程を通して実現する、教育効果の総決算である。他の側面が自信を持って遂行できる段階に到達することと、厳密な成績評価が遂行されることとは、連関性が高いはずであり、その意味でこうした連関性が達成されていない現状では、教育改革は未だ半ばに過ぎないのではあるまいか。
10)履修指導の充実
この項目への回答を見ると、前回より前進しているが、成果の検証が不可欠な段階にある。
11)履修科目登録の上限設定
既に半数以上が実施しており、前回より前進している。上記の単位制度の実質化が不十分な状態にあることと連動して考える必要があり、履修科目登録の上限設定=CAP制の改善が量的に増加を見たからといって過大評価するのではなく、単位制度の改善によって学生の学力向上に奏功したか否か、教育効果の内容面の検討が課題である。
12)FD(ファカルティ・ディベロップメント)の実施
前回の実施率が低く困難度が高かったのと比較すると、今回は隔世の感がするほど大きな進展を示した。その点では、FDが大学制度や組織に定着する制度化の動きは長足の進歩を遂げたと観察できるに違いない。その背景には、1998年の大学審答申によってFDが努力義務とされ、最近では機関別認証評価において義務化されている動きがあるなど、強制力が作用していることとの連関性があるのではなかろうか。
しかし、現状は十分な段階へ到達しているとは読めない。他のFDに関する研究でも実証されているように、実際に内容を吟味すると、FDの制度化は量的に進展を示した第1段階から、質的内容が吟味される第2段階へ移行する過渡期にあると把握できるのではあるまいか。少なくとも、教員の研究志向が教育志向よりも依然として強固であること、カリキュラム編成、履修指導、教育指導、厳格な成績評価、といった一連の改革が不十分との印象を与えること、等を勘案すると、FDが第2段階への入り口にあっても、いまだに初歩的段階を卒業するまでに到達してないと観察することは難しくないだろう。
他の研究では、FDの制度化は直線的に進展するのではなく、一見成功した後に挫折や失敗に直面する傾向が見られ、螺旋的に進展することが明らかになっている。そこには量的発展では一見成功を収めていると見えても、それは見せかけの現象であって、質的には問題を孕む事実が存在するのである。その意味で量的進展が見られる事実は評価できるとしても、それのみをもって無闇に評価できないだろう。
13)シラバス活用
この項目は、FDの実施率に次いで比率が高いものの、前回と比較すると、実施率は変わらないのに、困難度はやや増えている点が注目に値する。問題は、シラバス活用の本来の意味が実現しているか否かにある。学習者の学習を支援し、学習効果が実際に上昇しなければ無意味である。量的普及ではなく、果たして学生の学習効果に貢献しているか否かを問う、成果の検証が問われる段階に入っている現在、教員は行く手に立ちはだかる困難性を改めて意識しているのではあるまいか。
14)マルチメディアの効果的な活用
実施率はあまり高くないという事実は前回調査と変わっていない。なぜ進展を見ないかを検討して、改善を図ることが今日の課題となっている。IT革命によって、教授技術の改革が日程にのぼって久しいが、伝統的な教授方法と新たな技術革新の間には相当の距離が存在しているから、理工系の教員の場合はともかく、文系教員の場合には前者に代わって後者のマルチマディアを自由自在に活用するまでに至るには、意識変化が欠かせないし、相当な訓練や研修が欠かせないだろう。したがって、数字上である程度の進展があっても、内容の上でマルチメディアを専門的に活用し十分な教育効果をあげるまでには、時間を要するのは当然の成り行きであるに相違ない。今回の調査結果には、意識的にも行動的にも教員が躊躇する実態が透けて見えるのではあるまいか。
15)教育活動の評価の実施
前回に比較して、教育活動の評価実施は確かに前進している。それにもかかわらず、一見して前進して定着しているように見えながらも、その結果、実際に教育成果が上がっているのか否か、教養教育の質的保証が実現しているのか否か、具体的な評価内容までは立ち入った検討をしていないので、内容的な詮索はできない。上記の考察からも窺えるように、量的に改革が進展しているとの回答は種々の項目において見られるものの、実質的な成果に関しては必ずしも十分であるとは言えない実情にあることが分かった。その点、内容に関わる検討を深めるとともに、それに即した改革が不可欠である。
16)優れた教育活動を行っている教員の顕彰
教員の研究業績に対する顕彰は、国内外の学界において頻繁に行なわれる傾向がある半面、教育業績に対する顕彰は等閑に付されてきたことを勘案すると、今回の調査結果において量的な増加が見られることは、教育改革の進展を示す一つの確たる証拠と解されるはずである。とはいえ、顕彰の数が教育効果の業績と直結しているか否かはなお検証する必要があり、量的な増加が生じていることのみでは、不十分である。教育の成果や質的保証との関係の検討が課題であろう。
17)単位互換制度等の拡大
この項目への肯定的な回答は、前回より大幅に増加している事実がある。その中で、地方の中規模校は困難度が高いのは、置かれる地理的条件やある程度の独立志向があることが作用していると解される。
ここで、単位制度の不備に関しては上で検討した通りであるから、そのことを想起すると、互換制度は単位制度を前提として成り立つ制度であることに言及せざるを得ない。互換制度は、等質な単位制度の充実を踏まえて展開される度合いが少なくないから、そもそも単位の質保証に格差がある場合は、十分な進展を期待できないであろう。各大学の単位制度が厳格さを増し、大学間の単位制度遂行への等質化が実現することによって各大学間の単位に対する信用が増加するのであり、そのような段階に至るには、まず厳格な成績評価など単位制度の根幹をなす整備が欠かせない。
18)学長のリーダーシップを確立する組織運営体制の整備
この項目への肯定的回答が、前回より大きく進展したことは、大学改革が学長のリーダーシップを期待する方向へ進行している事実と関係が深いはずである。国立大学法人が出現した現在、従来の地位は高いが権限が付与されていない学長職から、地位も権限も付与され、権威が大幅に増した学長職とでは大きな落差があるに違いない。教授会が権限をもつボトムアップ型の管理運営方式から学長が権限をもつトップダウン型の管理運営方式が出現した現在、学長のリーダーシップは当然強化される方向へと踏み出したとみなされる。本調査結果においても、それを支持し、推進するための組織体制は大幅に整備されたことが分かる。
大幅な整備がなされた中で、果たして具体的成果があがっているのか否かは質問してないので不明であるが、今後は、大学毎にその成果の有無がきびしく問われる段階に突入し、中期目標・計画の成否、運営費交付金の成否、社会的評判の成否、等の要因と連動しながら、リーダーシップの成果の有無によって大学の盛衰の差異が具現する方向に向かうに違いないと予想される。
19)自己点検・評価の充実
前回よりも進展している。2004年度から導入された機関別認証評価制度の前提に自己点検評価が当然だとされる時代に移行している現在では、前回より肯定的回答に進展が見られるのは当然の結果であると観察される。機関別認証評価等が義務化された国立大学法人では、その成果をいかに教育研究の質的充実や保証に連携させるかが問われる段階に入っている。あらゆる外部評価や第三者評価の実施には、自己点検・評価の実施が不可欠の前提になっている以上、一層の充実が課題とならざるを得ない。
20)認証評価機関以外の第三者評価システムの導入
前回では、第三者評価システムを導入した国立大学は未だかなり低率(9.1パーセント)であったし、困難とする割合(47.3パーセント)もなお高かった。今回は、さらに機関別認証評価以外の第三者評価の導入を尋ねたが、実施率(19.5パーセント)、困難度(43.7パーセント)ともに、進展がはかばかしくない実態がみられる。その原因は何であろうか。法的に義務化が位置づけられた機関別認証評価への対応だけでも相当の負担となっている中で、その他の第三者評価システムの導入が伸び悩むのはある意味で想定できる結果であろう。最近、大学内部での「評価疲れ」が進行し始めている事実が観察されているが、この伸び悩みの数字はまさしくそうした「評価疲れ」の実情を直截に反映しているのではあるまいか。
今回の調査結果がこのような推論を喚起する側面がある限り、外部評価や第三者評価が義務化し、その前提に膨大な作業や労力を必要とする自己点検・評価が不可欠になっている現在は、大学教員・職員の「評価疲れ」を誘発することなく、しかもなおかつ教育・研究の効果を一層高めることの可能な、第三者評価の形態の開発が問われる時代を迎えつつあると考察できるのではあるまいか。
(16)GPA(Grade Point Average)方式の導入
GPAの導入は確実に進行しているが、量的導入に留まるのではなく、教育の質的保証にいかなる活用のされ方をするかを詮索することが今後の課題であろう。この点は、上で考察したように、日本の戦後大学教育のアキレス腱であったと言っても過言ではあるまい。単位制度の形骸化は、教育の質的保証の根幹に関わる重要問題でありながら、戦後60年間にわたって、殆ど手付かずの状態に放置されてきた。その結果、大学の学士課程教育の質的保証は不十分なままに停滞し、学生の学問への好奇心はもとより、学習力、学力の十分な開発が実現できなかった、と言っても過言ではあるまい。今回の大学改革が教育改革や教育革命と言われる理由は、この根幹に関わる制度の見直し、それと連関した意識や行動の見直しにあることに帰結するとみなされる。
調査結果から、GPAの導入が着実に増加していることは、少なくとも制度的には進展が見られることであるから、評価に値するであろう。ただ、一部の大学が導入して、他の多くの大学が導入していない状況では、単位不足で落第する学生(下記の退学勧奨制度の導入を参照)の受け皿ができないこと、落第する学生の不満が増加すること、導入した大学が受験生にとって不人気になり学生募集に苦戦すること、といった要因が作用し、概して、大学システム全体の教育効果を上げることに帰結しないという問題が生じる可能性が少なくないだろう。したがって、GPAの定着は、個々の大学レベルでも課題であるが、システム全体レベルでの真剣な取組みが必要な課題である。
(17)学生の多様化、学力低下等に対応する支援方策と成果
さまざまな取組みが実施されているが、効果が十分に発揮されるには時間がかかることが推察される。実施率が高いもの(80パーセント以上)は、「就職相談、学生生活・キャリア形成などの支援業務の強化」、「学生の相談にのりやすいような教職員の担任制度の設置」、「高大連携の強化」、「就職説明会や履修相談での卒業生や高年次生の活用」、「学修支援室や学修相談室などの教職員が学生の相談にのるシステムの整備」などである。実施率の低いもの(20パーセント以下)は、「GPA等を利用した成績不良者に対する退学勧奨制度の設置と実施」、「退職した大学教員や高等学校の教員、予備校等との連携した学力不足への対応」などである。「成果あり」(50パーセント以上)は「学修支援室や学修相談室などの教職員が学生の相談にのるシステムの整備」、「優秀な生成をおさめた学生に対する表彰制度や授業料減免制度の設置」、「学生が自主的に企画する教育研究プロジェクトに対する補助金の拠出」などである。
1)高大連携の強化
高大連携の実施率とその成果を肯定的に評価する割合のいずれも大きいことが分かる。大学と外部制度との接続の問題は、ユニバーサル・アクセスが実質化する時代には、避けて通れない問題である。接続には対高校と対社会(職業)が重要である。とりわけ、前者は教養教育との関係が深い側面であることは言うまでもない。大学は歴史的にエリート機関として発展したのであり、例えば、西洋のギムナジウム、リセ、グラマー・スクール等の学校に対して予備門的な性格を付与して発展した。これに対して、大学は大衆機関として発展した側面ももつのであり、初等教育や中等教育の発展に伴い、その延長上に発展した。この二つの系譜が現在の大学では対峙し、葛藤を惹起しているのであり、門戸の開放に前者は否定的であり、後者は肯定的である。
その意味で、高大連携の必要性は、後者の文脈で増していると言えるだろうし、調査結果はその方向を促進していることを明らかに示唆している。それは、大学の大衆化を促進し、教育機会の開放を遂行する方向である。
したがって、大衆化が高大連携を促進し、高大連携が大衆化を促進するという相互連関が機能するはずであるから、今後ユニバーサル・アクセスの進展に伴い、伝統的学生ばかりではなく社会人や留学生などの「ニュー・ステューデント」の増加が見込まれる。それと呼応して、なお増加が見込まれる学習力や学力の多様化した学生へ大学の門戸を開放し、同時に、これら「高校四年生」を対象に大学レベルの水準に学習力や学力を引き上げるための教育が一層必要とならざるを得ない。調査結果は、多くの大学で、その方向へかなり踏み込み始めている事実を示している。
2)リメディアル教育等の初年次教育や入学前教育の充実
高大連携と同様、実施率はかなり高く、効果もかなり大きいとされている。自由記述によって理解できるように、すでに多様な取組みが開花していることが分かる。この事実は、高大連携の拡大と表裏の関係で進行している事実であるから、個々の大学の実情に見合う対応や対策が進行している事実を示唆している。問題は、効果があがっていると回答した大学が増加しつつあるとしても、初年次教育や入学前教育を受けた学生の卒業時での学力が本当に大学水準の到達目標に達し、質的保証が十分達成されたのか否かを確認することである。
この種の問題は、大学の回答が重要であり、すなわち、自己点検・評価に関する自己申告を信用し、尊重することが前提である。その点では今回の調査結果は肯定的な方向を示唆しているとみなされる。しかし同時に第三者評価によって客観的に評価され検証されることが重要であり、その点では、導入された機関別認証評価の結果が一つの目安になるはずであり、導入間もない現時点では成果が十分に検証される段階に至っていないと言えるかもしれない。
3)学修支援室や学修相談室など教職員が学生の相談にのるシステムの整備
実施率と効果の両方共に比率が高い。
4)ピア・エデュケーション・システムの整備
実施率はまだ半分に達していないものの、成果を評価する割合は極めて高いことから、今後の普及が期待される段階にある。
5)退職した大学教員や高等学校の教員、予備校等と連携した学力不足への対応
実施率はいまだ低率であり、効果も必ずしも大きいとは言えない状態にあるが、今後は次第に普及する可能性を秘めている。
6)自学自習を促進するための学内外で利用できるe‐learningシステムの整備
実施率はすでに半数以上に達しており、成果も高く評価されている。
7)就職説明会や履修相談での卒業生や高年次生の活用
実施率も成果も大きいとされる。
8)学生支援センター、就職支援センター、キャリア支援センター等の機関の設置
実施率も成果も大きいとされる。
9)就職相談、学生生活・キャリア形成などの支援業務の強化
実施率も効果も大きいとされる。
10)学生や大学院生の事務的な業務への雇用やボランティアでの活用
実施率は5割弱であったが、その多くは成果を肯定的に評価している。
11)優秀な成績をおさめた学生に対する表彰制度や授業料減免制度の設置
実施率も成果も大きいとされる。
12)飛び級制度の設置
実施率は4割弱であるが、効果は高く評価されている。
13)GPA等を利用した成績不良者に対する退学勧奨制度の設置と実施
実施率は1割未満と低率であり、導入が開始されたばかりの段階を示している。
14)学生が自主的に企画する教育研究プロジェクトに対する補助金の拠出
実施率は4割未満であるが、成果は高いと評価されている。
15)各種資格を取りやすくするための補助金拠出や学内での試験会場提供
実施率は半数を超えており、成果は高いとされる。
16)学生の相談にのりやすいような教職員の担任制度の設置
ほとんどすべての実施母体が担任制度を設けており、成果にも肯定的である。
17)事務職員の教育スタッフとしての力量を高めるための諸方策の充実化
実施率も効果も大きいとされる。
以上、3)から17)までの項目への回答は、概して実施率が次第に伸びる傾向を示していると同時に、実施率の高い項目では成果もかなり高い状態になっているとの回答が多い。このことは、学生の多様化や学力の低下に対しては、各大学が腐心して、種々の対策や対応を具体的に進めている実態が察知できることを意味する。実施率には温度差が見られるものの、取り組めばかなりの効果が上がっているとみなされている以上、さらなる実施が期待される。恐らく、問題点や課題も多々出現していると推察されるので、それらに対するきめ細かな検討とさらなる改善が不可欠の課題になろう。
(18)『我が国の高等教育の将来像』(中教審答申)への対応
1)答申への具体的対応
対応は区々であるが、様々な対応が進行しはじめている。
2)実施上の問題点
困難点が出現しており、例えば次のようなさまざまな指摘があることが分かる。「地方大学と中央の大学の競争力の格差が生じる恐れ」、「全学的統一性の欠如」、「教養教育と専門教育の連携の不十分さ」、「学生の学力低下に対応する補習授業等の教員負担増と研究面での支障」、「運営費交付金の年々減少」、「大学院重点化に伴い教養教育のプロフェッショナルな専門家の欠如する状況」、「大学教育における教養教育の重要性にかんがみ、今後の客観的情勢の悪化が危惧される」。これらの声の多くは、すでに上記の統計的なデータを踏まえて行った考察や分析によって確認された内容と通底している。
中教審の答申は、国立大学法人が今後遂行すべき理念・目的・目標と直接間接に関わる以上、各大学が真剣に改革の方向を模索するのは当然の帰結であり、本調査には実際に具体的な対応が行われるとともに、実施上に実現を阻む条件や課題が多々山積している実情が指摘されていることが了解できる。それらを分析すると、概して組織、資金、理念、カリキュラム編成、人的資源、等の問題に帰着することが理解できるのであり、これらの各側面に対する改革が遂行されなければ、今後の国立大学法人の発展は無きに等しいことを示唆していると言えるだろう。
その意味で、これらの分析を総括し、集約して、国立大学法人が今後取組むべき、最も重要な事柄に関する論点を整理する必要があると考えられるのであり、その点を最後に述べておきたい。
3.教養教育の改善のための論点
以上の考察を踏まえて、いくつかの論点の整理が必要であると考えられるが、特に重要と考えられる5点を以下に指摘したい。すなわち、1.理念の確立―スカラーシップ観の見直し、2.教養教育カリキュラムの体系的編成、3.組織改革―学士課程の教養教育と大学院の専門教育の分化、4.教養教育担当部局と教員組織の明確化、5.教養教育重点強化予算措置、である。要点は、曲がり角に来ている教養教育の抜本的改革の必要性を強調している。
(1)理念の確立―スカラーシップ観の見直し
第1に、教養教育の理念を確立すると同時に教育重視のスカラーシップ観を確立することである。その理由は、次のような論拠に基づいている。
- 大綱化以後の大学改革の焦点は教育改革に置かれたにもかかわらず、裏腹に現在進行しているのは、教育の衰退にほかならない。研究重視は、大綱化以降に教育改革が重視されたにもかかわらず、その実現半ばに反転して、大学院重点化・部局化、研究予算の偏重、教員の研究志向、等々の現象の顕在化によって確認できるはずである。1991年からの改革は確かに教育改革に重点を置いたにもかかわらず、現実的には1996年に導入された「科学技術基本計画」を契機に、21世紀COEプログラム政策を含め、従来の研究偏重へと高等教育政策・計画の反動が生じたのである。国立大学法人の中の「研究大学」を中心に、しかも自然系の領域を中心に、教育よりも研究への振り子の揺り戻しが顕著になった。
- 教育と研究の統合を組織的に志向してきた伝統的な学部は、大学院重点化・部局化によって実質的に解体する過程を辿った半面、大学院での研究偏重に重点が移行した結果、学士課程教育は次第に無視され、看過される度合いを高めることになったことは否めない。大学院が重点を置く専門教育や研究の基礎や人材供給源として学士課程教育が手段的な役割を付与される傾向が次第に生じることになり始めた。本調査に具現した教養教育の衰退の兆候はこうした現象の象徴的な位置を占めると解される。
- 実際、今回の調査においては、全学の教養教育に関するコンセンサスが弱体化し、改革の主体であり推進力であるべき教員の意識の改革そのものがきわめて低調になっていると解される。そればかりか、いわゆる「全学出動体制」が崩壊し、一部の教養教育担当教員に教養教育の担当を押しつける傍ら、多くの教員には専門教育や研究への偏重傾向が読みとれ、大学共同体にひび割れ現象が進行していると読みとれるのは、理念の欠如に起因する大学内部の組織や風土の現状を如実に反映している証拠である。
こうした現状の中で、学士課程の理念・目的が曖昧となり、規範が崩壊し、無規範状態としてのアノミーが拡大したのに加え、教養教育と専門教育の統合、連携、融合の名の下に、教養教育の固有性や自己像が希薄になっていると解される。理念喪失は、教員の理念・目的の内面化を阻害し、意識の改革を停滞させ、理念を共有するコンセンサスの崩壊をもたらす「アノミア=心理的アノミー」が蔓延することになった。 - かかる現状を直視し、速やかに打開するには、教育の重要性、とりわけ教養教育の重要性を規範的に制度化する営みが欠かせないはずである。研究と教育が分断されるのではなく、スカラーシップ観=学識観として規範的に統合されることが追求されなければならない。アーネスト・ボイヤーが提唱した、研究、応用、統合、教育から構成されるスカラーシップ観では、教育を研究より上位に置いたスカラーシップ像の追求を提唱している。これは、研究優位の学識観が跋扈している現状では、ひとつの現実的かつ説得的な方法であるに違いないと考えられる。
それと同時に、組織的には、学士課程(学部)と大学院に教育と研究が分化する傾向を強める背景がある現在、新しいスカラーシップ観によって両者に架橋し、教育と研究が分化し断片化するのを回避し、それらを有機的に統合することが欠かせない課題である。学士課程でも大学院でも研究と専門教育のパラダイムが支配的になり、教養教育を学士課程に根付かせるという本来の教育改革の精神は実現されるどころか、次第に看過される方向へ動いている現在、この有機的統合を模索する方向での改革が欠かせない。
こうして、1、2、3、4を通して考察したように、今回の調査を基に現状の診断を行うならば、規範が統合力を喪失しているばかりか、教養教育に関わる組織が機能化し、分裂し、断片化している以上、教養教育を学士課程に位置づけ、専門教育は大学院へ移行させる措置を明確にした、規範の確立が重要である。併せて、教育は学士課程、研究は大学院へ主たる足場を構築する改革が重要である。そのことによって、研究と教育の葛藤を深めるのではなく、両者が有機的に統合されて追求される体制を確立することが課題である。その結果、研究と教育が理念的にも組織的にも統合され、教養教育が確固とした地位を付与されることが、日本の大学、とりわけ国立大学法人に現在求められる最も重要な改革の方向であり措置であると言わなければならない。
(2)教養教育カリキュラムの体系的編成
第2に、教養教育カリキュラムの体系的編成の必要性である。次のような諸点から、その必要性が生じていると考えられる。
- 教養教育の目的は、古くはパイディア=人間教育を原型に発展し、現在では「謙虚さ、人間性、柔軟性、批判精神、広い視野、倫理的・道徳的問題の解決」といった資質の涵養を標榜している。現実の科目では、教養ある人材養成、専門的能力をもった人材養成、環境など人類的環境への関心・知識、人権・平和などの価値観、世界各国の文化への理解、学生の社会性、等の内容を構成している。これらの教養科目が現実に体系的に編成されているか否かを詮索すると、必ずしもそうとは言えない状況を呈しており、「教養学」や「総合科学」といった専門分野の確立が困難な問題を孕むと同時に、教養カリキュラムの原理や編成に関しても相応の困難を孕んだまま、カリキュラムの体系性が十分確立しているとは言えないという状態に陥っている。そこには、コア・カリキュラム、主専攻、副専攻、コンセントレーション等のカリキュラム編成の根幹も十分に整備されているとは言えない実情が窺われるのである。
- 教養教育の理念や内容に関する学内的コンセンサスが混迷を極めている現実があるのは、各学部(あるいは研究科)の専門分野主義によって教養教育のカリキュラムに対する理解の温度差が横たわる事実を如実に裏書きしている。今回の調査では、前回以上に、教養教育と専門教育の有機的連携は達成されていない事実が判明しており、カリキュラムの体系化は一層の困難に直面している。カリキュラム編成の体系性に問題が生じていることと教養部の解体に伴う理念のアノミー化、さらには組織の脈絡を欠如した機能化とは密接な連関性がある。一般教育の専門分野の構築をめざす一般教育学会が大学教育学会へと変容して、カリキュラム研究に機能化が生じていることは、教養教育と専門教育の角逐がカリキュラム編成へ投影した結果、教養教育の体系的な構築が困難になっている現実と無関係ではあるまい。
カリキュラム編成の体系性の問題は、教養教育という専門分野の確立の問題と関係が深く、教養教育の学問的な研究の未発達性と関係が深いと考えられる。その証拠に、日本には高等教育のカリキュラム開発、とりわけ教養教育のカリキュラム開発の専門家がほとんど見当たらない現実があると言っても過言ではあるまい。当然、各大学にも専門家を欠如する現実がある。学内に専門家が不在なのに、教養教育のカリキュラム改革だけは進行している事実があり、その意味から、果たして十分なカリキュラム改革が行われているのかは疑問なしとしないのである。 - 今回の調査では、初年次教育、リメディアル教育、高大連携、入学前教育、キャリア教育、といった新たなカリキュラム編成が活発に展開されている事実が明確になった。高等教育の大衆化やユニバーサル・アクセス化が本格化する現在は、こうした新たなカリキュラムを学士課程に導入しなければ、多様化する学生の教育や学習に対応することは不可能になっている実情にかんがみ、こうした対応は当然の帰結とみなされる。それと同時に、グローバル化や知識基盤社会の到来は、一般教育の学的な遺産を吟味しつつ、教養教育の学的な新たな編成原理の検討を要請し、総合的・学際的・学融的なカリキュラム体系の確立を視界に入れた「知の再構築」が課題となる。教養教育が学士課程に確立されるべきだと考えるならば、これらの状況に対応したカリキュラム原理と編成の課題はますます重要性を高めるに違いないと同時に、教養教育カリキュラムの原理と編成の体系化の問題は一段と重要性を増す。
以上の1、2、3の現実を直視すると、現在の「ポスト一般教育」時代の教養教育の混迷はカリキュラム編成が次第に機能化し、多様化している半面、教養教育が断片化し、脈絡を欠如し、漂流し、教養教育というディシプリンの名に値する規範、凝集力、整合性、体系性を見失っている事実が明確になるのである。もし、現在の教養教育の後退を見極め、再生を期すのならば、学会等の英知を集め、国立大学法人の総力を結集して、再生する試みが不可欠である。
(3)組織改革―学士課程の教養教育と大学院の専門教育の分化
第3は、組織の改革を断行して、教養教育は学士課程で行い、専門教育は大学院へ移行させ、棲み分けすることである。なぜこのような抜本的な改革が必要であると考えるかは、次のような背景、経緯、理由が前提になっている。
- 大学審議会や中央教育審議会の答申は、教養教育と専門教育の統合によって、学士課程が「リベラル・アーツ教育」の拠点として発展することを構想したにもかかわらず、現実はむしろ教養教育の形骸化、空洞化、風化を招くに至った。1991年の大綱化政策以来、教養部解体が生じ、「一般教育」は瞬く間に「教養教育」へと変貌した。長年蓄積されてきた一般教育の遺産が継承されたか否か検討を要する課題である。変貌の原因は、専門学部への分属や大学院重点化への参画など、大学における研究主義や専門主義的な動きに対応した動きがかなりの比重を占めるに違いない。
他の箇所で検討したように、一般教育の縛りが希薄化したのに加え、教養教育が専門学部制支配のもとに研究主義や専門主義の浸透作用の中で形骸化・空洞化・風化を辿る方向へと展開した。規範の崩壊ばかりではなく、組織的には従来の拠点である教養部に代わるさまざまな代替機関へと機能化、多様化、複雑化する方向を辿ることになった。前回の調査結果には、機能化によって教養教育が復権すること、少なくとも衰退へ歯止めがかかることへの少なからぬ期待がまだしも残滓的に反映されていたが、今回の調査では機能化は一段と足早に展開されるに至ったばかりか、その方向を敷衍した場合、教養教育の凝集力は加速的に喪失を余儀なくされるに至ると予測される段階に到達した。 - この事実を踏まえて、学士課程において教養教育の組織的拠点としての実施責任部局がなし崩し的に後退する方向に向かうことはもはや回避できない。現在のような機能化による多様化や複雑化の進行は、皮相的には教養教育が活況を呈しているかに見えながらも、実際には組織的な崩壊の過渡期現象にほかならないとみなされるからである。その証拠に、前回の調査と比較して、崩壊過程は組織、担当教員、非常勤教員、単位数、カリキュラム編成、予算など全項目を通して進行する事実が確認できたのである。この憂慮すべき現状に対して遅ればせながら歯止めをかけ、再生への改革を断行することは可能なのであろうか。
- 日本の高等教育を代表すると自負する国立大学法人はこの教養教育崩壊過程という事態を招来したことに対して責任の自覚が要請されるに違いない。国立大学(法人)は、日本の高等教育において過去から現在にかけて「エリート」的機関として主導性を発揮して来たのであり、今後もその役割が期待される以上、現状を糊塗するのではなく、教養教育の再建に向けて、確固たる展望を示す責務と説明責任があるはずである。換言すれば、人材輩出による社会的貢献の観点に照らして、教養教育の重要性を再認識するとともに、その形骸化、空洞化、風化に対しては率先して歯止めをかける責任があるはずである。それを欠如すれば、後遺症が社会へと次第に波及し、遠からず社会発展の衰退を招く畏れが多分にあると予測される。
21世紀には、高等教育はユニバーサル・アクセスの時代を迎え、国民の大半が大学教育を受けること、日本の若年人口が総合特殊出生率1.25の事実にみるごとく急速に低下していること、等を勘案すると大学教育は実質的に義務教育に近似し、市民教育の場になること、少数の青年を対象とした質の高い教育が不可欠であること、は明らである。すべての大学、とりわけ国立大学法人は、広く国民の豊かな教養、識見、市民性を涵養することから回避できないのであり、その回避は国家社会の存亡を左右するほどの影響をもたらすと危惧されるのである。
しかしながら、今回の調査結果に依拠する限り、その危惧を払拭する明示的な証拠は何ひとつ得られなかった、と言わなければなるまい。すなわち、現実には、国立大学法人の4分の1は教養教育を重視していないばかりか、中教審の提言した「総合的なリベラル・アーツ教育」を標榜する大学は皆無であり、現在も今後も専門教育や研究への志向性が強い反面、教養教育や教育への志向性は極端に弱いという、瞠目すべき事実が得られたのである。
1、2、3において述べたように、かかる背景、経緯、現実を勘案すると、教養教育を学士課程の4年間に担保するには、今や国家社会の英知を結集した決断が必要なのではあるまいか。別言すれば、明確に教養教育の存在を脅かしている専門教育は組織的に学士課程から大学院へ移行させることを要請せざるを得ない。それは教養教育と専門教育に固有の拠点を付与し、棲み分け、それを足場に両者のそれぞれの固有性と充実性を期すこと、さらには後述する教育と研究に固有の拠点を確保すること、等が具現する現実的な方法であると考えられる。
(4)教養教育担当部局と教員組織の明確化
第4に、教養部に代わる教養教育責任担当部局を明確にすること、そのためには教員組織の性格を明確にすることである。それは次の理由に依拠している。
- 国立大学法人の多くの大学は、講座制と学科目制の教員組織によって運営されてきた。最近の中教審の答申(平成17年)は、講座制を学科目制に移行させることを提言しているので、従来の小講座制は今後次第に大講座や学科目制に切り替えられるものと予想される。講座制は学問、あるいはディシプリン=専門分野の確立と継承にとって効果を発揮する制度である。もとより臨床講座、実験講座、非実験講座等によって相違があるものの、一般的には1人の講座主任とそれを支える1人または複数の助教授、1人または複数の助手によって構成されている。こうした講座を基礎に学部(教育、文学、理学、工学、医学など)が構成されてきた。
これに対して学科目制は、小講座が独立に並立するのではなく、専門分野が集合する制度であるから、一つの専門分野の確立と継承に責任を担う側面は希薄である。専門分野を担当する教員ポストが空席になった場合、その専門分野を踏襲するよりも、他の新しい専門分野によって代替されるため、新しい学問が発展するのには効果を発揮するが、専門分野のスクラップ・アンド・ビルドや新陳代謝を加速する。 - 教養部は講座制に準じる構造が機能した関係上、一般教育の実施に対しては学問的にも組織的にも責任部局の役割を果たした。教養部の解体の進行は、各学部分属、センター方式、全学委員会方式、新学部設置方式、大学院重点化方式、等々の出現を招いた。
このうち、各学部分属方式の場合は、教養科目の縛りが弛緩する帰結をもたらした。各学部の伝統的な専門学部制が支配する中へ、教養部という準学部の枠組みを外れた教養教育が位置づく場所はないに等しい。しかも教養科目の空席を踏襲する人事よりも、新たな科目を新設する方向へ傾斜するから、教養科目は他の専門科目へ吸収され、教養教育の拠点性は崩壊を加速せざるを得ない。他方、各学部の専門分野は学部枠を超えた教養教育の成立には消極的かつ否定的であるから、教養教育への参加率が低くなるのは当然であろう。そのことは先行研究によって実証されているところである。
かくして、教養部の解体は、教養部教員が他の組織に分散して教養教育を担当する方向を強めた半面、他の専門分野からの応援は全学出動体制の拘束力の強い大学ではともかく、多くの大学では増強される方向を辿らなかった。 - センター方式、全学委員会方式などの場合も、講座を基軸にした専門学部の性格を付与されないので、専門学部に比較して低い地位や威信を付与されがちであり、そこに所属する教養教育の運命は分属方式と大同小異である。他方、教養部の形態を踏襲している総合科学部や教養学部方式は辛うじて、一般教育の学問的、組織的拠点性を残しながら、例えば教養教育科目40単位の80パーセント程度を担当している。しかしこの種の旧教養部に匹敵する組織は今回の調査では全国の国立大学法人の中では、極めて少ない事例であることが判明した。教養教育を自認する以上、「教養学」や「総合科学」のような専門分野を確立し継承する母体が存在しなければ、教養教育の凝集力や活力が減退するのは当然の成り行きであると推察されるにもかかわらず、もはやそれは例外的な現象と化している。現在の状態は、学問的にも組織的にも、そのような危機的状態が露呈しているなにものでもない。
- 上記のように今後は講座制よりも学科目制への移行が進展する以上、学問の形成や継承と関わる組織的拘束力は希薄になると見込まれるであろうし、講座制が保持したような凝集力は自壊するはずであるから、教養教育の凝集力の喪失には拍車がかかるであろう。もちろん、他の専門学部の専門分野も講座制が崩れる結果、専門学部主義が崩れ、専門分野の拠点が希薄となり、一般教育が辿ったような軌跡を歩む可能性がないのではない。学問の再編成は、新たな拠点制や枠組みを求めて、専門主義を超えた総合性・学際性・学融性を志向する方向へ向かうだろう。
そのことは、従来の研究と教育を講座の中で、あるいはその集合体の専門学部の中で統合する方式が曖昧になり、効力を喪失する過程にほかならない。そのような現実の中で、教養教育が「知の再構築」によって再生する可能性はないことはないが、拠点性や専門性と固有の方法論を見失っている現状を踏まえると、かなり困難であるのではあるまいか。
こうして、1、2、3、4のような現実を改革するには、教育と研究を学部のなかで統合することが困難になっている、現在の曖昧模糊とした体制を長らえるのではなく、思い切って教育組織と研究組織を分離して、アメリカの大学で発展した「学科制」の研究組織あるいは学問的組織に教員が分属し、そこから全員が教育組織(学士課程と大学院の両方)へと出向して教養教育と専門教育をそれぞれ担当する方式へと改革する必要があろう。教養教育担当への出向は全学出動方式であることは言うまでもない。
(5)教養教育重点強化のための予算措置の必要性
第5に、後退しつつある教養教育を梃子入れし、強化するためには特別の予算措置が必要という点である。その理由は、次の通りである。
- 教育の再建に際しては、上で言及したように、理念構築や組織改革に関わる側面の改革が不可欠の課題であると同時に、その実現には、文部科学省、行政、大学執行部、大学教員などの関係者を挙げて取組むことが必要である。それに加えて、教育へ十分な予算や資金を投入することが欠かせない課題である。
- 今回の調査で明確になった事実の一つは、国立大学法人の学長や副学長が運営費交付金を含め大学予算の抑制、削減、縮小がこれから将来にわたって必至となっていると危惧していることである。そのことによって、大学運営にかかる諸経費を削減することが予想されていると推察されるとともに、重要性が乏しいと判断される領域へは削減の矛先が向けられる可能性が高いとの空気が支配的となりつつある実態が観察されたと言えるだろう。
このことは、調査結果にも現れているように、すでに結果的に常勤教員、非常勤教員の削減、予算の削減が進行している教養教育そのものへと帰結することが予想される。 - 物的資源に乏しい日本の将来は、科学技術立国と人的資源の開発以外に特に重要な手だては見出されないと考えれば、豊かな人材開発と育成を標榜している教養教育の重要性は明白である。専門教育が重要であることはもちろんであるが、現状はその偏重のあまり、教養教育と専門教育の有機的連携が阻害され、ひいては教養教育が形骸化し、等閑視される傾向が助長されていることが判明した以上、それに歯止めをかけ、教養教育の再生に着手することが、将来の社会発展を導く源泉になることは論を待たないであろう。
かくして、1、2、3に考察した現実を勘案するならば、国立大学法人は日本の人材養成の根幹を形成する責任ある機関であること、かかる人材開発には教養教育が重要な役割を果たすこと、を重視する視点が欠かせないと考えられる。したがって、人材養成の重点施策として、政府、文部科学省、大学のすべてが連携することによって、教養教育重点強化のための予算措置の必要性を強調したい。
参考文献
- アーネスト・ボイヤー著(有本章訳)
- 『大学教授職の使命―スカラーシップ再考』玉川大学出版部、1996年
- 天野郁夫『高等教育の日本的構造』玉川大学出版部、1986年
- 有本章編著『大学のカリキュラム改革』玉川大学出版部、2003年
- 有本章「学士課程教育改革の現在」有本章・山本眞一編著『大学改革の現在』東信堂、2003年
- 一般教育学会編『大学教育研究の課題』玉川大学出版部、1997年
- 絹川正吉・舘昭編著『学士課程教育の改革』東信堂、2004年
- 倉敷芸術科学大学教養学部「大学の教養教育に関する実態調査」委員会『大学の教養教育に関する実態調査』報告書(大学教育学会委嘱調査)1999年
- 厚生労働省職業安定局(※厚生労働省職業安定局ウェブサイトへリンク)
- 関正夫「大学カリキュラム改革に関する回顧と展望―学士課程教育を中心として―」『大学論集』第36号、31~67頁、2006年
- 文教協会『全国大学一覧』2005年
- 吉田文「国立大学を分類する‐地域交流の視点から‐」『IDE‐現代の高等教育』No.431、54~60頁、2001年
教育・研究委員会および教養教育実態調査に係るワーキンググループ委員名簿
教育・研究委員会
| 委員長 | 平野 眞一 | 名古屋大学長 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 平山 健一 | 岩手大学長 |
| 副委員長 | 岩崎 洋一 | 筑波大学長 |
| 委員 | 鈴木 直義 | 帯広畜産大学長 |
| 委員 | 三浦 亮 | 秋田大学長 |
| 委員 | 益田 隆司 | 電気通信大学長 |
| 委員 | 吉村 融 | 政策研究大学院大学長 |
| 委員 | 菊池 龍三郎 | 茨城大学長 |
| 委員 | 飯田 嘉宏 | 横浜国立大学長 |
| 委員 | 寺尾 俊彦 | 浜松医科大学長 |
| 委員 | 成瀬 龍夫 | 滋賀大学長 |
| 委員 | 柳澤 保徳 | 奈良教育大学長 |
| 委員 | 一井 眞比古 | 香川大学長 |
| 委員 | 下村 輝夫 | 九州工業大学長 |
| 委員 | 住吉 昭信 | 宮崎大学長 |
教育・研究委員会教養教育実態調査に係るワーキンググループ委員(五十音順)
活動期間:平成17年10月~平成18年7月
| 座長 | 丸本 卓哉 | 山口大学長 |
|---|---|---|
| 委員 | 有本 章 | 広島大学高等教育研究開発センター教授(監修及び第2部執筆) |
| 委員 | 伊豆蔵 好美 | 奈良教育大学教育学部助教授(第1部2(15)~(18)執筆) |
| 委員 | 沖 裕貴 | 前山口大学大学教育センター教授 立命館大学大学教育開発・支援センター教授(第1部1(1)~(7)執筆) |
| 委員 | 高橋 信夫 | 北見工業大学機能材料工学科教授(監修) |
| 委員 | 夏目 達也 | 名古屋大学高等教育研究センター教授(第1部2(12)~(14)執筆) |
| 委員 | 吉田 香奈 | 山口大学大学教育センター講師(第1部1(8)~(11)執筆) |
お問合せ先
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室