ここからサイトの主なメニューです
 |
大学教員のファカルティディベロップメントについて
| ○ |
ファカルティ・ディベロップメント |
| |
| … |
教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称。その意味するところは極めて広範にわたるが、具体的な例としては、教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催、新任教員のための研修会の開催などを挙げることができる。 |
|
| ○ |
ファカルティ・ディベロップメントに関する主な法令上の規定 |
| |
「21世紀の大学像と今後の改革方策について」(平成10年10月26日大学審議会答申)を受けて、平成11年9月14日より大学設置基準において努力義務を規定。更に、「新時代の大学院教育−国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて−」(平成17年9月5日中央教育審議会答申)を受けて、大学院設置基準において義務化(平成19年4月1日より施行)。
|
| |
【大学設置基準】(昭和31年10月22日文部省令第28号)<抄>
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
| 第25条の2 |
大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究の実施に努めなければならない。 |
【大学院設置基準】(昭和49年6月20日文部省令第28号)<抄>
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
| 第14条の3 |
大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 |
|
| ○ |
ファカルティ・ディベロップメントの実施状況の推移 |
| |
| 平成12年度: 341大学(約52パーセント)から平成16年度: 534大学(約75パーセント) |
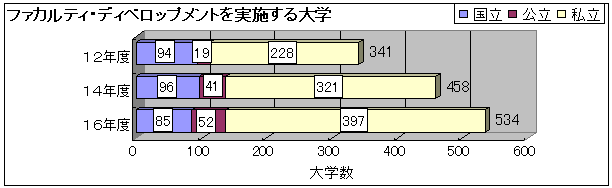
| 調査対象: |
全ての国公私立大学(短期大学を除く。放送大学は私立大学に含む。)
平成16年度の調査対象大学数は709校(国立87校、公立77校、私立545校) |
|
○ファカルティ・ディベロップメントの内容
| ・ |
学部もしくは研究科でファカルティ・ディベロップメントを実施した大学 |
| |
国立 |
公立 |
私立 |
計 |
| a.実施している |
85大学
(97.7パーセント) |
52大学
(67.5パーセント) |
397大学
(72.8パーセント) |
534大学
(75.3パーセント) |
| ・ |
ファカルティ・ディベロップメントを実施した学部 |
| |
国立 |
公立 |
私立 |
計 |
| a.学部 |
304学部
(85.6パーセント) |
90学部
(56.6パーセント) |
909学部
(69.4パーセント) |
1,303学部
(71.5パーセント) |
| ・ |
学部もしくは研究科でファカルティ・ディベロップメントを実施している大学 |
| |
国立 |
公立 |
私立 |
計 |
| a.新任教員のための研修会 |
53大学
(60.9パーセント) |
14大学
(18.2パーセント) |
157大学
(28.8パーセント) |
224大学
(31.6パーセント) |
| b.新任教員研修以外の教員のための研修会 |
56大学
(64.4パーセント) |
21大学
(27.3パーセント) |
180大学
(33.0パーセント) |
257大学
(36.2パーセント) |
| c.教員相互の授業参観 |
50大学
(57.5パーセント) |
9大学
(11.7パーセント) |
135大学
(24.8パーセント) |
194大学
(27.4パーセント) |
| d.教員相互による授業評価 |
31大学
(35.6パーセント) |
7大学
(9.1パーセント) |
61大学
(11.2パーセント) |
99大学
(14.0パーセント) |
| e.教育方法改善のための講演会の開催 |
63大学
(72.4パーセント) |
33大学
(42.9パーセント) |
212大学
(38.9パーセント) |
308大学
(43.4パーセント) |
| f.教育方法改善のための授業検討会の開催 |
54大学
(62.1パーセント) |
20大学
(26.0パーセント) |
171大学
(31.4パーセント) |
245大学
(34.6パーセント) |
| g.授業方法改善のためのセンター等の設置 |
35大学
(40.2パーセント) |
7大学
(9.1パーセント) |
92大学
(16.9パーセント) |
134大学
(18.9パーセント) |
| h.g以外の学内組織等を設けている |
44大学
(50.6パーセント) |
21大学
(27.3パーセント) |
161大学
(29.5パーセント) |
226大学
(31.9パーセント) |
| ・ |
学部におけるファカルティ・ディベロップメントの内容 |
| |
国立 |
公立 |
私立 |
計 |
| a.新任教員のための研修会 |
145学部
(40.8パーセント) |
19学部
(11.9パーセント) |
341学部
(26.1パーセント) |
505学部
(27.7パーセント) |
| b.新任教員研修以外の教員のための研修会 |
149学部
(42.0パーセント) |
29学部
(18.2パーセント) |
297学部
(22.7パーセント) |
475学部
(26.1パーセント) |
| c.教員相互の授業参観 |
93学部
(26.2パーセント) |
13学部
(8.2パーセント) |
286学部
(21.8パーセント) |
392学部
(21.5パーセント) |
| d.教員相互による授業評価 |
51学部
(14.4パーセント) |
10学部
(6.3パーセント) |
102学部
(7.8パーセント) |
163学部
(8.9パーセント) |
| e.教育方法改善のための講演会の開催 |
179学部
(50.4パーセント) |
48学部
(30.2パーセント) |
454学部
(34.7パーセント) |
681学部
(37.4パーセント) |
| f.教育方法改善のための授業検討会の開催 |
133学部
(37.5パーセント) |
26学部
(16.4パーセント) |
292学部
(22.3パーセント) |
451学部
(24.7パーセント) |
| g.授業方法改善のためのセンター等の設置 |
116学部
(32.7パーセント) |
10学部
(6.3パーセント) |
244学部
(18.6パーセント) |
370学部
(20.3パーセント) |
| h.g以外の学内組織等を設けている |
96学部
(27.0パーセント) |
28学部
(17.6パーセント) |
324学部
(24.8パーセント) |
448学部
(24.6パーセント) |
FD(ファカルティ・ディベロップメント)・大学教員の養成に関するこれまでの大学審議会答申等の主な提言について
| ◇ |
21世紀の大学像と今後の改革方策について(答申)(平成10年10月26日 大学審) |
|
| |
○ |
各大学は,個々の教員の教育内容・方法の改善のため,全学的にあるいは学部・学科全体で,それぞれの大学等の理念・目標や教育内容・方法についての組織的な研究・研修(ファカルティ・ディベロップメント)の実施に努めるものとする旨を大学設置基準において明確にすることが必要。 |
| |
○ |
教育方法の改善に当たっては,マルチメディアの効果的な活用にも十分配慮が必要。ビデオを活用した授業参観によるファカルティ・ディベロップメントなど,各大学における積極的な取組の推進が望まれる。 |
| ◇ |
新時代の大学院教育−国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて−(答申)(平成17年9月5日 中教審) |
|
| |
○ |
今後の大学院教育の組織的展開が有効に機能するためには,体系的な教育課程とともにそれを支える教員の教育・研究指導能力の向上が重要な課題となる。このため,個々の教員の教育・研究指導能力向上とそのための組織的な研修体制の充実や学生に対する成績評価の管理,さらには,教員の教育研究活動を適切に評価する仕組みが一体となって機能することが必要である。また,授業内容を公開するなど,教育・研究指導の内容を同一学科内の教員が評価できる仕組み(いわゆるピアレビュー)を導入することも効果的である。 |
| ○ |
研究者等の養成の場合と同様の要素に加え,これまで脆(ぜい)弱であった教育を担う者としての自覚や意識の涵養と学生に対する教育方法等の在り方を学ぶ教育を提供することが求められる。このため,例えば,ティーチングアシスタント(TA)等の活動を通じて,授業の実施方法や教材等の作成に関する教育などを実施することが考えられる。 |
| ○ |
各大学院における教育課程の編成,実践等に当たっては,関係する教員が課程の目的,教育課程等について共通理解を深めるとともに,教員の教育・研究指導能力の一層の向上を図る取組があいまって初めて効果的に機能するものである。このような教育の課程の組織的展開の重要性にかんがみ,それぞれの大学院教育の現場における教育研究の特色,創造性等が阻害されることのないよう留意しつつ,各大学院における課程の目的,教育内容・方法についての組織的な研究・研修(ファカルティ・ディベロップメント(FD))を実施することが必要である。これを踏まえ,各大学において授業及び研究指導の内容等の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする旨の規定を大学院設置基準に置くことが適当である。 |
| ○ |
教員の教育・研究指導能力の向上には,FDの実施や成績評価基準等の明示等とともに,自らの教育研究活動についての評価を行うことによって,その実効性を担保し,更なる改善のための材料とすることが重要である。
各大学院においては,自主的・自律的な検討に基づき,教育活動に関する評価の積極的な導入を図るとともに,人事・採用面における処遇等にも活用・反映していくことが期待される。また,個々の教員の活動は,各大学院における教員の組織的な役割分担や学問分野,時期等によって多様であることを踏まえ,「教育」か「研究」かといった単純な区分ではなく,各大学院における自主的な調査研究に基づき,個々の教員の多様な活動状況を考慮した形で,活動評価を行っていく方法も有効であると考えられる。 |
|
 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology