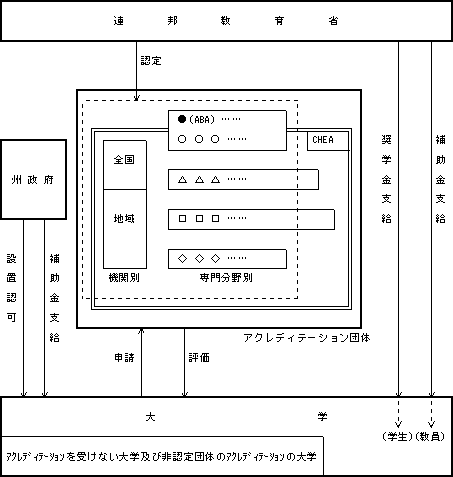|
アメリカにおける大学のアクレディテーションについて
| 【概要】 |
| ○ |
連邦教育省のアクレディテーション関係に係る主な関与は次のとおり |
| |
| ・ |
アクレディテーション団体の認定(認定期間は5年以内)
<アメリカ法典(US Code)> |
| ・ |
連邦教育省認定のアクレディテーション団体からアクレディットされた大学に学生奨学金や教員の研究費等の補助金を支給(あるいはアクレディットされた大学の学生又は教員に直接支給)<アメリカ法典(US Code)> |
| ・ |
アクレディテーション団体の認定基準の策定(連邦教育省規則) |
|
| ○ |
州政府は、大学の設置認可や補助金支給等に関して、アクレディテーションの有無を適宜活用 |
| |
| <例> |
| ・ |
認可の更新制を採用している州において、機関アクレディテーションを受けた大学は審査免除 |
| ・ |
州政府独自の補助金(教員の研究費等)を支給 |
|
|
| ○ |
アクレディテーション団体について |
| |
| ・ |
大別して2種類
機関別アクレディテーション団体(地域団体6、全国団体7)
専門分野別アクレディテーション団体(連邦教育省認定は48分野49団体) |
| ・ |
評価基準は各アクレディテーション団体が独自に設定 |
| ・ |
概ね5〜10年周期で定期的にアクレディテーションを実施 |
| ・ |
アクレディテーションの結果について当該大学はアクレディテーション団体に異議申立てが可能 |
|
| |
【評価(地域別アクレディテーション)の状況】 |
| |
| アクレディテーション団体 |
認定対象校数 校) 校) |
条件附き認定 件) 件) |
認定取消 件) 件) |
| 取消猶予 |
警告 |
理由提示請求 |
| 中央諸州 |
490 |
1 |
2 |
1 |
0 |
| ニューイングランド |
209 |
0 |
- |
6 |
0 |
| 北中部地区 |
976 |
9 |
- |
- |
2 |
| 北西部地区 |
152 |
5 |
9 |
0 |
0 |
| 南部地区 |
783 |
18 |
50 |
- |
2 |
| 西部地区 |
4年制 |
148 |
4 |
秘 |
2 |
1 |
| 2年制 |
138 |
6 |
12 |
2 |
0 |
| 計 |
2,896 |
43 |
 73) 73) |
11 |
5 |
| ※1 |
1997年〜2000年の状況。なお、同一校に対する複数の措置はダブルカウント。 |
| ※2 |
認定を取り消された5大学は、その後間もなく閉校している。 |
| ※3 |
大学評価・学位授与機構森 利枝助教授調べ |
|
| <アメリカ> |
| 連邦教育長官諮問委員会がアクレディテーションの再編に関する検討 |
連邦教育長官の諮問委員会が,2006年3月と5月の2回にわたり,高等教育機関相互による教育・研究の質保証制度であるアクレディテーションの再編を提案するイシューペーパーを連邦教育省の同委員会関連ページに掲載し,関係者の間で大きな関心を呼んでいる。同委員会の関係者から提出されたイシューペーパーは,現在地域別に実施されている機関アクレディテーションの廃止,単一の全国団体による統一的な保証制度の導入など,現行の仕組みの大胆な再編を提案している。イシューペーパーは検討材料のひとつと見なされており,そうした提案も視野に入れた検討を踏まえ,最終報告が2006年8月1日までに連邦教育長官に提出されることになっている。
|
| 連邦教育長官諮問委員会 |
「高等教育の将来に関する連邦教育長官諮問委員会」(以下,「委員会」)[注1]は,10〜20年先の高等教育の将来像を描くことを目的として連邦法に基づき設置された連邦教育長官の諮問機関である。高等教育への進学(accessibility),教育費負担(affordability),教育や研究の成果に関する説明責任(accountability),高等教育の質(Quality)などを論点とし,2005年10月〜2006年5月にかけて,全米各地で「国民的対話(National Dialogue)」と称する会議(討議5回,公聴会2回)において,連邦教育省や国防総省,労働省,商務省の関係者も出席して,検討を重ねた。
|
| イシューペーパーの内容 |
アクレディテーションは説明責任や質に関する具体的な重要テーマの一つとされたものである。3月に公表されたイシューペーパー [注2]は,大学同士で教育・研究の質を保証し合うことを基礎とし,費用・作業負担を認定される側である大学に負っているというアクレディテーションの構造を確認した上で,教育の成果に対する責任や情報公開,遠隔教育の普及など今日的な課題に現在の制度が適合していないことを問題点として指摘する。そして,こうした状況を改善するため,地域別,団体別に実施されている現行制度に代えて,官民共同運営の「全米高等教育アクレディテーション機構(The National Accreditation Foundation)」を中心とする統一的な制度の導入を提案している。また,5月に公表されたイシューペーパー [注2]は,大学同士で教育・研究の質を保証し合うことを基礎とし,費用・作業負担を認定される側である大学に負っているというアクレディテーションの構造を確認した上で,教育の成果に対する責任や情報公開,遠隔教育の普及など今日的な課題に現在の制度が適合していないことを問題点として指摘する。そして,こうした状況を改善するため,地域別,団体別に実施されている現行制度に代えて,官民共同運営の「全米高等教育アクレディテーション機構(The National Accreditation Foundation)」を中心とする統一的な制度の導入を提案している。また,5月に公表されたイシューペーパー [注2]も,激化する国際競争,高等教育機関のアカウンタビリティ,情報の透明性,高等教育の構造の変化などが,アカウンタビリティの仕組みの変化を要請しているとし,アウトプットに視点を置いた全国的な評価枠組みの創出,多様な高等教育関係者を含めた制度の管理運営体制の確立,学生の学習成果を測定する期待水準の開発などを提案している。 [注2]も,激化する国際競争,高等教育機関のアカウンタビリティ,情報の透明性,高等教育の構造の変化などが,アカウンタビリティの仕組みの変化を要請しているとし,アウトプットに視点を置いた全国的な評価枠組みの創出,多様な高等教育関係者を含めた制度の管理運営体制の確立,学生の学習成果を測定する期待水準の開発などを提案している。
|
| イシューペーパーの位置づけと反応 |
「委員会」では,2006年8月1日までに連邦教育長官に最終報告書を提出することとなっている。「委員会」の議長は,アクレディテーションに関するもののを含め,合計で15本公表されているイシューペーパーについて,優れたアイディアは「委員会」として採用する意向を示しているものの,必ずしもすべてを最終報告に盛り込むものではないとし,アクレディテーションに関する提案も「一個人の大胆なアイディア」と述べている。こうした革新的な提案に対して,高等教育関係者からは,一考の価値があるという評価があるものの,多くは「米国高等教育の強さや多様性を損なうもの」(高等教育アクレディテーション協議会(CHEA)会長),「型にはまった尺度」(地域アクレディテーション団体幹部)など否定的な声が出ている。
(資料1,2参照)
| 注1: |
「高等教育の将来に関する連邦教育長官諮問委員会(The Secretary of Education’s Commission of the Future of Higher Education)」は,2005年9月17日,高等教育政策立案に係る連邦教育省長官の諮問委員会として連邦政府諮問委員会法(P.L.92-463)に基づき創設された。「委員会」は「国民的対話(National Dialogue)」と称し,米国の高等教育の将来像を探る検討会議を昨年10月から重ねている。
「委員会」の概要は次のとおり。 |
| |
| ○ |
委員会の目的 |
| |
| ・ |
変化する経済の中で将来必要な労働力を形成するため,現状分析並びに高等教育における連邦,州,地方及び機関の役割に関する検討を行い,高等教育システムを改善する方法を明らかにする。 |
| ・ |
2006年8月1日までに最終報告を連邦教育長官に提出する。 |
|
| ○ |
委員の構成 |
| |
| ・ |
委員は合計で19名。うち約半数は大学における経歴を持つ者であるが,多くは学長等の経営陣で,教官は3名のみ。このほか高等教育関係団体の代表,企業代表等から構成。学生は含まれない。 |
| ・ |
このほか,連邦教育省,商務省,国防総省,労働省,エネルギー省の幹部各1名が職権委員となる。 |
|
|
「高等教育の将来に関する連邦教育長官諮問委員会」の委員構成(職権委員は含まない)
| 氏名 |
役職 |
| Nicholas Donofrio |
Executive Vice President,Innovation and Technology IBM Corporation |
| James J. Duderstadt |
President Emeritus University Professor of Science and Engineering Director, The Millennium Project University of Michigan |
| Gerri Elliott |
Corporate Vice President Worldwide Public Sector Microsoft Corporation |
| Jonathan Grayer |
Chairman and CEO Kaplan, Inc. |
| Kati Haycock |
Director The Education Trust |
| James B. Hunt, Jr. |
Chairman, Hunt Institute for Educational Policy and Leadership Former Governor of North Carolina |
| Arturo Madrid |
Murchison Distinguished Professor of Humanities Department of Modern Languages and Literatures Trinity University |
| Robert Mendenhall |
President Western Governors University |
| Charles Miller(議長) |
Private Investor Former Chairman of the Board of Regents, University of Texas System |
| Charlene R. Nunley |
President Montgomery College |
| Catherine B. Reynolds |
Chairman and CEO Catherine B. Reynolds Foundation EduCap Inc. |
| Arthur J. Rothkopf |
Senior Vice President and Counselor to the President U.S. Chamber of Commerce President Emeritus, Lafayette College |
| Richard (Rick) Stephens |
Senior Vice President, Human Resources and Administration The Boeing Company |
| Louis W. Sullivan |
President Emeritus, Morehouse School of Medicine Former Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services |
| Sara Martinez Tucker |
President and CEO Hispanic Scholarship Fund |
| Richard Vedder |
Adjunct Scholar, American Enterprise Institute Distinguished Professor of Economics Ohio University |
| Charles M. Vest |
President Emeritus Professor of Mechanical Engineering Massachusetts Institute of Technology |
| David Ward |
President,American Council on Education |
| Robert M. Zemsky |
Chair and Professor University of Pennsylvania |
| |
○ |
委員会の協議状況 |
| |
|
| ・ |
2005年10月17日,ワシントンD.C.で第1回会合を開催。以後2006年5月18日までに,テネシー州,カリフォルニア州,ワシントン州など全米各地で5回の会合,及び2回の公聴会を実施。 |
| ・ |
協議内容は,アカウンタビリティ,教育費負担,進学,教育費負担,労働力,アクレディテーションであり,会合ではこれらが共通の協議のテーマとなっている。 |
|
高等教育の将来に関する連邦教育長官諮問委員会の開催状況
| |
開催日 |
開催場所 |
協議内容 |
| 第1回会合 |
2005年10月17日 |
ワシントンDC |
委員会設置趣旨説明等 |
| 第2回会合 |
2005年12月8日〜9日 |
テネシー州ナッシュビル |
アカウンタビリティ,教育費負担,進学,質の保証 |
| 第3回会合 |
2006年2月2日〜3日 |
カリフォルニア州サンディエゴ |
進学,教育費負担,質の保証,労働力,アカウンタビリティ |
| 公聴会 |
2006年2月7日 |
ワシントン州シアトル |
(大学幹部職員等からの意見聴取) |
| 公聴会 |
2006年3月20日 |
マサチューセッツ州ボストン |
(大学幹部職員等からの意見聴取) |
| 第4回会合 |
2006年4月6日〜7日 |
インディアナ州インディアナポリス |
高等教育費負担,アクレディテーション,接続,アカウンタビリティ |
| 第5回会合 |
2006年5月18日〜19日 |
ワシントンDC |
進学,教育費負担アカウンタビリティ(評価と情報公開,アクレディテーション) |
| 注2: |
2006年3月に公表されたイシューペーパー(The Need for Accreditation Reform)は,「委員会」の顧問(Executive Consulting)であるRobert C. Dickesonによって執筆された。Dickesonは政治学の教官として大学に勤務した後,大学学長,財団理事長,州知事筆頭補佐等を歴任。学長時代には高等教育団体(AACTE)から「優秀学長」の表彰を受けている。同年5月に公表されたペーパー(Assuring Quality in Higher Education: Key Issues and Questions for Changing Accreditation in the United States)は,連邦教育省職員で「委員会」の事務局を務めるVickie Schrayによる。
なお,イシューペーパーは合計15本公表されている。「委員会」の委員長及び委員のほか,「委員会」の顧問,事務局及び会議出席者などが執筆者となっている。内容は「委員会」が扱うこととなっているものであり,アカウンタビリティ,教育費負担,進学など多岐にわたるが,正面からアクレディテーションをテーマにしたものは,今回紹介したペーパーのほか,Schrayによるもう1つのペーパー(Assuring Quality in Higher Education: Recommendations for Improving Accreditation)を加えた計3本が公表されている。 |
[The Chronicle of Higher Education (2006年4月14日,5月18日(Web版))/Robert C. Dickeson, The Need for Accreditation Reform, A National Dialogue: The Secretary of Education’s Commission on the Future of Higher Education, Issue Paper (Fifth in a series of Issue Papers released at the Request of Chairman Charles Miller to inform the work of the Commission),
(http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/hiedfuture/eports/dickeson.pdf)(※ED.govホームページへリンク)(PDFファイル)/Vickie Schray, Assuring Quality in Higher Education: Recommendations for Improving Accreditation/(Forteenth in a series of Issue Papers released at the Request of Chairman Charles Miller to inform the work of the Commission)
(http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/hiedfuture/reports/dickeson.pdf)(※ED.govホームページへリンク)(PDFファイル)] |
「高等教育の将来に関する連邦教育長官諮問委員会」イシューペーパー
「アクレディテーション改革の必要性」(仮訳)
Robert C. Dickeson
【要約】
米国における高等教育のアクレディテーションは、細分化し、難解で、論理的というより歴史的な諸活動や過程や構造の寄せ集めであり、もはやその有用性を失いつつある。それ以上に、アクレディテーションは将来に向けて求められる期待に応えていない。本ペーパーでは、アクレディテーションの高等教育機関にとっての目的(institutional purposes)と国や国民にとっての目的(public purposes)との違いを明らかにし、現状に代わる1つの有効な選択肢を提案する。
アクレディテーションの意味
「アクレディテーション」は、以下に挙げるものの1つまたは複数を意味するということができる。
| ・ |
大学(a college or university)は、その地理的な場所に応じて、6つの地域アクレディテーション団体のうちの1つから総合的なアクレディテーション(general accreditation)を受ける。これらの団体は高等教育機関自身が運営するボランティア組織であり、機関全体を対象にアクレディテーションを行う。アクレディテーションの基準は地域ごとに異なるが、高等教育機関が自らの目的の達成度について行う自己点検(self-study)を基本とする。地域アクレディテーション団体はメンバー機関から資金提供を受ける。 |
| ・ |
職業教育を中心とする営利の私立カレッジ(proprietary career college)を含む特定目的の機関は、11の全国的なアクレディテーション団体のうちの1つからアクレディテーションを受ける。これらの団体はアクレディテーションを受ける側の機関によって運営され、参加機関が支払う手数料等により資金供給されている。 |
| ・ |
各機関内の教育プログラムは、66の専門・職業アクレディテーション団体のうちの1つもしくは複数から専門(specialized)アクレディテーションを受けることができる。専門アクレディテーションを受けることは通常、任意であり、各機関はある学問分野(例えばビジネスや看護など)においてアクレディテーション審査を受けることができるが、義務ではない。法律などの分野や多くの保健医療分野では、アクレディテーションを受けた機関を卒業することが専門職資格取得の要件になっている。専門アクレディテーションの基準は職業や学問領域ごとに定められており、一般にはアウトカムよりもインプット(博士号を持つ教員の割合、学生教員比率など)に焦点を置いている。いくつかの教育プログラムには複数の専門アクレディテーション団体が存在しており、各機関は認定を受けたい団体-及びそれに付随する基準-を選択することができる。専門アクレディテーションはしばしば「同業者中心主義的("guild-centric")」であるとされる。 |
| ・ |
アクレディテーション団体自身は、全国コーディネーション機関である高等教育アクレディテーション協議会(the Council for Higher Education Accreditation; CHEA)による「認証」を受ける(”recognized”)。CHEAは創設以来まだ数年であるが、その役割は解体された前身組織から受け継いでいる。CHEAは、その憲章によれば、複数のアクレディテーション団体をコーディネートすることにより、アクレディテーションを「強化」(”strengthen”)することを目指している。 |
| ・ |
50の州は、特定のキャリアや職業を規制する免許や資格の下付要件を通じてアクレディテーションに関与する。例えば、教員養成のプログラムは、その卒業生が州の教員免許を取得できるようにするため、州のアクレディテーションを受ける。対象プログラムと基準は50の州ごとに異なる。 |
| ・ |
連邦政府もアクレディテーション団体の認証を行う。連邦政府の認証は、アクレディテーション団体の基準が各教育機関やプログラムが学生奨学金等の連邦のイニシアティブの対象となるに足る水準を満たすことを保証することを目的としている。この認証は強力なてこである。アクレディテーションを受けない教育機関は連邦の財政援助を受けられないのである。 |
アクレディテーションの目的
矛盾し、時に相容れない管轄やプロセス、構造のすべてを通して調べると、米国におけるアクレディテーションには高等教育機関にとっての目的と国や国民にとっての目的の2つの主要な目的が存在する。
高等教育機関にとっての目的
| 1. |
大学は自己改善のためにアクレディテーションを用いる。自己点検を行い、それに対して外部のピア集団からお墨付きを与えられることによって、機関は自身を顧み、長期にわたり組織を進展させることができる。 |
| 2. |
高等教育機関は、アクレディテーションが学問の質の向上につながると主張する。ここでいう「質」とは、多くの場合、入学者のプロファイルや教員の資質、特定の学科に割り当てられる設備などのインプットと同義である。 |
| 3. |
アクレディテーションは計画につながる。多くの場合、アクレディテーションにおける訪問調査の結果やコメントは、後の組織計画や予算の立て方の方向性を与える。アクレディテーション評価者は、通常、機関が計画を策定していることを期待する。大学の学長はアクレディテーションを戦略的計画を後押しする原動力とみなしている。 |
| 4. |
高等教育機関はアクレディテーションを機関間交流の媒体としても活用する。他大学の単位は、もし認められるとすれば、アクレディテーションを受けた機関のものに限られる。アクレディテーションを受けた大学で学位を得た学生のみが、大学院やプロフェッショナルスクールへの入学を許可される。そして、教員や事務職員は、アクレディテーションを受けた機関で学位を得ている場合にのみ、採用される。 |
国や国民にとっての目的
| 1. |
アクレディテーションの第一の国や国民にとっての目的は、消費者保護である。国民一般は、高等教育機関のあらゆる側面を調査することはできないので、アクレディテーションを頼りに良い機関と悪い機関、法令に則った運営とディプロマ・ミルとの違いを見分け、各機関の学位授与機能が正当なものであることを確信する。 |
| 2. |
アクレディテーションは、とりわけ公的投資の観点から、公の利益に資するものでなければならない。教育機関は、公的資金を受け取るだけでなく、免税されたり、税額控除の対象となる寄付金を受けられるといった利益に浴している。国民一般は報酬がその投資に見合うものであるか、教育機関が受ける優遇措置が正当なものであるかについて、知ることを求める。 |
| 3. |
国民一般は、質について知る権利を持つ。高等教育機関が授与した学位や単位は質の高いものであるか。その機関は信用できる情報を発しているか。その機関が行う研究は卓越性に関する基準を満たしているか?その機関は誠実に運営されているか。その機関が生み出す成果は国際競争力を持つか?良いアクレディテーションはこれらの問いに答える。 |
| 4. |
高等教育には、確かなアクレディテーションに頼らねばならない多くの利害関係者がいる。学生や受験生、学生を支える家族、寄付者、卒業生を雇う雇用者、そして国民一般などである。すべての利害関係者は、提供される教育の成果や高等教育機関が生み出す成果の価値について、筋の通った明確かつ首尾一貫した情報伝達を必要としている。 |
現在実践されているアクレディテーションに関するあらゆる分析は、国や国民にとっての目的より高等教育機関にとっての目的の方が優位にあるとの結論に至っている。
こうした状況には、歴史的かつ現実的な理由が存在する。
| 1. |
米国におけるアクレディテーションは、高等教育機関によって開始された。1885年、機関の枠を越えて質を保証する手段を求める高等教育機関によって、ニューイングランド地区大学協会が設立された。これに続いて、1919年までに他の5つの地域団体がそれぞれの管轄区域内に作られた。 |
| 2. |
アクレディテーションは教育機関によって維持されている。地域団体はアクレディテーション活動の取りまとめを担う職員を雇ってはいるが(例えばニューイングランド地区大学協会では253の学位授与機関のアクレディテーションを監督するために7人の職員を雇っている)、大半の仕事はアクレディテーションを受ける側である高等教育機関からの多数の教職員がボランティアとして担っている。 |
| 3. |
アクレディテーションの費用は高等教育機関が負担している。多くの場合、機関の規模や、立候補や訪問調査にかかるコストに基づく手数料や費用負担のシステムを通じて、アクレディテーション団体は教育機関からの資金提供を受ける。 |
| 4. |
CHEAを通じたアクレディテーションの調整は、全体の調整の必要性を認識した高等教育機関の長たちが作り出したものである。CHEAは1996年に設立された。 |
| 5. |
アクレディテーション全体の方向性としては、国や国民にとっての目的よりも高等教育機関にとっての目的が優位に立っている。下表に示すとおり、多くの地域アクレディテーション団体では、その高等教育統治機構(訳注:アクレディテーション団体)に何人かの公衆の(高等教育関係者以外の)代表者を参画させている。
|
以上は、各高等教育機関がアクレディテーションの国や国民にとっての目的を無視ないし敵対視しているということを主張しているのではない。高等教育機関自身によって作られ、維持され、資金提供され、治められるシステムが、必然的に、機関の利益に向いているということである。
地域アクレディテーション理事会における高等教育関係者以外の代表者数
| 団体 |
全体の理事数 |
高等教育関係者以外の理事数 |
| ニューイングランド |
23 |
6(26パーセント) |
| 中部 |
27 |
0 |
| 北部中央 |
17 |
3(8パーセント) |
| 南部 |
77 |
11(14パーセント) |
| 北西部 |
24 |
4(17パーセント) |
| 西部 |
20 |
3(15パーセント) |
アクレディテーションの諸問題
| 1. |
米国の質の高い高等教育の評判は凋落の危機にある。 |
| |
| ・ |
OECDの最近の報告によれば、米国は高等教育学位取得者の割合が加盟国30カ国中で7位である。この統計は、高等教育における学生の業績に関する記録の付け方が芳しくないことによるところが大きい。アクレディテーションは学生の成功を認めて報告しなければならない。そうすることによって、学生やその家族はより良い情報を基に入学先を決定することができ、高等教育機関は学生の成功確率を改善しようと意識するようになり、政策立案者は高い目的を達成した高等教育機関に報いることができる。 |
| ・ |
12月に発表された全米成人リテラシー調査(the National Assessment of Adult Literacy)によると、1992年から2003年にかけて大卒米国人の平均リテラシーが著しく低下し、調査において「堪能(proficient)」とみなされる成績を収めたのは大卒者のうちのわずか25パーセントであった。この恥ずべき結果に対してアクレディテーションはどのような役割を果たすべきなのか。これらの成人は一体どの大学を卒業したのか。アクレディテーションが何らかの意味を持つとするならば、作文や数学といったリテラシーの基準を達成することこそ、アクレディテーションが機関評価において評価すべき中心的なものである。 |
| ・ |
大学に入学する学生のうち3分の1が読解、作文、数学のいずれかの治療教育(remediation)を必要としている。アクレディテーションは高等教育機関のアドミッション・ポリシーやその実践の有効性を評価すべきである。各機関はある程度成功が期待できる学生を入学させているのか、あるいは、財政的な目的で数合わせをしているに過ぎないのか。準備不足の学生の流入によって卒業要件が下がっていないか。科目レベルの評価は学業成績の付け方に基づいて行われるが、学業成績そのもののインフレーションが全国的に問題視されている。結果的に質の低下が起こっていないと証明するために、アクレディテーションは何をしているのか? |
| ・ |
最近の4年制大学学長を対象としたアンケートによれば、74.5パーセントの学長が「大学は学生の教育成果についてもっと説明責任を果たさなければならない」と感じている。国民一般や政策立案者にも共有されているこの印象を、アクレディテーションが現実のものに変えなければならない。 |
|
| 2. |
重要な情報を知りたいという国民一般のニーズは満たされていない。 |
| |
| ・ |
学生とその親は、入学許可基準、受けられるプログラム、実際の費用、経済的援助を受けられる可能性や規模、入学できる可能性のある大学はどこまでかなど、大学進学に関することについて信頼できる情報を欠いている。アクレディテーションは、各大学が公表する情報についてより一層の透明性の確保を促すとともに、国民一般が大学への進学、コスト、学業成績、適用される基準などの関連データに完全にアクセスできることを期待すべきである。 |
| ・ |
高等教育機関及びアクレディテーション団体は、国の委員会や高等教育団体からの度重なる透明性向上の要求を無視し続けてきた。(いくつかの例を挙げれば、全米高等教育費用委員会(1997)、ビジネス・高等教育フォーラム(2004)、統治評議会協会「10の高等教育に関する公共政策課題」(2005)など。)アクレディテーションは今後の認定の条件に透明性を含めるべきである。 |
| ・ |
国民一般が更なる情報を求めていることや、情報を共有することが賢明であるということについて、すべてのアクレディテーション団体が賛成しているわけではない。アクレディテーションに関して指導的立場にある者の中には、更なる情報公開は、平等でなく敵対的なアクレディテーション・プロセス、自己分析において不可欠な信用の抑圧、学校問題に関する不必要な報道、学校による情報の隠蔽等を招くと危惧している。また、こうした者の中には更なる情報に対する国民の需要の存在そのものを否定し、典型的なアクレディテーションの報告書は国民一般が求めているような情報を含むものではないと指摘する者もいる。さらには、更なる情報の必要性を理解しながらも、他国の例を見れば更なる情報公開が否定的な影響をもたらしていると指摘する者もいる。 |
| ・ |
国民一般が求める情報を提供するアクレディテーションが存在しない中、その隙間を埋めてきたのがUSニューズ&ワールド・レポートであり、その毎年度の分析と高等教育機関ランキングは同社の最も人気ある出版物となっている。USニューズ型の説明責任に不平を言う高等教育機関は、アクレディテーション団体こそが正しい問いを投げかけ、またその答えを公表することによってその責務を果たすべきであると主張しなければならない。 |
|
| 3. |
アクレディテーションの伝統的な方法は今日のニーズに見合っていない。 |
| |
| ・ |
テクノロジーの発達によって、アクレディテーションにおける昔ながらの管轄別アプローチは時代遅れのものとなった。実際、地域ごとに基準は様々である。国境を越える遠隔教育や電子的な教育内容の伝達の普及は、教育提供者と学生とが国を隔てることが可能であることを意味している。今日のキャンパスや教育内容は地理的な境界と関係がない。教育を受けるために国境を越えたり、同時に複数の高等教育機関に入学したりしようとする学生が増えている。アクレディテーションは、増加する新しい形態の教育を受ける学生の達成度に取組の照準を合わせるとともに、国際的な質保証への取組を拡大すべきである。 |
| ・ |
現在のアクレディテーションは、最低限の基準を満たすことで良しとしている。ほぼすべての高等教育機関が認定を受け、認定を受けられない機関はほとんどない。それによって、アクレディテーションの意義や妥当性が薄れている。アクレディテーションを持つ他の機関で得た単位を受け入れない高等教育機関があるのは、それらの高等教育機関がアクレディテーションは同等の質を保証するものではないと考えているからだと思われる。アクレディテーションをより厳格な基準に基づくものとし、質のレベルに差をつけるようにすれば、高等教育の全体像がより正確に反映されるようになるだろう。アクレディテーションにいくつものレベルが存在するようになれば、各高等教育機関は(USニューズのランキングに向けてそうしているように)名誉ある地位を目指して競い合うようになり、高等教育の利害関係者達はそれぞれの利害に応じて各機関の違いを見分けられるようになるであろう。 |
| ・ |
アクレディテーションは通常10年単位で認定される。歴史的に、ボランティアの教員たちが自己点検を記載し、訪問調査を行う必要があったことを考えれば、この期間は妥当である。しかしながら、知、ITの力、組織改革スピードの増大に伴い、10年という期間は適時性の観点から長すぎるものとなっている。アクレディテーションは継続的な収集、検索、分析、公表が可能な主要な質的・量的指標に焦点を絞るべきである。 |
| ・ |
アクレディテーションの構造は時代遅れで、あまりに多くの層やフィルターを含んでいる。例えば、国民一般の関心事項は政治家を通じて表明され、それがCHEAに伝わり、アクレディテーション団体に伝わり、最終的に各高等教育機関に伝えられる。アクレディテーション団体の意見申し立てプロセスは到底使いやすいものとはいえず、意見申し立てに関する方針は、アクレディテーション団体が各高等教育機関の特権に干渉しないと明言している。このプロセスこそが、アクレディテーションは各機関の言いなりだという批判を端的に反映している。 |
| ・ |
米国におけるアクレディテーションの費用の大半はアクレディテーションを受ける機関によって負担される。コストには、地域別アクレディテーション団体、全国的なアクレディテーション団体、及び専門別アクレディテーション団体の各団体に支払われる手数料、ボランティアとしてアクレディテーション団体で働く教員や職員の人件費、自己評価を行うための人件費や物件費が含まれる。高等教育機関がコスト抑制の圧力を受ける中で、質の高いアクレディテーションが行えなくなることのないようにしなければならない。 |
| ・ |
重要なアクレディテーション・プロセスにおいてボランティアの役割が過信されるきらいがある。各機関のフルタイム教員が減少し続ける中で、在籍する教員に対し、キャンパス内での義務を果たしながら外でのアクレディテーションの責務を果たせという圧力が強まっている。 |
|
アクレディテーションをどう改革するか
既にアクレディテーションを受けた高等教育機関が持つ排他的特権を残すこと以上に、アクレディテーションの重要性が増している状況にあって、米国におけるアクレディテーションの改革は不可欠である。アクレディテーションは、長年、高等教育機関によって、その自治が生み出した重要な産物であるとみなされてきた。しかし、機関を越える圧力の衝突によって、プロセスの統合化が求められている。
これらの圧力に含まれるものは、
| ・ |
インプットの測定からアウトカムの評価・公表へのシフト。特に学生の達成度について。 |
| ・ |
国内の高卒者の70パーセントが高等教育機関へ進学する中、アクレディテーションが益々国民の関心事となっているという認識。 |
| ・ |
教育、研究、公的サービスを通じた生活の質の向上、経済発展、国際競争力の向上という面での高等教育に対する国の依存の増大 |
| ・ |
プラスのリターンを期待した上での官民からの高等教育投資の拡充 |
| ・ |
多くの利害関係者の目から見た高等教育の重要性の拡大
|
アクレディテーションと説明責任の整合性、高等教育機関にとっての目的と国や国民にとっての目的の整合性、重要性と質の整合性、投資とリターンの整合性は、国家の利益に資する新たな基準とプロセスによって運営される新たな団体の創設によって強化し得るかもしれない。
代案:全米高等教育アクレディテーション機構(The National Accreditation Foundation)
新たな団体は複数の整合性へのニーズを満たし得る。議会及び大統領が、全米高等教育アクレディテーション機構の設置法を制定する。創設されれば、全米高等教育アクレディテーション機構は官民共同運営とし、以下のことを行うことができるものとする。
| ・ |
全米の高等教育機関に適用すべき、厳格かつ透明な質の基準を作成し、維持する。 |
| ・ |
機関やプログラムに適用される、従来よりも効率的かつ効果的な新たなアクレディテーション・プロセスを監督する。 |
| ・ |
情報と説明責任を改善すべく、アクレディテーション審査の結果を国民一般に伝達する。 |
| ・ |
学生の経済的支援や連邦の研究支援等、現在連邦機関が有しているアクレディテーションの責務を引き継ぐ。 |
| ・ |
国家レベルで専門性の高いアクレディテーションを前進させるための資金源として、永久基金(permanent endowment)を官民から資金を集めて創設し、維持する。 |
全米高等教育アクレディテーション機構は、国民一般、高等教育機関、産業界、州政府及び連邦政府の代表からなる理事会によって統治される。統治理事会は、代表を選出するほか、その目的を実現しその正当性を維持するために必要な専門スタッフを選出する。
基金は、教育成果の測定方法の改善を模索したり、専門資格の付与において各州間でより統一された基準を確保したり、より強固で創造的な高等教育システムの創出を主張したり、さらには米国の高等教育の成功に対する一般の関心を高めるため、その権威を活用する。
[Robert C. Dickeson, The Need for Accreditation Reform, A National Dialogue: The Secretary of Education’s Commission on the Future of Higher Education, Issue Paper (Fifth in a series of Issue Papers released at the Request of Chairman Charles Miller to inform the work of the Commission)
(http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/hiedfuture/eports/dickeson.pdf)(※ED.govホームページへリンク)(PDFファイル)] |
「高等教育の将来に関する連邦教育長官諮問委員会」イシューペーパー
「高等教育の質保証:アクレディテーション改善に関する提案」(仮訳)
Vickie Schray
 . . |
はじめに |
| |
2005年10月17日、マーガレット・スペリングス長官が「高等教育の将来に関する委員会」(以下、「委員会」)の設置を発表した。委員会は、高等教育の将来に関する国民対話の推進を目的に設置され、知的かつ競争力ある21世紀の労働力を求める国家のニーズに我が国の高等教育システムが応え続けていくために国家投資を最大限活用する方法について検証することを要請された。長官が委員会に検討を要請したのは、アクセシビリティ、アフォーダビリティ、アカウンタビリティ、クオリティ(質)の4つのテーマである。
高等教育の質保証においてアクレディテーションが果たす重要な役割(連邦・州・民間からの資金提供の入り口(gateway)の提供、アカウンタビリティの促進)に鑑み、委員会は、現在のアクレディテーション・システムをレビューするとともに、その改善方法について、アクレディテーションの関係者・団体及びその他の高等教育の利害関係者と対話を行った。本ペーパーではその成果を紹介する。
|
 . . |
概説 |
| |
アクレディテーションは米国の高等教育において極めて重要な役割を果たしている。高等教育コミュニティと政府は、ともに、質保証と公共の利益の保護のためにアクレディテーション・システムを活用している。アクレディテーションは、高等教育コミュニティが期待する質の水準を定めるための一つの主要な方法であり、また、政府や国民一般(the public)が高等教育において最重要な公共の利益を定義しそれについて意見交換するための一つの主要な方法である。
アクレディテーションは、連邦、州、民間の規制者からなる巨大かつ複雑な官民システム(public-private system)である。アクレディテーションは、自己規制とピア・レビューの原則によっている。アクレディテーション団体の大半は、アクレディテーションを受ける側の機関やプログラムによって運営される会員組織である。これら民間のアクレディテーション団体は、その会員と協力しながら質の基準を設定する。団体はまた、機関やプログラムが基準を満たしアクレディテーションを受けるにふさわしいかどうかを決定するピア・レビューのプロセスにおいても、ボランティアの会員を活用する。このプロセスは、自己点検やピアによる提案を通じた質の改善の促進にも寄与している。
1950年代以降、連邦政府は連邦の奨学金の対象資格を機関やプログラムに付与するメカニズムとして、この自己規制による民間システムを活用してきた。連邦政府は、連邦の質基準を設定し、この基準を民間アクレディテーション団体の認証に用いた。それ以来、各高等教育機関やプログラムが年間800億ドルにのぼる連邦や州の助成金、奨学金を受けられるかどうかがアクレディテーションの有無で決まることになり、高等教育においてアクレディテーション団体は重要な「門番」(”gatekeeper”)機能を果たすようになった。雇用者もまた、高等教育機関が提供する数十億ドルもの授業料援助を被雇用者に受けさせようと、アクレディテーションを活用した。アクレディテーションの最も重要な公共の利益は、50年間に渡り、消費者や連邦及び州の学生奨学金プログラムを不正行為や濫用から保護することと定義されてきた。
アクレディテーションは、長年にわたり、高等教育をめぐる環境の変化に応える形で進化してきた。高等教育機関の多様性の拡大や、遠隔教育のような新たなデリバリーメカニズムの登場、教育・ビジネス・エンジニアリングといった専門プログラムの質保証への官民からの関心の高まりに応える形で、アクレディテーション団体は数の面でも多様性の面でも増大を遂げた。この結果、異なる基準やプロセスを持つアクレディテーション団体が100以上も誕生し、政府その他の利害関係者にとって完全に比較可能ではなく透明性を欠く事態に至った。
本ペーパーの目的は、アクレディテーション関係者・団体やその利害関係者との対話に基づき、高等教育が直面する主要な課題のうちアクレディテーションと関係が深いものについてを概観することである。本ペーパーの結論では、米国のアクレディテーションの改善に向けた主要な提言を示す。
|
 . . |
アクレディテーションの主な課題 |
| |
高等教育を取り巻く新たな環境は伝統的なアクレディテーションの基盤そのものに疑問を呈し、抜本的な変革の必要性に迫っている。このような新たな環境として、少なくとも次の5つが挙げられる。
| ・ |
国際競争力と質: 米国の国際競争力と高等教育システムの質の維持を心配する声が高まっている。頑強な高等教育システムは将来の米国の経済的な国際競争力にとって重要であり、学生や労働者を経済的成功へ導くものである。この状況において、質の最低基準を満たすか否かに着目することはもはや十分でない。米国の高等教育を、極めて競争的で世界的に卓越性した業績を生むものにしなければならない。質及びその厳格さの定義に関し高等教育機関と国民一般との間で緊張感が高まっていることを考慮すれば、米国の高等教育の質の強化は喫緊の課題である。アクレディテーションは、高等教育を最低限の質の確保から卓越した業績の発揮へと移行させる上で重要な役割を持つ。その際、各機関やプログラムはその使命において多様であり、結果として、卓越性の定義は常に機関やプログラムの使命や、似通った使命を共有するピアの業績を考慮に入れつつ決定しなければならないということをはっきり認識することが必要である。また、各機関やプログラムがアクレディテーションを受けそれを維持する前提として、継続的に状況改善の証明を行うことを求めるという改革を行うことが必要である。ボールドリッジ基準(the Baldrige criteria)が、業績の卓越性を定義づける上で、また、各機関やプログラムが継続的な改善措置を採っていることを確かめる上での、有望な出発点となる。ボールドリッジ基準は、各機関に対し、類似する(similar)機関の中で最善の業績を出しているものの業績を、卓越した業績の基準として定義させるものである。これによれば、各機関やプログラムに卓越した業績を目指させる一方で、各機関等がまったく使命の異なる機関等と比較されることはないということになる。ボールドリッジ基準はまた、類似する機関との相対比較によって、幅広い活動業績の継続的改善を証明することを求める。 |
| ・ |
アカウンタビリティ: 政府、消費者、国民一般に対する説明責任を求める声が高まっている。国民は、透明性の向上と、高等教育のパフォーマンスに関する消費者にとってわかりやすい情報の提供を求めている。アクレディテーションは、パフォーマンスのアウトカム、とりわけ学生の学習成果に関するアウトカムを重視するようアクレディテーションの基準を変更することで、その主要な役割を果たしうる。これまで州、機関、プログラムの各レベルにおいて、新たなアカウンタビリティ要件を含めるために多大な努力が図られてきたにも関わらず、いまだに大きな隙間が存在している。この隙間は、州のアカウンタビリティ・システムと民間のアカウンタビリティ・システムの間、アクレディテーション団体間、各州、教育省及びCHEAの間での要件の違いの現れである。さらに、アカウンタビリティは「使命やプログラムに応じて定義される」ものであり、すなわち必ずしも公的な利益を反映しない。結果として、アウトカムは国民にとってわかりにくく、機関間で比較できない、「公的なアカウンタビリティ」システムには結びつかないものになってしまっている。アクレディテーションは、主要な利害関係者や国民に関係する情報を(機関間)比較可能な形で継続的に公表できる一定のテンプレートをつくり、国民に情報提供する役割を担わなければならない。このテンプレートは、継続的で比較可能な情報の提供に対するニーズと各機関やプログラムの使命の多様性の尊重に対するニーズとのバランスに配慮したものでなければならない。 |
| ・ |
変化する高等教育の構造: 高等教育の構造や供給方法の変化には、新しいタイプの高等教育機関や遠隔教育の活用が含まれる。これらによって各機関は世界規模の運営を行うことができ、また、これらは価値やアクセスを改善する可能性を持つ。伝統的な地理的な境界、あるいは学問領域やプログラム、供給の諸形態の境界は薄れつつある。今日の学生は、しばしば同時に複数の教育機関に通ったり、異なる供給形態の教育を受けたりしている。こうした現実から、転学のプロセスを柔軟にするための新たな解決方法が必要となっている。アクレディテーションのプロセスは、各機関やプログラムの利害には応じながら、こうした新しい環境において生じるニーズに即応できるものとなっていない。既にアクレディテーションは新たな要求に応えきれない状態にある。アクレディテーション・システムは、時折その目的や知見を逸脱した機能を任されている。アクレディテーションの評価者は、現行システムにおけるピア・レビューやボランティア主義は「忍び寄る法律主義」(”reeping legalism”)によって制圧されてしまうのではないかと危惧している。しかしながら、機関評価がピア・レビューとボランティア主義に頼り続ける限り、高等教育システムがより複雑になるにしたがって(訳注:アクレディテーションの)制度上の能力・機能の問題が生じてくる。例えば、ボランティアの教員がアウトカム評価や財務諸表のレビューに関する知見を持ち合わせるとは限らない。 |
| ・ |
透明性: アクレディテーションのシステムは非常に複雑でわかりにくい。官民共同のアクレディテーションのシステムはより開かれた透明なものとし、基準の設定や機関・プログラムへのアクレディテーションの認定において機関の利益と公的な利益とのバランスを保証するものとしなければならない。そのためには、アクレディテーション基準により一貫性をもたせることや、アクレディテーションへの外部の利害関係者の参画をより多くすることが必要であろう。 |
| ・ |
価値とアフォーダビリティ: コストの上昇と連邦・州からの提供資金の減少が、高等教育機関におけるアフォーダビリティの拡大と高等教育の価値の改善を抑圧している。また、高等教育への投入資源の減少によって、資金の効率的活用と説明責任とが求められている。さらに、アクレディテーション評価者がアクレディテーションのプロセスを「投資」とみなしている一方で、各機関はそれをリターンの少ない多大なるコストとみなしている。アクレディテーションのプロセスが効率性の向上や生産性の改善や「コスト削減」につながることはほとんどない。専門アクレディテーションの評価者は社会一般から特定の同業者を守るための一種のギルド(guild)であるとみなされている。 |
|
 . . |
有望な努力 |
| |
過去10年の間、アクレディテーションの改善には大きな進展があり、一部には成功もあったという事実を知ることは重要である。1992年以来、連邦政府は、アクレディテーション団体に対し、「各機関の使命に照らしつつ、コースの修了、州の資格試験、就職率などを含む学生のアチーブメント」を含む基準を開発するよう要請してきた。(注:この要請は1992年の改正案では9番目に挙げられていたが、1998年の改正案で1番目に移動した。)学生の学習成果が新たに強調され、アクレディテーション団体はこの要求に応えるべく迅速に動いた。すべての地域アクレディテーション団体は評価基準を改め、学習成果に関する新たな基準を加えた。工学の高等教育プログラムのアクレディテーション団体であるABET Inc.は、アクレディテーション基準を修正し、プログラムのカリキュラム、教員、施設といったインプット中心の評価をアウトカムベースの評価モデルへと改めた。さらに、各州は、政策や管理や予算を考慮する際に活用するため、高等教育のアカウンタビリティに関する報告書をつくった。
高等教育のアカウンタビリティが改めて議題となったことで、これまでのこうした個々の努力を融合し、また国を挙げて高等教育の質の向上・保証に向けて取り組む素地ができた。
|
 . . |
提言 |
| |
委員会は、国民のニーズに特に焦点を置きつつ、連邦教育長官に対し、全米アクレディテーション・ワーキング・グループ(以下、WG)の設置を提言すべきである。WGは、すべての主要なアクレディテーションの利害関係者の参画の下、国家のアクレディテーション改革の青写真を描くものである。この青写真には以下の内容を含む。
| 1. |
官民共同運営を強化する |
| |
提言:
公的な利益が確保されるためには、現行の自己規制のシステムを拡大し、より多くの官民の参画を得てアクレディテーションを行うようにする必要がある。参加者には、企業や連邦・州政府の代表も含め、高等教育コミュニティと官民の利害関係者の代表者をバランス良く含まなければならない。すべての利害関係者のニーズに応え、システム全体を通じた一貫性と透明性の向上につながるようなアクレディテーションの認定基準とプロセスを築き上げるためには、こうした幅広い参画が不可欠である。こうした官民運営体制の強化は、以下の3つのレベルで行われる必要がある。
| ・ |
国家認証プロセスの運営: 連邦教育省によるアクレディテーション団体の認証基準の策定及び適用には、すべての利害関係者が参画することが必要である。各州及び連邦政府の既存のアクレディテーション要件を統合し、かつ、(地域、全国、専門の)すべてのアクレディテーション団体が官民双方の利益に資するようにするためには、このような官民共同運営体制の強化が不可欠である。 |
| ・ |
アクレディテーション団体の運営: アクレディテーション団体はその大半が評価を受ける側の機関により運営される会員組織である。現在のアクレディテーション団体の評議会には一般の代表者が参画しているが、その人数や関わり方ともに十分ではない。雇用者、連邦・州政府を含め、あらゆる主要な官民の利害関係者の代表者をバランス良く参画させる運営協議会の各アクレディテーション団体への設置を求めるべきである。 |
| ・ |
機関アクレディテーションの評価プロセス: 機関やプログラムの利益を代表する機関メンバーからのボランティアによるピア・レビューワーがアクレディテーション評価を行っている。公共の利益を確保し透明性を高めるためには、評価は公的な訓練を受けた資格ある独立した評価者であってアクレディテーションのプロセスにおいて国家アクレディテーション基準を適用できる者によって、評価が行われるべきである。
|
| |
論理的根拠: |
| ・ |
アクレディテーションの歴史的な成り立ちは、公的投資と政府関与を最小限とした自己規制のモデルを基盤としている。この自己規制システムには3つの中心的要素がある。 |
| |
| ○ |
アクレディテーション団体は評価を受ける機関による会員組織である |
| ○ |
アクレディテーション団体とその会員機関が自ら評価の基準とプロセスを定める |
| ○ |
評価とアクレディテーションは質の評価や監査に通じた外部専門家ではなくボランティアの教職員が行う |
|
| ・ |
アクレディテーション団体が連邦制度の門番的機能を持つことによって、政府の関与が徐々に強まり、法的な課題が生じ、改善重視と政府が定める要件遵守との緊張関係が高まった。 |
| ・ |
公共の利益を保護するため、質保証への一般国民の関与の拡大を求める声が高まっている。アクレディテーションの自己規制と内部統制の仕組みの信用性が問われ始め、一般の参画と透明性がより必要とされている。 |
| ・ |
新たな官民共同運営モデルを構築し、業界の自己規制と公共の利益との均衡を保つことが課題である。 |
| ・ |
他の分野における質のコントロールに関する先例が、この新モデルを開発するための戦略を提供するかもしれない。 |
|
| 2. |
全国共通アクレディテーション枠組みを開発する |
| |
提言:
アクレディテーションは高等教育を結果に対してアカウンタブルなものにしなければならない。すべてのアクレディテーション団体は、機関評価やプログラム評価において、パフォーマンスに関するアウトカム、とりわけ学生の学習成果に焦点をおいた判断を下さなければならない。全国共通アクレディテーション枠組みにおいて不可欠な要素は、次の3つである。
| ・ |
パフォーマンスに関するアウトカムの指標: 機関及びプログラム自身による成果の証明、特に学生の学習成果に関する証明こそ、最も重視されるべきものである。枠組みは、有効で信頼できる評価基準に基づいて、学生の学習成果を公表する。また、枠組みは、学生の学習成果に関するものを含む比較可能ないくつかの指標を各機関・プログラムの使命に応じて定め、これをアクレディテーションや世間への公表及び消費者への紹介に用いることができるようにする。 |
| ・ |
新たなプロセス基準: 枠組みは、高等教育におけるイノベーションと多様性を促す柔軟で開かれたプロセス基準を促進するものとし、特定のインプットやプロセスの基準(施設、教員など)は規定しないものとする。この国家的なプロセス基準は、ボールドリッジ基準のような実績ある官民モデルに基づいて定められるものとする。ボールドリッジ基準は、特定の組織構成、資源、アプローチなどを規定せず、各機関が組織的な学習管理と継続的な改善(情報管理、プロセス管理など)を行う能力を持っているか否かだけを問うという点で、開かれたものである。また、ボールドリッジ基準は、継続的に変化し適応する創造的な解決を促し、効率的に成果を得て継続的な改善を促すという点で、柔軟なものである。 |
| ・ |
継続的な改善: 枠組みは世界水準の質を目指した変革と国内外のピアとの関係において測定可能な進捗状況の公表とを各機関・プログラムに対して求めるものとする。この要請は、ベンチマーキングと継続的改善技術に関する先進的事例を活用することによってモデル化される。 |
| 論理的根拠: |
| ・ |
現在の高等教育環境において、地域や機関の類型ごとに異なる基準を用いることは無意味であり、公共の利益にも資さない。 |
| ・ |
パフォーマンスのアウトカムとプロセスとのバランスが求められている。 |
| ・ |
アクレディテーションは継続的な改善と最良事例を基準に行う評価(ベンチマーキング)を促すものであるべき。 |
| ・ |
アクレディテーションは、質の最低基準を満たすことを保証するものから、卓越したパフォーマンスに向けた継続的改善を促すものへと変化することが必要である。 |
| ・ |
各機関には、最良事例をベンチマークに、挑戦的な目標を設定させるべきである。各機関は、(それぞれの使命と目標に応じて国内外から)ピアを選び出し、ピア機関と比較可能なパフォーマンスの評価指標のベンチマーキング情報を提供しなければならない。 |
| ・ |
あらゆるタイプの機関やプログラムについて、国レベル、世界レベルのベンチマーキングに対するニーズが存在する。 |
| ・ |
現時点では、アクレディテーション団体によって活用されている学習成果に関するベンチマークは存在しない。 |
|
| 3. |
学生の学習成果に関する評価水準を設定し、その測定強化を図る |
| |
提言:
各機関あるいは各教育プログラムが自らの学生の学習成果を測り評価するための国レベルの基準を開発し、各機関あるいは各教育プログラムがその目的を達成できるようにするための戦略を提案する。この基準は、以下の内容を含むものとする。
| ・ |
学生の学習成果を定義する:基準は、各機関あるいは各教育プログラムに、それぞれの使命と企業その他の利害関係者からのインプットとに基づいて学生の学習成果を計らせるものとする。しかしながら、機関等ごとの類似点や相違点が学生、親、雇用者に対してわかりやすいものとなるよう、各機関あるいは各教育プログラムに共通のフォーマットを使わせるようにすることが必要である。 |
| ・ |
有効で信頼できる評価:基準はまた、学位や資格を取得する学生がその機関やプログラムの謳うスキルを現に有していることをアクレディテーション団体がある程度公に証明できるよう、有効で信用できる評価のための用件を設定するべきである。
|
| 論理的根拠: |
| ・ |
学生の学習成果の測定の必要性については、コンセンサスが拡大しつつある。学生が知るべきことやできるべきことを明示し、それが現に学習されたことを証明することが求められる。 |
| ・ |
各高等教育機関が継続的にこのプロセスを実行するためのガイダンスやサポートが必要となろう。 |
| ・ |
それには、学生の学習成果に焦点を置きつつ他の評価指標(在学率や卒業率、労働市場に関する指標等)とのバランスの取れた評価のテンプレートを作成することが必要となる。 |
|
| 4. |
透明性向上を促進する。 |
| |
提言:
アクレディテーションの条件として各機関あるいは各教育プログラムに求めるべき経営、報告、情報共有の在り方を定めた情報管理に関する基準を開発する。この基準には少なくとも以下を含むものとする。
| ・ |
情報公開:パフォーマンスに関するアウトカムの情報を含め、情報は公表されなければならない。 |
| ・ |
学生レベルの情報の共有:パフォーマンスを計りその継続的改善を促すための、学生レベルの情報の共有に関する基準。ただし、同時に、プライバシーや安全を保護するものでなければならない。 |
| ・ |
データの質の確保:各機関あるいは各教育プログラムが公に有効かつ信頼できるデータを提供していることを保証するための、情報の管理及び公表(例えば、ウエブサイトや出版物、報告書、消費者説明)に関する基準。
|
| 論理的根拠: |
| ・ |
概念としての透明性は絶対的に重要だが、十分ではない。各機関はそれを完全なものとするための実用的なツールを持つことが必要である。 |
| ・ |
このシステムには機関・プログラム単位のデータについて公表するための共通テンプレートが必要である。 |
| ・ |
信用性を高めるため、消費者はカリキュラム、サービス、コストに関する正確な情報を必要としている。 |
| ・ |
透明性を担保するためには、より一貫性あるアクレディテーション基準を設定するとともに、アクレディテーションのプロセスにより多くの外部の利害関係者を参画させることが必要である。 |
| ・ |
正確さと公平性を確保するためには、このシステムにおいて各機関あるいは各教育プログラムが消費者に提供する自己公表情報の裏付けを取る仕組みが必要。 |
|
|
 |
結論 |
| |
| ・ |
高等教育の新たな発展とともに、評価される機関から距離を置いた、全国的な基準やプロセスに基づく官民共同運営システムによるアクレディテーションのプロセスへの変革が必要とされている。 |
| ・ |
21世紀において最も重要な公共の利益は、世界水準の質とパフォーマンスの実現のためのアカウンタビリティの向上である。 |
| ・ |
アクレディテーションは、アカウンタビリティの向上と公共の利益の保護を担う他の官民のシステムと切り離すことができない。 |
| ・ |
アクレディテーション・プロセスは、プロセス重視からアウトカム重視へと転換しなければならない。
|
|
| |
[Vickie Schray, Assuring Quality in Higher Education: Key Issues and Questions for Changing Accreditation in the United States(Forteenth in a series of Issue Papers released at the Request of Chairman Charles Miller to inform the work of the Commission)
s (http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/hiedfuture/reports/dickeson.pdf)(※ED.govホームページへリンク)(PDFファイル)] |
|
 |