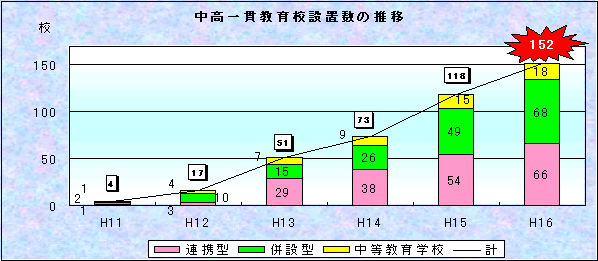(中等教育学校・併設型中高一貫教育校)
 |
中等教育学校前期課程及び併設型中学校と中等教育学校後期課程及び併設型高等学校の指導内容の一部について、相互に内容の関連する教科・科目間で入れ替えて指導することを可能とする。
| 例: |
中学校3年「社会」
(公民的分野・政治に関する内容)
↓
高校 公民「現代社会」(政治に関する分野)
中学校3年 「社会」
(公民的分野・経済に関する内容)
↑
高校 公民「現代社会」(経済に関する分野) |
|
 |
中等教育学校前期課程及び併設型中学校の指導内容の一部を、中等教育学校後期課程及び併設型高等学校に移行・統合して指導することを可能とする。
| 例: |
中学校3年「理科(第2分野)」
(生物に関する内容)
↓
高校 理科「生物 」 」 |
|
 |
中等教育学校後期課程及び併設型高等学校の指導内容の一部を、中等教育学校前期課程及び併設型中学校において指導した場合、当該内容については中等教育学校後期課程及び併設型高等学校入学後、再度指導しないことも可能とする。
| 例: |
中学校3年「国語」
↑
高校 国語「古典」の一部 |
|
|
※現行の特例は引き続き適用する。 |
|
(連携型中高一貫教育校)
 |
必修教科の授業時数を年間70単位時間の範囲内で減じ、内容を代替できる選択教科の授業時数の増加に充てることができる。(中)
|
 |
各選択教科の授業時数(第1学年:年間30単位時間以内、第2・3学年:年間70単位時間の範囲内)を各学校において増加することができる。(中)
|
 |
普通科の学校設定教科・科目について、卒業に必要な修得単位数に含めることのできる単位数の上限(20単位)を30単位まで拡大することができる。(高) |
|
※現行の特例を適用する。 |