| 資料3−2 |
| 学校の組織運営に関する資料 |
| 1.学校組織のイメージ |
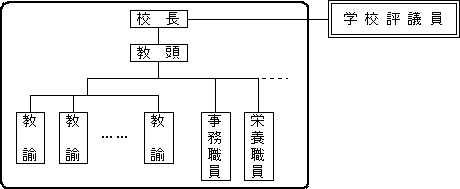
| 2.学校の組織運営の改善 |
| (1) | 校長等の資格要件の緩和
|
||||||||
| (2) | 職員会議
|
||||||||
| (3) | 主任制
|
民間人等の管理職への登用について |
| 校長等の管理職については、開かれた学校・信頼される学校づくりを進めるとともに、創意工夫にあふれた教育を展開できる、しっかりした学校運営を行える人材を登用することが求められている。 |

| 文部科学省における取組 |
| より人物・識見を重視する点から管理職の登用のあり方の改善について教育委員会を指導。 |
|
| 校長に幅広く人材を確保することができるよう、教員免許状を持たず、教育に関する職の経験がない者(いわゆる「民間人」)であっても、校長に任命できることとした。(学校教育法施行規則の改正(平成12年4月施行)) |

教員出身者でない者の校長任用実績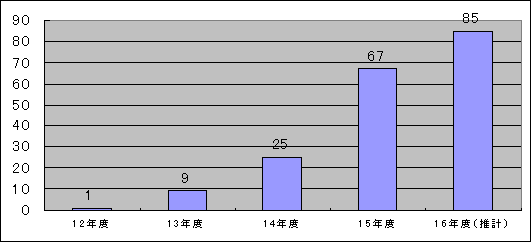 |
教員評価の改善について |
| これまでの経緯 |
| ○ | 教員の評価については、昭和30年代の日教組による勤評闘争(勤務評定による人事管理に反対し勤評の実施に反対する運動)があり、その後も学校現場の根強い横並び意識もあったため、適切な勤務評定が行われず、評定結果の人事や給与への活用は行われていなかったのが実態。 |

| 能力と実績に応じた評価と処遇 |
| ○ | しかし、信頼される学校づくりのため評価と公開がより一層進められる中で、校長や教育委員会が、個々の教員の勤務の状況を詳細に把握し、それに基づいて、学校の組織体制を整えること、研修等によって資質向上を図ること、優れた勤務成績を挙げている者にはそれに応じた処遇を行うことが重要。 |

| 教員の評価システムの改善に関する調査研究の委嘱(平成15〜17年度予定) |
| ○ | 文部科学省では、18年度から実施予定の公務員制度改革を見据え、全都道府県・指定都市教育委員会に、新たな教員評価システムについて調査研究を委嘱。 ⇒これにより、可及的速やかに教員評価の改善を図るよう教育委員会を指導 |
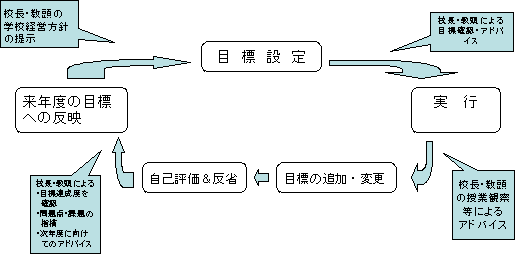 |
| 1. | 要求要旨 学校教育の成否は、その直接の担い手である教員に負うところが極めて大きく、教育改革を実現し地域住民等から信頼される学校づくりを進めるためには、教員一人一人が、その資質能力を向上させながら、それを最大限に発揮し、学校運営に積極的に参画することが不可欠である。そのためには、教員一人一人の能力や実績等が適正に評価され、それが配置や研修、給与等の処遇等に適切に結びつけられることが必要である。 中央教育審議会答申(平成14年2月21日)や「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(平成14年6月25日)では、新しい教員評価システムの導入が提言されており、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日)においても、教員の一律処遇からやる気と能力に応じて処遇するシステムへの転換を進めることが提言されている。 このため、平成18年度から実施される予定の公務員制度改革も踏まえつつ、現行の勤務評定制度の改善のみならず、人事考課制度等の新たな評価の仕組みも含め、教員の評価システムの改善に関する実践的な調査研究を、引き続き全都道府県・指定都市に委嘱して実施するものである。 |
| 2. | 要求内容 教員の評価システムの改善に関する実践的な調査研究を教育委員会に委嘱し、調査研究に必要な経費を支出する。 委嘱件数 60件(全都道府県及び全政令指定都市) 委嘱期間 3年間(平成15〜17年度) |
指導力不足教員の人事管理システムの構築について |
| ○ | 指導力不足教員については、公務員の身分保障や勤務評定の問題もあり、事実上分限処分も難しく、結局学校を「たらい回し」になるなど、適切な措置が講じられていないのが実態。(臨教審や中教審等でもその対策を提言) |

| 教員の児童生徒に与える影響が極めて大きいことに鑑み、公教育の信頼を確保するためにも、指導力不足教員について、継続的な指導、研修を行うとともに、状況に応じて分限免職や他の職への転任等必要な措置を講じ、指導力が不適切な教員を「教壇に決して立たせない」ようにすることが重要。 |

| 文部科学省における取組 |
| 指導が不適切な教員の他の職への転任 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正(平成14年1月施行) |
|
| 指導力不足教員の人事管理システムの構築 全都道府県・指定都市教育委員会に調査研究を委嘱(平成13〜14年度) |
| ○ | 指導力不足教員として認定・措置された人数は、平成14年度289名で、平成13年度149名に比べ約2倍に増加。(参考2参照) |
指導力不足教員の人事管理システムを運用している 都道府県・指定都市教育委員会の数 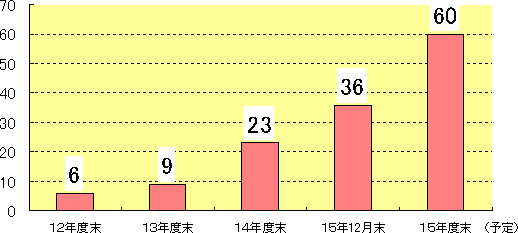 |
| ※ | 平成15年12月末までに運用を開始した36教育委員会 北海道、岩手県、宮城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、千葉市、名古屋市、京都市、広島市、北九州市、福岡市 |
| 指導力不足教員に対する認定、措置等の状況(平成15年4月1日現在)
(単位:人)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 平成14年度進学指導対応教員を、都立高等学校及び都立盲・ろう・養護学校教員から公募。 平成15年度からは、加えてエンカレッジスクール対応教員、開設準備等担当教員について同様に公募。 |
| ○ | 平成15年度から府立高等学校及び府立盲・ろう・養護学校で、校長の教育方針のもと教育実践を行う教員を公募。 |
| ○ | 平成15年度より府立学校で、校長が自校の課題に応じて教員を募り、自ら意図する人材を確保できる「教員公募制度:TRYシステム」を導入。 |
| ○ | 「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究」の実践研究校の新宮市立光洋中学校において、平成15年度より原則2年間研究実践に参加し成果を広く各地に発信できる教員を公募。 |
| ○ | 平成15年度、「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究」の実践研究校の尾道市立土堂小学校で、公募された校長の理念のもと教育実践を行う教員を公募。 |
| ○ | 希望転任制度(配置者数;110名、「FA」宣言者数;178名) 平成16年度から、一定の要件を満たす教員が異動を希望し、受け入れを希望する校長と協議を行い、配置する制度を導入(教員版フリーエージェント制) |
| ○ | 教員公募制度(配置者数;18名、応募者数;39名) 平成16年度から、市町村立学校において、校長が学校経営ビジョンを示して教員を募り、自校に配置する制度を導入 |
| ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |