- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 中央教育審議会 > 初等中等教育分科会 > 教員養成部会 教員免許制度ワーキンググループ > 教員養成部会 教員免許制度ワーキンググループ(第12回) 配付資料 > 資料8 教員免許更新制を導入する場合の実施規模のイメージ(未定稿)
資料8 教員免許更新制を導入する場合の実施規模のイメージ(未定稿)
※ 議論の参考とするため、いくつかの条件を仮定して実施規模のイメージを作成したものであり、詳細なデータに基づき、実施規模を推計したものではない。
1.更新の申請者数
[前提条件]
- 免許状取得者のうち、60歳以下の免許状取得者が更新の申請をすると仮定した。
- 各年度の新規免許状取得者は、平成16年度までは、当該年度の大学等新規卒業者のうちの免許状取得者実数(注1)を用いた。
平成17年度以降は、0~14歳の人口動態(注2)の推計値から新規免許状取得者を推計した。 - 免許状取得者のうち、現職教員とペーパーティーチャーの比率は、すべての年度において1対4とした。
1、2から概算される免許状取得者総数 約523万人(a)
平成16年度の本務教員数(注3) 約109万人(b)
(a)-(b) 約415万人- (注1)文部科学省調べ
- (注2)「日本の将来推計人口(平成14年1月推計)」国立社会保障・人口問題研究所
平成14年 - (注3)「平成16年度 学校基本調査報告書」文部科学省 平成16年
(1)新規の免許状取得者から適用する場合
- a:現職教員のみ更新の申請をすると仮定
- b:現職教員に加えて、ペーパーティーチャーの20パーセントが更新の申請をすると仮定
- c:現職教員に加えて、ペーパーティーチャーの40パーセントが更新の申請をすると仮定
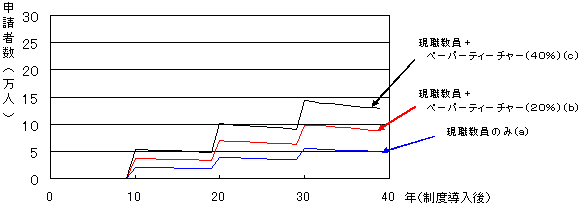
※概ね3,4年後に制度が開始されると過程した。
制度導入約30年後
- a:約 5万5千人
- b:約 9万9千人
- c:約14万3千人
(2)現に免許状を有する者も対象とする場合
- a:現職教員のみ更新の申請をすると仮定
- b:現職教員に加えて、ペーパーティーチャーの20パーセントが更新の申請をすると仮定
- c:現職教員に加えて、ペーパーティーチャーの40パーセントが更新の申請をすると仮定
※ 現に免許状を有する者は、最初の10年の間に1回目の講習を受講するものとし、受講対象者を各年度に均等配分して、制度設計
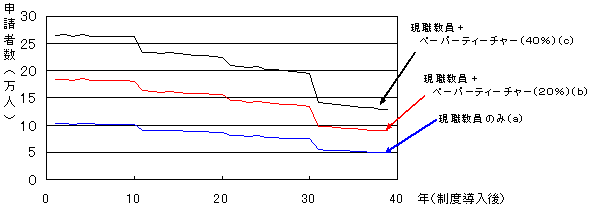
制度導入時
- a:約10万3千人
- b:約18万5千人
- c:約26万7千人
(3)都道府県ごとの申請者数
[前提条件]
- 各都道府県における申請者数は、各都道府県の現職教員数(注4)の比を用いて算出した。
- 更新の申請者は、当該者が居住する都道府県に申請するものとした。
- 申請者数の規模が大きい上記(2)の制度導入時について検討した。
(注4)「平成17年度 学校基本調査報告書」文部科学省 平成17年
| 申請者数 | (2)aの場合 | (2)bの場合 |
|---|---|---|
| 1.500人~999人 | 10 | 0 |
| 2.1,000人~1,999人 | 21 | 13 |
| 3.2,000人~2,999人 | 6 | 11 |
| 4.3,000人~3,999人 | 2 | 11 |
| 5.4,000人~4,999人 | 4 | 2 |
| 6.5,000人~5,999人 | 2 | 1 |
| 7.6,000人~6,999人 | 1 | 1 |
| 8.7,000人~7,999 人 | 1(約7,800人) | 2 |
| 9.8,000人~8,999人 | 0 | 2 |
| 10.9,000人~9,999人 | 0 | 1 |
| 11.10,000人~10,999人 | 0 | 1 |
| 12.11,000人~11,999人 | 0 | 1 |
| 13.12,000人~ | 0 | 1(約14,000人) |
| 合計 | 47都道府県 | 47都道府県 |
2.必要となる講習コース数
[前提条件]
- 更新講習は、有効期限の満了時の直前1年間で30時間受講するものとした。(2年間で30時間と仮定としても1年あたりの申請者は推計上同数)
- 1回の講習(1コマ)は1.5時間とした。したがって、更新講習の終了のためには、20コマの受講が必要であり、20コマの講習プログラムのセットを1コースとした。
- 1回の講習の受講者数は50人と仮定した。
必要なコース数=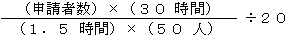
(1)新規の免許状取得者から適用する場合
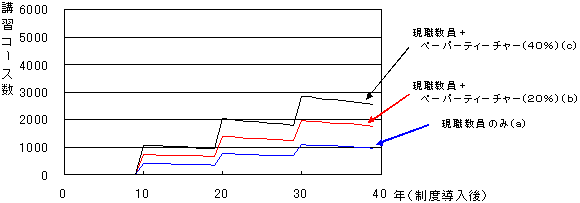
制度導入約30年後
- a:約1,100コース
- b:約2,000コース
- c:約2,900コース
(2)現に免許状を有する者も対象とする場合
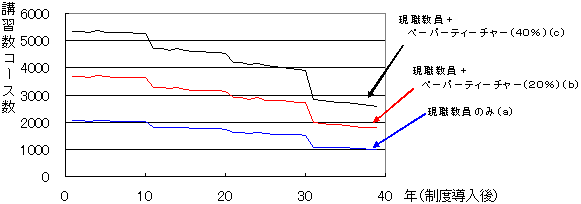
制度導入時
- a:約2,100コース
- b:約3,700コース
- c:約5,300コース
(3)都道府県ごとの講習コース数
[前提条件]
- 更新の申請者は、当該者が居住する都道府県内で講習コースを受講するものとした。
- 1.(3)において算出した都道府県ごとの申請者数に対する講習コース数を算出した。
| 講習コース数 | (2)aの場合 | (2)bの場合 |
|---|---|---|
| 1.0~24コース | 15 | 1 |
| 2.25~49コース | 21 | 18 |
| 3.50~74コース | 2 | 13 |
| 4.75~99コース | 4 | 5 |
| 5.100~124コース | 3 | 1 |
| 6.125~149コース | 1 | 1 |
| 7.150~174コース | 1(約160コース) | 2 |
| 8.175~199コース | 0 | 3 |
| 9.200~224コース | 0 | 1 |
| 10.225~249コース | 0 | 1 |
| 11.250~274コース | 0 | 0 |
| 12.275~ | 0 | 1(約280コース) |
| 合計 | 47都道府県 | 47都道府県 |
3.講習コースを開設する場合の各都道府県の状況
[前提条件]
- 講習コースは、当該県に所在する課程認定大学、当該県の教育センターにおいて開設されるものとし、大学と教育センターで均等に開設するものとした。
- 更新の申請者は、当該者が居住する都道府県内の課程認定大学又は教育センターで講習コースを受講するものとした。
- 教育センターが実施している研修については、
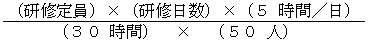
として、講習コース数に換算した。 - 申請者数、講習コース数の規模が大きい上記1.2.(2)bの制度導入時について検討した。
(1)必要な講習コース数が小規模の県の例
1.実施規模
- 更新の申請者数 :約2,300人
- 講習コース数 :約45コース
2.受け入れ機関数
- 課程認定大学数 :4大学
- 教育センター 合計 5機関
3.1機関あたりの実施規模
- 受け入れ数 :約460人
- 講習コース数 :約9コース
4.受け入れ機関の現状
- 1大学における開設授業数(注5):約90コース
- 教育センターの研修 :約95コース
(注5) 大学における開設授業数は、当該県に所在する国立教員養成系大学の教職に関する科目の授業数をコース数に換算したもの(以下同様)
(2)必要な講習コース数が中規模の県の例
1.実施規模
- 更新の申請者数 :約3,700人
- 講習コース数 :約74コース
2.受け入れ機関数
- 課程認定大学数 :15大学
- 教育センター 合計 16機関
3.1機関あたりの実施規模
- 受け入れ数 :約230人
- 講習コース数 :約5コース
4.受け入れ機関の現状
- 1大学における開設授業数 :約93コース
- 教育センターでの研修 :約74コース
(3)必要な講習コース数が大規模の県の例
1.実施規模
- 更新の申請者数 :約11,000人
- 講習コース数 :約230コース
2.受け入れ機関数
- 課程認定大学数 :59大学
- 教育センター 合計 60機関
3.1機関あたりの実施規模
- 受け入れ数 :約180人
- 講習コース数 :約4コース
4.受け入れ機関の現状
- 1大学における開設授業数 :約260コース
- 教育センターでの研修 :約320コース
お問合せ先
初等中等教育局教職員課