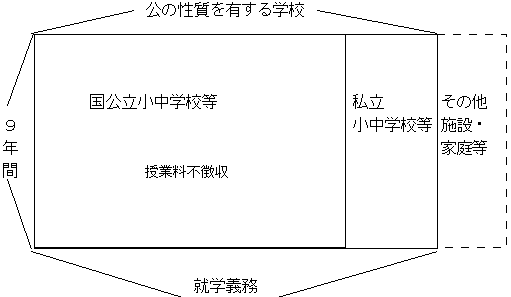| (1) |
憲法
| ・ |
国民が「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」を保障するために、国が法律を定め必要な措置を採るべき旨を定めるとともに、この権利を最低限度実現させる手段として、国民に対し「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」を負わせ、かつ、義務教育を無償とする |
| |
……憲法第26条 |
|
| (2) |
就学義務と年限・年齢 |
| |
……教育基本法第4条 |
| |
| ・ |
保護者は、子女を満6才から満12才まで小学校に、その修了後満15才まで中学校に就学させる義務を負う。
|
|
| |
……学校教育法第22条、第39条 |
| |
| ・ |
就学が困難と認められる者の保護者に対しては、就学義務を猶予または免除することができる。 |
|
| |
……学校教育法第23条
|
| (3) |
義務教育諸学校の種類と修業年限 |
| |
……学校教育法第19条、第37条
|
| (4) |
義務教育諸学校の設置義務
| ・ |
市町村は、必要な小学校、中学校を設置しなければならない。 |
|
| |
……学校教育法第29条、第40条、第74条
|
| (5) |
義務教育の無償
| ・ |
国、地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない |
|
| |
……教育基本法第4条、学校教育法第6条 |
| |
|
| |
……義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律第1条
|
| |
| * |
これに対して国は、必要な援助を行う。(義務教育費国庫負担法、市町村立学校職員給与負担法、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律等) |
|
| |
第6条 |
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。 |
| |
第17条 |
小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
|
| |
第18条 |
小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げ
る目標の達成に努めなければならない。 |
| |
|
| 一 |
学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。 |
| 二 |
郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 |
| 三 |
日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 |
| 四 |
日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 |
| 五 |
日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 |
| 六 |
日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。 |
| 七 |
健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 |
| 八 |
生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 |
|
| |
第19条 |
小学校の修業年限は、六年とする。 |
| |
第22条 |
保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 |
| |
 |
前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 |
| |
第23条 |
前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 |
| |
第29条 |
市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 |
| |
第35条 |
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。 |
| |
第36条 |
中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。 |
| |
|
| 一 |
小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
|
| 二 |
社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
|
| 三 |
学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
|
|
| |
第37条 |
中学校の修業年限は、三年とする。 |
| |
第39条 |
保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。 |
| |
 |
前項の規定によつて保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒 と称する。 |
| |
 |
第二十二条第二項及び第二十三条の規定は、第一項の規定による義務に、これを準用する。 |
| |
第40条 |
第十八条の二、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、中学校に、これを準用する。この場合において、第十八条の二中「前条各号」とあるのは、「第三十六条各号」と読み替えるものとする。 |
| |
第79条 |
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第七十一条の二の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。 |