| 資料1 |
|
|||||||||||||||||||||||
| ・ | 義務教育は,近代国家における基本的な教育制度として憲法に基づき設けられている制度であり,普通教育が民主国家の存立のために必要であるという国家・社会の要請とともに,親が本来有している子を教育すべき義務を国として全うさせるために設けられているものである。このように,国民に教育を受けさせる義務を課す一方,国及び地方公共団体は共同して良質の教育を保障する責任を有しており,義務教育の充実を図っていく必要がある。(中教審答申H15年3月「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」) | |
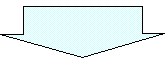
|
||
| ○ | 義務教育制度は、この教育の使命(目的)を実現するための最も基盤的な教育制度であり、教育の機会均等とその水準の維持を義務教育費国庫負担制度や教科書無償制度等により実質的に保障。また、戦後の我が国の経済社会の発展や国際社会への貢献を支えてきた重要な要素の一つ。このように、義務教育制度は、未来の我が国を築いていくために必要不可欠な国の根幹的制度と位置づけることができ、そのような位置づけについては、いかなる社会の変化にあっても変わることはないのではないか。 |
|
| ・ | (義務教育の役割は)人間として、また、家族の一員、更には社会の一員として、国民として共通に身につけるべき基礎・基本を習得させるための教育。
(中教審答申H11年12月「初等中等教育と高等教育の接続の改善について」) |
|
| ・ | (義務教育の意義は)国民個人が、個人として、また国民としての最低限度の徳性、智識、および教養を有すること。
(田中耕太郎「教育基本法の理論」) |
|
| ○ | 義務教育においては、社会的自立に向けて「知・徳・体」の基本的能力をバランス良く習得させ、生涯にわたる学習や職業・社会活動の基盤を形成する資質を形成するとともに、才能・能力を発見、伸長していくことがその役割として求められているのではないか。具体的には、下記に示す点については、普遍的に求められる義務教育の役割ではないか。 |
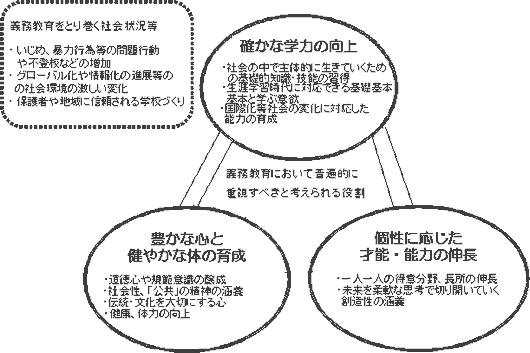
| ○ | このような役割が、将来にわたって適切かつ十分に果たすことが可能な制度を整備し、それにより教育の質を確保していくことが適切ではないか。 | |
| ○ | さらに、義務教育を取り巻く社会状況等を踏まえ、今日、義務教育のどのような面にどのような課題があるか、それに対しどのような制度上の改革を行っていくことが必要であるか等の観点から検討することが必要ではないか。 |