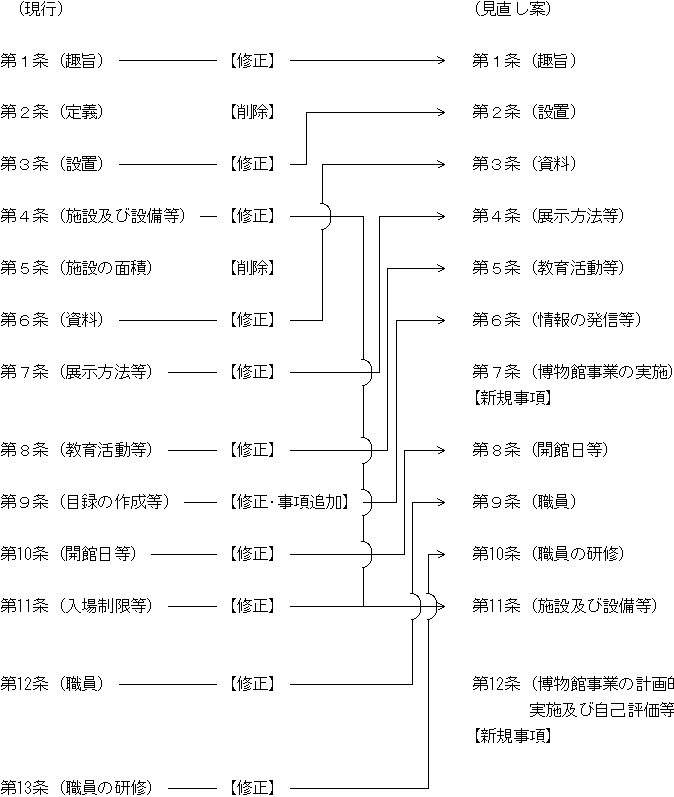| 資料6−1 |
公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準について
| 1. | 経緯
|
| 2. | 基準の見直しについて
|
| 【 | 参考】
|
| 資料6−2 |
「公立博物館の設置及び運営上の望ましい基準」(案)
(趣旨)| 第 | 一条 この基準は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項に規定する公立博物館(以下「博物館」という。)の設置及び運営上の望ましい基準であり、博物館の健全な発達に資することを目的とする。 |
| 2 | 博物館及びその設置者は、この基準に基づき、博物館の水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。 |
| 第 | 二条 都道府県は、一又は二以上の博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等様々な分野にわたる資料を取扱うものとする。 |
| 2 | 市町村は、その規模及び能力に応じて、単独で又は他の市町村と共同して、博物館を設置するものとする。 |
| 第 | 三条 博物館は、実物又は現象に関する資料(以下「一次資料」という。)について、当該資料に関する学問分野、地域における当該資料の所在状況及び当該資料の展示上の効果を考慮して、必要な数を収集し、保管し、及び展示するものとする。 |
| 2 | 博物館は、実物資料について、その収集若しくは保管(育成を含む。)が困難な場合、その展示のために教育的配慮が必要な場合又はその貸出しが困難な場合には、必要に応じて、実物資料に係る模型、模造、模写又は複製の資料を収集又は製作するものとする。 |
| 3 | 博物館は、一次資料のほか、一次資料に関する図書、文献、調査資料その他必要な資料(以下「二次資料」という。)を収集し、保管するものとする。 |
| 4 | 博物館は、一次資料の所在を調査して、その収集及び保管(現地保存を含む。)に努めるとともに、資料の補修及び更新、新しい模型の製作等により所蔵資料の整備及び充実に努めるものとする。 |
| 第 | 四条 資料の展示に当たっては、利用者の関心を深め、資料に関する知識の啓発に資するため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
|
| 第 | 五条 博物館は、利用者の教育活動に資するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
|
| 第 | 六条 博物館は、利用者の便宜のために、資料に関する目録、展示資料に関する解説書又は案内書等を作成するとともに、資料に関する調査研究の成果の公表その他の広報活動を行うものとする。 |
| 2 | 博物館は、広く一般公衆の利用に供するため、博物館事業の内容、資料等を電子情報化し、インターネット等で提供するものとする。 |
| 第 | 七条 博物館は、博物館事業を行うに当たっては、学校、社会教育施設、社会教育関係団体及び官公署等と緊密に連絡、協力するなど学校、家庭、地域社会の連携の推進に努めるものとする。 |
| 2 | 博物館は、青少年、高齢者、障害者、外国人、乳幼児の保護者等の事業への参加が可能となるよう努めるものとする。 |
| 3 | 博物館は、博物館事業を行うに当たり必要な知識・技能等を有する者のボランティアとしての参加を一層促進するよう努めるものとする。 |
| 第 | 八条 博物館は、開館日及び開館時間の設定に当たっては、利用者の要請、地域の実情、資料の特性、展示の更新所要日数等を勘案し、夜間開館の実施等、利用者の便宜を最大限に図るよう努めるものとする。 |
| 第 | 九条 博物館には、館長及び学芸員を置き、博物館の規模及び活動状況に応じて、事務又は技術に従事する職員を置くよう努めるものとする。 |
| 第 | 十条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の博物館の館長、学芸員その他職員の資質・能力の向上を図るために、研修機会の充実に努めるものとする。 |
| 2 | 市町村の教育委員会は、当該市町村の教育委員会の所管に属する博物館の前項に規定する職員を、同項の研修に参加させるよう努めるものとする。 |
| 第 | 十一条 博物館には、博物館事業を実施するに必要な施設及び設備を確保するよう努めるとともに、青少年、高齢者、障害者、外国人、乳幼児の保護者等の利用を促進することができるよう必要な施設及び設備を確保するよう努めるものとする。 |
| 2 | 博物館には、資料を保全するため、必要に応じて、耐火、耐震、防虫害、防塵、防音、温度及び湿度の調節、日光の遮断又は調節、通風の調節並びに汚損、破壊及び盗難の防止に必要な設備を備えるよう努めるものとする。 |
| 3 | 博物館は、利用者の安全を確保するため、防災及び衛生に必要な設備を備えるとともに、必要に応じて、入場制限、立入禁止等の措置をとるものとする。 |
| 第 | 十二条 博物館は、博物館事業の水準の向上を図り、当該博物館の目的及び社会的使命を達成するため、各年度の博物館事業の状況について、自ら点検及び評価を行うとともに、その結果を住民に公表するよう努めるものとする。 |
「公立博物館の設置及び運営に関する基準」の見直しについて 整理表