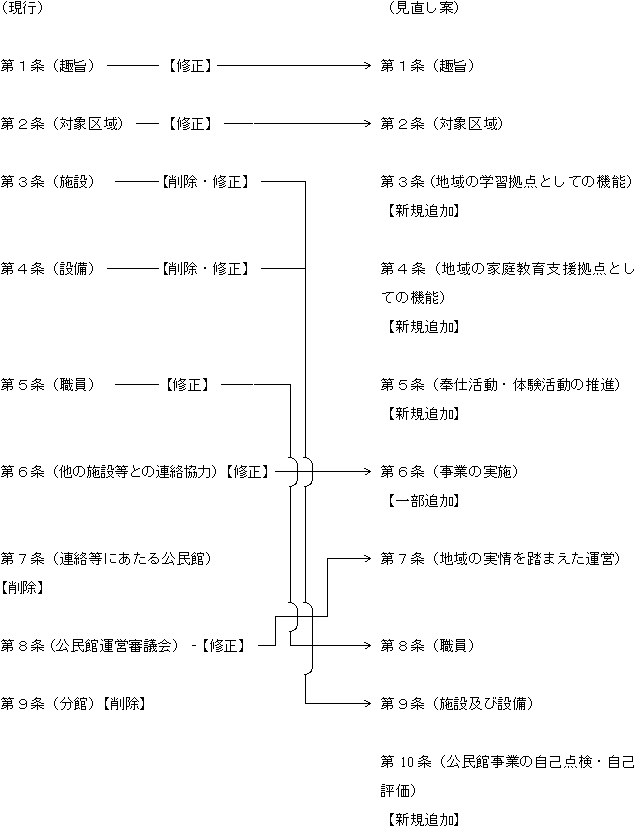「公民館の設置及び運営に関する基準」について
| 1. |
経緯
| ○ | 昭和34年当時、公民館がすでに社会教育の中心的役割を果していたにもかかわらず、施設・設備が不十分で、適正な公民館活動を営むのが困難な状況にあった。
|
| ○ | このため、文部大臣が公民館の設置運営上必要な基準を設け、これに従って文部大臣及び都道府県の教育委員会がその施設・設備その他の運営上必要な事項について指導、助言、援助を与えることができるよう、社会教育法の一部を改正(第23条の2)。
|
| ○ | 昭和34年12月28日、文部省告示第9号をもって「公民館の設置及び運営に関する基準」を告示。 |
|
| 2. |
基準の見直し
| ○ | 平成10年9月生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育行政の在り方について」の記述
| 「公民館の設置及び運営に関する基準」(文部省告示)は、社会教育法第23条の2第1項の規定に基づき定められている。この基準においては、公民館の設置運営に必要な基準として、必要な施設、設備、職員等が細かく規定されている。しかしながら、公民館は地域に密着した活動が求められる施設であり、画一的かつ詳細な基準を定めることは適当ではないことから、今後、こうした基準については、公民館の必要とすべき内容を極力大綱化・弾力化するよう検討する必要がある。 |
|
| ○ | 平成14年10月地方分権改革推進会議「事務・事業の在り方に関する意見」の記述
| 公立博物館や公民館の設置及び運営に関する基準については、基準を定量的に示したものとなっているが、平成14年度中を目途に大綱化・弾力化を図り、国の関与の限定化と地域の自由度の向上に努める。 |
|
| ○ | 以上のような状況を踏まえ、「公民館の設置及び運営に関する基準」について、その大綱化・弾力化や現代的課題への対応について検討するため、平成14年11月「見直し検討会」を設置 |
|
| 【 | 参考】
 | 社会教育法
(公民館の基準)
| 第 | 二十三条の二 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。 |
| 2 | 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。 |
|
 | 公民館の設置及び運営に関する基準(2ページ) |
 | 「見直し検討会」設置要綱(3ページ) |
|
| ○ | 公民館の設置及び運営に関する基準(昭和34年12月28日文部省告示第98号) |
最終改正:平成10年12月7日文部省告示第160号
(趣旨)
| 第 | 1条 この規程に定める基準は、公民館を設置し、及び運営するのに必要な基準を示すものであるから、公民館の設置者は、この基準に従い、公民館の水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。 |
(対象区域)
| 第 | 2条 公民館を設置する市町村は、公民館活動の効果を高めるため、当該市町村の小学校又は中学校の通学区域(児童又は生徒の就学すべき学校の指定の基準とされている区域をいう。)人口、人口密度、地形、交通条件、社会教育関係団体の活動状況等を勘案して、当該市町村の区域内において、公民館の事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)を定めるものとする。 |
(施設)
| 第 | 3条 公民館の建物の面積は、330m2以上とする。ただし、講堂を備える場合には、講堂以外の建物の面積は、230m2を下らないものとする。 |
| 2 | 公民館には、少なくとも次の各号に掲げる施設を備えるものとする。
| 一 | 会議及び集会に必要な施設(講堂又は会議室等) |
| 二 | 資料の保管及びその利用に必要な施設(図書室、児童室又は展示室等) |
| 三 | 学習に必要な施設(講義室又は実験・実習室等) |
| 四 | 事務管理に必要な施設(事務室、宿直室又は倉庫等) |
|
| 3 | 公民館には、前2項に規定するもののほか、体育及びレクリエーションに必要な広場等を備えるように努めるものとする。 |
| 4 | 第1項及び第2項に規定する施設は、公民館の専用の施設として備えるよう努めるものとする。 |
(設備)
| 第 | 4条 公民館には、その事業に応じ、次の各号に掲げる設備を備えるものとする。
| 一 | 机、椅子、黒板及びその他の教具 |
| 二 | 写真機、映写機、テープ式磁気録音再生機、蓄音器、テレビジョン受像機、幻燈機、ラジオ聴取機、拡声用増幅器及びその他の視聴覚教育用具 |
| 三 | ピアノ又はオルガン及びその他の楽器 |
| 四 | 図書及びその他の資料並びにこれらの利用のための器材器具 |
| 五 | 実験・実習に関する器材器具 |
| 六 | 体育及びレクリエーションに関する器材器具 |
|
(職員)
| 第 | 5条 公民館には館長及び主事を置き、公民館の規模及び活動状況に応じて主事の数を増加するように努めるものとする。 |
| 2 | 公民館の館長及び主事は、社会教育に関し識見と経験を有し、かつ公民館の事業に関する専門的な知識を有する者をもって充てるように努めるものとする。 |
(他の施設等との連絡協力)
| 第 | 6条 公民館は、その事業の実施にあたっては、他の公民館、図書館、博物館、学校その他の教育機関及び社会教育関係団体等と緊密に連絡し、協力するものとする。 |
| 2 | 公民館は、その対象区域内に公民館に類似する施設がある場合には、必要な協力と援助を与えるように努めるものとする。 |
(連絡等にあたる公民館)
| 第 | 7条 2以上の公民館を設置する市町村は、その設置する公民館のうち、1の公民館を定めて、当該公民館の事業のほか、市町村の全地域にわたる事業、公民館相互の連絡調整に関する事業、その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施させることができる。 |
| 2 | 前項に規定する公民館の講堂以外の建物の面積は、330m2以上とするように努めるものとする。 |
| 3 | 第1項に規定する公民館は、第4条に規定する設備のほか、当該公民館の館外活動及び第1項の事業の実施に必要な自動車その他の設備を備えるものとする。 |
(公民館運営審議会)
| 第 | 8条 市町村は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項ただし書の規定により、2以上の公民館について1の公民館運営審議会をおくときは、これを前条に規定する公民館に置くようにするものとする。 |
(分館)
| 第 | 9条 公民館の事業の円滑な運営を図るため、必要がある場合には、公民館に分館を設け、当該公民館の象区域内における第2条の条件又は当該公民館の事業の内容に応じて分館の事業を定めるものとする。 |
「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直し検討会設置要綱
平成14年11月15日
生涯学習政策局長決定
| 1. | 趣 旨
地域における学習・交流の拠点である公民館活動は、社会教育法をはじめとする関係法令の制定に先だって開始され、既に50余年を経過し、活力と潤いのある地域社会の実現のため、大きな役割を果たしてきた。
しかしながら、人々の多様化・高度化する学習ニーズや生涯学習社会の進展、地方分権の推進等新たな状況が生じており、今後、社会の変化に対応した社会教育の推進が求められているところである。特に、公民館に対しては、地域に密着した活動・取り組みが期待されており、地域の自由度を一層高めていくことが求められているところである。
このため、「公民館の設置及び運営に関する基準」の大綱化・弾力化を図るなど、その見直しを図り、もって公民館活動の振興と充実に資する。
|
| 2. | テ ー マ
| (1) | 「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直し |
| (2) | その他 |
|
| 3. | 実施方法
別紙の者による検討会を行う。
|
| 4. | 実施期間
平成14年11月15日から平成15年3月31日までとする。
|
| 5. | そ の 他
実施に当たっての庶務は、生涯学習政策局社会教育課において処理する。 |
<別紙>
「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直し検討会委員
| 渥 美 省 一 | | 我孫子市生涯学習センター長
|
| 石 川 正 夫 | | 社団法人全国公民館連合会事務局長
|
| 岡 野 智 子 | | 貝塚市立浜手地区公民館館長
|
| 奥 山 恵美子 | | せんだいメディアテーク館長
|
| 加 藤 雅 晴 | | 川村学園女子大学教育学部教授
|
| 小久保 茂 昭 | | 社団法人中央青少年団体連絡協議会理事
|
| 今 野 雅 裕 | | 政策研究大学院大学教授
|
| 庄 子 平 弥 | | 仙台シニアネットクラブ事務局長
|
| 進 和 彦 | | 香川県飯山町教育長
|
| 武 田 早 苗 | | グループ アイ・エヌ・ジー会長
|
| 野 島 正 也 | | 文教大学人間科学部教授
|
| 雲 雀 信 子 | | NPO法人子育てサポーター”チャオ”代表 |
「公民館の設置及び運営に関する基準」(案)
(趣旨)
| 第 | 1条 この基準は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の2に基づく公民館の設置及び運営上必要な基準であり、公民館の健全な発達に資することを目的とする。 |
| 2 | 公民館及びその設置者は、この基準に基づき、公民館の水準の維持、向上を図ることに努めなければならない。 |
(対象区域)
| 第 | 2条 公民館を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)町村は、公民館活動の効果を高めるため、当該市町村の人口分布、人口密度、地形、交通条件、社会教育関係団体の活動状況等を勘案して、当該市町村の区域内において、公民館の事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)を定めるものとする。 |
(地域の学習拠点としての機能)
| 第 | 3条 公民館は、講座等を主催するとともに、必要に応じて学校、社会教育施設、社会教育関係団体やNPO(特定非営利活動法人)などの民間団体、官公署等と共催するなど、多様な学習機会の提供に努めるものとする。 |
| 2 | 公民館は、地域住民の学習活動に資するよう、インターネット等の情報通信技術を活用し、学習機会や学習情報の提供の充実に努めるものとする。 |
| 3 | 公民館は、その対象区域内に公民館に類似する施設がある場合には、必要な協力と援助に努めるものとする。 |
(地域の家庭教育支援拠点としての機能)
| 第 | 4条 公民館は、家庭教育に関する学習機会や学習情報の提供、家庭教育に関する相談・助言、交流機会の提供等家庭教育への支援の充実に努めるものとする。 |
(奉仕活動・体験活動の推進)
| 第 | 5条 公民館は、ボランティアの養成のための研修会を開催するなど、奉仕活動・体験活動に関する学習機会や学習情報の提供の充実に努めるものとする。 |
(事業の実施)
| 第 | 6条 公民館は、事業を行うに当たっては、学校、社会教育施設、社会教育関係団体やNPO(特定非営利活動法人)などの民間団体、官公署等と緊密に連絡、協力するなど学校・家庭・地域社会の連携の推進に努めるものとする。 |
| 2 | 公民館は、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の事業への参加を促進するよう努めるものとする。 |
| 3 | 公民館は、地域住民その他の者の学習の成果や知識・技能を事業において生かすことが出来るよう、機会の提供に努めるものとする。 |
(地域の実情を踏まえた運営)
| 第 | 7条 公民館の設置者は、社会教育法第29条第1項に規定する公民館運営審議会を設置するなど、地域の実情に応じ、地域住民の声を十分に踏まえた公民館の運営がなされるよう努めるものとする。 |
| 2 | 公民館は、地域住民の利用を促進するため、開館日及び開館時間の設定に当たっては、地域の実情に応じた夜間開館の実施等、その便宜を最大限に図るように努めるものとする。 |
(職員)
| 第 | 8条 公民館には館長を置き、公民館の規模及び活動状況に応じて主事その他必要な職員を置くよう努めるものとする。 |
| 2 | 公民館の館長及び主事は、社会教育に関する十分な識見と経験を有し、かつ公民館の事業に関する専門的な知識と技術を有する者をもって充てるよう努めるものとする。 |
| 3 | 公民館の設置者は、館長、主事その他職員の資質・能力の向上を図るため、研修機会の充実に努めるものとする。 |
(施設及び設備)
| 第 | 9条 公民館は、その目的を達成することができるよう、地域の実情に応じ、必要な施設・設備を備えるとともに、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の利用の促進が図られるよう施設・設備の確保に努めるものとする。 |
(公民館事業の自己点検、自己評価)
| 第 | 10条 公民館は、その実施する事業の水準の向上を図り、当該公民館の目的を達成するため、各年度の事業の状況について、公民館運営審議会等の協力を得ながら、自ら点検及び評価を行うとともに、その結果を地域住民に対して公表するよう努めるものとする。 |
「公民館の設置及び運営に関する基準」の見直し(案)
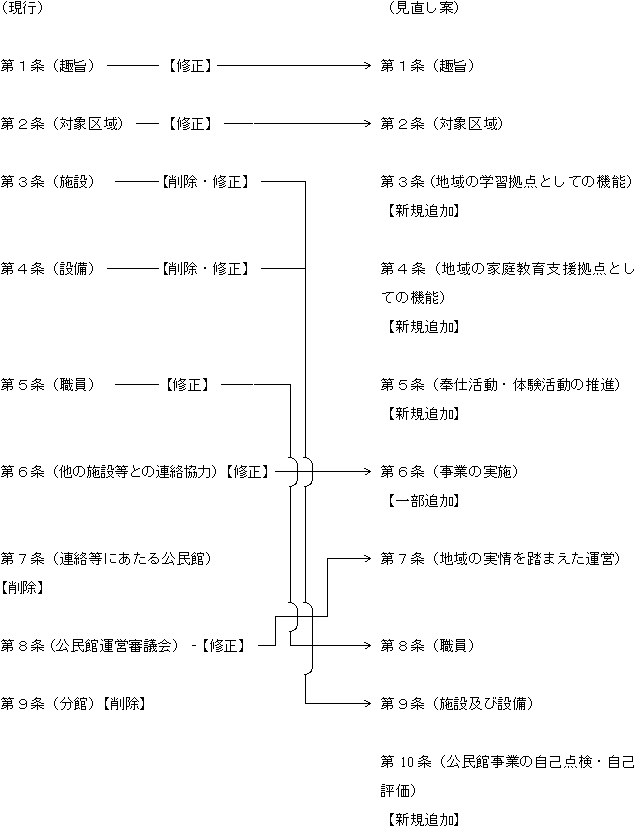
ページの先頭へ