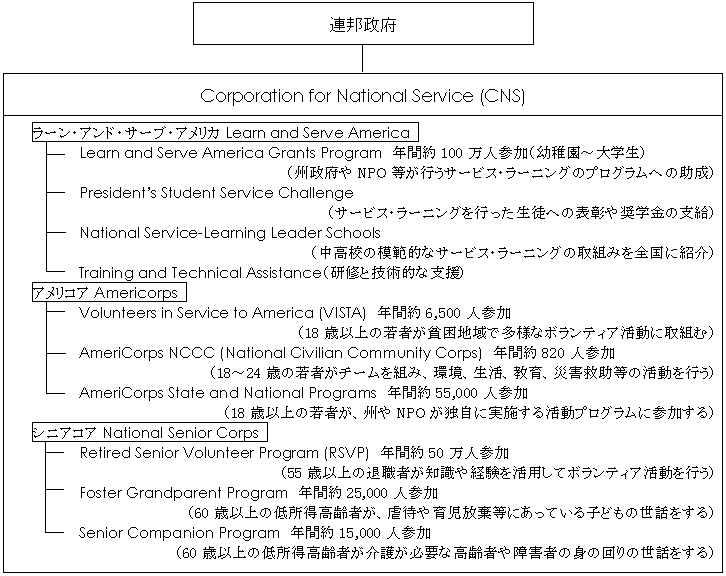| III.調査対象国ごとの要約 |
| |
|
| 1. |
アメリカ |
| |
|
| |
| ■ |
アメリカでは多数のNPOが活発に活動を展開しており、子どもから高齢者までの多様な人々の社会奉仕活動の実践の場となっている。連邦政府も、子どもや青少年、退職者、低所得高齢者を対象としたボランティア活動プログラムを実施している。 |
| ■ |
コミュニティのために活動をしようとする人は、身近なボランティア・センター等で自分にあった活動場所を調整してもらうことができる。活動の結果は、大統領や知事等の多様なレベルからの評価を受けることができるとともに、大学進学や就職の際に高く評価されることが多い。 |
| ■ |
近年、コミュニティのための活動を教育課程に採り入れて市民として必要な知識や経験を深めるサービス・ラーニングが注目されている。 |
|
|
| |
(1) |
社会奉仕活動に関する考え方 |
| |
|
社会奉仕活動に近い言葉に、ナショナル・サービスあるいはコミュニティ・サービス[15]があり、その概念はNational
and Community Service Trust Act of 1993によって定義された。 また、同法律は、すべてのアメリカ人に、国家あるいはコミュニティへの奉仕の実践を通じてアメリカ社会に貢献する機会を保証している。 |
| |
|
| 【コミュニティ・サービスとはNational and Community Service
Trust Act of 1993 Sec. 12501. Findings and purpose】 |
| ■ |
アメリカ社会全体が直面している社会福祉、教育、環境、治安等の緊急の課題に対して、すべての年齢の国民が協力して取り組むことである。コミュニティ・サービスを通じて、コミュニティを改善し、よりよい市民となることができる。 |
| ■ |
また、コミュニティ・サービスへの参加は、市民としての責任感を涵養し、ひいてはコミュニティ全体の意識の向上を図ることができる。 |
| ■ |
コミュニティ・サービスの担い手は、すべての国民であるが、法律では、低所得者層や青少年に焦点をあてている。特に、青少年は、コミュニティ・サービスの実践を通じて、自身の能力向上を図ることが期待され、かつ、将来的にはコミュニティのリーダーとなることが期待される。 |
|
|
| |
|
特に、青少年については、コミュニティ・サービスの教育的効果を重要視したサービス・ラーニングを通じて、健全で活力ある未来の社会を担う市民を育成するために、生きる力、社会的責任の理解、人間的成長、職業的な経験を得ることなどが期待されている。また、退職者や高齢者のように社会とのつながりが弱くなりがちな人々には、コミュニティ・サービスを通じて、社会への関与を強めていくことや社会に役立っているという経験を得ることが期待されている。
|
| |
|
| <National and Community Service Trust Act 1993によるサービス・ラーニングの定義> |
| ■ |
学生が、十分に組織化され、コミュニティのニーズに基づいた活動への積極的な参加を通じて、学習し発達するための一つの方法である。 |
| ■ |
小・中・高等学校、コミュニティ・サービス・プログラムおよびコミュニティと協働で行われるものである。 |
| ■ |
市民の責任感を育成することに資するものである。 |
| ■ |
学校カリキュラム等の一環として行われるものである。 |
| ■ |
参加者が活動経験について内省する決められた時間を確保する。 |
|
|
| |
|
| |
| 図表 1 |
全米の公立学校における、 生徒がコミュニティ・サービスに参加している学校の割合、 生徒がコミュニティ・サービスに参加している学校の割合、 生徒のためにコミュニティ・サービスの機会を提供している学校の割合、 生徒のためにコミュニティ・サービスの機会を提供している学校の割合、 生徒がサービス・ラーニングに参加している学校の割合 生徒がサービス・ラーニングに参加している学校の割合
|
|
| |
| 学校類型 |
学校数 |
 生徒がコミュニティ・サービスに参加している学校の割合 生徒がコミュニティ・サービスに参加している学校の割合 |
 生徒のためにコミュニティ・サービスの機会を提供している学校の割合 生徒のためにコミュニティ・サービスの機会を提供している学校の割合 |
 生徒がサービス・ラーニングに参加している学校の割合 生徒がサービス・ラーニングに参加している学校の割合 |
| 全体 |
79,750 |
64% |
57% |
32% |
| 小学校 |
49,350 |
55% |
49% |
25% |
| 中学校 |
14,398 |
77% |
71% |
38% |
| 高校 |
16,002 |
83% |
71% |
46% |
| 注: |
高校には、小中高校の一環教育を行う学校を含んでいる。このデータの学校の最高学年は最低で9年生である。 |
| 出典: |
”National Student Service-Learning and Community Service Survey
in spring 1999” National Center for Education Statistics November
1999 |
|
| |
|
|
| |
(2) |
社会奉仕活動に関する法律 |
| |
|
1993年に制定されたNational and Community Service Trust Act
of 1993や、1997年に制定されたThe Volunteer Protection Act(ボランティア保護法)がある。 |
| |
|
| <連邦政府による社会奉仕活動の振興策の経緯> |
| ■ |
1961年にケネディ大統領によって、開発途上国に対してアメリカの青年が援助活動を行う「平和部隊(Peace Corps)」が設立された。 |
| ■ |
1965年には、Economic Opportunity Act of 1964に基づき、平和部隊の国内版として、アメリカの青年が国内の貧困者への援助活動を行う「ビスタ(VISTA,
Volunteers in Service to America)」というボランティア活動プログラムが創設された。 |
| ■ |
1970年代には、国内ボランティア法Domestic Volunteer Service Actが制定され、VISTA、平和部隊、「退職高齢者ボランティア・プログラム(RSVP,
Retired Senior Volunteer Program)」(1971年に創設)などは、国内のボランティア活動の総合的推進を図る政府機関アクションACTIONに吸収されることとなった。 |
| ■ |
その後、1990年にNational and Community Service Act of 1990が、1993年にはNational
and Community Service Trust Act of 1993が制定され、連邦政府が社会奉仕活動を行うプログラムに助成することができるようになった。この助成を担当し、全米の社会奉仕活動を振興する機関として、Corporation
for National Service (CNS)が設置された。 |
| ■ |
また、1997年にThe Volunteer Protection Actが制定され、ボランティア活動中の事故においてのボランティア活動者の責任範囲が規定された。 |
|
|
| |
|
なお、National and Community Service Trust Act of 1993に基づいて、Corporation for
National Service (CNS)が設置されており、CNSを通じて各種のボランティア活動プログラムが実施されている[16]。 |
| |
|
|
| |
(3) |
制度による施策・事業 |
| |
|
連邦政府がCNSを通じて実施しているコミュニティ・サービスの活動プログラムは、次図表の通りである。 |
| |
|
| |
図表 2 CNSの組織構造と担当プログラムの概要 |
| |
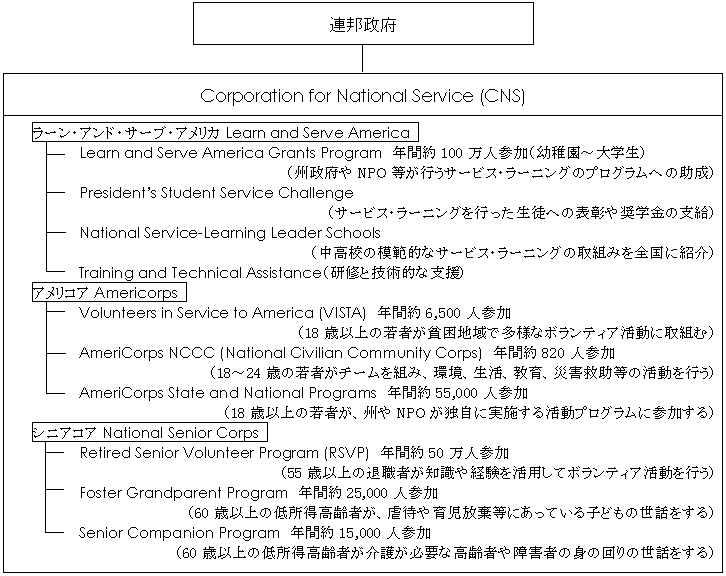 |
| |
|
|
| |
1) |
小・中・高校生を対象とした活動プログラム〜サービス・ラーニング |
| |
|
CNSは、学校や地域のNPOにおいて実施されるサービス・ラーニングの活動に助成している。また、実施主体に対して、サービス・ラーニングの考え方や成功事例等の情報提供を行ったり、相談に応じるなどの支援を行っている。CNSでは、サービス・ラーニングの分野として、教育、環境、社会の安全、その他の未解決なヒューマン・ニーズの4つを定めており、これらの分野での活動を通じて、以下のような成果を期待している。 |
| |
|
| <期待される成果> |
| ■ |
学業および職業訓練:テストの点数、GPAの点数、コミュニケーション技術、分析技術の向上、クラスへの参加、宿題の達成、やる気、仕事に対するスキルと姿勢、キャリアに対する知識の向上 |
| ■ |
社会:日常生活のスキル、問題解決能力、意思決定能力、リーダーシップ能力の向上、健全育成、自信の獲得、社会への適応能力、他者との協力関係の向上、薬物、アルコール、暴力などのリスクの軽減など |
| ■ |
人間関係:他者への思いやり、仲間との関係、教師と学生の関係の構築、文化的な違いの容認 |
| ■ |
市民性:市民としての責任感、市民としてのスキル等の向上 |
| ■ |
学校:積極的な学校の雰囲気づくり |
| ■ |
コミュニティ:学生と学校がコミュニティの構成員の一つであるという認識の向上 |
|
|
| |
|
|
| |
|
| <リーダー・スクール[17]の活動事例:リンデン高校(ニュージャージー州)> |
| ■ |
リンデン高校では、1994年にCNSからの助成金を受けて、サービス・ラーニングへの取組みが始まった。1994年の活動は、脳性小児麻痺のために車椅子の生活をしている学生達のために、美しい庭園を整備して、園芸療法の場を提供することであった。 |
| ■ |
1996年からは、脳性小児麻痺の子ども達の通う施設において、毎週勉強を教える活動を行っている。 |
| ■ |
別のプログラムでは、科学専攻の学生が、地域のナーシング・ホームに出向いて、老化のプロセスを学んだり、施設でのケアを手伝う活動を行ったりしている。ダンスの授業をとっている学生は、高齢者のために振りつけを創作し、ダンスのしかたを教えている。また、小学生に勉強を教える活動も行っている。 |
| ■ |
これらの活動は、地域の社会福祉施設、自治体の社会福祉担当部局、病院等との協力関係のもとに実施されている。 |
|
|
| |
|
|
| |
|
 メリーランド州の学校での取り組み メリーランド州の学校での取り組み |
| |
|
アメリカではサービス・ラーニングに取り組んでいる小中高校が多く、高校卒業の単位要件としている学校もみられる。特に、メリーランド州では、1993年から、州内の全ての高校において75時間のサービス・ラーニングを終了していることが卒業要件とされている[18]。なお、75時間には、準備・実際の活動・活動後の反省と熟考(サービス・ラーニングの3つの段階)の全てが含まれる。 |
| |
|
| |
図表 3学校区での対応例〜アン・アルンデル郡 |
| |
| 対応 |
報告方法 |
転校・転入への対応 |
| ・ |
5年生から10年生の間に、特定の授業に取り込んで実施する。 |
| ・ |
フェロー[19]と呼ばれる訓練された協力者を活用して実施している。 |
| |
<詳細> |
| |
5年生 |
社会科5時間 |
| |
6年生 |
学際的なチーム・プロジェクト10時間 |
| |
7年生 |
学際的なチーム・プロジェクト10時間 |
| |
8年生 |
学際的なチーム・プロジェクト10時間 |
| |
9年生 |
政治20時間 |
| |
10年生 |
英語10時間、科学10時間 |
|
各学年でのサービス・ラーニング終了時に報告カードを提出する。 |
| ・ |
転校の場合には、終了している活動時間を転出先の学校区に報告する。 |
| ・ |
11学年から転入してきた場合は、20時間の活動を行う。最終学年での転入は、学校長の指示に従う。 |
|
|
| |
|
|
| |
|
| <活動の具体例:フレデリック郡公立高校:中学生がニーズの高い人々への奉仕活動を行う> |
| 関連する学科:国語、社会、数学、科学対象学年:6年生 |
| ■ |
中学生が地域社会のなかの貧困問題について取り組むことを目的としている。 |
| ■ |
この活動プログラムは、サービス・ラーニングを初めて経験する生徒を対象として作成され、生徒は、この活動プログラムを通じて、将来学校内外で社会奉仕活動を行うためのスキル、自覚や自信を身につけることが期待されている。 |
| ■ |
生徒は、国語の時間に「クリスマス・キャロル」を読んで、貧困問題について考える機会を持った。 |
| ■ |
その後、幼児を抱えたシングル・マザーを支援するために、地域の行政の担当部署と協力して、どのような支援をしたらよいかを話あった。その結果、シングル・マザーが必要としている物品を決め、生徒自身でそれを集めて、シングル・マザーに直接的あるいは間接的に提供した。 |
|
|
| |
|
|
| |
|
| <活動の具体例:ハワード郡公立高校:ホームレスへの食事提供> |
|
| 関連する学科:算数対象学年:6〜12年生 |
|
| ■ |
この活動プログラムは、算数の課程のなかで実施され、参加した生徒は消費者として必要な算数のスキルを学ぶことを目的としている。また、メリーランド州の算数テストへの準備という位置付けもある。 |
|
| ■ |
この活動は、「ビジネス・スキル」とも呼ばれており、ビジネスの概念である利益、損失、総益、純益、割引、税金などについて学び、これを通じて、四則演算、小数、分数の考え方や計算技術を身につけるものである。 |
|
| ■ |
学生は、ホームレスの人々に食事を提供するために、資金調達を行い、地域のスープ・キッチンに寄付を行った。資金調達のために、ポスターを作成し、地元企業の名簿を作成して寄付を依頼する手紙を送った。この過程で、学生は、地域の様々な企業との接触することができた。 |
|
|
|
| |
|
| |
<サービス・ラーニングの支援機関 Maryland Student Service
Alliance (MSSA)> |
| |
メリーランド州では、各学校がサービス・ラーニングを実施するための支援機関として、MSSAを設置している。MSSAは、州内の24の学区を4地域に分類し、各々に地域プログラム・コーディネーターを配置している。このコーディネーターを通じて、サービス・ラーニングのプログラムの実施や質の向上のためのアドバイスや情報提供、実施のために必要な会合等の調整、教師への研修機会の提供などの支援を行っている。また、MSSAでは、サービス・ラーニングに関する様々な教材等を出版したり、活動の結果を評価するための指針[20]を設定して、ノウハウの普及を図っている。 |
| |
|
|
| |
|
 メリーランド州の地域のNPOでの取り組み メリーランド州の地域のNPOでの取り組み |
| |
|
学校以外では、地域のボランティア・センター等のNPOが中心となって、サービス・ラーニングを実施している。ボランティア・センター等でサービス・ラーニングに参加した生徒は、ボランティア・センターや受入先団体から活動証明書を発行してもらい、学校に提出して単位認定を受ける。 |
| |
|
| <ボランティア・セントラル(ボランティア・センター)でのプログラム実施上の工夫> |
| ■ |
メンターがついたチーム制によって受入団体に負担をかけない
6〜10人程度の子どもが一つのチームをつくり、そこに2人のメンター(指導者)がついて、貧困やホームレス等の地域の課題に取り組んでいる。メンターは、18歳以上の大人と12〜18歳までの青少年のボランティアであり、チームの子ども達の世話や指導・監督を行う。
|
| ■ |
子どもを活動プログラムの企画段階から参加させる |
| ■ |
地域の教育委員会、大学、公立の小中学校、NPO等との協力関係を構築して、活動の円滑化を図る |
|
|
| |
|
|
| |
|
 メリーランド州のサービス・ラーニングに対する評価と今後の課題[21] メリーランド州のサービス・ラーニングに対する評価と今後の課題[21] |
| |
|
サービス・ラーニングを高校の卒業要件とすることについて、導入当初は教職員等を中心として反対意見があったが、現在では成功事例が増加し、多くの教職員等の賛同を得ている。
州教育委員会では、サービス・ラーニングの導入段階をほぼ終了し、今後は質の向上を図る段階に入ってきたと認識している。このために、教職員の能力の向上、児童・生徒の自主性の確保[22]、ホーム・スクーリングの生徒への対応[23]などの課題に取り組んでいく必要があると考えられている。
|
| |
|
|
| |
2) |
18歳以上の若者を対象とした活動プログラム |
| |
|
CNSは、18歳以上の若者を対象として、アメリコアのプログラムと大学におけるサービス・ラーニングに助成を行っている。小中高校におけるサービス・ラーニングは主に市民として必要な知識や経験を習得することに主眼が置かれているが、大学でのサービス・ラーニングはより専門的な学業との関連が強いものとなっている[24]。メリーランド州立大学のように必修科目の授業の教育手法の一つにサービス・ラーニングを位置付けている大学[25]や、地元のNPOで一定期間インターンとして活動を行うことを義務付けている大学などがある。 |
| |
|
| |
図表 4アメリコアが実施するプログラムの概要 |
| |
| VISTA (Volunteers in Service to America) |
| ・ |
18歳以上の若者が、貧困地域において、健康、住居、教育・識字、環境、コミュニティ開発、飢え、犯罪防止・安全の確保、家庭内暴力などの分野でのボランティア活動に取組む。 |
| ・ |
貧困地域において活動しているNPOのボランティアとして活動することが多い。具体的には、NPOの運営管理、ボランティア・プログラムの作成、プログラムに必要な資金調達などの活動を行っている。 |
| ・ |
18歳以上の若者が対象。VISTAボランティアは他のアメリコアのプログラムとの兼務はできない。 |
| ・ |
約6,500人参加 |
| ・ |
貧困地域において活動しているNPOが受入先となる。VISTAボランティアを受入れるNPOにとっては、一定の教育水準を満たしているボランティアを一定期間確保することとなる。 |
| ・ |
ボランティアは、プログラム終了後に、年に4,725ドルの報酬を支給される。 |
| AmeriCorps*NCCC (National Civilian Community Corps) |
| ・ |
若者が10〜12人がチームを編成し、全米の5つのキャンプ[26]で共同生活を行いながら、環境、生活、教育、災害救助、安全などの分野での実際のサービス提供を行う。 |
| ・ |
VISTAボランティアがNPOの組織運営を支援するボランティアを行うのに対して、NCCCボランティアは、直接サービス提供に従事する。 |
| ・ |
18歳から24歳までの若者が対象。年間約820人の若者が活動。 |
| ・ |
活動期間は10ヶ月間 |
| ・ |
NCCCボランティアは10ヶ月間ボランティア活動を行い、その間に、週に100ドルの小遣いが支給される。 |
| AmeriCorps*State and National Programs |
| ・ |
州政府やNPOに補助金を配分し、各々が独自に実施するプログラムにおいてボランティア活動を行う。具体的には、高校の授業の面倒をみるなどの直接サービスに従事する。 |
| ・ |
18歳以上の若者。VISTAボランティアやNCCCボランティアは他の仕事との兼務はできないが、このプログラムのボランティアは兼務が可能。 |
| ・ |
55,000人の若者が参加している。 |
| ・ |
ボランティアは、プログラム終了後に、年に4,725ドルの報酬を支給される。 |
| ・ |
低所得者向け住宅の中でPCの使い方を教えたり、情報弱者への対応を行うなど、IT関連の活動プログラムが見られるようになってきた。 |
|
| |
|
|
| |
|
| <ボランティア・メリーランド(アメリコアの活動プログラムの実施主体の一つ)にみる活動プログラムの評価と今後の課題> |
| ■ |
評価:プログラムの活動者と受入団体の両方に3年間の時限で追跡調査を行っている。この結果、活動者の9割超が、活動終了もなんらかのボランティア活動を行っている。また、受入団体の9割は、今後も活動者を受入れていきたいと希望している。 |
| ■ |
今後の課題:今後ともよりよい受入団体や活動者を確保して質の高い活動を実施することが課題である。また、プログラムの持続可能性を確保するために、スタッフの能力の向上とともに、財源を多様化して政基盤の安定化を図っていくことも課題である。 |
|
|
| |
|
|
| |
(4) |
民間主導による社会奉仕活動 |
| |
|
アメリカでは、多くのNPO[27]がボランティアを活用しながら、コミュニティの課題に取り組む活動を行っている[28]。NPOが提供する多様な活動の機会が、アメリカ国民にとって、コミュニティ・サービスやボランティア活動に参加する身近な機会となっている。
コミュニティ・サービスやボランティア活動を行いたい人は、地域のNPOに直接申込むか、あるいは、身近なボランティア・センターに出向いて自分にふさわしい活動を紹介してもらう。
1998年には18歳以上のボランティア活動者数は109百万人を超えて過去最高の水準となり、全米の18歳以上人口の56%がボランティア活動に参加したとされている[29]。
|
| |
|
| <アメリカ赤十字の例> |
| ■ |
アメリカ赤十字では、約120万人のボランティアが活動しており、これはアメリカ赤十字のスタッフ総数の97%以上を占めている。 |
| ■ |
ボランティアの年齢・職業は多様であるが、24歳以下の青少年が全体の40%以上を占めている。 |
| ■ |
青少年には、災害救助、他国の赤十字等で活動する国際活動、健康と安全サービス(エイズ教育、応急手当、心肺停止の蘇生救急、水難防止などの教育を受けるとともに、仲間に教えられるようにインストラクターになる)、軍隊での緊急サービス(全世界の軍施設のなかの診療所や病院でのボランティア活動)、献血(17歳以上)、学校での赤十字活動などの活動機会が提供されている。 |
|
|
| |
|
|
| |
|
| <YMCAの例> |
| ■ |
YMCAは、アメリカで最も大規模な非営利のコミュニティ・サービスの実施団体の一つである。YMCAでは、活動プログラムを通じて、他人への思いやり、正直、尊敬と責任といった価値観を構築することができると位置付けている。 |
| ■ |
活動プログラムは、健康増進のための運動、キャンピング、子どものケア、コミュニティづくり(職業訓練、薬物乱用防止など)、家族への支援、高齢者への支援、国際活動などであり、大半がボランティアによって運営されている。 |
| ■ |
ボランティアには、プログラム・ボランティア(プログラムの実施を担当)、サポート・ボランティア(事務所のなかで、受付等の事務を担当)、基金ボランティア(資金調達のためのイベント等を担当)、ポリシー・ボランティア(組織や事業の方針や計画の策定)、管理ボランティア(組織の管理や運営を担当)といった種類があり、プログラムに中心的に関わるボランティアだけでも541,036人に上っている(2000年)。 |
|
|