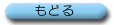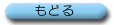中央教育審議会では、こうした教養の歴史も踏まえながら、今後の新しい時代に求められる教養とは何か、また、それをどのようにして培っていくのかという観点から審議を行った。
答申では、まず、第1章において、今なぜ教養について考える必要があるのか、その背景を述べ、第2章において、新しい時代に求められる教養の概念について整理を行った。その上で、第3章において、すべての人が生涯にわたって教養を広げ、高め、豊かな生き方を実現するために求められる方策について、個人の生涯の段階を 幼・少年期、
幼・少年期、 青年期、
青年期、 成人期に分け、それぞれの段階ごとに求められる教養の課題を提示しつつ具体的に提言した。
成人期に分け、それぞれの段階ごとに求められる教養の課題を提示しつつ具体的に提言した。
この答申が、今後の激しい変化の中で、一人一人が自らの生き方を主体的に打ち立てる力を培う支えとなり、また、新しい時代にふさわしい品格を備えた教養社会の実現に向けての取組を推し進める一助となることを切に願うものである。
これらの大きな社会的変動の中で、既存の価値観が大きく揺らいでいる。一方で、新たなモラルや、これからの社会、その中で生きる個人の姿は明確になっておらず、個人も、社会も、自らへの自信や将来への展望といったものを持ちにくくなっている。
社会全体に漂う目的喪失感や閉塞感の中で、学ぶことの目的意識が見失われ、まじめに勉強したり、自ら進んで努力して何かを身に付けていくことの意義を軽んじる風潮が広がっている。特に子どもたちや若者に、自ら学ぼうとする意欲が薄れているとの指摘がなされている。こうした傾向の広がりは、我が国社会の活力を失わせ、その根幹をむしばむ危機につながるものと危惧せざるを得ない。
このような時代においてこそ、自らが今どのような地点に立っているのかを見極め、今後どのような目標に向かって進むべきかを考え、目標の実現のために主体的に行動していく力を持たなければならない。この力こそが、新しい時代に求められる教養であると考える。
| (2) |
具体的な方策 |
 |
家庭や地域で子どもたちに豊かな知恵を育てる |
|
教養教育の原点は家庭教育である。その重要性は、どんなに社会が変化しようと変わるところはない。
また、地域社会において、子どもが他者と触れ合う中で、人間関係や集団のルール、公共心や規範意識などを身に付けることができるよう、社会全体で子どもを育てる環境づくりを進める必要がある。
平成14年度からの完全学校週5日制を意義あるものにするためにも、家庭や地域の教育力の向上は緊急の課題であり、取組の一層の充実が必要である。
|
|
| ◇ |
家庭での日常生活を基本にした教育の充実 |
|
各家庭における子どもの日常生活を大切にすべきである。例えば、絵本や昔話の読み聞かせ、家庭での年中行事や地域の行事への積極的な参加、子どもに毎日決まった手伝いをさせるなど家庭での役割を与える、テレビやゲームに費やす時間を制限するなど、規律ある生活習慣を身に付けさせるための「我が家のきまり」づくりなどを奨励する必要がある。 |
| ◇ |
文化施設・社会教育施設の子どもの教養教育の資源としての積極的な活用 |
|
美術館や博物館、図書館等が子どもの教育に取り組むことは、子どもの教養の涵養にとっても、これら施設の活性化にとっても意義が大きい。例えば、美術館や博物館における子供向けの館内ツアーや参加・体験プログラムの実施、土・日曜日における学校図書館の開放を積極的に進める必要がある。また、これら施設に対する評価の実施に際し、子ども向けの取組状況を積極的に評価することも求められる |
| ◇ |
地域社会における子どもの居場所づくりの推進 |
|
地域で子ども同士が思い切り遊んだり運動したりすることのできる場や、自然と触れ合うことのできる場の整備、親子で参加できるスポーツ活動や地域行事の充実など、子どもが地域で伸び伸びと育つことのできる環境づくりを推進する必要がある。 |
|
|
 |
確かな基礎学力を育てる |
|
多様な個性の基盤には、基礎的・基本的な知識・技能が不可欠である。子どもの個性や自主性の重要性を強調するあまり、基礎的・基本的な知識・技能を繰り返し教える指導をも「一方的に教え込む」ものとして、好ましくないとする見解も一部にある。しかし、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、それを基盤として、更なる自主的学習につなげることによってはじめて、多様な個性も伸ばすことができるものである。各学校は、すべての児童生徒が、「読み、書き、計算」をはじめとする基本的な事項を確実に習得し、学習する習慣や物事に粘り強く取り組む態度、科学的にものを考える力や態度を身に付けることができるよう、全力を注いで指導する必要がある。
|
|
| ◇ |
基礎学力の徹底のためのきめ細やかな指導の充実 |
|
読み・書き・計算などの基本的な事項を徹底するため、各学校では、反復練習や個別の家庭学習の課題の設定、放課後の個別指導や補習などのきめ細やかな指導を行う必要がある。このため、社会人や大学生等をティーチングアシスタントとして積極的に活用するべきである。中学校や高等学校の教員が、小学校や中学校での指導に参加することも有意義である。あわせて、教職員定数の更なる改善を図る必要がある。 |
| ◇ |
国語教育や読書指導の重視 |
|
国語教育を一層重視する必要がある。その際、素読や暗唱、朗読など、言葉のリズムや美しさを体で覚えさせるような指導の良さを見直すべきである。また、近年多くの学校に広がっている「朝の10分間読書」は、読書の楽しみを知るだけでなく、集中力の向上などにも大きな成果があると言われ、このような活動が更に広がっていくことが期待される。あわせて、司書教諭の配置やボランティアの活用、情報機器の整備などを通じ、図書館の総合的な機能の充実に取り組んでいく必要がある。 |
| ◇ |
取組を検証する仕組みづくり |
|
確かな基礎学力を育てるための取組をより実効あるものとするためには、絶えずその成果を検証することが重要である。このため、各学校において、学校の教育活動の自己点検・評価に取り組む必要がある。また、全国的な学力調査の実施を通じ、児童生徒の学習到達度を把握するとともに、その結果を踏まえた改善策を速やかに講じる必要がある。さらに、論理的思考力や応用力等の評価方法の研究等にも取り組むべきである。 |
|
|
 |
学ぶ意欲や態度を育てる |
|
学ぶことの意義や目的を見出し、自ら進んで学び考え、物事に挑戦しようとする意欲や態度を育てることは、この時期の大きな教育課題の一つである。
子どもたちが、自然との触れ合いや体験の中で、物事に興味・関心を持ち、知的好奇心を伸ばすこと、尊敬できる大人と出会う機会を得て、学ぶことや大人になることの意味を実感したりすることができるよう、取組を推進する必要がある。
|
|
| ◇ |
子どもたちの知的好奇心を喚起する取組の促進 |
|
授業に実験やものづくりの実習等、各種の体験活動を多く取り入れる、学校の卒業生など地域で活躍する人材を講師として活用する、異年齢の子どもたちで学習する機会を設けるなど、子どもたちの知的好奇心を呼び起こし、集中力を高め、学ぶことの意味を実感することができるような指導方法の工夫改善に取り組む必要がある。その際、美術館や博物館、劇場、地域の文化財、図書館等を活用することも有効な方策である。また、各種のメディアを活用しながら、情報を活用する能力を身に付けることも重要である。 |
| ◇ |
学ぶ進度等に応じた指導の充実 |
|
発展的な学習や補充的な学習など、子どもの学習の進度に応じた指導を行い、子どもの学ぶ意欲を育てる必要がある。特に、発展的な学習に関する指導方法の開発や、学習の過程で子どもがつまずきやすい事項を分析し、指導を改善するための実践的研究を行い、その成果を学校における指導に積極的に取り入れていく必要がある。また、指導に当たっては、それぞれの子どもの長所を見つけ、適切にほめることが、意欲を高め、その長所を更に伸ばすことにつながることを重視すべきである。 |
|
|
 |
豊かな人間性の基盤を作る |
|
豊かな人間性や、社会との関係で自己を位置付ける力などの基盤は、幼・少年期において培われる。特に、子どもの時期の体験は、その人の人格形成やその後の生き方に大きな影響を与える。学校、家庭、地域社会が一体となって、多様な体験活動の機会を提供するとともに、道徳教育の充実などを通じ、子どもたちに豊かな心を育んでいく必要がある。
|
|
| ◇ |
道徳教育の充実 |
|
学校教育全体にわたる道徳教育を充実し、人間として生きていく上で必要な基本的態度を育てる必要がある。このために、豊かな人生経験を持つ社会人や一つの道を究めた専門家に学校での道徳教育への参加を求めたり、すぐれた文学作品や映像作品を教材として活用することも有効である。自然の中で生き物を見つめたり、四季の移り変わりに生と死の循環を感じたりするなどの体験や、様々な分野での社会奉仕体験などの体験を通じて、豊かな心を育むことも重要である。 |
| ◇ |
知・徳・体の調和のとれた育成 |
|
古典や歴史なども含めた文化・芸術や、様々なスポーツ等を体験させ、豊かな感性や、たくましく生きるための体力や精神力など、知・徳・体の調和のとれた人格を育てることが重要である。例えば、演劇のように、五感を働かせ、体を使う活動は、体そのものの使い方や制御の仕方を学び、集中力や想像力、コミュニケーション能力などを高める上で有効である。こうした活動を教育活動に積極的に取り入れていくことが望まれる。 |
|
|
 |
教員の力量を高める |
|
児童生徒の教育に当たり、教員の与える影響は計り知れない。子どもたちに教養の基礎を培っていくためには、教員一人一人が、生涯にわたって教育者として力量を高めるとともに、常に向上心を持って教養を磨くことが必要である。教員の養成・採用・研修を通じて、一貫してこの姿勢を重視する必要がある。 |
|
| ◇ |
教員の研究や自己啓発活動の奨励 |
|
教員が自ら研究したり、読書等を通じて自己研鑽に励む姿は、子どもたちにあこがれの気持ちを抱かせ、向学心を高めるなど良い影響を及ぼす。教員の研究活動を奨励したり、教員用の図書や映像資料を充実したり、校内で教員と子どもが一緒に読書できるスペースを充実するなどの取組が求められる。 |
| ◇ |
社会体験研修の大幅な拡充等教員研修の抜本的充実 |
|
教員研修の抜本的な充実が必要である。とりわけ、教員に幅広い視野を確保するため、社会体験研修、ボランティア体験研修や、青年海外協力隊等への派遣を大幅に拡充することが必要である。また、完全学校週5日制の実施に伴い、教員は地域の一員として地域活動やボランティア活動に積極的に取り組むべきである。 |
| ◇ |
評価等の促進 |
|
保護者や地域の住民等への授業の公開をはじめ、多様な観点から授業の改善のための評価を受けることは、教員の自己啓発を促し、力量を高める上で意義深いものであり、積極的な導入が期待される。あわせて、各都道府県教育委員会等における勤務評定の評価方法等の工夫、表彰制度や特別昇給の実施等を通じて、優秀な教員を適切に評価しその処遇の改善を図っていくことも求められる。 |
|
|