- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 中央教育審議会 > 教育制度分科会 > 地方教育行政部会 > 地方教育行政部会(第12回) 配付資料 > 資料1 教育委員会制度及び県費負担教職員制度の運用実態に関する調査 > 3.意向の調整や意見聴取の活動状況
3.意向の調整や意見聴取の活動状況
3‐1 政令指定都市教育委員会と県教育委員会および教育事務所との意向調整
政令指定都市の場合、都道府県や教育事務所で必要とされるような、市町村教育委員会との意向の調整は想定されない。ただし、政令指定都市と近隣市町村との間に異動が想定されている場合などには、相互の調整等が必要となる。
一般教員に関して
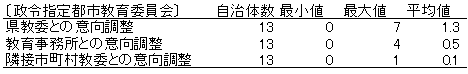
学校管理職に関して
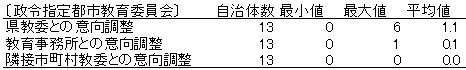
政令指定都市と県での意向調整については、都市間で相当のばらつきがみられた。一方で、教育事務所や市町村教委との意向調整については総じて低調であり、先に確認した異動範囲の状況と同様に、政令指定都市が独立して教職員人事を進めていることがわかる。
3‐2 書類による意向調査の実施状況
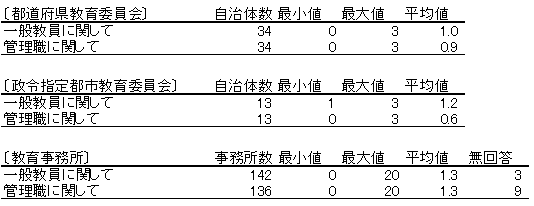
都道府県では、一般教員・管理職を問わずほとんどの自治体において意向調査は「1回」という回答であった。政令指定都市でも「1回」という回答が多かったが、管理職に関しては平均値も低く、意向調査を特に行っていないという政令市も散見された。教育事務所でも、一部の例外を除きほとんどが1回から3回という回答であった。
ここで都道府県における0回という回答については、教育事務所が主体となって調査を行うため都道府県教育委員会では実施しないという場合がある。同様に教育事務所における0回という回答については、都道府県教委が主体となって調査を実施する場合がある。
3‐3 人事異動に関するヒアリングの実施状況
都道府県教育委員会でのヒアリング実施状況
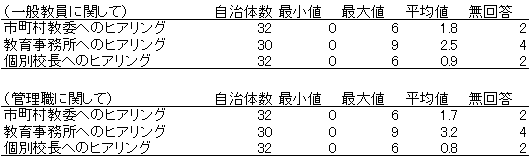
書類による意向調査の実施状況と同様に、「0回」と回答した都道府県の場合、ヒアリングの実施主体が教育事務所となる(そのため県教委としては実施しない)というケースがある。都道府県教委としては、教育事務所に対するヒアリングを多く取る傾向があり、市町村教委へのヒアリングについてもある程度機会が確保されている。一方で、都道府県教委から個別校長に対する直接のヒアリングはあまり想定されていない。書類調査よりも活動状況が活発であると言うことができる。
教育事務所による市町村教委へのヒアリング実施状況
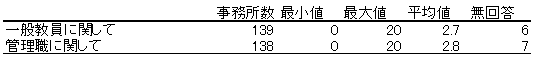
都道府県教育委員会が実施する回数よりも多くの回数を市町村教育委員会に対するヒアリングに割いているという状況がわかる。都道府県教育委員会が人事権者として教職員の異動を実施する上で、教育事務所の担う役割が単なる情報の伝達役にとどまらないことは他の項目でも指摘したが、この項目ではその役割にあわせた情報収集や調整といった活動の状況が明らかになった。
教育事務所による各学校長へのヒアリング実施状況
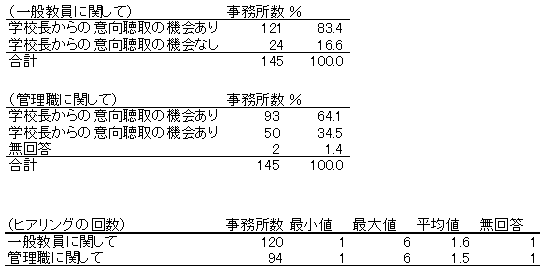
市町村教育委員会による学校長からの意向聴取とは別に、教育事務所が独自に個別の学校長から意向や要望を聴取しているという回答が多くみられた。特に一般教員の異動に関してはこのような活動が広く行われている。ここからも、都道府県教育委員会(本庁)の活動を補完し、教員の人事行政について一定の役割を分担しているという教育事務所の活動状況が明らかになった。
政令指定都市教育委員会による各学校長へのヒアリング実施状況
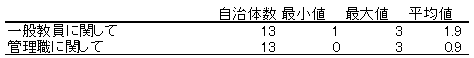
政令指定都市教育委員会においても、3‐2で整理した「書面による意向確認」よりも若干多い回数をヒアリングの機会として確保していることが分かる。
なお、政令指定都市教育委員会が行うヒアリングは市町村教委や教育事務所を対象とするのではなく、個別の学校長を対象とするものとなる。これを都道府県教委が実施するものと比較すると、特に一般教員に関してはヒアリングの回数が多い。また教育事務所の活動と比較しても一般教員に関するヒアリングの回数は若干多い結果を示している。
3‐4 学校長からの意見具申の取り扱い状況
一般教員に関して
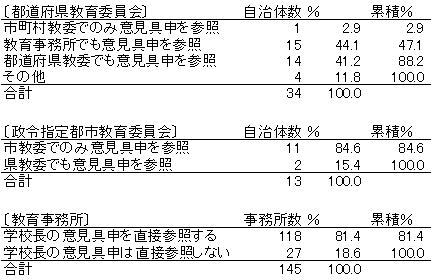
制度上、市町村教育委員会が都道府県教育委員会に内申を行う際、個別学校長からの意見具申を添付するものとされている。調査結果からは、学校長からの意見具申は実際にも市町村だけではなく、教育事務所や都道府県教育委員会においても参照され、異動事務で参考とされている状況がわかる。
学校管理職に関して
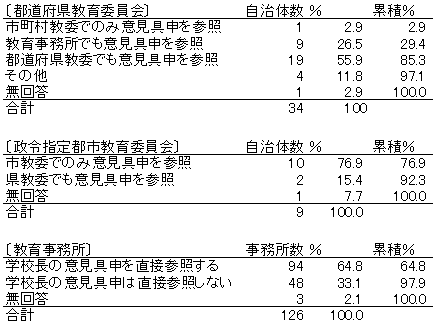
一般教員の異動事務と比較して、学校管理職の人事に際しては意見具申を教育事務所ではなく都道府県教委で参照する傾向が強い。これは、一般教員以上に都道府県教育委員会(本庁)が広域人事の担い手として機能していることを示すものである。
3‐5 各種団体(校長会や教職員団体等)からの意見聴取や調整の状況
一般教員に関して
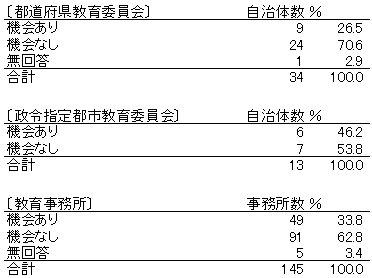
学校管理職に関して
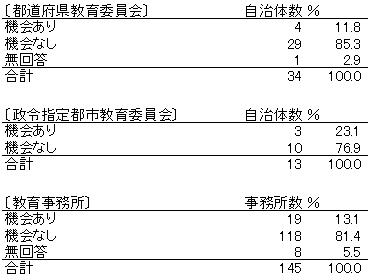
校長会や教職員団体から意向を聴取する機会を設けている都道府県や政令指定都市は比較的少数にとどまり、教育事務所単位で見てもこの傾向は同様であった。一般教員の人事についてもこうした傾向は確認できたが、学校管理職の人事に関する回答を見るとこの傾向が一層強く出ており、ほとんどの都道府県・政令指定都市は校長会や教職員団体から意向聴取を行っていない。
3‐6 意向調整における問題点(自由記述回答より)
調整手続きに関するものと、個々の意向に関する問題に記述が集中した。
都道府県・政令指定都市教育委員会
調整に要する事務手続きに関するもの…7件
- 「県教委の人事異動方針に基づいた異動を推進しているが、異動に当たっては、市町村教育委員会の理解を得ることに多くの時間を要する」
- 「意見の調整については、基本的には教育事務所で行っているが、教員数の多い中核市の意思調整に時間を要する」
- 「市町村の議会の時期と重なり、意見調整の時間確保が難しい」
個々の意向に関するもの…3件
- 「一般教員の人事異動において個人の意向を尊重してきた経緯があり広域的な人事交流が難しくなっている」
- 「異動希望先が、特定の都市部に集中しがちである」
- 「県及び教育事務所との協議においては、双方合意が前提となる為、異動規模が小さくなる」
教育事務所
調整に要する事務手続きに関するもの…32件
- 「各学校長の意向が多すぎて、調整が困難である」
- 「管内では定数に対して教員の数が多い過員状態なので学校や市町教委の意向の調整に多くの時間を要する」
- 「個人の意向に添わない異動を行う場合、調整に多くの時間を要する」
- 「人事担当者がいる市教委との調整が難しい。(活発な人事交流が停滞しがち)」
- 「ヒアリング時での確認事項と実際の異動時前の意向が変わることがあり、調整に手間どることがある」
- 「特に管理職採用について、各市町村教委との意向調整に時間を要している」
- 「他管内との交流に関して調整に多くの時間を要する」
- 「複数の市町村を管轄しているので、各市町村教委の意向の調整に手間取る」
意向の不均衡や地域格差に関するもの…28件
- 「指導力不足傾向のある教員をとりたがらず、最後までもつれることがある」
- 「力量のある教員を永年になっても残しておきたく、異動に難色を示される場合がある」
- 「指導力不足等教員などの課題のある教員に対して、校長が指導を進めず、安易に異動転出により解決をはかろうとするケースが多いので、校長・市町村教委を指導することが多い」
- 「へき地への人事確保」
- 「異動対象者の意向のない、他市町村への異動が行いにくい」
- 「異動希望が都市部に集中し、郡部で人材不足が生じる」
- 「各市町村独自の人事異動に関する課題をかかえているため、その事を考慮すると、市町村間の人事の公正さ、公平さのバランスが崩れることもある」
お問合せ先
生涯学習政策局政策課