- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 中央教育審議会 > 教育制度分科会 > 地方教育行政部会 > 地方教育行政部会(第12回) 配付資料 > 資料1 教育委員会制度及び県費負担教職員制度の運用実態に関する調査 > 2 市区町村教育長調査にみる小規模自治体教育委員会の運用実態
2 市区町村教育長調査にみる小規模自治体教育委員会の運用実態
つぎに、市区町村教育長調査を用いて、小規模自治体の教育委員会の無力論を検証する。ここでも、人口規模と教育委員会の運用実態にかかわる変数との間にみられる統計的に有意な関係に注目しつつ、小規模自治体教育委員会についての示唆を得たい。
(1)人口規模別にみた改革進展度
小規模自治体教育委員会が教育改革の進展に無力であるのか否かを検証するために、ここでは、各教育委員会の改革の進展度を示す質問項目をいくつか用意し、その質問への回答をもとに改革進展度を示す変数を構成して、それを従属変数とし、人口規模を説明変数としてクロス集計を行った。各教育委員会の改革の進展を示す質問項目は、学校に関係する改革、とりわけ、学校支援に関わるものに教育委員会がどう取り組んでいるかに関するものから構成されている。具体的に質問項目の主なものをあげると以下の通りである。
- 各学校における裁量権の拡大に関する質問項目(校長裁量予算の配分、教員人事における意見具申の方法・手続きの見直しの実施など)、
- 直接的に学校の組織能力の開発に関わる質問項目(地域独自の副教材の作成、地域人材活用予算の措置の実施など)、
- 間接的に学校の組織能力の開発に関わる質問項目(学習情報ネットワークの構築、学社連携担当職員の配置など)、
- 手引書の作成など財政的な資源よりも人材とその労力に依存する質問項目(学力向上プランの作成、自己点検・自己評価の手引書の作成など)
その結果は、人口規模が小規模ほど改革進展度の低い教育委員会の数が増加している。改革進展度の高い教育委員会と低い教育委員会の割合は、3~5万人の部分で逆転し、特に、5万~10万人を境として、その傾向はより明確となっている。そして、20万人以上の教育委員会では、実にその96.8%が改革進展度が高い層に属している。このことは、地方自治体が一定規模、少なくとも10万人前後の人口規模を有していることが、改革を進めていく上で必要な環境のひとつの目安であることを示している。

さらに教育委員会会議の活発度(1‐2‐(2)を参照)と人口規模とのクロス集計を行ってみると、人口規模が小さくなるほど、会議が不活発の層に属する教育委員会が増加しているという結果となった。人口規模が3万人未満の自治体の教育委員会では、その過半数が会議が不活発の層に属しているのに対して、それ以上の人口規模の自治体の教育委員会では、過半数が会議が活発な層に属している。
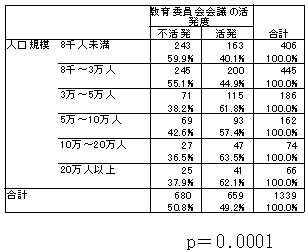
(2)教育委員の役割
教育委員の役割(1‐3‐(5)を参照)について人口規模別に見ると、「政策アイデアの提供」の項目に関して、人口規模が小さくなるほど、「あてはまる」と回答する教育長が少なくなるという結果となった。また、両項目に関しては、人口規模が小規模になるほど、「あてはまらない」の割合が大きいものとなっている。
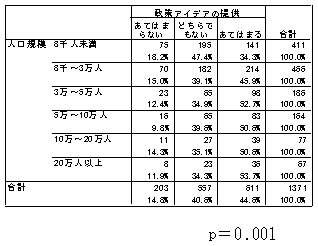
同様の質問に対する教育委員長調査のデータ(1‐3‐(1)を参照)によれば、「教育政策のアイデアを述べる」は比較的人口規模の小さい自治体の教育委員長で「あてはまらない」との回答がやや多い傾向がある。一方で、「PTA等の地域団体との調整において役割を担う」については、比較的小規模の自治体で「あてはまる」「よくあてはまる」と回答する委員長がやや多く見られる。
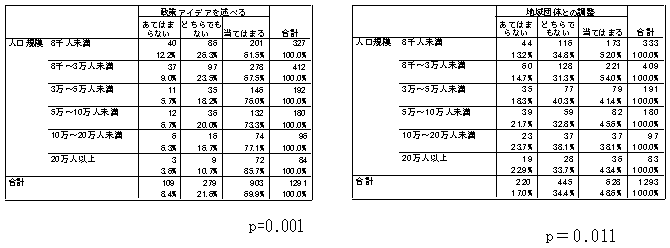
(3)教育委員会事務局の果たしている役割
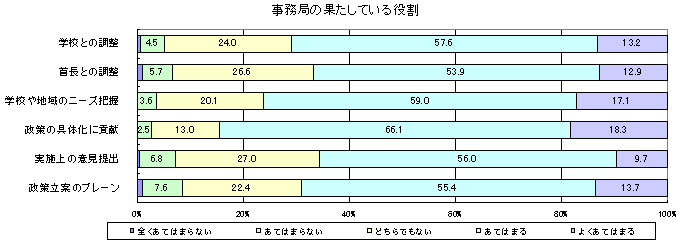
| 全くあてはまらない | あてはまらない | どちらでもない | あてはまる | よくあてはまる | 市町村平均 | 都道府県平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校との調整 | 0.7 | 4.5 | 24.0 | 57.6 | 13.2 | [3]3.78 | [2]4.32 |
| 首長との調整 | 1.0 | 5.7 | 26.6 | 53.9 | 12.9 | [4]3.72 | [5]3.97 |
| 学校や地域のニーズ把握 | 0.1 | 3.6 | 20.1 | 59.0 | 17.1 | [2]3.89 | [5]3.97 |
| 政策の具体化に貢献 | 0.1 | 2.5 | 13.0 | 66.1 | 18.3 | [1]4.03 | [1]4.50 |
| 実施上の意見提出 | 0.4 | 6.8 | 27.0 | 56.0 | 9.7 | [6]3.68 | [3]4.21 |
| 政策立案のブレーン | 1.0 | 7.6 | 22.4 | 55.4 | 13.7 | [5]3.70 | [4]4.18 |
教育長の認識している事務局の役割に関しては、準備した全ての項目で「あてはまる」と「よくあてはまる」を合計した割合が過半数以上を占める結果となった。特に高得点であったものは「政策の具体化に貢献(平均値4.03)」であり、「あてはまる」と「よくあてはまる」をあわせて84.4%にのぼる。最も得点が低い「実施上の意見提出(平均値3.68)」でも、「あてはまる」と「よくあてはまる」をあわせると、65.7%となった。その他の項目については、「学校や地域のニーズ把握(平均値3.89)」、「学校との調整(平均値3.78)」、「首長との調整(平均値3.72)」、「政策立案のブレーン(平均値3.70)」の順となっている。
教育委員会事務局の果たしている役割についての質問項目への回答と、人口規模とのクロス集計を行ったところ、全ての項目で、人口規模が小さくなるほど「あてはまる」と回答した教育長の割合が減少するという結果となった。質問項目は、教育委員会事務局の活動に関して肯定的なものとなっていることから、人口規模の小さな自治体ほど、教育委員会事務局の活動が活発ではない可能性が高いことが理解できる。
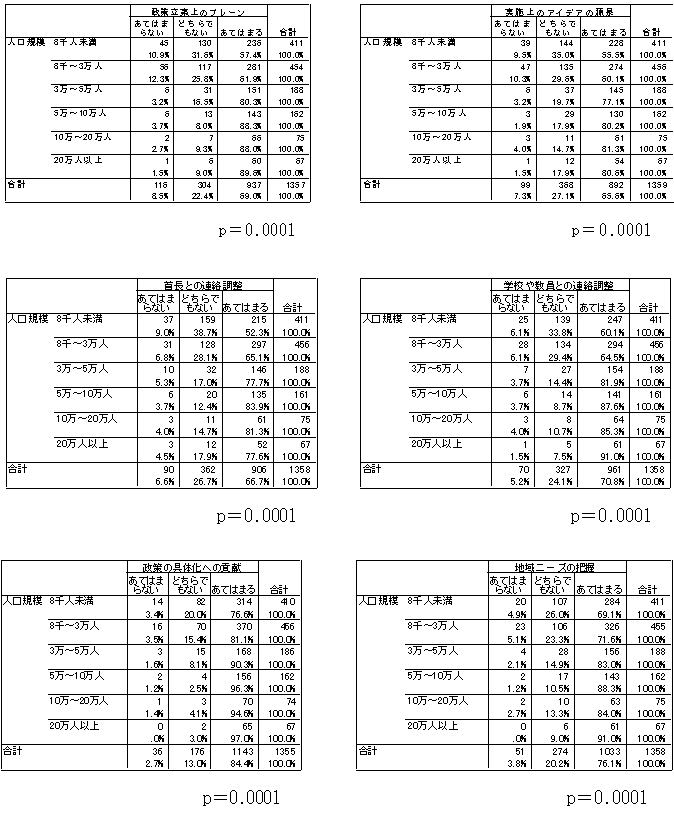
(4)首長と教育長の関係
幹部会への出席頻度と人口規模とのクロス集計を行ってみると、8千人未満の自治体と8千~3万人の自治体で、12回以下の教育委員会が50%前後にのぼっていること、そしてその割合は、人口規模が大きくなるほど減少していくこと、そして、幹部会に1年間に49回以上(週1回以上)出席している教育委員会の割合が、自治体規模が小さくなるほど減少していくという結果となった。
首長との個人的なつきあいについては、人口規模とのクロス集計を行ったところ、人口規模が小さくなるほど、就任以前からのつきあいがある割合が増えていくことが分かる。そして、人口規模が大きくなるに従って、つきあいがないと答える教育長の割合が増加するという結果になった。
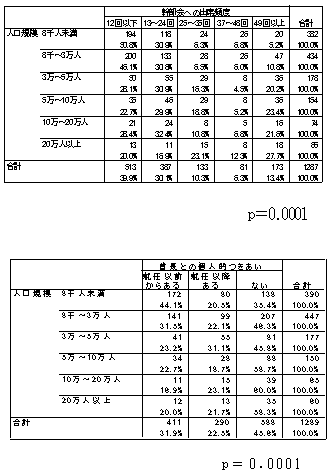
(5)地域住民のニーズに対応した行政の推進
教育長に、地域教育懇談会などの、地域住民の参加する集会に出席しているかどうかを聞いたところ、84%の教育長が「よく出席する」あるいは「時々出席する」と回答している。「よく出席する」を1点、「全く出席しない」を5点としたときの平均点は1.85である。多くの教育長が地域住民が参加する集会に出席していることが明らかとなった。
本項目の回答と人口規模との間のクロス集計を行うと、人口規模が小規模であるほど、住民の集会に出席する教育長が多いという結果となった。
以上の分析からは、住民集会への参加といった点から見ると、小規模自治体の教育長の方が、地域住民のニースに敏感であるということが理解できよう。
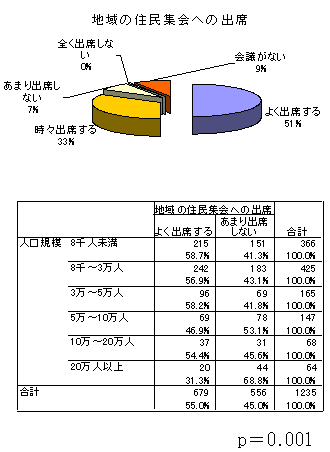
お問合せ先
生涯学習政策局政策課