- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 中央教育審議会 > 教育制度分科会 > 地方教育行政部会 > 地方教育行政部会(第11回) 配付資料 > 資料1 教育行政制度に関する米国調査について > 1 米国における教育委員会制度の概要
1 米国における教育委員会制度の概要
1.教育委員会の責務・活動実態
(1)会議
- 州及び学区の双方において、教育委員会の最も主要な活動は定例の会議。州レベルでは年12~14回程度、学区レベルでは月に2回あるいはそれ以上の頻度で開催。
- 1回の会議の審議時間は、州レベル(メリーランド州の場合)では1日半(初日は午前9時頃から午後5時頃、二日目は午前9時頃から正午頃)、学区レベル(モンゴメリー学区の場合)では終日(午前9時頃から午後5時頃)あるいは夕方からの2~3時間(午後7時頃から午後9時あるいは午後10時頃。案件によっては深夜に及ぶこともある。)。
- 審議内容は、州レベルでは州内共通の初等中等教育の枠組み(教育課程の基準、ハイスクールの修了要件、教員免許制度等)を、学区レベルでは所管公立学校の運営に直接関わる事項(カリキュラムやテスト、施設設備の管理、教職員人事等)を審議。
- 最も重要な審議内容は予算。州や一部の学区では、教育予算を含めた全体予算の決定は議会が行うものの、支出については教育委員会が権限を有する。また、学区教育委員会にとっては教育行政の専門家である教育長の任用が予算と並んで重要な審議事項。
- 定例の会議では、政策決定のほかに、退学処分(学区教育委員会)等に関する異議申し立ての機会を提供。
- 会議は原則公開。一般住民の傍聴が可能であり、学区レベルの会議では住民の意見陳述の時間が毎回設けられているほか、審議の状況がケーブルテレビで放映されている(モンゴメリー学区の場合)。
(2)地域住民との対話、会合への出席等
- 地域に対してアカウンタビリティを果たすために、教育委員には地域住民との対話が強く求められている。特に学区の教育委員は尊敬される立場であるとともに、地元に密着した存在とされている。
- モンゴメリー学区では、州議会や郡議会への出席のほか、父兄や人種団体など地域の住民や団体との対話の場に教育委員が参加している。また、コネチカット州のように、州教育委員会が学区教育委員会と意見交換を図る場を設けている場合もある。
- 住民との対話は、教育委員会の取組に対する理解を深めてもらうための貴重な機会として見なされており、そのための工夫がなされている。
(3)インターネットによる情報発信
- インターネットによる情報発信は、教育委員会の取組に対する住民の理解促進のための重要な手段ととらえられており、州及び学区で積極的に実施。
- すべての州教育委員会及び州教育局は専用のサイトを設けており、州教育委員会が制定する法令・基準、教育関連統計、カリキュラムに関する基準、州内統一の学力テストの結果、州内の学区のサイトへのリンクを掲載しているほか、教育委員会の審議日程等も公表。
- 学区レベルでも規模の大きなところを中心に多くの学区教育委員会がサイトを設け、教育委員会が制定する法令・基準、教育関連統計、州内統一の学力テストの結果などを掲載しているほか、教育委員会の審議日程等を公表。
2.教育行政の独立性
(1)教育行政の独立性の背景
- 米国では、上下水道や公園の管理、警察行政など分野に応じて特別区が設けられ、市や町が行う一般行政とは独立して特定の公共サービスを提供。公立学校を所管する学区も特別区のひとつであり、教育行政は伝統的に一般行政から高い独立性を維持。
- 教育行政が独立性を維持してきた背景のひとつとして、教育が政策的及び財政的に極めて重要なものと見なされ、政党や首長などからの党派的影響を避ける必要があるという認識が共有されてきたことが指摘されている。
- また、当該地域最大の公的支出である教育(公立学校)に関する権限を市長など一極に権限を集中させないことが民主主義にとって重要と考えられてきたことも指摘されている。
(2)教育委員会の独立性の維持
- 一般行政から分離された教育行政を司る教育委員会の独立性は制度的に保障されている。例えば、州知事による任命制が採られているメリーランド州でも、一旦任命された教育委員は倫理的問題を起こさない限り解任されないことが、法律によって規定。
- 公選制か任命制かを問わず、教育委員の入れ替えは一部の委員(通常2~3名)について行われ、継続的、安定的な政策の立案、実施が行える仕組み。
(3)教育委員の選任
- 教育委員の選任方法は、州教育委員会の場合、約三分の二の州では州知事による任命、残りの三分の一では公選。学区教育委員会の場合、95%は公選で、残りの5%が任命。
- 教育委員の選挙の投票率は、州及び学区の双方とも低く、5%から25%程度。ただし、地域で重要な争点がある場合には投票率が上がる。
- 教育委員会の規模や任期は州によって多様。州教育委員会の場合は9名(表1参照)、任期は4年(表2参照)とするところが多い(ただし、任期については半数以上の州で5年以上)。学区教育委員会の場合は7~8名(表3参照)、任期は4年(表4参照)とするところが多い。
表1 州教育委員会の規模
| 規模 | 州数 | 州名 |
|---|---|---|
| 7名 | 8 | アラスカ、デラウェア、フロリダ、モンタナ、ニューハンプシャー、ノースダコタ、オクラホマ、オレゴン |
| 8名 | 5 | コロラド、アイダホ、ミシガン、ミズーリ、ネブラスカ |
| 9名 | 13 | アラバマ、アリゾナ、コネチカット、イリノイ、アイオワ、メイン、マサチューセッツ、ミシシッピ、サウスダコタ、バーモント、バージニア、ウェストヴァージニア、ワシントンDC |
| 10名 | 4 | アーカンソー、カンザス、ネバダ、テネシー |
| 11名 | 7 | カリフォルニア、インディアナ、ケンタッキー、ルイジアナ、ロードアイランド、ワシントン、ワイオミング |
| 12名 | 1 | メリーランド |
| 13名 | 4 | ジョージア、ハワイ、ニュージャージー、ノースカロライナ |
| 15名 | 2 | テキサス、ユタ |
| 16名以上 | 4 | ニューヨーク(16名)、オハイオ(19名)、サウスカロライナ(17名)、ペンシルバニア(21名) |
[出典] National Association of State Boards of Education (NASBE),State Education Governance At-a-Glance,Jan. 2004.
表2 州教育委員の任期
| 任期 | 州数 | 州名 |
|---|---|---|
| 3年 | 1 | ロードアイランド |
| 4年 | 22 | アラバマ、アリゾナ、カリフォルニア、コネチカット、フロリダ、ハワイ、インディアナ、カンザス、ケンタッキー、ルイジアナ、メリーランド、ネブラスカ、ネバダ、オハイオ、オレゴン、サウスカロライナ、サウスダコタ、テキサス、ユタ、バージニア、ワシントン、ワシントンDC |
| 5年 | 6 | アラスカ、アイダホ、メイン、マサチューセッツ、ニューハンプシャー、ニューヨーク |
| 6年 | 11 | アーカンソー、コロラド、デラウェア、イリノイ、アイオワ、ニュージャージー、ノースダコタ、オクラホマ、ペンシルバニア、バーモント、ワイオミング |
| 7年 | 2 | ジョージア、モンタナ |
| 8年 | 3 | ミシガン、ミズーリ、ノースカロライナ |
| 9年 | 3 | ミシシッピ、テネシー、ウェストヴァージニア |
[出典] National Association of State Boards of Education (NASBE),State Education Governance At-a-Glance,Jan. 2004.
表3 学区教育委員会の規模(サンプル調査)
| 規模 | 比率 |
|---|---|
| 5名未満 | 0.9% |
| 5~6名 | 36.9% |
| 7~8名 | 44.7% |
| 9名 | 14.3% |
| 10名以上 | 3.2% |
表4 学区教育委員の任期(サンプル調査)
| 任期 | 比率 |
|---|---|
| 4年未満 | 30.4% |
| 4年 | 63.2% |
| 5~6年 | 6.5% |
[出典] National School Boards Association,School Boards at the Dawn of 21st Century: Conditions and Challenges of District Governance,2002.
- 委員の経歴は多様であるが、PTAやその他の地域団体等で積極的な活動経験、あるいは組織の中での管理的な立場の経験のある者がなる場合が多い。また、州教育委員の場合は、学区の教育長、学区の教育委員の場合は校長や教員経験者が選出されることも少なくない。
表5 教育委員会の組織構成等に関する日米比較
| 学区、市町村レベル | 州、都道府県レベル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 米国(2000年度) | 日本(2003年度) | 米国 | 日本(2003年度) | ||
| 教育委員会数 | 14,859(学区数) | 3,365 | 48(ワシントンDCを含む) | 47 | |
| 男女比 | 61.1:38.9 | 75.3:24.7 | 56:44 | 67.7:32.3 | |
| 年齢構成 | 40歳未満 | 5.9% | 0.4% | 多くは45~60歳 | 0.4% |
| 40-49歳 | 40.1% | 8.7% | 9.9% | ||
| 50-59歳 | 33.8% | 26.5% | 24.6% | ||
| 60歳以上 | 20.3% | 64.4% | 65.1% | ||
[出典]
- 米国:
- U.S. Department of Education,Digest of Education Statistics 2002
- National School Boards Association,School Boards at the Dawn of 21st Century: Conditions and Challenges of District Governance,2002.
- 州教育委員会の男女比及び年齢構成については州教育委員会協議会(NASBE)のインタビューによる。
- 日本:
- 文部科学省『平成15年度地方教育行政調査 中間報告』、平成16年
3.教育委員会と教育長との関係
(1)教育長の選任
- 教育長の選考・採用は教育委員会にとって重要な責務。特に、学区においては公立学校を切り盛りする専門職としての教育長の雇用は、学区の教育行政を最も左右する重要事項と見なされている。
- 州及び学区では、教育長募集の広報を実施すると同時に、専門のコンサルタント等、外部組織を活用して候補者の選定を実施。これらの過程で絞り込まれた候補者リストの中から最終的な決定を教育委員会が多数決で決定。
- モンゴメリー学区の場合、教育長の任用に当たり、地域住民から地域の教育課題などに関する情報を収集し、必要とする候補者像を明らかにする手続きを実施。
- 学区の教育長の選任や解任に当たって、州教育委員会の承認を必要としている場合もある。
(2)教育委員会と教育長の関係
- 教育委員会と教育長は、多くの場合、雇用関係にあり、任命・雇用者である教育委員会は教育長を解雇する権限を所有。このため、教育委員会と教育長の間には一種の緊張関係が存在。
- 近年は、教育政策・行政におけるアカウンタビリティが重視され、学力テストの得点や出席率等の各種データによって、教育長の行政手腕が厳しく問われるようになっている。
図 州教育委員会及び州教育長の選任
州教育委員会及び州教育長の選任は、多くの場合、次の四つのモデルに分類される。
- 州教育委員会は州知事が任命。州教育長は州教育委員会が任命(モデル1)
- 州教育委員会は州知事が任命。州教育長は選挙により選出(モデル2)
- 州教育委員会は選挙により選出。州教育長は州教育委員会が任命(モデル3)
- 州教育委員会及び州教育長とも州知事が任命(モデル4)
このほか、教育委員の一部を州知事が任命し、残りを選挙により選出する場合(ルイジアナ)、教育委員の一部を生徒諮問委員会及び州高等教育委員会が任命し、残りを州知事が任命する場合(マサチューセッツ)、州議会が任命する場合(ニューヨーク)などがある。
モデル1
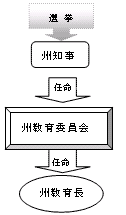
10州
アーカンソー、コネチカット、フロリダ、イリノイ、ケンタッキー、メリーランド、ミズーリ、ニューハンプシャー、バーモント、ウェストヴァージニア
モデル2
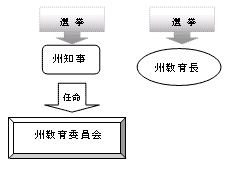
10州
アリゾナ、カリフォルニア、ジョージア、アイダホ、インディアナ、モンタナ、ノースダコタ、オクラホマ、オレゴン、ワイオミング
モデル3
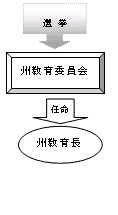
8州
アラバマ、コロラド、ハワイ、カンザス、ミシガン、ネブラスカ、ネバダ、ユタ
モデル4
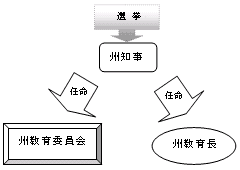
8州
アラスカ、デラウェア、アイオワ、メイン、ニュージャージー、サウスダコタ、テネシー、バージニア
[全州教育協議会(ECS)ウェブサイトのデータ(2004年4月時点)に基づく]
(3)教育委員会と教育長の役割分担
- 州及び学区双方とも、教育委員会は政策・方針・基準等の決定、教育長は決定された施策の実施という役割分担があるという認識が一般的。
- 州及び学区いずれの場合も、教育長(及びその事務局である教育局や教育事務所)が教育政策に関する案を作成して教育委員会に上程し、その採否を教育委員会が決定するというのが、政策決定へのプロセス。
4.教育委員会に対する支援組織
(1)教育委員会を支える組織
- 教育委員会を補佐する役割は、通常、教育長を頂点とした事務局(州教育局、学区教育事務所)全体で担うこととなっている。
- フロリダ州やカリフォルニア州のような大規模州では予算分析や議会対策等を目的として州教育委員会の補佐組織が置かれているところもある。また、学区レベルでも、モンゴメリー学区のような大規模学区には教育委員会を支援する専門スタッフが置かれているところもある。
(2)支援団体
教育委員会の活動を支えるものとして、教育長及び事務局以外に、教育委員会及びその他の全国的な教育関係団体の役割も重要。
例えば、州教育委員会の全国団体(全米州教育委員会協議会(NASBE))は州教育長の候補者選びに対する支援のほか、教育委員を対象としたワークショップの開催、調査研究(委託)及びその成果の公表、その他、各種パンフレットの作成等を実施。
学区教育委員会の全国団体(全米学区教育委員会協議会(NASB))も、調査研究の委託及び結果の公表、広報紙や機関誌の発行等を通じて、教育委員会による効果的な活動を支援。
上記の教育委員会の関係団体は加盟する教育委員会のほか、他の教育関係団体ともネットワークを持ち、ここから蓄積された豊富なデータを加盟教育委員会に提供するほか、教育委員会を代表して連邦政府等の政策に意見を述べる役割も遂行。
5.都市部における教育委員会制度の見直しについて
(1)教育委員会制度の見直し
- 近年、大都市において、市長の権限を拡大する観点から教育委員会制度の見直しの動きがある。ただし、ごく一部の都市に限定された動きであって、全米的な傾向ではない。また、州によっては学区の教育行政権を州に引き上げる事例も見られるが具体的事例は少ない。
- ほとんどのケースは、公選制の教育委員を市長による任命制に変更するもの。ただし、任命する委員の数は市によって異なり、すべての委員を市長が任命する場合や、一部の委員のみを任命する場合がある。
- 法令上の手続きは州によって異なり、次の三つの手続きのいずれかによって実施。
- 州が、公選制の学区教育委員に代えて市長によって任命される教育委員を置く州法の改正を行う場合
- 州が、学区教育委員の任命権限を市長に付与するか否かの住民投票を実施することを決定した場合
- 住民が投票により市長に学区教育委員会の任命権限を認められる場合
- これらは、学区教育委員における公選制から任命制への固定的な制度変更ではなく、むしろ問題解決のための暫定的な措置として導入されており、問題状況についての改善が認められた場合には公選制に戻されることが一般的。
- 教育委員会の決定権を市長部局に吸収し、教育委員会制度を廃止したのは、ニューヨーク市学区のみ。ただし、ニューヨーク市学区についても、教育政策に関する重要な案件については、保護者等から構成される委員会組織に諮問し、承認を得なければならないと規定されている。
(2)制度見直しの背景
- 首長の権限強化は、人種問題や貧困層の存在などの社会構造的な課題と密接に結びつく都市部の教育問題が、学区教育委員会単独で解決できる範疇を超えるものとなっていることが最大の背景。
- 多様な都市部の問題状況の改善を目指し、市長と産業界が協力、実施する総合的な地域振興策の一環として市長への権限移管が導入される傾向。
- 首長による政治的なパフォーマンスであるとする指摘もある。
(3)制度見直しに対する評価
- 全国的な教育団体や州及び学区の教育委員会事務局の関係者の間では現状では限られた地域における取組としてとらえられている。
- 積極的な評価としては、市長を中心とする集権的体制により教育改革を戦略的に前進させようとしていること、学力の低い児童生徒群あるいは教育成果の上がらない学校に焦点を当てることで政策の方向性が明瞭であること、教育成果に対する責任(アカウンタビリティ)の所在を明確にしていることなどが指摘されている。
- 消極的評価としては、教育政策を重視しない市長が就任して従来の取組が継続されない可能性に対する憂慮や、制度見直し後の教育政策が州内統一テスト等で測定される児童生徒の学力に対して過度に重点を置く傾向が見られることへの批判が指摘されている。
- ニューヨーク市の場合、市長による極度に集権的な体制に対して批判がある。また、権限移管を行っていない都市部の市長の中には、専門の組織(教育委員会、教育長)に任せたほうが優れた成果を得られると述べる者もいる。
- ワシントンDCの場合、最近、市長が学区教育委員会の権限を市長部局に移管するため、繰り返し条例の改正を試みたが、ワシントンDC議会の反対により、結局実現しなかった。これは、議会が現市長への権限の集中を嫌ったためであると指摘されている(現市長も、議会議員の大半も同じ民主党員であるとのこと)。
お問合せ先
生涯学習政策局政策課