- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 中央教育審議会 > 教育制度分科会 > 地方教育行政部会 > 地方教育行政部会(第5回) 配付資料 > 資料1 第5回地方教育行政部会 意見発表者説明資料(小島理生教育長)
資料1 第5回地方教育行政部会 意見発表者説明資料(小島理生教育長)
小島理生教育長(羽島郡四町教育委員会)説明資料 平成16年6月15日
「中央教育審議会教育制度分科会地方教育行政部会」説明資料
羽島郡四町教育委員会
教育委員会共同設置の実際の運用状況
1.羽島郡四町教育委員会の組織体制
1.法的な根拠
機関の共同設置・・・関係市町村が共同して教育委員会などの委員会や付属 機関を設置することができる。§地方自治法第252条の7

教育委員会を共同で処理することで、事務を簡素化し経費の節約に資しつつ合理的な行政を確保する。
2.背景
羽島郡は地勢的に小規模で交通の便もよく、古くから郡内4町間に共通する慣行行事を持っており、交流も盛んであった。
- 以前から郡学校教育会が組織され、教育実践の面で郡内の交流が盛んだった。
- 年々専門化・複雑化する教育行政事務の対応を一般行政職員で当たっていた。
- 地域の教育を高めたいという共通意識があった。
- 郡内を勤務の本拠地とする優秀な教職員を確保する必要があった。
- 郡内では既に組合立の中学校を設置しており深いつながりをもっていた。
- 郡内4町の合併、市制施行を模索する動きがあった。
3.経過・沿革
| 年月日 | 経過事項 |
|---|---|
| 昭和44年5月30日 | 教育委員会の統合についての郡内各町長・議会議長教育委員長による合同会議開催。 |
| 6月5日 | 羽島郡教育委員会設置準備委員16名を選出。(以後、会議を重ね共同設置を確認) |
| 7月25日 | 羽島郡教育委員会発足。幹事町:笠松町 |
| 昭和51年7月25日 | 名称を「羽島郡四町教育委員会」変更 |
| 平成14年4月1日 | 幹事町:岐南町に変更 |
4.構成団体の概要
羽島郡四町教育委員会を構成する関係町は4町 単位:人
| 構成する町 | 平成16年5月1日 | 昭和44年5月1日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 児童生徒数 | 人口 | 児童生徒数 | |
| 川島町 | 10,361 | 1,066 | 6,629 | 927 |
| 岐南町 | 22,905 | 1,938 | 10,581 | (岐南・笠松の計) 3,865 |
| 笠松町 | 22,093 | 1,782 | 21,983 | |
| 柳津町 | 12,694 | 863 | 8,827 | 750 |
| 合計 | 68,053 | 5,649 | 48,020 | 5,542 |
※ 昭和44年~47まで岐南町は岐阜市との組合立中学校を設置しておりその生徒数は計上していない。
5.事務局組織図
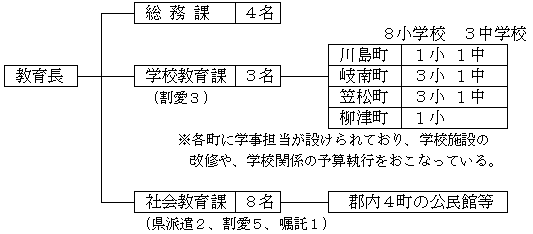
※ 各町の公民館に社会教育主事1名を派遣。
幹事町・・・・岐南町(規約で定めた地方公共団体)
6.教育委員の選任
構成団体の町ごとに1名推薦(教育長を除く)
・・・・関係団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係町の長が当該団体議会の同意を得た上、幹事町の長が選任する。
7.四町教育委員会予算
- 教育委員会予算は規約の定めるところにより、構成団体である4町の負担。
- 歳入歳出予算は、幹事町の予算に計上し執行されており、幹事町では特別 会計として、一般的な予算とは分離している。
- 監査については、幹事町の監査委員がこれを行う。
- 各町の学校施設費や公民館活動等の予算は各町の予算に計上。
〔平成16年度特別会計予算〕歳入歳出総額 160,457千円
歳入
| 款・項 | 金額 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担金 | 156,631 |
|
||||||||||
| 分担金 | 2,116 | |||||||||||
| 繰越金 | 1,500 | |||||||||||
| 諸収入 | 210 | |||||||||||
合計 |
160,457 |
歳出
| 款・項 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
教育費 |
教育総務費 | 144,365 | |
| 学校教育費 | 7,064 | ||
| 社会教育費 | 6,102 | ||
| 保健体育費 | 1,926 | ||
| 予備費 | 予備費 | 1,000 | |
| 合計 | 160,457 | ||
8.構成団体の教育関係予算
平成16年度
| 構成町 | 川島町 | 岐南町 | 笠松町 | 柳津町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 3,464,000 | 7,306,100 | 6,065,000 | 4,471,000 | |
| 教育費 |
358,626 | 1,331,967 | 689,528 | 370,641 | |
| 教育総務費 | 52,608 | 109,716 | 87,037 | 37,959 | |
| 小学校費 | 77,161 | 137,189 | 168,024 | 137,028 | |
| 中学校費 | 61,343 | 337,049 | 70,190 | 86,072 | |
| 給食センター費 | 48,002 | 53,465 | 64,215 | (小学校費に含) | |
| 社会教育費 | 91,994 | 627,006 | 212,984 | 82,087 | |
| 保健体育費 | 27,518 | 67,542 | 87,078 | 23,608 | |
| 幼稚園費 | - | - | - | 3,887 | |
2.四町の議会・首長との関係
1.運営協議会の設置
教育委員会の円滑な運営を教育行政の資質向上を目的として設置されてる。
- 構成は関係町の議会議長、町長
- 年2回程度開催
- 共同設置規約や条例の制定・改廃、予算決算等の重要事項について協議
2.各町の議会や首長に対して
共同設置の教育委員会は、地方自治体の執行機関であるので、独立の法人格を持つものではない。

共同設置した教育委員会が、それぞれの関係町の教育委員会の役割を果たす。
したがって、各町の町長や議会に対し、それぞれの町の教育委員会としての担任事務を処理している。
例えば、各町の定例議会への出席や、学校教育・社会教育等の重要事項の協議や決定、推進等。
3.教育委員会共同設置の利点と課題
総務関係
利点について
- 教育長報酬や教育委員報酬等の関係する費用が四分の一の経費で済む。
- 広域的な団体の育成に対応ができることと、補助金についても一本化できることで経費の削減につながる。
- 単独では購入が困難な備品もそろえることができ、郡内の教育施設の共有備品として広く活用できる。例えば、子どもたちに本物の芸術に触れてもらうため、絵画(名画の複製、40点=8,240千円)を購入し、11小中学校を巡回展示している。
課題について
- 各町の財政力や担当職員数が異なるため、郡内の各種ソフト・ハード事業の均一的な向上を図ることが困難な面がある。
- 教育委員会が各町にとって離れた存在にならないよう努める必要がある。
学校教育関係
利点について
- 教職員の人事異動などの人事管理が四町教育委員会で行うことができる。
人事管理が広域化することによって、教職員の特性を生かした適材適所への人的配置がしやすくなった。このことは特色ある学校づくりや学校の活性化に大きく貢献している。 - 各学校の指導をきめ細かく行うことができる。
11の小中学校について、教育委員会の学校訪問、教育委員訪問をはじめ、教育長訪問、教育振興事務所訪問など、学校を訪問して教育課程の進捗の様子をつかむ機会を多く設けている。それぞれの小中学校での学校経営の取組を比較したり、紹介したりすることを通して、きめ細かな指導を行うことができている。 - 四町教育委員会の独自の教職員研修を行うことができる。
四町教育委員会では、教育委員会が企画運営する次のような教員研修を行っている。- ア、『豊かな体験活動』推進事業
事業の内容としては、「豊かな体験活動推進会議」、「ふれあい体験活動」「児童生徒の宿泊体験学習」(三泊四日の御嶽登山)、「豊かな体験活動講演会・交流会」などを行っている。 - イ、英語活動支援事業
小学校の全学級に対して、4時間分の英語教師(日本人)を派遣する事業を行っている。 - ウ、不登校対策「フレンドリーカウンセラー派遣」
児童生徒の不登校対策として平成4年度から実施している。対象の児童生徒に、家庭での生活相談を中心に生活意欲(登校を含む)を高めようとするものである。岐阜聖徳学園大学の協力を得て、学生をフレンドリーカウンセラーとして派遣している。 - エ、教職員対象研修事業
- (ア)教職員海外特別研修(4泊5日・・・10月に実施)
海外の特色ある地域を選定して、それぞれの土地の人文、社会、自然等の分野についての研修を深め、教職員としての視野を広めるとともに、一般教養を高めるための研修を行っている。 - (イ)職場体験研修(夏休み中に2日間実施)
教職経験2~5年目の若い先生方を職場や施設に一日派遣し、体を動かし、汗を流す直接体験の研修を通して、社会人としての視野を広め、仕事の厳しさ、教育の厳しさを身をもって体験する。
- (ア)教職員海外特別研修(4泊5日・・・10月に実施)
- オ、羽島郡学校教育会研修事業
学校教育会に参加している教職員数が270名ほどの適正規模のため、充実した研究会を小中合同で実施できている。教職員の資質向上に役立つ実のある研修になっている。
- ア、『豊かな体験活動』推進事業
課題について
近年、広域の人事異動が多くなり、他郡市から異動してくる教員数が増えたため、3年で異動する教員が目立ち、腰を落ち着けた教育への取組が望まれる。
社会教育関係
利点について
- 四町教育委員会に多くの職員が配置できる。
共同設置の教育委員会に、社会教育課だけでも事務局に9名もの職員が配置され、そのうち各町公民館に4人の教員の社会教育主事を置いている。加えて、県派遣の社会教育主事が各四町間の連絡調整に当たるなど、その配置によって、郡全体の社会教育の進展に大きな効果・成果を上げている。 - 郡で連合体を組織して研修ができる。
郡内の4つの町に、社会教育におけるPTA・各種スポーツ団体・文化団体等の連合体が組織され、郡単位の大会・研究会・研修会を開催することができる。
その結果、郡全体の社会教育のレベルアップに大きな役割を果たしている。
例えば、郡連合PTA・郡スポーツ少年団協議会・郡体育協会・郡体育指導員協議会・読書団体協議会・各種郡スポーツ大会・郡リーダー研修会・郡文化財研修事業等々があり、相互に切磋琢磨し合って高め合っている。
また、羽島郡少年少女合唱団は、教育委員会が統合されてすぐに発足した広域ならではの教育団体で、定期演奏会や県芸術祭、各種のフェスティバル等に活躍している。 - 各町の特色ある生涯学習活動が定着している。
共同設置といえども、教育委員会は、郡全体の社会教育の方針と重点は立案するが、各町の実態に即した特色ある社会教育の創造を、常に優先するように努めている。その上で、社会教育団体の育成や関係職員の研修の充実強化と指導力の向上を図っている。
(例)・郡図書館職員研修会・郡公民館職員研修会・郡社会教育関係職員研修会等々。
その結果、社会教育関係者が切磋琢磨し合い、研鑽を積んだ職員の創造性や企画力・実践力が高まり、共同設置以来、各4町全ての公民館が、次々と文部大臣表彰を受賞したこともその成果といえる。 - 各町に地域のコミュニティー文化が育ち、連帯感が醸成されている。
人の顔が見える規模の町だからこそ、各町ごとに住民へのきめ細かな学習サービスができる。そして郡全体に、地域の連帯感やコミュニティー文化が生まれてきたと実感している。
課題について
- 各町の町民意識がネックになっている。
各町の特色ある活動を奨励しており、また教育委員会のみが共同設置である関係で、他町の住民に対して学級・講座の参加を呼びかけたり、広域連携講座を開催したりする場合に、各町の閉ざされた町民意識が逆に障害となっている。 - 四町教育委員会としての性格上の問題がある。
本郡は羽島郡教育委員会ではなくて、四町教育委員会として位置づけている。そのため、同じことを4つやるわけで4倍の労力をかけることになる。つまり、教育長は勿論のこと、教委事務局の社会教育課には5名の職員がいるが、4つの町の特色を尊重した4倍の対応は大変であり、十分にできない場合もある。
お問合せ先
生涯学習政策局政策課