参考2
立山カルデラ砂防博物館 飯田 肇
大日岳の各標高での積雪分布を事前に把握することは、登山計画や安全対策に有効であるが、アメダス等の気象観測点が無く、積雪量は平野からの類推ではうまく表現できないのが現状である。大日岳のような大きな標高差を持つ山岳での積雪分布特性には未知の部分が多い。
| 1 | 千寿原(研修所) | 475メートル | 登山研修所の超音波積雪深計により10分毎に自動計測 |
| 2 | 冬山前進基地 | 1,300メートル | 積雪深ポールを設け来訪時やヘリからの目視観測 |
| 3 | 雪見平 | 1,560メートル | 登山指導員研修会時に積雪断面観測 |
| 4 | 室堂平 | 2,450メートル | 立山カルデラ砂防博物館で観測 |
表1、図1に標高別に3点以上で積雪深測定を実施した日の結果を示す。これらより、一般的に標高が増すほど積雪深が大きくなることは認められるが、年々の変動傾向は観測点により異なる。
表1 標高別積雪深(センチメートル)
| 測定日 | 千寿原 | 冬山前進基地 | 雪見平 | 室堂平 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標高メートル | 475メートル | 1,300メートル | 1,560メートル | 2,450メートル | |
| 2002年2月3日 | 130センチメートル | 460センチメートル | 680センチメートル | ||
| 2002年2月24日 | 135センチメートル | 465センチメートル | 720センチメートル | ||
| 2003年2月12日 | 90センチメートル | 380センチメートル | 740センチメートル | ||
| 2003年2月22日 | 104センチメートル | 400センチメートル | 465センチメートル | 760センチメートル | 研修所積雪深計計設置 |
| 2004年2月3日 | 111センチメートル | 330センチメートル | 550センチメートル | ||
| 2004年2月11日 | 198センチメートル | 440センチメートル | 710センチメートル | 悪天で前進基地までの入山 | |
| 2005年2月8日 | 192センチメートル | 420センチメートル | 600センチメートル | ||
| 2005年2月12日 | 187センチメートル | 430センチメートル | 470センチメートル | 520センチメートル | |
| 2006年2月8日 | 234センチメートル | 420センチメートル | 600センチメートル | ||
| 2006年2月14日 | 236センチメートル | 430センチメートル | 625センチメートル | 660センチメートル | |
| 2007年2月8日 | 52センチメートル | 420センチメートル | 480センチメートル | ||
| 2007年2月16日 | 74センチメートル | 430センチメートル | 365センチメートル | 520センチメートル | |
| 2008年2月4日 | 103センチメートル | 380センチメートル | 580センチメートル |
図1 年毎の標高別積雪深分布
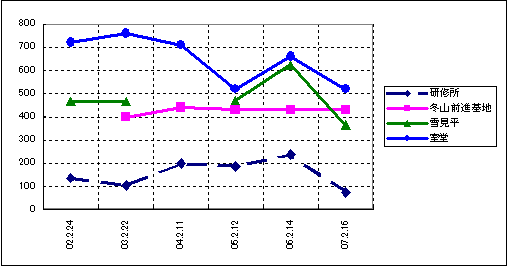 |
図2〜5に、標高別に4点の積雪深観測を実施できた日の標高と積雪深との関係を示す。各日とも、標高と積雪深にはよい相関がみられ、直線的に回帰できることがわかる。各観測日の直線回帰式と相関係数を図中に示す。
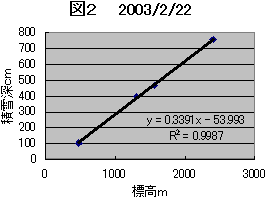 |
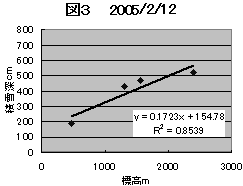 |
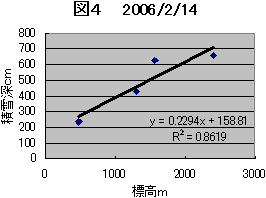 |
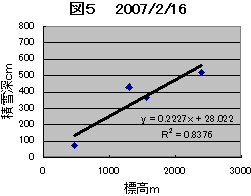 |
図6〜9に、観測された積雪深について、各観測点間の関係を示す。研修所と雪見平でよい相関がみられるがサンプル数が少ない。一般に、各地点間の積雪深にはよい相関はみられない。これは、年毎の変動が激しいためと考えられる。
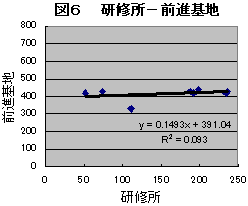 |
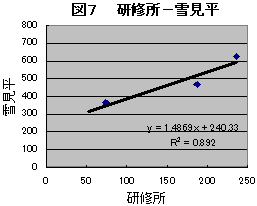 |
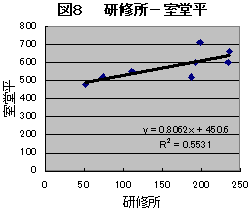 |
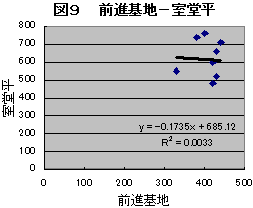 |