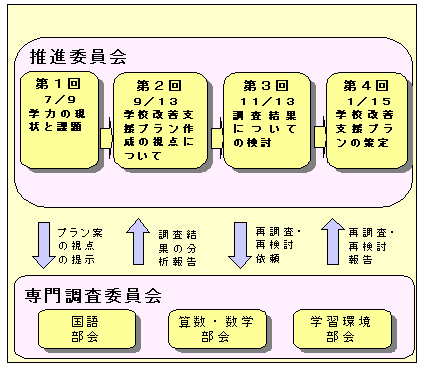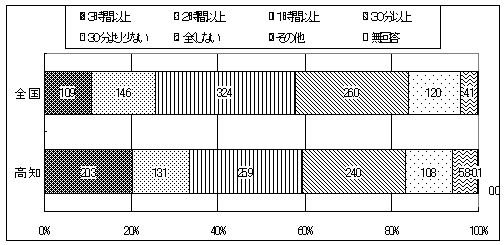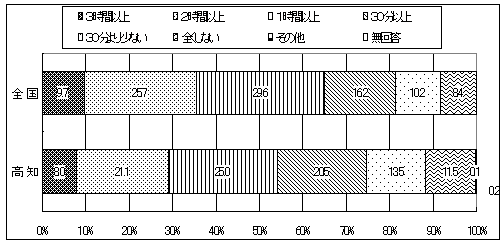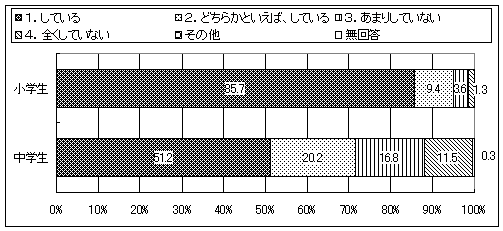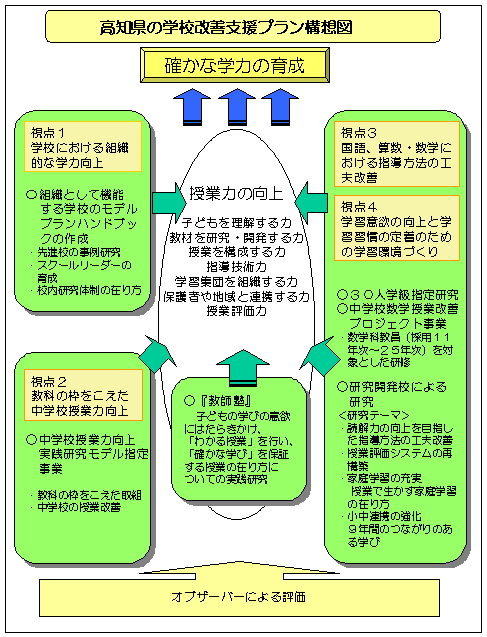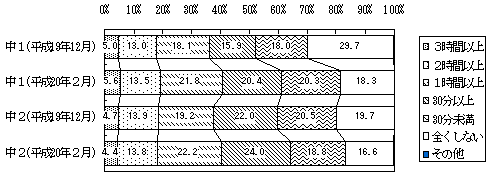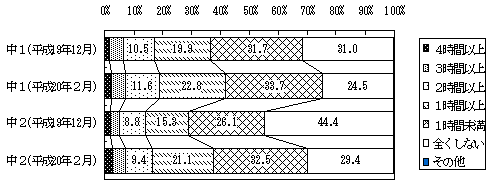|
別添2 高知県学校改善支援プラン−確かな学力の育成を目指して−高知県検証改善委員会 はじめに 子どもたちに「確かな学力」を身に付けさせ、学力向上を図ることは、本県の教育にとって大きな課題であり、平成9年度から18年度までの土佐の教育改革においても最重要課題として位置付け、取り組んできた。 1 検証改善委員会の体制について 本県の検証改善委員会は、「高知県学校改善支援プラン検討委員会」の名称で、本山町教育長である岩塚忠男氏を委員長として、推進委員会と専門調査委員会の2つの委員会で構成し、分析・協議を行った。 【高知県学校改善支援プラン検討委員会】 2 学校改善支援プランの概要 調査結果から見える本県の子どもたちの学力の課題として、特に中学校における学力の定着状況において、知識・技能、また、これらを活用する力がともに大きな課題が見られた。
3 全国学力・学習状況調査の結果分析について本県の全国学力・学習状況調査の結果分析において、以下の点が明らかになった。 (1)学力の状況
(2)児童生徒の学習や生活の状況
(3)学校の取り組みの状況
4 学校改善支援プランについて 学校改善支援プランは、教員が授業力を高め、子どもたちが、「確かな学力」を身に付けるために、高知県として重点的に取り組んでいくものである。 (1)学校における組織的な学力向上
(2)教科の枠をこえた中学校授業力向上
(3)国語、算数・数学における指導方法の工夫改善
(4)学習意欲の向上と学習習慣の定着のための学習環境づくり
5 学校改善支援プランを受けた取組について学校改善支援プランの周知を図るために本年度はまず、次の説明会等を実施し、全国学力・学習状況調査結果の分析結果と学校改善支援プランについての説明を行った。
6 学校改善支援促進事業について 学校改善支援プランの促進のための取り組みとして、後期の学校改善促進事業に応募し、11月末に選定された。
これらの取り組み内容の決定にあたっては、これまでも学校現場から学習に遅れのある生徒への個別的な支援を行うための人的配置や、家庭において基本的な生活習慣を身につけさせることの大切さを保護者に情報発信すること等について、強い要望を受けていたことを考慮した。 具体的な取り組みについて(1)非常勤講師「学力向上支援員」の配置 12月から3月まで、非常勤講師として「学力向上支援員」を中学校18校に延べ21名を配置した。職務内容は、ティームティーチング、補習の補助、家庭学習の点検・課題の作成、生徒の個人データの作成などで、学力向上支援員は多感な中学生に対して柔軟かつ積極的に関わった。 (2)保護者向け啓発リーフレットの配付 全国学力・学習状況調査における質問紙調査結果の分析から、高知市の中学3年生は学校以外での学習時間が少なく、家庭で宿題をしている生徒の割合も少ない。
を「今日から家庭でできる3つのポイント」としてリーフレットにまとめ、小・中学校の保護者や地域住民等の学校関係者に配付した。 【家庭学習リーフレット】 (3)基礎問題集「家庭学習ノート」の配付 中学校においてこれまで中心的に行われてきた自主学習ノートの取り組みにかわり、中学生が具体的に取り組めるものとして、中学校1、2年生用に基礎問題集を作成した。 (4)標準学力検査の実施による取り組みの検証 促進事業における取り組みの成果を検証し、さらに今後の手立てに役立てることを目的として、2月に中1(国・数)、中2(国・数・英)の全ての生徒を対象として標準学力検査を実施した。結果は各学校に約2週間後に提供され、各学校では生徒に個人票を示しながら今後の学習方法等について指導した。 (5)「家庭学習に関するアンケート」の実施 家庭学習の状況を継続的に把握していく必要から、中1・中2の生徒全員を対象として「家庭学習に関するアンケート」を実施した。中3の「全国学力・学習状況調査」の結果と比較するとともに、学習状況の推移をみることができるように、「全国学力・学習状況調査」の質問紙調査5問のうち3問を共通とした。
学校の授業時間以外に,普段(月曜日から金曜日),1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか。(塾・家庭教師を含む) 土曜日や日曜日などの学校が休みの日に,1日当たりどれくらいの時間,勉強をしますか。(塾・家庭教師を含む) (6)成果と課題 調査結果を分析することによって、学力の定着状況と学習状況に関する客観的データが得られ、学力を支える基盤として家庭の大切さについて保護者へ直接働きかけることができた点は大きな成果である。 (7)今後の取り組み今後、この促進事業における取り組みを踏まえ、高知市においては平成20年を「授業改革元年」と位置付け、次のような取り組みを通じて徹底した授業改革を推進していく。
また、これらの取り組みの成果について、学校改善支援プラン検討委員会においては、他の市町村へ普及・啓発を行うことにより、支援プランにおける具体的な取り組みとして、県全体に広めていきたいと考えている。 7 おわりに 子どもたちの学力向上のためには、学校・家庭・地域が連携し、それぞれの役割の中でできることを確実に果たしていくことが必要である。
|
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology