資料5 参考資料
| 平成19年3月9日 | 平成18年度自己評価・公開方法の推進会議〔都道府県担当者 |
| 平成19年4月13日 | 第1回自己評価プロジェクト委員会〔各地区担当者 |
| 平成19年5月1日 | 第2回自己評価プロジェクト委員会〔各地区担当者 |
第3回自己評価プロジェクト委員会開催予定日⇒7月2日
財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
文部科学省 初等中等教育局 幼児教育課 専門職 梅原弘史
| 平成17年1月 | 中央教育審議会答申:「子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方について」⇒幼児教育に特化した答申 |
| 平成18年2〜8月 | 新幼児教育振興プログラム策定フォーラム(全4回) 「幼児教育振興アクションプログラム(素案)」の意見募集 |
| 平成18年7月 | 経済財政諮問会議:「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(骨太の方針2006)閣議決定
|
| 平成18年10月 | 認定こども園法「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の施行
|
| 第二条の二 | 幼稚園は、その教育水準の向上を図り、当該幼稚園の目的を実現するため、当該幼稚園の教育活動、その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 |
| 2 | 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同行の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。 |
| 第二条の三 | 幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。 |
| 第八 | 管理運営等 |
| 六 | 認定こども園は、自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。 |
学校評価の最終的な目的は、学校をよくすること。

幼稚園における教育水準の維持・向上
−幼稚園教育要領に基づく質の高い幼児教育の提供−
幼稚園における評価ガイドラインを作成し、自己評価、外部評価等を通じて幼児教育の質の評価を充実するとともに、認定こども園を含めた幼児教育に関する評価の在り方についても検討。
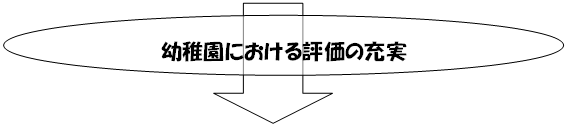
幼児教育の質の向上
財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 研究研修委員長 安家周一
| 平成12年12月 | 教育改革国民会議『新しい時代に向けた新しい学校づくり』 |
| 平成12年 | 『学校評議員制』の導入(文部科学省) |
| 平成14年3月 | 『改正・幼稚園設置基準』(文部科学省) |
| 第2条の2 | 幼稚園は、その教育水準の向上を図り、当該幼稚園の目的を実現するため、当該幼稚園の教育活動、その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 |


上記内部評価と同じ。
評議員の中から教職員・保護者・卒園生・学識経験者などに地元地域の人々などを加えた外部評価委員会を組織し、学園を一定基準で評価する。
今後、第三者評価機構ができ、学校法人に対する評価が実施される場合でも、第三者評価機構は、学園の外部評価機構に対する監督等を実施し、改善を促すようなシステムとする。
パネリスト 秋田喜代美〔東京大学大学院教育学科研究科教授〕
宮下友美恵〔静岡県・静岡豊田幼稚園園長〕
東 重満〔財団法人全日私幼研究機構研究研修副委員長〕
コーディネーター黒田秀樹〔財団法人全日私幼研究機構研究研修副委員長〕
Q1.自己評価をなぜ実施するのか?
A.幼児教育において、保育内容や教員の資質向上といったものは外部評価しにくい。よって、自分の保育を見直し、明日の保育を創造するための自己評価が重要になってくる。
Q2.全国の都道府県での自己評価の実施状況は?
A.現在は全国規模での実施はされていないが、静岡県においては「自己評価完全実施3年計画」が県主導で実施されていて、評価項目の見直しが行われている。
Q3.私立幼稚園は毎年園児募集の際に保護者から選ばれているという点で、外部評価を受けているのではないか?
A.私立幼稚園が私学としての独自性を有していると言えども、公金(税金)が補助金として出ている以上、『公教育の担い手』として、良好な経営状況の保持・教育内容の保障・教員の資質向上を実施する義務があり、自己評価は必要不可欠なものとなる。
Q4.自己点検・自己評価の内容は?
A.自己点検・自己評価は人間ドック的で網羅性と包括性を有し、色々多くの項目を評価し、なおかつ全体像として保育を評価する。また、専門性を生かして、自分(専門家)だから見えるものを評価する。さらに、自分の、あるいは我が園の保育を語る場、あるいは自らのアイデンティティを高める場としての役割も有している。
財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
以上、2点について各委員の意見をまとめて提出する。
財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
前回委員会からの宿題に関して、提出した広島県・福岡県・鹿児島県・神奈川県の4名が各々資料を基に意見発表を行った。⇒以下に、各委員からの意見の抜粋を掲載します。
教育内容の保障、並びに教員の資質向上を目的とした『自己評価の実施』
![]()
評価結果を基にしたグループ(経験年数等)内、学年内、園長と教員の話し合い
![]()
設置者・園長による総合的所見(園全体としての評価)
![]()
自己評価結果(総合所見)の公表 例:園だより、園説明会、HPなど
財団法人全日私幼研究機構として、自己評価ガイドライン(最低限の、あるいは理想的な)を6月末までに作成して、各地区教研や各都道府県団体研修会で自己評価を普及していただきたい。
自己評価ガイドライン作成ワーキンググループは、財団法人全日私幼研究機構 副理事長 田中雅道・奥先 楓,同機構研究研修委員長 安家周一,同 副委員長 東 重満・黒田秀樹の5名で構成する。
以上の4点について、各自意見をまとめて、E-mailまたはFAXで事務局まで送付する。