- 現在位置
- トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等(初等中等教育) > 人権教育の指導方法等に関する調査研究会議 > 人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ] > 別冊 人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ] 実践編 > 3.効果的な研修プログラムの例
3.効果的な研修プログラムの例
(1)内容別・目的別の研修
1)人権尊重の理念の基礎・基本の理解を図る研修(児童生徒理解、人間関係づくり等の基本を学ぶ)
事例35:子どもたち同士の対立の解決方法を考えさせる指導案づくりの研修(子どもたちがつながる1-どうするか考えてみよう)
1 目的と概要
日常生活で発生する子どもたちどうしの対立の解決方法を、ワークシートを活用して子どもたちに考えさせる授業について、その指導案づくり等の研修を行う。体験参加型の研修として、教育センターや校内で小グループを活用することが効果的である。
2 対象
小学校教員
3 研修の内容・進め方
- 「もめごとの場面」の絵とふきだしが描かれたワークシートを活用してどのような授業を行うか(子どもたちに考えさせるためどのように指導するか)、参加者に考えさせる。
授業の展開は、概ね、下のアウトラインによるものとする。
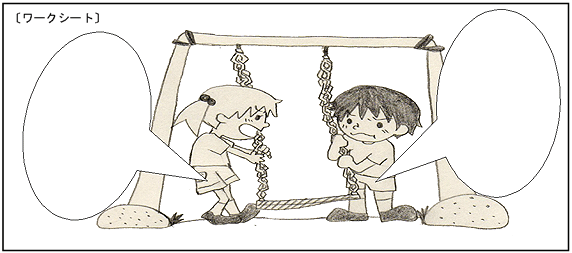
- 授業展開のアウトライン
活動 留意点 (1)絵を見て、どんな状況なのかを話し合う - 自分たちの生活をふりかえりながら考えさせる。
- 一人一人の考えを大切にする。
(2)ふきだしに、せりふを書く - 自分の書きやすいふきだしから書きこませるようにする。
(3)書いたふきだしを発表する - 様々な思いを認め合うようにする。
(4)対立を解決する方法を話し合う - 「対立は悪いこと」というだけの結論にならないよう配慮する。
- 授業展開のアウトライン
- 一連の指導計画の中でこの授業案をどのように活用するか、活用例を考える。
※ 指導の成果が子どもたちの毎日の生活に活かされることとなるよう、指導計画の全体イメージを作る。 - もめごと(ぶらんこの取り合い)の場面以外の場面での指導案を作成する。
事例36:児童生徒の人間関係づくりを促進するための指導方法の研修(子どもたちがつながる2-今どんな気持ち?)
1 目的と概要
日常の学級経営の中で児童生徒間の豊かな人間関係づくりを促進するため、様々な資料(絵カード、ワークシート)を活用した取組を行う指導方法等について、研修を行う。
体験参加型の研修として、教育センターや校内で小グループを活用して行うことが効果的である。
2 対象
小・中学校教員
3 研修の内容・進め方
- 様々な資料(絵カード、ワークシートなど)活用してどのような指導を行うか(子どもたちに考えさせるためどのように指導するか)、参加者に考えさせる。
指導の展開は、概ね、下のアウトラインによるものとする。- 様々な資料の例
-
絵カード ふきだしのワークシート サイコロトークの絵 
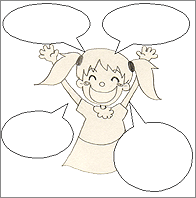
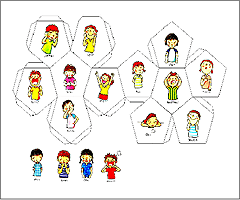
- 指導展開のアウトライン
※ 朝の会、帰りの会等での継続した取組として実施することも想定。
活動 留意点 (1)絵カードを見て、気持ちと場面について話し合う - 自分たちの生活と重ねて考えさせる。
(2)絵カードの気持ちを考え、ワークシートに書く - 一人一人の考えが大切にされるよう配慮する。
(3)気持ちの伝え方を考える - いろいろな伝え方があることに気づかせる。
(4)考えた方法で気持ちを伝える (5)気づいたこと、感じたことについて話し合う - 表情、しぐさなどでも気持ちがわかることに気づかせるようにする。
(6)いろいろな場面での気持ちの伝え方を考える
- 様々な資料の例
- これらの取組を継続して行う際の取組方法について考える。
- 人間関係づくりのプログラムを作る。
参考:児童生徒理解・集団づくりに関する研修のテーマ例
人権尊重の理念を学校教育の中で実現するための基礎・基本として、児童生徒理解や集団づくりに関する事項については、教員研修においても繰り返し確認を行い、確実にこれを身に付けることが必要である。
以下に示すのは、児童生徒理解・集団づくりに関し、研修を実施する際の研修テーマの例である。
児童生徒理解・集団づくりに関する研修のテーマ例
1.児童生徒理解・集団づくりに向け系統立てた取組に関する参加型研修
1.子どもとつながる
- 教師が自分の姿を見せる
- 自分の子ども時代を温かく振り返る(他の人と聴き合いながら)
- 自尊感情・自己肯定感を高める
- 子どもと対話する姿勢(聴くと話すの基礎)
- 子どもと対話するためのレッスン
- 「読む、書く」ことでの子どもとの対話
2.子どもがつながる
- 対話のあるクラスをつくる
- 子どもがつながるプログラムをつくる
3.集団づくりのために
- 子どもたちの人間関係をつかむ
- 集団づくりの方針をたてる
- 友だちの関係を図で表す
- 集団を分析する
2.児童生徒理解・集団づくりに関する実践事例を基にした参加型研修
1.心をはぐくむあたたかな学級づくり
- 学級の人間関係を友好的にするには
- 対人関係スキルを身につけるには(人間関係トレーニング)
- 互いに支えあう力を身につけるには
- ストレスに対処する力を身につけるには(ストレスマネジメント学習)
- 担任がひとりで抱え込まないためには
2.子どもや保護者との信頼関係づくり
- 子どもが○○と訴えてきたとき
- 子どもに事情を聴きたいとき
- 子どもと相談するとき
参考:授業等で配慮したいポイント例(人権尊重の視点から)
人権教育においては、その教育内容や方法の在り方とともに、教育・学習の場そのものの在り方がきわめて大きな意味をもつこととなる。
教員は、日々の授業や学習活動、学級経営の中で、児童生徒に対する適切な配慮を行い、一人一人が大切にされる学習環境づくりに努めなければならない。
これらを踏まえ、以下のような視点から、日々の授業等の在り方を繰り返し検証し、学習環境の改善に努めていく必要がある。
授業等で配慮したい人権尊重の視点からのポイント例
| 場面 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 児童生徒の呼名 | 子どもによって異なる呼び方が不公平感等を与えていないか (「○(まる)さん」、「○(まる)ちゃん」、「○○(まるまる)!」等) |
子ども一人一人に対するイメージやとらえ方が、呼称の違いに表れることがある。 一人一人に不公平感等を感じさせない配慮が必要である。 |
| 座席替えやグループ決め | くじびき、名簿順等で決めたり、児童生徒同士で決めさせたりしていないか | 座席やグループを決める際には、児童生徒の個々の事情(視力・聴力等の身体的な事情、心理面の状況を反映する友人関係等)に十分に配慮する必要がある。変更等を行う場合にもその判断を行うのは教員である。 |
| 教室での指名 | 日付順、席順、名簿順、物理的条件等によって指名していないか | 常に児童生徒の応答を予想し指名を行う。求める内容に応じて、教師が指名の方法を選択し、意図的・計画的に発言を求めていく。 |
| 机間(個別)指導 | 机間指導の仕方に偏りがないか | 児童生徒の求めに応じて机間指導を行うと指導の在り方に不均衡が生じてくる場合がある。個別指導の記録をとり、意図的・計画的な机間指導が行えるようにする。 |
| 児童生徒の言動等に対する改善点の指摘 | 特定の児童生徒への改善点の指摘を、他の児童生徒に求めていないか (「(今の発言が)聞こえましたか?」等) |
児童生徒の言動等への否定的な評価に基づく改善点の指摘をクラス内の他の児童生徒に求めていると、当該児童生徒に対する負の評価観を、クラス内で固定化してしまうことにもつながっていく。このような評価・指摘は、原則として教師自身が、自らの責任で行う。 |
| 時間配分・進行管理等の判断 | 教員自らの判断を曖昧にしていないか (「時間が来たので終わりにしましょう」、「時間が来たら知らせてください」 等) |
学習活動に関する時間の配分や活動の開始・終了の周知は、教員が自らの判断で行う。 個人面談等、一定の時間配分でものごとを進める場合においても、その進行については、他者に委ねるのではなく、教員自身で管理を行う。 |
2)人権尊重の課題について認識を深める研修(知的理解を深める)
事例37:人権教育への取組姿勢を主体的にするための個別人権課題等に関する研修-教育委員会における研修の進め方-
1 目的と概要
学校における人権教育の推進を図るためには、教員が様々な研修の機会を通じ、人権教育に主体的にかかわろうとする意欲や態度を高めていけるようにすることが大切である。特に人権侵害が厳然として存在する状況等を踏まえ、個別の人権課題等に関する正しい理解を深めるような教員研修の機会を提供することにより、人権教育に携わる上で必要とされる主体的な取組姿勢を喚起する。
2 教育委員会による研修等の進め方例
※ 各学校の人権教育担当者を対象とする研修会の内容として位置付け、年間を通して計画的に取り組む。研修を主催する教育委員会の指導主事等が、人権に関わる関係機関との連絡調整を行い、これら機関の協力を得ながら、幅広い人権課題についての研修を行えるようにする。
市教育委員会による人権教育担当者研修等の進め方例
| 学期 | 回 | 研修等の進め方 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 一学期 | 第1回 |
|
|
| 第2・3回 |
|
|
|
| 夏季休業期間/二学期 | 第4・5回 |
|
|
| 三学期 | 第6・7回 |
|
|
| 第8回 |
|
|
3)人権尊重の理念を確実に身に付ける研修(人権感覚を磨く)
事例38:人権感覚を培う参加体験型グループ研修
1 目的と概要
校内研修等において、アクティビティを取り入れた参加体験型のグループ研修を実施し、教職員の人権感覚を培う。また、これらのアクティビティは、教育委員会が主催する人権教育の指導者養成研修等において、アクティビティの進行役となるファシリテータ(学習促進者)の役割を実際に体験させ、ファシリテーション技能の向上を図る実技研修のメニューとしても活用できる。
教育委員会は人権教育担当教員向けにファシリテーション実技研修を主催し、担当教員はその成果を持ち帰り、自らファシリテータとなってアクティビティを実施することにより、各学校に参加体験型の研修を広めていくことが望まれる。これらの教員を、PTAの研修や公民館等の講座の指導者として活用することも有効である。
2 対象
全校種の教職員(ファシリティ実技研修のメニューとしては、主に人権教育担当教員対象)
3 多様なアクティビティ等を活用した体験型グループ研修の内容例(ファシリテータ実技研修のメニューとして、又は、人権感覚育成等のための校内研修として)
(1)ファシリテータの役割についての講義(ファシリテータ実技研修の前段として)
参加体験型の研修において重要な役割を果たすファシリテーターの役割について、講義形式で確認する。
【ファシリテータの役割】
- 参加者の感情を受け入れる、リラックスした雰囲気を演出する。
- 「人の心」に配慮した進行をする。(人間理解が大切である。)
- 参加者の主体性を引き出す。(人の行動を変えるものは外にあるのではなく、その人の内にある。)
- 体験をより大きな気付きへと導く。
- 葛藤の場面を用意し、主体的な発言を促す。問題の解決方法を教えるのではなく、解決は参加者に任せる。
※ ファシリテータの役割を果たす上では、自らもその場から学ぼうとする態度が特に重要となる。
(2)初めて出会った者同士の緊張を解きほぐすための活動(アイスブレーキング)
研修の実施に当たり、まず、初めて会う参加者同士が、お互いの緊張した心を解き放ち、これから行う研修への意欲を高めるための活動を行う。その後の研修の中で、率直に自分を表現できるようにするトレーニングとしての意味合いも持つ(心の中の「氷」を割っていくことから「アイスブレーキング」と呼ばれる。)。
【アイスブレーキングの方法例】
1.誕生日チェーン
- ねらい
- 参加者の緊張をほぐし、和やかな雰囲気をつくる
- 口頭や文字による会話以外のコミュニケーションを体験する
- 自分から行動することの大切さに気づく
- 方法
- 会話をしないという条件で、誕生日の月日順に一列に並んでもらう(意志の伝達は、身振り・手振りなど言葉以外の方法で行う)。
- 並び終えたら、順番に誕生日を発表してもらう。
- 感想を出し合う。
2.あいさつと自己紹介
- ねらい
- お互いに名乗りあい、名前を覚えて親しくなる
- コミュニケーションにおける視線の重要性を感じる
- 方法
- はじめは、人と視線を合わせないように、ひとりでぶらぶら歩く。
- 次に、一人一人と視線を合わせ、目であいさつしながら、歩き回る。
- 視線を合わせたときと合わせないときの感情の違いを出し合う。
- 最後に、一人一人と握手して、相手の目を見ながら「こんにちは。まるまるです。よろしくお願いします。」と声に出して、あいさつしてまわる。
- 感想を出し合う。
3.自己紹介
- ねらい
- 名前を覚えて親しくなる
- 方法
- 列(輪)になって並び、はじめの人から自分の前の人までの名前を覚えて、順に発表し、最後に自分の名前を付け足して紹介する。
- 隣の人も同様に、自分の前の人までの名前を順に発表し、最後に自分の名前を付け足して紹介する。
(3)校内で実施できるアクティビティ
人権教育担当教員等が、ファシリティ実技研修などの機会を通じて様々なアクティビティの実施方法等を修得した後、自らファシリテータとなって、広く校内の教職員の参加の下に、これを実践する。
1.コミュニケーションスキル -聴いてもらうと気持ちいい-
- ねらい
- 受容的に話を聴いてもらう心地よさを体験する
- 受容的に話を聴く態度を身に付ける
- 方法
- 2人1組(または3人1組)で話し手と聞き手を決める。(3人組の場合は、一人が対話の様子を観察する)
- はじめに、話し手が自分の事(趣味や仕事など)を話し、聞き手は相手と目線を会わさず、相づちも打たないで聞く。
- 次に、話し手は同じ話をするが、聞き手は頷いたり、感心したりしながら聴く。
- 最後に、話し手は同じ話をし、聞き手は共感的な理解を示したたり、時々要約しながら相手の話に合わせて聴く。
- 話し手と聞き手を交代し、同様のことを行う。
- 3つの聴き方に対して、話しているときに感じたことを交流する。
2.自尊感情を高める -あなたの、よいところさがし-
- ねらい
- 自分を肯定的に評価されることで自尊感情の高まりを体験する
- 相手を肯定的に評価する態度を身に付ける
- 方法
- 2人1組になって、一人が相手のこれまでの行動で、よいなあと思ったことを一定時間内(3分)で伝える。もう一人は、自分へのメッセージを頷きながら黙って聞く。
- 聞き手と話し手を交代する。
- 感想を出し合う。
3.価値観の多様性に気づく -ランキング-
- ねらい
- 意見の違いに気付く
- グループでコンセンサスを得る能力を身に付ける
- 方法
- 予め用意されたワークシートを使い、その中の項目を自分が重要だと思うものから順位付けする。
- グループの中で、それぞれの考える順位を、その理由とともに発表する。
- メンバーによって違う順位を、お互いに意見を出し合いながら、グループの意見にまとめる。
- グループごとに発表する。
4.先入観に気づく -フォトランゲージ-
- ねらい
- 人それぞれに先入観や価値観の違いがあることに気付く
- 幅広いものの見方を身に付け
- 方法
- 写真や絵を使い、その中の人の立場に立って考えたり、どの場面なのかを想像して意見を発表する(その際に使う題材には、評価や価値観に異論が出やすいものや違ったイメージで捉えられやすいものを選ぶ。)。
- 使用した題材の説明をする。
- 意見交流する。
(2)教職員のライフステージに応じた研修
事例39:ライフステージに応じた総合的な研修計画
1 目的と概要
個々の教員に求められる役割は、経験年数によっても変わることとなる。人権教育に関しても、個々の教員のライフステージに応じ、適切な研修機会が提供されなければならない。初任者研修、10年経験者研修等の年次研修のプログラムの中にも、人権教育に関する必要な研修内容が盛り込まれる必要がある。
教育委員会・学校においては、ライフステージを通じた総合的な研修機会の提供を行うとともに、個々の教員においても、自らのライフステージに応じ、適切な研修計画を立て、実施していくことが望まれる。
2 対象
全校種の教員
3 ライフステージを通じた人権教育研修の全体計画例
各年次研修等の横の連携を図った研修計画例
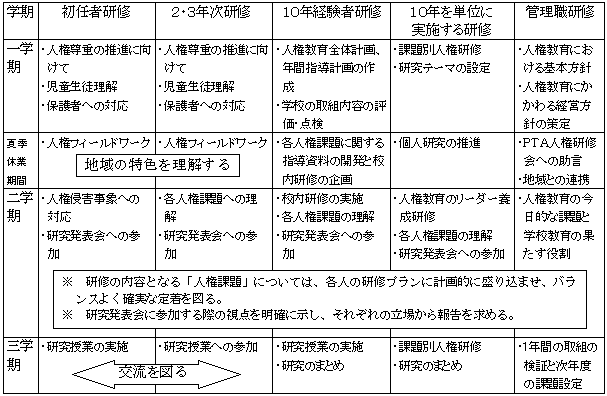
※ 各ライフステージにおける教員に求められる役割と年次研修のねらい
1.初任者研修、2・3年次研修
ライフステージの早い時期には、まず、人権に関する正しい理解と認識を持つこととともに、児童生徒の実態の把握と理解、保護者への対応等、人権教育にかかわる基礎的な知識と技能を習得することが必要である。
2.10年経験者研修
一定の経験経た段階においては、これまでの研修や実践を基礎に、研究会等で授業公開・実践発表ができるような力を身に付けさせたい。また、自らの成果と課題を明確にすることも大切である。
3.10年を単位に実施する研修
経験を積むにしたがい、学年や学校全体としての取組において主導的役割を求められるようになる。また、社会の変化に伴い人権教育の内容も時代と移り変わっていくことや、児童生徒・保護者の意識が、今後ますます多様化が進んでいく等を勘案すると、経験を積むだけでは様々な変化に応じることが難しく、一定の期間を単位とした研修の機会を充実させることが望ましい。
事例40:家庭や地域等との連携によるライフステージに応じた教員研修の全体構想
1 目的と概要
学校教育と社会教育が連携し、総合的に人権教育を推進するために、両者の関連を意識した研修計画を立案する。学校・教育委員会における教員のライフステージに応じた研修と社会教育研修とを相互に密接に連関させ、家庭・地域の取組等とも協力して、総合的な研修機会の提供を図る。
2 研修計画の全体構想例
【全体構想図】
(学校及び教育委員会における研修)
教員のライフステージに応じた研修と家庭・地域の取組等との連携(例)
<教員のライフステージに応じた研修>
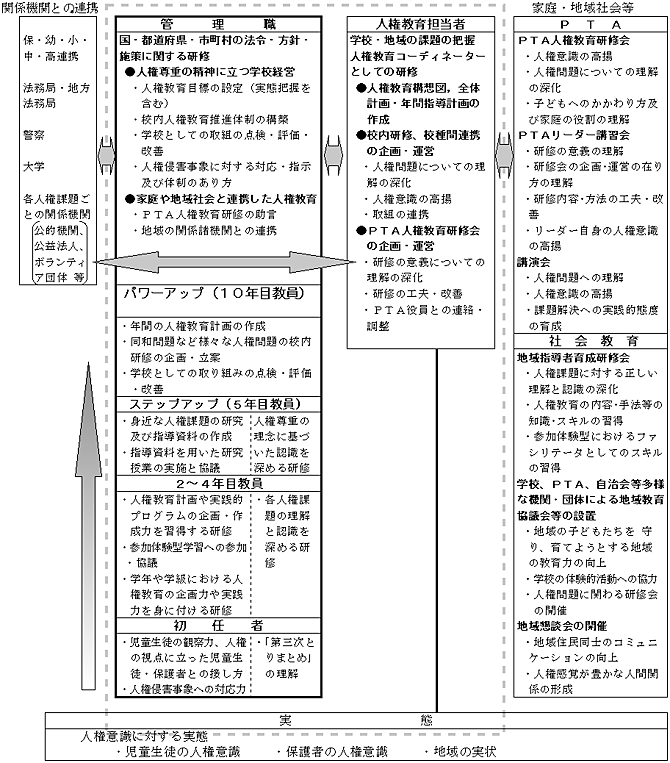
(3)学校と地域等が一体となって行う研修
事例41:教員を地域の人権教育指導者として養成し、活用する研修
1 目的と概要
長期休業期間中の教員が、教育委員会が主催する人権教育の指導者養成研修会に参加し、指導者として必要な知識や技能を身に付ける。研修を終えた教員は、PTAや地域の人権研修会の講師等となり、人権教育指導者としての更なるスキルの向上を図るとともに、保護者や地域住民等の人権意識の啓発等に資する。
2 対象
全校種の教員(人権教育担当者)、保護者・地域住民等
3 長期休業期間を利用した研修の実践例
(1)指導者としての養成
1.夏季休業期間中の教員を対象とする指導者養成研修会
各学校の人権教育担当教員を、地域における人権教育指導者として養成するため、参加体験型の研修方法を体験・実習させ、指導者として必要な基本的な知識と技術を身に付させる。
「教員のための人権学習ファシリテータ入門講座(10回)」
夏季休業日中前期に10回の集中講座を実施する。
【第1~7回】
出会いのための人間関係づくりのトレーニングをはじめとしたファシリテータとしての基礎的な技術を取得し、個別の人権課題について学ぶ。
【第8~10回】
受講者自らがグループでワークショップのプログラムを作成し、発表し合う。
※ 研修の工夫
- 毎回の研修終了後には、各回のポイントをまとめたプリント(「レッツ・コミュニケート」)を配付し、各研修者が研修内容を振り返るための用に供する。
- 講座終了後にはアンケートを行い、寄せられた感想や意見を記録として残す。
- 本講座の修了者を、PTAを対象とする研修会の講師として活用する。
(2)地域における指導者としての実践
1.夏季休業期間におけるPTAを対象とする研修会
指導者としての養成を受けた教員がリーダーとなり、保護者等を対象とした校内での研修会の指導に当たる。教員と保護者等が共通の体験を通して、人権教育の基本的な内容を理解し合い、学校と家庭の連携の基本的な体制を整える。
2.冬季休業期間における地域(青少年対策協議会・民生・児童委員)を対象とする研修会
社会教育及び関係部署との連携を図り、教職員・PTAを対象とした研修と同じ内容の研修会を地域の教育関係者を対象に実施する。この研修会には、教職員・PTAの代表者の参加も求め、三者の共通理解を深めるとともに、その地域における人権教育の基本的な方向性について確認し合う。
事例42:人権週間に合わせた研修の機会の設定
1 目的と概要
学校・家庭・地域が連携した人権研修の取組を、人権週間の活動の中に位置付けて、様々な対象者別の研修会を企画・実施するとともに、教員、保護者、地域住民等が一堂に会する場を設定することにより、相互の理解促進と連携体制のより一層の充実を図る。
2 対象
全校種の教員、保護者、地域住民等
3 教員・保護者・地域を対象とした研修の実践例
(1)教員を対象とする研修
1.研究発表会への参加
教育委員会が指定する人権教育の研究奨励校が研究発表を行う。研究発表には、全学校の参加を求め、研究の成果については、各学校における教育活動に還元させる。
2.「○○○学校 人権研究発表会」の開催
授業公開や人権意見発表会、教育講演会を実施し、お互いの人権を尊重し合うことの大切さについて参加者とともに理解を深めていく。
- ※ 参加者
- 児童、保護者、教職員(他校の参観者を含む)、人権擁護委員、民生委員等
- ※ 内容
- 道徳の授業公開(各教室)
- 人権意見発表会(体育館)
- 教育講演会
(2)保護者、地域住民等を対象とする研修
1.保護者のための人権教育集中講座の実施
保護者を対象として、複数のテーマの人権教育講座を、連続して実施する。文部科学省が配付している「家庭教育手帳」等も活用し、人権教育のテーマと子育てとの関連性を持たせるよう、研修内容の調整を行う。PTA組織に働きかけ、全ての学校の保護者が何らかの形で参加するよう協力を求める。
2.人権学習会等の実施
学校を開放し、保護者や地域住民等が自由に参加できる学習会等を開催する。
- ※ 参加者
- 保護者、地域関係者、教職員等
- ※ 内容
- 人権に関する作文の朗読
- 国語科や道徳の時間等に指導した人権作文を活用
- 人権啓発ビデオの視聴
- 人権コンサート(例;「響きあうしあわせ・よろこびのうたコンサート」など)
- 音楽家を招聘して講演・演奏会を開催
(3)教員、保護者、地域住民が一同に会した研修会
1.人権フォーラムの開催
教育委員会等と関係各部局・機関が連携して、教員、保護者、地域住民が一同に会した研修会(「人権フォーラム」)を開催する。
研究奨励校の発表、各学校における実践の紹介など、学校による積極的な参画も求めるとともに、保護者・地域住民等を対象とする課題別研修や、講演会、体験型の研修の機会も設定し、様々な観点から、人権意識の啓発と高揚を図る。
- ※ テーマ「育てようこころのちから」
- ※ 発表内容
【学校教育部門】- 研究奨励校の研究発表(公会堂ホール)
- 各学校の人権教育に関する実践発表パネル展(公会堂ロビー)
- 人権講談会;人権をテーマにした講談師による講演
- 課題別ワークショップ
- 家庭の中でできる男女共同参画-女性がいきいきできる社会-(女性の人権)
- 子どもの心の叫びがきこえますか?(子どもの人権)
- 考えてみましょう 差別をなくす一言を、自分にもできることを(同和問題)
- 地域で働く外国人(外国人の人権)
- 体験型研修
- 楽器を通してつながろう!わたしとあなたと世界と
2.人権週間における成果発表と「市民のつどい」
市教育委員会と市長部局担当課等のコーディネートにより、人権週間を、人権教育・啓発の1年間の取組を総括する期間として設定し、学校、地域等において様々な成果発表の機会を設けるとともに、課題の検証を行い、次年度へとつなげる。
さらに、人権週間中の日曜日には、学校・家庭・地域の関係者が一堂に会す場(「市民のつどい」)を設け、相互の交流を図る
人権週間における成果発表、課題検証等の取組
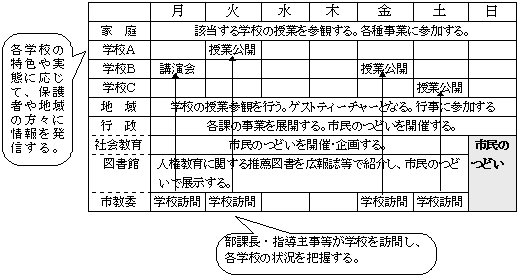
お問合せ先
初等中等教育局児童生徒課