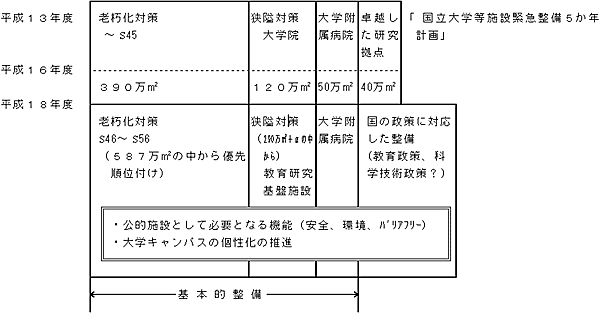|
既存施設の再生整備(老朽化対策)
老朽化対策の必要性
| ○ |
大学においては教育研究等の活動を支える基礎的基盤である施設を有効かつ効率的に活用し、また安全性を確保するために、老朽化した施設の改善を図ることが最重要の課題である。 |
現行耐震基準制定前の施設の改修整備
| ○ |
既存施設の再生整備については、「緊急整備5か年計画」において、緊急に改善すべき対象として昭和45年以前に整備された施設の老朽改善整備(約390万m2)を進めている。これらの施設整備に引き続き、現行の耐震基準制定前(昭和56年以前)に整備された施設(約590万m2)のうち、現行基準が求める耐震性能を満たしていない建物について耐震性能の向上等のための老朽改善整備を図る必要がある。 |
| ○ |
但し、老朽化対策が必要な施設整備需要は膨大であるとともに、これらを計画的かつ効果的に進める必要があることから、地震防災に係る地域性、建物の耐震性の状況や教育研究の活性化への効果などにより、優先順位を付けつつ計画的に整備していく必要がある。 |
改修整備の目的の明確化
| ○ |
なお、改修整備を行う際には、その目的が単に機能上、構造上の経年劣化の解消だけではなく、改修の後に行われる教育研究等の活動が大学の理念・目標や社会のニーズに対応し、整備はそのことを実現するために行われるということを社会に明らかにする必要がある。 |
|
 |
必要なスペースの確保(狭隘化対策)
各大学の状況に応じたスペースの確保
| ○ |
「緊急整備5か年計画」では、「大学院施設等の狭隘化の解消」等の観点から5年間で緊急に整備すべき施設について重点的・計画的な整備が進められているが、この他にも同計画の策定時点で狭隘化の解消を目的として約290万m2の整備需要が存在している。この中には、法人化後特に重要性が増す学生の教育研究のための基盤的な施設も含まれており、重点的な整備が必要である。 |
| ○ |
また、今後、大学院生、留学生等が引き続き増加することや新たな教育研究の展開のためのスペースが必要となると見込まれるところもあり、既存施設の点検・評価による既存施設の有効活用を前提として、各大学の従来からの施設整備状況を踏まえ、必要なスペースの確保のための整備を行う必要がある。 |
学生教育研究基盤施設の整備
| ○ |
特に大学にとって基本的機能とも言える学生の教育活動、研究活動のために基盤となる施設については、国際的に遜色の無い水準とすべく重点的に整備を行う必要がある。 |
| ○ |
具体的には、学生の活発な教育研究活動を直接的に促す重要な基盤として、多様な媒体による情報拠点である図書館の充実や情報化の進展に対応したマルチメディア対応の講義室や自学自習スペース等の確保などが考えられる。また、間接的には、大学は、学生等の主な生活の場であり、人間形成の場ともなっていることから、談話や交流のためのスペースや食堂等の福利施設、さらには屋外環境等についても整備することが重要である。
なお、これらの施設を整備する際に、利用者の利便性、施設の効率的運営を考慮して、既存施設の増築や複合施設として計画することを検討する必要がある。 |
| ○ |
さらに、大学等では学生、教職員が教育研究をはじめとする多種多様な活動を日常的に展開する場であることから、事故や災害を防止するために安全性の確保に十分配慮する必要がある。特に実験研究施設においては様々な化学物質や実験機械・器具を取扱うことから関係法令に則った安全対策を適切に講じる必要がある。 |
|
 |
附属病院の整備
| ○ |
附属病院については、施設の老朽化とともに、医療の高度化等に伴う医療機器の増大、医療制度・社会の変化に伴う患者ニーズの多様化等による狭隘化の問題があり、「緊急整備5か年計画」においては、これらの問題を解決するために再開発整備が行われている。 |
| ○ |
今後とも先端医療、臨床医学の教育研究、地域医療の中核を担う機関として、適切な教育研究活動、医療活動等が行われるよう、附属病院施設の運営コスト等を踏まえつつ、引き続き整備を図る必要がある。 |
|
 |
公的施設としての機能の確保
省エネルギーなど環境への配慮
| ○ |
大学キャンパスは、数千〜数万の学生、教職員が多種多様な活動を行っており、電気、ガス等の消費されるエネルギーも膨大である。施設の管理運営コストの観点から、施設整備時や運営における省エネルギー対策を行うことは重要であり、また、このことは、エネルギーの効率的利用や地域環境の保全にもつながることになる。 |
バリアフリー化等
| ○ |
少子化・高齢化が進み、また生涯学習のニーズが高まっていることから、大学キャンパスは、バリアフリーにも配慮して、既存の学生だけでなく社会人をはじめ、すべての世代に目を向けた施設としての整備する必要がある。また、海外からの研究者、留学生等に対して、適切な標識や掲示版を整備するなどの対応も求められる。 |
安全対策
| ○ |
大学施設の多くは、災害時には学生、教職員の安全の確保のみならず周辺地域住民の応急避難場所としての役割も求められていることから、相応の整備を積極的に図る必要がある。 |
|