| a) |
鉄骨軸組筋かい耐震性能 ISB |
| |
ア)算定方法
当該建物の桁行方向耐震要素が鉄骨軸組筋かいである場合、次式により鉄骨軸組筋かい耐震性能ISBを算出する。なお、桁行方向耐震要素が鉄骨軸組筋かい以外(鉄筋コンクリート造壁など)である場合は、分類をAとする
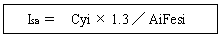 |
| |
ここで、Cyiは、鉄骨軸組筋かいの降伏層せん断力係数の推定値で下記による。
| |
構造計算書がない場合:Cyi=0.25
|
|
構造計算書がある場合:Cyi=0.22×(f/σ)min
|
| | |
(f/σ)minは筋かい部材の短期許容応力度の地震時作用応力度に対する比(余裕度)で、構造計算書より読み取る。なお、複数の筋かいについて計算している場合は、それらの最小値を採用する。
|
また、Aiは、建築基準法施行令第88条のAi、Fesiは同令第82条の4にいうFesと見なして評価する。なお、下記に該当する場合はその数値を採用してもよい。
| |
鉄骨造平屋建の場合: |
|
AiFesi=1.0 |
| |
鉄骨造の2層の場合: |
(第2層) |
AiFesi=1.4 |
| |
|
(第1層) |
AiFesi=1.0 |
| |
RS造又は複合構造*21の2層の場合: |
AiFesi=2.0 |
|
| |
イ)評価ランク
上記ア)で算出したISBの値により、下表のとおり分類する。
| 分 類 |
A |
B |
C |
| ISBの値 |
0.7以上 |
0.3以上0.7未満 |
0.3未満 |
|
| b) |
鉄骨腐食度 F
ア)算定方法
代表的軸組材と露出型柱脚に対して下記により評点を付け、その平均値Fを算出する。
なお、露出型柱脚が無い場合(確認できない場合を含む。)は、代表的軸組材のみにより分類する。なお、鉄骨腐食度の状況は、「既存鉄骨造 学校建物の耐力度測定方法(改訂版)3.2.4 鉄骨腐食度」を参考にして、目視調査により判断する
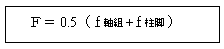
| |
f軸組は、代表的軸組材の腐食度、f柱脚は、露出型柱脚の腐食度で、下記の区分による。なお、露出型柱脚が無い場合(確認できない場合を含む。)は、F=f軸組とする。 |
| |
| 腐食度の区分 |
| 無し |
1.0 |
| 仕上げ錆 |
0.8 |
| 部分錆 |
0.6 |
| 欠損錆 |
0.3 |
|
イ)評価ランク
上記ア)で算出したFの値により、下表のとおり分類する。
| 分 類 |
A |
B |
C |
| Fの値 |
0.8以上 |
0.6以上0.8未満 |
0.6未満 |
|
| c) |
座屈状況 N
ア)算定方法
代表的軸組材について、局部座屈と全体座屈に分けて下記により評点を付け、その相乗値Nを算出する。なお、座屈状況の状況は、「既存鉄骨造 学校建物の耐力度測定方法(改訂版)3.2.5 座屈状況」を参考にして、目視調査により判断する。
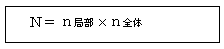
| |
n局部は、代表的軸組材の局部座屈、n全体は、代表的軸組材の全体座屈で、下記の区分による。 |
| |
| 座屈状況の区分 |
| 無し |
1.0 |
| 軽微 |
0.8 |
| 明確 |
0.6 |
|
イ)評価ランク
上記ア)で算出したNの値により、下表のとおり分類する。
| 分 類 |
A |
B |
C |
| Nの値 |
0.7以上 |
0.5以上0.7未満 |
0.5未満 |
|
| d) |
溶接状況 M
ア)算定方法
代表的ラーメン架構の柱梁溶接仕口部の状況について調査し、下記によりMを算出する。
なお、溶接状況は、「既存鉄骨造 学校建物の耐力度測定方法(改訂版) 3.2.8接合方式」を参考にして、目視調査により判断する。
| |
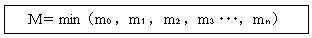
mnは、代表的ラーメン架構の柱梁溶接仕口部の溶接状況で、調査した箇所の中の最低のmをMとする。 |
| |
| 溶接状況の区分 |
| 異常なし |
1.0 |
| 変形*22 |
0.7 |
| 破損*23 |
0.4 |
|
イ)評価ランク
上記ア)で算出したFの値により、下表のとおり分類する
| 分 類 |
A |
B |
C |
| Mの値 |
1.0 |
0.7 |
0.4 |
|
| e) |
構造安全性
代表的軸組材等について、下記の3項目を調査し、下表のとおり分類する。なお、いずれかの項目でも該当する場合は、分類をCとする。
(表2.3.12)代表的軸組材等における危険性の有無による分類 |
| 分 類 |
A |
C |
| 危険性の有無 |
認められない |
認められる |
| 危険性に関するチェック項目
|
| イ |
代表的軸組材及びその接合部に関して、設計図書と現状との構造
耐力上重要かつ危険側の食い違い。(部材の欠落、断面サイズやボルト本数の違いなど) |
| ロ |
代表的軸組材及びその接合部に関して、錆及び座屈以外の著しい変形や損傷、断面欠損、鉄骨部分の亀裂など。 |
| ハ |
桁行方向架構に関する軸組筋かいの一部撤去など。 |
|
| f) |
落下物等に係る安全性
当該屋内運動場において、下記表の例に示すような転倒、落下等の危険性のある構造部材等の有無を調査し、下表のとおり分類する。なお、1箇所でも、転倒、落下等の危険性のあるものが確認された場合は、分類をCとする。
(表2.3.13)落下物等の危険性の有無による分類 |
| 分 類 |
A |
C |
| 危険性の有無 |
認められない |
認められる |
| 転倒・落下等の危険性のある箇所の例
|
| イ |
ブロック壁[面外への転倒など] |
| ロ |
屋根面筋かい又は屋根構成材(小梁等)[接合部での破断による落下など] |
| ハ |
コンクリート内に埋め込まれた鉄骨定着部(柱脚、梁定着部等)[損傷によるコンクリート片の
落下など] |
| ニ |
壁仕上げ材、吊り物、天井材等[落下など] |
| ホ |
床組支持材(束材)[移動、転倒など] |
|
| g) |
想定震度
当該建物が立地している地域の想定震度を調査し、その結果により下表のとおり分類する。なお、想定震度が設定されていない場合は、分類をBとする。
| 分 類 |
A |
B |
C |
| 想定震度 |
震度  強以下 |
震度 弱 弱 |
震度 強以上 強以上 |
|