| 1. | 保健師・助産師・看護師に共通した看護学の基礎を教授する課程であること |
| 2. | 看護生涯学習の出発点となる基礎能力を培う課程であること |
| 3. | 創造的に開発しながら行う看護実践を学ぶ課程であること |
| 4. | 人間関係形成過程を伴う体験学習が中核となる課程であること |
| 5. | 教養教育が基盤に位置づけられた課程であること |
2.看護生涯学習の出発点となる基礎能力を培う課程であること
看護学は、図1のとおり、4年間の学士課程での学修を基盤に、生涯にわたり、看護実践体験を通して研鑽を重ねつつ専門性を深める学問である。この研鑽の方法には、大学院での系統的学修も含まれる一方で、日々の実務の中で特定の専門的能力を高める方法や各種の研修・講習への参加も含まれる。そのため、学士課程では、生涯にわたり専門性を深めていくための基礎能力を確実に培っておくこと、すなわち、看護生涯学習の基盤を創ることが大切である。
大学院での看護学教育では、教育者・研究者育成、高度な実践者・指導者*4育成が行われている。いずれにおいても、個人の看護実践体験が重要な意味を持つ。それは、看護実践が看護職者自らの人間的かかわりを介して援助としての意味を成すという特質を持つためである。学士課程卒業直後に、一定期間の実務経験を通して看護の意味を自ら理解していく過程を踏むことは、専門性を深める上で重要であり、さらには看護の研究をする場合も極めて重要な意味を持つ。他の医療専門職では、6年一貫教育の方法を採用している分野もあるが、看護学は、上記の特質上、学士課程卒業後の看護実践体験を織り込んだ大学院教育が追究されている。
したがって、学士課程においては、看護学の特質を十分理解し、看護実践を体験することへの関心を深めることは当然であるが、自分の看護実践体験を客観的にとらえ、それを基点に継続して自己を成長させる能力が求められる。
| 図1 学士課程における看護学教育を基盤とした看護生涯学習 |
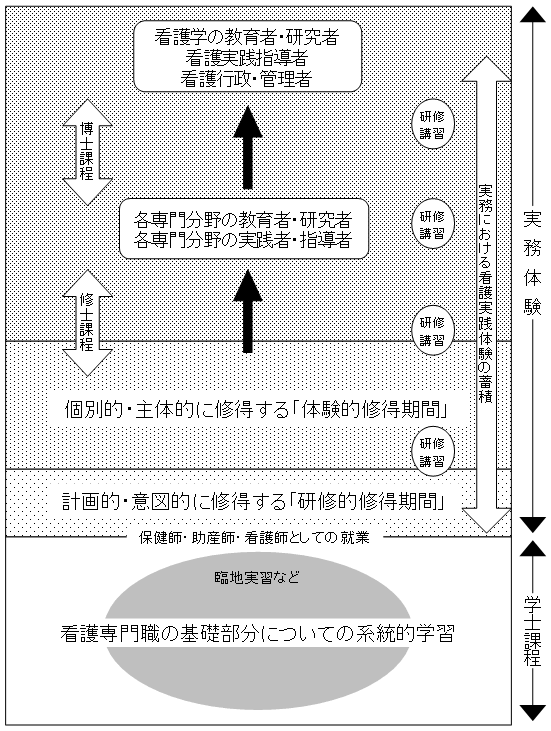 |
3.創造的に開発しながら行う看護実践を学ぶ課程であること
1)利用者ニーズの充足に向けた方法の開発
日々の看護実践は、利用者のニーズの充足に向けられる。そのニーズは、個別的で多様であるので、慣例的に実施している方法だけでは、解決できないことが多い。したがって看護職者は、日常的に主体的・創造的に開発しながら、利用者のニーズ充足に向けた看護実践を行っている。学士課程では、このような日常的な看護実践の開発について教育する必要がある。
看護職者は、医療施設だけではなく、極めて複雑な生活の場で看護上の問題をとらえる。最も複雑なのは、利用者とそのケアにかかわる人々との人間関係の中で、問題解決を図っていくことである。慣例的で一般的な手法による対応方法だけでは、問題を解決できない場合もある。したがって、事例等を用いて、利用者ニーズ充足のために、どのような創意工夫による看護が行われたか、その事実や実施した看護職者の考えから学ぶ事が大切となる。
2)学士課程の集大成に位置づけられる卒業研究
創造的な看護実践は、看護学実習においても学習されるが、創造性の追究を系統的に学習するのが卒業研究である。多くの看護系大学で、卒業研究が教育課程に位置づけられており、自己学習を重視し、個別に研究指導がなされる場合がほとんどである。この科目は、学士課程の集大成と位置づけられ、卒業後に研鑽を重ね、創造的に専門性を深めるための基盤を形成するという意味で、看護生涯学習の出発点となる。そのため、卒業研究については看護実践の創造的な開発を追究するための基礎能力を育成するという観点から、何を、どこまで修得させるのかを明示する必要がある。看護事象と関連のない一般的な研究手法の修得を目指したり、看護実践から乖離した研究指導をしたりするのではなく、看護実践の改革と深くかかわりを持った指導をすることがとりわけ大切である。
3)看護実践の改革に向けた指導能力を有する教員による指導
創造的に開発しながら行う看護実践の教育に必要なのは、教員の看護実践における指導能力である。看護学を担当する教員には、十分な看護実践能力を有していることはもちろんのこと、学生に看護実践を改革していく必要性を伝え、その実施方法を教授する能力が求められる。そのため、研究活動についても、上記の教育を導くのにふさわしい質的要件を備えていること、すなわち、利用者のニーズ充足に向けた方法を創り出す看護の魅力を伝え、創造性を高める道筋を示すことにつながるものであることが重要である。これらの研究活動は、教員の行う講義・演習及び臨地実習における教育内容や方法にも現れてくる。
教員の研究活動は、本来、多様な性格のものが混在してこそ、学問の確実な基盤となる。しかし、看護学において最も期待されているのは、国民のヘルスケアニーズに対応して、質の高い看護サービスを提供できる人材の供給であるので、教員には看護実践改革へと導く指導能力が問われる。その意味では、現時点では、看護実践の改革にかかる研究が重要である。
4.人間関係形成過程を伴う体験学習が中核となる課程であること
看護は、看護職者という人間が利用者と接しながら利用者のニーズを満たすものであり、看護職者がどのような人間関係を形成するかによって、看護の質が左右されるという特徴がある。看護は、ヒューマンケア、すなわち人権の尊重を基盤にした健康生活の支援であり、実施に際しては、正確な知識・技術と豊かな人間性に基づく行為が求められる。
したがって、学士課程では、学生が看護を実際に体験する中で、利用者と直接対峙し、援助的な人間関係の形成について学ぶことが重要である。その人間関係を基盤にして看護の諸目的を遂行する方法を体得する。この学習では、看護倫理にかかる教育の強化が極めて大切となる。
近年、人々の健康生活を支援する職種が増え、専門職種以外の人々も、多様な立場で健康生活支援にかかわるようになっている。これは、社会が成熟し、個人や社会が人間らしい生活を求めてきた成果であり、極めて好ましいことである。だからこそ、子どもから高齢者に至るすべての健康課題について、看護職の社会的役割や他職種との違いが厳しく問われている。特に、診療や療養生活支援を受けながら地域社会での生活ができるようにと、在宅ケアの推進等、医療施設外での看護への期待は大きい。看護職者に対しては、ヒューマンケアの担い手としての実践能力や倫理的判断力が求められている。
5.教養教育が基盤に位置づけられた課程であること
学士課程の特色のひとつに、教育課程の中に教養教育が組み込まれていることがあげられる。教育課程における教養教育の位置づけや教育方法は、各大学が人材育成の目的・目標や教育理念に基づき独自に設定するものである。本章では、看護実践能力育成の観点から、看護系大学の学士課程に共通する基本的な在り方について論じ、各看護系大学における教養教育の一層の充実を期待したい。
1)看護系大学の学士課程における教養教育の位置づけ
大学基準協会は、1991年の大学設置基準大綱化を受け、「看護学教育に関する基準」*5を策定した。この中で看護学の授業科目は、教養科目・専門関連科目・専門科目の3つに区分された。教養教育は、専門科目及び専門科目と関連の深い学問領域を含む専門関連科目とは別に、卒業生が一人の人間として求められる能力、すなわち確実な価値観に基づく判断力や行動力を身につけるために必要であるとしている。また、2002年の中央教育審議会答申*6は、新しい時代に求められる教養とは何かの記述の中で、「個人が社会とかかわり、経験を積み、体系的な知識や知恵を獲得する過程で身に付ける、ものの見方、考え方、価値観の総体」としている。
本報告では、より質の高い看護実践能力の育成を追求する立場から、教養教育を看護学の専門技術や知識の学習に直接関連してくる教育内容とは別にとらえ、21世紀社会に生きる人間の育成にかかわる他の学問領域の学習を広く教養教育として位置づける。
2)看護学教育において教養教育が重要な理由
看護職の活動は、人間や人間の生活に深くかかわりながら、利用者の人としての生き方・希求・価値観に沿って、その人の健康生活と自己実現を支えるという特色を持つ。その過程では、個別的状況に応じた深い人間理解と、人間的・倫理的な判断力が問われる。その意味で、広い視野での見識や多様な価値観の育成が期待される。
また、学生は卒業直後から、看護実践を通して人とのかかわりや社会との関係性を深め、自己と周辺の世界との関係性をとらえ、自分自身を育て自己実現を追究する。そのための基礎的な力を培うという意味での教養教育の持つ意味は大きい。
さらに、学士課程の卒業者は、将来、看護職集団や保健・医療・福祉チームの中で指導的役割を担うことも期待されている。そのため、指導者や責任者にふさわしい幅広い教養や豊かな人間性を育成することが大切である。
3)教養教育充実のための課題
教養教育充実のための課題は、各看護系大学が自大学の教育の理念と目標に応じた教養教育の目指すものを明確化し、それに基づいた論理的・系統的な科目・科目群の設定をすることである。特に大切なことは、学生に対して、学士課程の教養教育の目的や履修の意義を説明する等、履修指導を強化することである。
そのためには、教養教育に関する教員の意識改革が重要である。教養科目については、看護学の教員は直接関与していないために、教養教育の意義やその教育方法の充実について、主体的な議論や検討をする機会に乏しい。教育課程の充実を図るには、教養科目、専門関連科目、専門科目全てを含む課程全体を視野に入れる必要がある。したがって、個々の教員が教養教育に深い関心を持つことが大切である。
| *2 | 「21世紀に向けての看護職の教育に関する声明」1999-1-30 「21世紀に求められる看護学教育−高度な看護実践の実現に向けて」2000-2.学長・学部長会 |
| *3 | 「21世紀の看護学教育−基準の設定に向けて−」1994-3 |
| *4 | 高度な実践者・指導者には、専門看護師等がある。専門看護師(Certified Nurse Specialist,
CNS)は、日本看護協会が認定する資格であり、その教育課程は日本看護系大学協議会が認定している。この課程認定基準( H10.6.22制定)によると、専門看護師は、ある特定の看護分野において「卓越した看護実践能力」を有することとし、専門看護分野において、実践・教育・相談・調整・研究・倫理の6つの役割を果たすことが、「共通能力水準」として示されている。 |
| *5 | 「21世紀の看護学教育−基準の設定に向けて−」1994-3 |
| *6 | 「新しい時代における教養教育の在り方について(答申)」2002-2 |