| 資料3 |
| ア | 保健師・助産師・看護師に共通した基本を教授する看護学の専門の基礎課程であること, | |
| イ | 大学院教育によって専門性を深めるための基礎を学ぶ課程であること, | |
| ウ | 創造的に開発しながら行う看護実践を学ぶ課程であること, | |
| エ | 正確な技術の基礎の教育とともに,人間関係形成過程を伴う体験学習が中核となる課程であること, | |
| オ | 教養教育が基盤に位置づけられた課程であること |
| 看護学の学士課程は、保健師・助産師・看護師の国家免許資格に繋がる専門職業教育型の課程である。学士課程で看護学を修めた卒業者は,社会に機能するときは、それぞれの国家試験を受けて免許を取得するという制度原理に基づいて発展してきた課程である。 大学課程が開始された当初は,三職種の「統合教育」と言われ、単なる「統合」であった時代には,卒業要件となる単位数は140単位以上に及び,授業時間割は過密であったが,近年では,大学教育が成熟化とともに,124単位に近づき,大学課程に相応しい主体的学習条件づくりができるようになってきた。この背景には,教授内容の精選や教授方法の開発とともに,大学院教育の進行も深くかかっている。すなわち,大学院ではより専門性の高いものを教授し,学士レベルでは,「看護学の専門の基礎」を教授するという形で,学士・修士課程各レベルの教授内容の棲み分けができると同時に,学士課程の教育内容の精選と統合が着実に進んできた。 しかし,看護学の大学教育は,発展途上にあるために,すべての大学が上記の段階に達しているとは言いがたく,各大学が学士課程の教育について,一層の充実を図るべき時期にある。次に、学士課程の考え方を確認するため、3職種の教育という観点から検討しておきたい。 |
| 1) | 保健師について 看護学の学士課程の中で,保健師の受験資格につながる教育をすることは,1952年の学士課程開始時より,統合教育などと称して比較的理解され易い状況があった。 わが国の保健師の誕生は,保健所に看護職員を配置したことから始まった。その後、就業の場は,保健所・市町村など地方自治体の保健福祉事業を担う看護の技術職として発展した職種である。そのため、教育内容については,看護の保健・福祉行政の成り立ち、行政サービスとしての各種事業の特性に及ぶ学習が必要となる。 保健師は,行政サービスの枠組みで中での保健・福祉活動、予防の諸活動における看護の専門性を生かした役割に関し,社会変化に応じて住民ニーズへの対応方法を常時開発していかなくてはならない立場にある。また、わが国の保健予防の体制は、学校・産業の場について,地域とは別立ての仕組みがある。近年,これらの場でのヘルスケアニーズは多様になり,学校看護・産業看護の充実の必要性が高まっていることも忘れてはならない。 現在107大学で定員8081名が保健師免許への受験資格を付与する教育体制となっている。しかし、平成13年度の卒業状況では,表1のとおり,63大学・4847名の卒業者のうち,保健師就業者は447名で、そのうち保健所56名・市町村309名である。保健師への就業は、需要量・採用数の減少などに著しく影響を受け、就業志望者数は増大しても,就職できずにいるという現状である。 一方、従来からの保健師養成所・短大専攻科は,58校・1888名の卒業者を出し、保健師就業者821名(保健所88・市町村487)である。大卒とあわせて保健所144・市町村796、合計943名が平成13年度の需要量であり、この数字は近年縮減している。ことに自治体の合併問題を控え、市町村の採用は著しく抑制され、今後は改めて自治体の行政サービスに看護職の専門性で住民サービスがどのように充実し得るかについて、強力なPR活動が必要となっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 看護師について
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師養成が医療施設の要員養成という色彩が強かった時代は,教育内容が施設内看護に際し必要となる技術中心であった。その時代には,外来療養生活支援・退院支援・訪問看護活動など,施設外に及ぶ看護活動については,病院が保健師有資格者を採用して担当させていた。近年では,医療施設利用者のニーズが変わり,慢性疾患を持ちながら社会生活をする人のケアへの支援が求められ,その対応への認識も変化し,看護師がこれらの活動や在宅看護・訪問看護に従事するのは当然と考えられるようになっている。看護師教育課程でも、生活の支援、在宅看護の視点が強化された。したがって、保健師の資格の有無を問うことなく、看護師の基本的能力の中に、従来保健師教育で付与した療養生活支援は包含されているものと考えられるようになった。 さらに,看護師の対応の現実においては,健康に関する学習支援の方法、健康管理支援に加えて、保健・医療・福祉チームの中での調整や社会資源の活用支援などにかかわる能力が求められる事態となっている。 学士課程においては、当初から看護師・保健師などと職種区分することなく,これらの能力を統合した形で,教育内容の精選と効果的な教育方法の創出を進めてきている。この方向での人材育成活動は,社会の要請に効率的に応える方法で,今後もいっそう強化していかなくてはならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 助産師について 助産師の学士課程での教育は、1967(昭和42)年に開始され、その後次第に増設された。基本的には、「看護学の専門の基礎」の課程の中で履修するが,助産科目の一部を各大学が定めた選択必須または自由科目により必要な単位を取得する形となっている。この方法によって、現在では、107大学のうち73の学士課程で国家試験の受験資格を付与する教育がなされている。上記の助産科目の一部に該当するものとして助産実習があげられる。これは学士課程の基本となる臨地実習とは別に,さらに分娩介助の実習を加えるのであるが,指導できる学生数を制約しつつ十分な指導体制を整えているのが現状である。 これらの教育課程の編成は,各大学が学士課程での人材育成の本来的意義を踏まえ,方法を多様に開発してきた。看護学の学士課程教育では,専門科目のうちでも、いずれかの看護分野を選択して履修する部分を開発することは,極めて重要で,助産師の国家試験の受験資格の付与に不可欠な実習等教育内容の担保は,この選択必須科目の中で行うことができる。また,自由科目などで履修するにしても学生負担が過重にならない方法を開発し,定着してきている(後日資料提供)。 また,助産師教育として重要となる学習内容には,次代を育む女性や家族を対象とした、生涯にわたる健康やリプロダクティブヘルスの支援技術が位置づけられる。これらの支援方法は,看護師及び保健師の活動にも必須のものであり、看護職者の基盤として教育されている。教授方法などについては、その実態について事実検証と共通認識のものとに,現段階では,学士課程としての基礎的人材育成の意義を一層発展させる努力が必要である。 助産師の大学課程での養成数,国家試験受験数,資格取得数,就業数など,実態調査が必要である(改めて調査予定・後日報告)が,とりあえず,国家試験受験者数で見ると,表のとおり,349名である。卒業後の就業状況は,後日実態調査を行い,報告予定である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護学は、図(次頁)のとおり,4年の学士課程を基礎に実践体験を加味しながら,大学院教育で専門性を深める学問領域である。したがって,学士課程の要件としては、将来に亘り専門性を深めていくための基礎能力を育成しておくことも大切となる。学生時代に看護生涯学習の基盤を創るという意味である。 看護学の大学院では、教育者・研究者の育成も重要であるが、国民のヘルスケアニーズに応えるためには、「専門看護師*」というような形で,卓越した看護実践能力を持ち実践の改善・開発に貢献できる者,すなわち高度な看護実践提供者・指導者を多様な看護分野について供給していく体制づくりが不可欠である。 また,看護学領域では、教育者・研究者育成,高度な実践提供者・指導者育成のいずれについても、専門性を深める大学院教育に際しては、看護実践に関する一定の経験が重要となる。それは、看護援助というものが、看護職者自らの人間的かかわりを介して意味のあるものにしていくものであるためである。卒業直後における一定の実務経験の中では,看護の意味を自ら理解していく過程を体験するのであるが,それは,専門性を深めていくとき、あるいは看護の研究をするとき、重要な意味を持つ。 近年、他の医療専門職では,6年一貫教育の方法を採用しているけれども、看護学においては、学士課程でその専門の基礎を学修した後に,一定の看護実践体験を経て,大学院などで系統的学修を重ねる方式を追究している。その意味では、学士課程では、看護学の特質について十分理解し、関心を深め、自分の看護実践体験を客観的に確認しつつ、自己成長を取り組むことができる能力を育成することである。看護実践の中で,看護対象者と人間関係を形成しつつ支援することを重ね、実践の場での研鑽を積むことが,看護学の専門性を深める基盤である。 |
| 脚注: | 専門看護師は,1996年度(平成8)から日本看護協会が導入し,個人を審査して認定する方式を採用している。教育課程は、日本看護系大学協議会が1998年度から認定開始している。この課程認定基準(
H10。6。22制定)によると,専門看護師は、ある特定の看護分野において「卓越した看護実践能力」を有することとし,専門看護分野において、実践・教育・相談・調整・研究・倫理の6つの役割を果たすことが,「共通能力水準」として示されている。 |
| |
| 看護実践体験を通して 専門性の発展基盤形成をする看護学の特徴 |
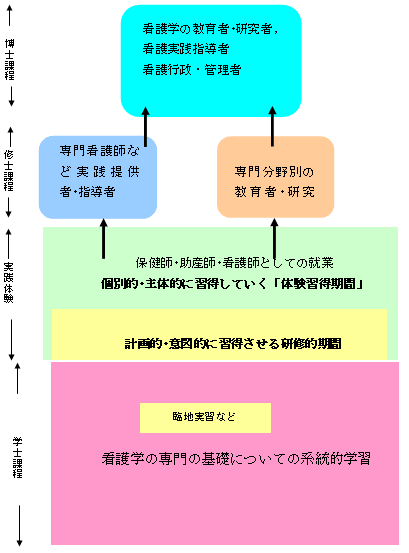 |
| 看護実践の場での看護職者の活動の中核は,援助対象者側の存在するニーズの充足に向けられる。ニーズは,個別であるのは当然であり,極めて多様に複雑で,慣例的に実施している現有の方法や条件では解決困難なことが多い。したがって,看護職者は,対応方法を常に創造的に開発することが不可欠で,この作業を抜きにしては,看護の質の向上はありえない。学士課程では,この側面を伝える教育上の取り組みを意図的にしなくてはならない。 医療の場ばかりではなく,どこにあっても,看護職者は,人々の生活の原点で課題を捉えるのであるが,その解決には,治療やケアにかかわる人々の問題意識に迫りながら協力を求めて対策をして行く。そのため,実習などでの学習では、慣例的で一般的な手法での対応を覚えるだけでは、目的を達成できない。実践改革者としての人材育成面では,利用者ニーズへの対応のために,看護職者がどのような取り組みをしたのか,その事実の紹介やそれを実施した看護職者の考え,看護の場への影響などを学ぶ事が大切である。 |
| 1) | 大学における教育活動と研究活動との関係の見直しの必要性: 現在,大学教員の採用では研究業績が問われ,さらには大学評価においても業績が評価されている。看護学固有の業績評価基準が必要なところであるが,看護学の教員の研究では,上記の学士課程の教育を導くに相応しい質的要件を備えた研究活動が重要となる。 すなわち,看護学の教員としては,最低限でも,学生に向けて看護実践の改革を導くことの必要性と,その実施を導く方法を教授できる研究実績・業績が必要である。看護実践が常に看護を受ける人のニーズ充足に向けて,その対応方法を創り出す仕事であり,その仕事の魅力と,専門性を深める道筋を導くに十分な実績・業績こそ重要である。これらの実績は,教員の行う講義・演習及び臨地実習における教授内容と方法にも現れてくるものである。 研究活動は,本来多様な性格のものが存在してこそ,学術の発展を促すこととなる。しかし,看護学においては,大学教育が前述した社会目標に向け期待されてきたという事情を考えるとき,看護実践の改革を目指した組織的取り組みに貢献できる研究を現時点では最優先されなければならない。このような看護学の現状に相応しい研究方法の開発が必要である。 |
|
| 2) | 4年課程の集大成に位置づけられる卒業研究の見直しの必要性: 看護学の学士課程では,他分野と同様に,卒業研究が行われている。科目名称は多様であるが,自己学習を重視し,多くは個人別研究という形式で指導される。この科目は,看護学の学士課程の集大成と位置づけられ,卒業後に研鑽を重ね専門性を深めるための基盤を付与するという意味で,看護生涯学習の出発点となる。 したがって,看護実践の改革を追究する能力を育成するためには,卒業時までには何を,どこまで修得させるのかということを明示しておく必要がある。とくに,看護学の専門能力の発達過程については,(2)に述べたように卒業後に実践経験の中で各自が専門性を検証しつつ深めていくことが確認されている。したがって,学士課程の卒業研究の到達目標は,修士課程との違いを明確にしながら,各大学が独自に提示するものである。 なお,現状においては,看護の臨地実習との関連性についての確認がなく,看護事象とはかかわりなく一般的な研究手法の習得を目指した研究指導をしたり,看護実践からの乖離した研究指導をしたりするなど,4年課程の集大成とはいえない状況や混乱も散見される。卒業研究では,看護学における研究方法の習得や倫理的判断力の育成を念頭において,現行の看護実践の改革と深くかかわりを持たせて指導をすることが,とりわけ大切であることを確認しておきたい。 |
| 看護は、看護職という人間を介して諸技術を提供し,人々の健康問題への対応を支えるところに最大の特徴がある。これは,ヒュウマンケア,すなわち人間としての権利の尊重を基盤にした健康生活の支援であり,とりわけ看護は,ヒュウマンケア展開の過程で,正確な知識に基づく技術の展開が求められる。 したがって,教育課程においては,前回の検討会が取り上げた技術学習項目などの習得と同時に,学生が自らの実践,すなわち実習を通して,サービスの受け手と人間関係を形成しながら,諸目的を遂行する方法の原則を体得させる事が基本となる。この過程では,いっそう看護倫理教育の強化が図られなくてはならない。 近年,高齢者問題においても,また子どもの問題においても,人々の健康生活の支援に関係してくる職種は拡大されてきている。また,専門教育や訓練を受けた職種ばかりではなく,一般の人々も多様に関連してくる状況がある。このこと自体は,極めて好ましいことであり,社会の成熟とともに,人間らしい生活を個人も社会も求めてきた結果である。だからこそ,子どもから高齢者に至るすべての健康課題について,看護職者の責任性が増大し,同時に他職種との違いも厳しく問われている。とくに,近年では,治療や医療的ケアを受けながら社会生活を可能にすることが模索され,在宅ケアの推進など,医療機関外での看護への期待が広がっている。そのために,看護職者に対しては,単なる看護技術提供者ではなく,ヒュウマンケアとしての実践能力や倫理的判断力に期待が寄せられ,その反映として一般の人々からの看護職への評価は厳しくなっている。 知識社会の進行は,現在ますます速度を速め,同時に一般の人々が求めるケアサービスの質は高まっている。今,それに応えることは,看護職として最優先しなくてはならない。 そのために,看護学の学士課程においては,正確な技術の習得とともに,看護援助の基盤となる人間関係の形成過程について,実地体験の中で意図的に学ぶことが重要である。これは,すでに多くの大学で講義・演習・実習を通して,効果的方法を多様に開発をしているところでもある。 |
| 1) | 現状と課題 平成14年度の本協議会が実施した調査(回答60大学)によると,表4のとおり,教養教育の単位数は,20単位未満5%・20-29単位52%・30-34単位27%・35単位以上12%となっていて,約7割の大学が,卒業要件の20%,あるいはそれ以上の単位数を教養教育に当てている。また,各大学が教養教育の充実に向けた課題としてあげていることは,総合・複合大学,単科大学により,また,国公私立により傾向が異なる。全体を通して,課題内容は,「高学年次に移行させたい」「学科毎の意見の違い」「キャンパスの移動にかかる時間・経済的問題」「カリキュラム全体の見直し」「他大学・放送大学での履修」「開設科目数の増加」「学生の基礎学力低下など」があげられている。現状としては,これらの改善策を各大学は取り組まなくてはならない段階にある。 |
| 表4 卒業要件となる単位数区分別・教養科目の単位数別大学数 |
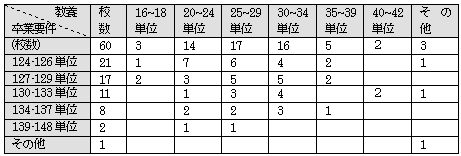
|
| 日本看護系大学協議会2002調べ |
| 2) | 看護学の学士課程で教養教育が重要な理由 教養教育の方法は,各大学が多様に工夫し,独自の成果を追究すべきものであるが,看護学の学士課程としての基本的在り方や原則は,共通に議論されるべきものである。その意味で,看護学分野において,学士課程の卒業者が社会に出て活躍するという観点から,教養教育の重要性を次の2点について確認しておく。 1つ目は,看護の仕事が,前述のとおりヒュウマンケアであり,人間と人間生活に深くかかわって,その人の生き方,希求,価値観に沿った援助をするという特色がある。その過程では,個別的な状況における深い人間理解と人間的・倫理的判断をしていくところに看護サービスの質の良否が深くかかわってくるからである。教養教育に求めることは,広い視野での見識であり,ヒュウマンケアを追究する基盤としての能力であり,看護の専門領域に関連してあるいは直結して,とくに必須の知識体系の習得を求めるものではない。学生は,将来看護実践で,人とのかかわりや社会との関係性を深め,自己と周辺の世界との関連性を見つめ,その中で,自分を育てて行くわけであるので,自己実現を追求するための基礎的な力を培う。 2つ目は,大学課程を修めた看護職者は,全看護職集団の中では,将来は指導的役割を担う事が期待される。したがって,他分野においても,市民社会の指導者や責任者に対しては,幅広い教養と豊かな人間性の涵養が求められるのと同様に,看護学の大学課程に相応しい教養教育が不可欠となる。 |
|
| 3) | 教養教育について大学毎に目的明示と学生への指導 2002年の中央教育審議会答申は,新しい時代に求められる教養とは何かの中で,「個人が社会とかかわり,経験を積み,体系的な知識や知恵を獲得する過程で身に付ける,ものの見方,考え方,価値観の総体」を教養としている。看護学の専門性において,生涯に亘り自己の生き方を追究するためには,自己を確立すること,自己の存在の原点をさぐることが大事であるし,自分の関係してくる人々との関係性を拓いていくことを学生時代に追究しておくことは欠くことが出来ない。 そのような意味では,各大学が課程ごとに教養教育の目指すところを明示して学生を導き,さらにそのために設定した科目または科目群毎に,系統的枠組みの意図と学習の目的を明確化すべきである。 特に看護学では,専門科目の中で看護実習という形で,人間的関係づくりや健康障害を持つ時期の人との接点の体験をとおして,自己の人間的成長・発達に深くかかわる個人的体験をする。この体験は,学生個人の身体・精神・情緒面に大きな影響をもたらしているものであり,これに合わせて教養教育の科目配置など課程編成を工夫することによっては,他の学科とは異なる効果も期待できる。 |
|
| 4) | 看護学の大学教員の教養教育にかかわる認識の変革の必要性 看護学の学士課程において,教養教育の意義を否定されることはないけれども,単に人間性の涵養などして一括されたり,専門関連科目と混同されたりすることが多い。実際にも,看護学以外の学問領域の専門家により提供される。また,かつては教養部(学部)などが専門的に提供していたことも影響し,専門学部の立場から主体的にその意義や教育方法を検討することが少なかった。 本協議会の調査から,看護学科が組織として,当該学科の教養教育の位置づけやその教育方法の充実に努力していることは事実である。しかし個々の教員の現状に注目してみると,教養教育への関心は極めて低いと言わざるを得ない。4年間の学士課程における人材育成に主体的にかかわるべき教員としては,当該学科の教養教育について積極的に関心を向け,看護学の専門の基礎における教養教育の在り方を追究する必要がある。とくに,現状においては,教員の教育背景は極めて多様であり,教養教育への認識も多様である。ファカルティデベロップメントの主題としたり,カリキュラム改訂の組織的検討を強化したりするなどして,教員意識の充実・向上に努めることは,学士課程教育の内実を高めるために極めて有効な方法である。 |
|
以上(2003-7-26) |