| 資料8 |
| 我が国の開発コンサルタントの現状 |
我が国の開発コンサルタントの現状
報告者:社団法人 海外コンサルティング企業協会 副会長代理 倉並 千秋
(株式会社 パデコ 取締役ジェネラル・マネージャー)
1. 日本の開発コンサルタントの概要
開発コンサルタントの形態は、法人コンサルタントと個人コンサルタントの2種類がある。法人コンサルタントはさらに営利企業(株式会社・有限会社等)と公益法人(財団法人・社団法人・NPO特定非営利団体等)の2種類がある。
日本の二国間援助の技術協力実施機関である国際協力事業団(JICA: Japan International Cooperation Agency)はコンサルタントの登録制度を設けている。本年4月1日現在で、626法人の法人コンサルタントと141人の個人コンサルタントが、JICAに登録されている。これらの法人コンサルタントのうち、実際に積極的に技術協力案件に参加しているのは100法人程度に留まる1 。個人コンサルタントは役務提供案件や業務委託案件の補強要員としてコンサルティング業務に参加している。なお、国際協力銀行(JICA: Japan Bank for International Cooperation)は、コンサルタントの登録制度を有していない。
上記のJICA登録され積極的に開発援助案件に参加している約100法人のうち86の法人コンサルタントが(社)海外コンサルティング企業協会(ECFA: Engineering Consulting Firms Association)の会員となっている 2。ECFAは、日本のコンサルティング企業の海外活動振興を目的に1964年に通商産業省(現経済産業省)および建設省(現国土交通省)の認可により設立された公益法人である。現在、会員企業を中心に、![]() セミナー・研修の開催、
セミナー・研修の開催、![]() ODA研究、
ODA研究、![]() プロジェクト発掘・形成支援、
プロジェクト発掘・形成支援、![]() 海外業務安全管理支援、等を行っている。また、各援助実施機関や外務省等の官公庁対するODA改善策を業界の立場から提言あるいは意見交換を随時行っている。
海外業務安全管理支援、等を行っている。また、各援助実施機関や外務省等の官公庁対するODA改善策を業界の立場から提言あるいは意見交換を随時行っている。
2. 日本の開発コンサルタントによる開発援助事業への参画状況
ECFAが実施した『2000年度海外コンサルティング活動の現状』調査の結果によると、日本の開発コンサルタントの受注総額は736億円であった。ECFA非会員による海外コンサルティング活動を考慮すると、海外コンサルティングの市場規模は約1,000億円程度と推定される。
2.1 セクター別受注実績
図1にセクター(分野)別の受注実績を示した。「運輸・交通」や「電力・エネルギー」分野が大きい部分を占める。これは同分野では円借款等による1件あたりの規模が大きいローン事業が多いためである。注目すべきは、「環境」分野での実績が急速に伸びてきていることが挙げられる。「保健・教育・社会開発」分野は1件あたりの受注額は小さい事業の件数は着実に増加してきている。
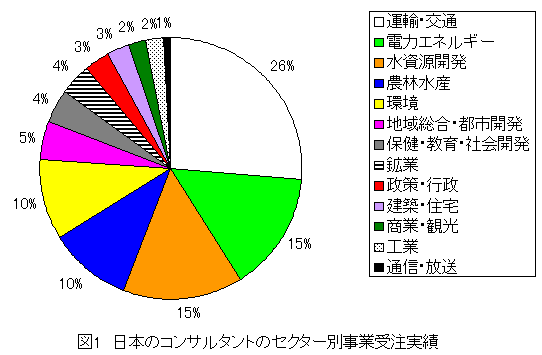
| [出所] | (社)海外コンサルティング企業協会 『2000年度海外コンサルティング活動の現状』 ECFA 2001年(2000年度ECFA会員企業73社データに基づく) |
2.2 対象国・地域別受注実績
一連の日本政府主導によるTICAD等の流れを受けて、アフリカ諸国への支援も重視されつつあるものの、やはりアセアン諸国を中心とするアジア地域での比率が63%と大部分を占めるに至っている。
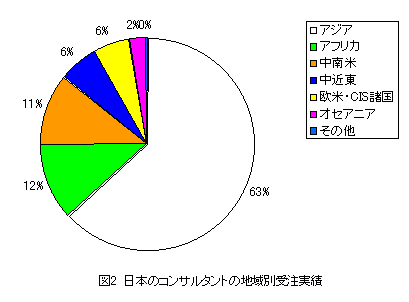
| [出所] | (社)海外コンサルティング企業協会 『2000年度海外コンサルティング活動の現状』 ECFA 2001年(2000年度ECFA会員企業73社データに基づく) |
2.3 資金別受注実績
資金別受注実績では、JBICやJICA等の日本政府による二国間援助事業が88%を占めている。国際機関や対象外国政府等の資金による事業は12%に留まる。なお、借款の場合は本体事業のクライアントは途上国政府となるため、ここでは資金別実績を示した。
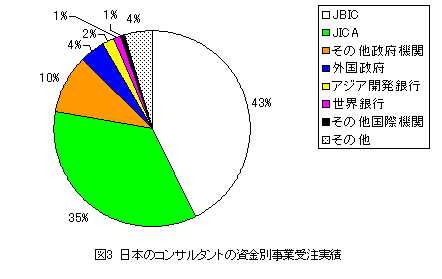
| [出所] | (社)海外コンサルティング企業協会 『2000年度海外コンサルティング活動の現状』 ECFA 2001年(2000年度ECFA会員企業73社データに基づく) |
2.4 国際開発金融機関への出資比率と受注比率比較
図4に、世界銀行およびアジア開発銀行への日本の出資比率とコンサルティング業務受注比率の比較を示した。出資比率に比較してコンサルティング業務の受注率が低いことが明らかである。
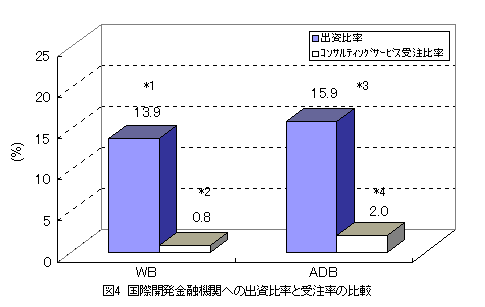
| [出所] |
|
||||||||
| [注] | 世界銀行のデータには日本タイドの日本職員コンサルタント信託基金(JSCTF: Japan Staff and Consultant Trust Fund)および本体事業の貸付部分を除く。 |
3. 日本の開発コンサルタントが大学に寄せる期待とコンサルタントからみた課題
3.1 開発コンサルタントと大学教官による連携の現状と事例
≪日本の大学の現状≫
現在のところJICAにコンサルタント登録されている大学はないため、JICA事業において大学教員がプライム・コンサルタントとしての業務は行っていない。補強要員として個人ベースで開発調査等のコンサルティング業務に参加している大学教員の事例はあるかもしれない。大学教員が参画したJICA事業は、主に、プロジェクト方式技術協力の専門家や個別専門家としての派遣3、プロジェクト方式技術協力の国内支援委員や開発調査における作業管理委員としての専門的見地からコメントや指導の提供、に留まる4。JBIC事業では、コンサルタントに準ずる形態でテーマ別事後評価の請け負ったり、SAF(Special Assistance Facilities)5に補強要員として個人ベースでコンサルティング業務に参加している大学教員の事例が見られる。
国際機関や外国政府6をクライアントとする調査等においては、補強要員として参加した実績が少なくとも下記の通り数件はある。
|
参考:日本の大学教官が参加した開発コンサルティング業務の事例
|
≪海外の大学の現状≫
海外の大学は、20〜30年以上前から大学が国際機関や自国の二国間援助機関から業務委託を受けてコンサルティング業務に従事している。現状の日本の大学教官が参加する際の個人ベースの契約ではなく、大学が組織として契約をクライアントと締結する方式を取っている。よって、Instituteを設立するなどしてコンサルティング業務を受託するための事務バックアップ等の体制を確立している大学もある。
調査案件の業務委託を受けるだけでなく、第三国研修を大学が受託することもある。たとえば、カナダの大学がカナダ国際開発庁(CIDA: Canadian International Development Agency)を通じてアジア工科技術院(AIT: Asian Institute of Technology)での運輸交通関連の研修を請け負った事例や、オーストラリアの大学がオーストラリア国際開発庁(AusAID: Australian Agency for International Development)の依頼で、インドネシアで実施した研修の事例がある。こうしたプロジェクトはキャパシティ・ビルディングと呼ばれ、大学(教官)は研修モジュール・カリキュラム・テキストの作成、研修の実施などを行う。
| 3.2 | 開発コンサルタントからみた大学教官との連携に関わる課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 開発コンサルタントからみた大学教官との連携に関わるメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将来的には、大学教官が個人ベースの参加する現状の形態から、大学が組織として開発コンサルタントのパートナーとして連携体制が取れるような状況を期待している。当面は、大学教官の開発コンサルタントへの補強要員としての参加の促進・拡大により、大学の開発コンサルティング業務への円滑な参画を支援することが望ましいと考える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 大学との連携に必要な具体策
4.1 大学関係者との懇談会
コンサルティング業界と大学関係者との率直な意見交換の場が必要であろう。コンサルティング業界はコンサルティング業務に従事する際の大学教官が抱える問題や障害を十分に理解していない。一方、大学は、コンサルティング業務とは何か正確かつ十分には理解していないと考えられる。これまでは、大学とコンサルティング業界との間での交流の機会が少なかったゆえに、相互の理解が十分でなかった。双方の相互理解を深める上で、意見・情報交換を目的とした懇談会を開催することは有益であろう。
4.2 コンサルティング業務参加への関心の高い大学および教官のデータベース整備
具体的にどの大学のどの教官が、どんな分野やどんな国・地域を対象にしたコンサルティング業務に従事したいと考えているのか−そういった情報をデータベース化してコンサルティング業界と共有することが必要であろう。このようなデータベースを整備し、大学とコンサルティング業界の双方が必要な人材を知る機会が提供されることにより、大学とコンサルティング業界の連携案件が形成されるなど、連携が強化されていくと思われる。
4.3 大学関係者向けの研修
大学教官が自由な知的探究心に基づきこれまで行ってきた学術活動と、履行期限の厳守やクライアントの要望に沿った成果等が求められる契約に基づきビジネスとして行うコンサルティング業務との間には差異がある。また、大学が組織としてコンサルティング業務を行っていくには、コンサルタントとして活動する大学教官のみならず事務バックアップ(事務や秘書)側にも、新たなスキルが必要となる。さらには、開発援助一般に関わる基本的な用語や概念に関する知識も身に付けることが求められる。専門分野での学術研究実績だけでは対応できない状況も、多種多様に存在するため、大学関係者向けの研修が必要であろう。
4.4 大学とコンサルティング業界との交流
大学での研究活動や教育活動で用いられる学術理論と開発現場での実務との乖離が少なからず見られるようだ。その格差を縮小すべく、大学教員は可能な範囲でコンサルタントとして参加した大学教員が所属する大学の学術活動へフィードバックすることが望まれる7。さらには、コンサルティング企業と大学との間に人事交流を図り、![]() 大学における開発現場に即した学術理論の研究や教育の実現、
大学における開発現場に即した学術理論の研究や教育の実現、![]() 日本のコンサルティング業務の理論強化により国際競争力強化、等双方にとって有益であると考えられる。
日本のコンサルティング業務の理論強化により国際競争力強化、等双方にとって有益であると考えられる。