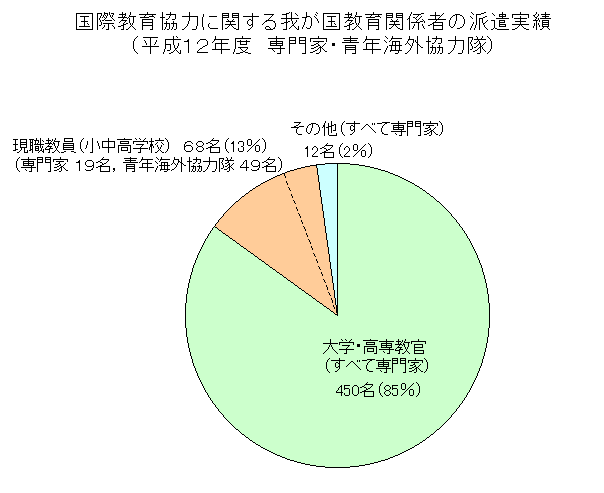|
|
| |
| インパクトのある協力のあり方について(考えられる論点) |
| |
| 1. 現職教員のより有効な活用によるインパクトの拡大 |
| |
| (現 状) |
| ・ 現職教員:国際教育協力の重要なリソース(全国の小中高校に約90万人) |
| →指導案作成、教材開発、各種指導技術など、児童生徒に密着した実践的な経験や能力 |
| ・ 大学教官に比べ国際教育協力への極めて限られた参加の現状(別紙:平成12年度実績) |
| |
| (前回懇談会) |
| ・ 「青年海外協力隊、シニア海外ボランティアへの現職・退職教員の参加促進」を提言 |
| →平成13年度、青年海外協力隊に「現職教員特別参加制度」を創設(合格者87名)。 |
| (*併せて、自治体の主体的な取り組みを促すための「一県一国支援」の考えを提言) |
| |
| ・問題点: |
・ 隊員が単発的に、且つばらばらに派遣されるため、 |
| |
| (1) |
自治体としての現職教員派遣を長期的な人事計画の中に組み込みにくい。 |
| (2) |
自治体の「顔」が見えにくい(派遣先国と県・学校との関係が薄い)。 |
| (3) |
各隊員が培った経験を次の隊員にフィードバックすることが難しい。 |
|
| |
|
| |
・ 一県(自治体)で一国を支援するのは負担が大。 |
|
| |
| (論 点) |
| 現職教員派遣の人数拡大とインパクトのある協力(より生産的で存在感があり、且つ我が国の効力感が溢れる協力)を進めていくための検討が必要? |
| |
| (改善のためのたたき台案・教育協力隊構想) |
| (1) |
複数の自治体が中長期的に現職教員を派遣することにコミットし、そこから推薦された複数の現職教員からなるチームを途上国の学校等へ派遣(一国多県支援) |
| (2) |
相手国の教育関係者や校長等をカウンターパート研修で各々の自治体に受入 |
| (3) |
相手国との間で生徒レベル間の交流を促進 |
|
| |
| 2. 協力事業の総合化によるインパクトの増大 |
| |
| (論 点) |
| 単発で終わっている現行の協力事業をよりインパクトの高いものとするため、ハードとソフトのパッケージ化などを通じて、我が国の経験を生かした新たな協力分野も含めて協力事業を総合化し、相乗効果を高めることが必要? |
| |
| (たたき台案・学校の地域教育拠点化モデル) |
| (1) |
学校を地域の教育拠点とし、ハード(学校建設等の環境整備)とソフト(各種の教育活動)に対してパッケージで協力することにより、我が国の経験や英知を集中的に注入し、存在感のある協力を実現。
|
| (2) |
ソフトに関しては、子供を対象とした公教育(各種教科、学校保健・給食等)と親などの成人を対象としたノンフォーマル教育(女性教育、識字教育等)に対してセットで協力することにより、相乗的な効果の発現を喚起。
|
| (3) |
現地のコミュニティや我が国NGO等との密接な連携により、行政レベルから草の根レベルまでをカバーした裨益効果の高い協力を推進。 |
| (4) |
我が国の学校や生徒との交流を促進。 |
|
| |
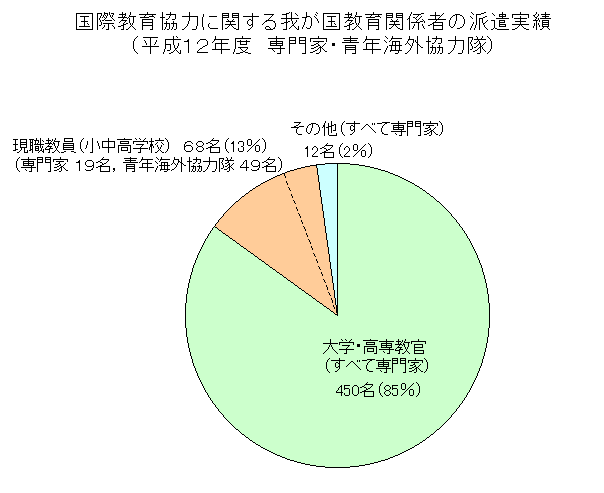 |