資料2
我が国の国際教育協力の現状について
我が国の初等中等教育レベルにおける国際協力の現状(1999年度実績)
我が国の高等教育レベルにおける国際協力の現状(1999年度実績)
我が国教育ODAにおける援助形態別のシェア(1999年度実績)
我が国教育ODAにおけるハードとソフトの連携(1999年度実績)
我が国の初等中等教育レベルにおける国際協力の現状(1999年度実績)
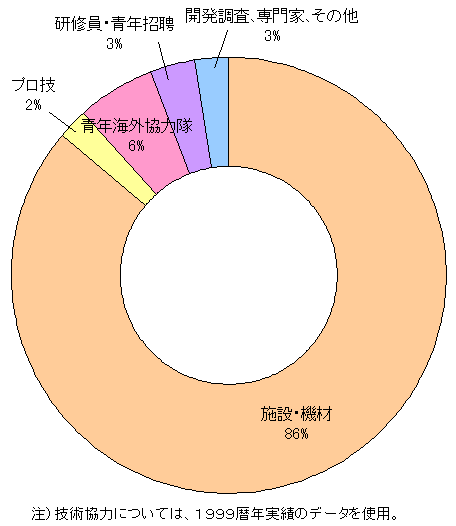 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我が国の高等教育レベルにおける国際協力の現状(1999年度実績)
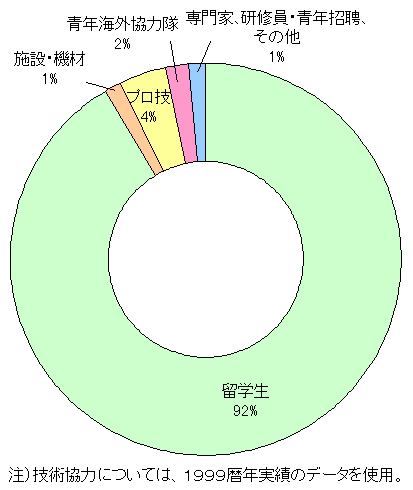 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 国内の学校・教育関係団体による協力・交流活動 | |
| 国内の学校・教育関係機関では、途上国の学校に対する物品等の寄付や、これを発展させた児童生徒間の交流活動などが実施されている例がある。国内の教育活動と途上国との関係を有機的に連携させたいとする関係者の声は多い。具体的な活動事例は以下のとおり。 | ||
| (1) | 日本PTA全国協議会による文具の寄贈 | |
| 同協議会では、全国の小中学生から未使用の文具の提供を呼びかけ、平成2年から10年間に亘り、中国、カンボディア、ラオスの学校へ寄贈。また、毎年約100名の中学生を「日中友好・少年少女の翼」プログラムとして中国の学校へ短期派遣している。 | ||
| (2) | 全国子ども会連合会による「世界の子ども救援募金運動」 | |
| 同連合会(全国の町中会を基盤とする子ども会の全国組織)では、「世界の子どもに教育を」の標語のもと、子どもの手による救援募金運動を実施している(平成12年度実績約4千万円、タンザニア、トルコ等)。 | ||
| (3) | 東京都荒川区の小学校による机と椅子の寄贈 | |
| 同区では、小学校入学時に高さなどの調節ができる机と椅子を児童一人一人に支給し、卒業時に持ち帰れる制度となっているが、生徒が持ち帰らなかったものを97年からドミニカ及びジャマイカに寄贈している(今年はジャマイカへ約100組を寄贈)。 | ||
| (4) | 高知商業高校によるラオス学校建設支援 | |
| 同校(生徒会が中心)が地元のNGOなどと連携しながら、ラオスの小学校建設に協力。生徒自身がラオスで調達した工芸品等の販売益や募金などにより、平成7年からこれまでに4校の建設を支援(援助額約500万円)した。生徒の現地派遣も毎年実施されている。 | ||
| 2. | NGOによる教育協力活動 | |
| NGOによる協力は、地域コミュニティにおける活動が主となっており、地域に対する幅広い支援活動(保健、井戸掘りなど)の一環として教育協力が実施されている場合が多い。 | ||
| また、奨学金や学用品の支援など、子ども一人一人に対する直接的な支援事業が含まれている点が、ODAによる教育協力とは異なる点である。具体的な事例は以下のとおり。 | ||
| (1) | ワールド・ビジョン・ジャパン | |
| チャイルドスポンサーシップ・プログラム(支援対象の子どもを特定してスポンサーを募集)を通じて寄せられた資金により、教育分野を含む地域開発プログラム(学校建設、学用品支給、教員研修、給食など)を実施(フィリピン、タイ、ベトナム、ウガンダ等)。 | ||
| (2) | シャンティ国際ボランティア会 | |
| 教育分野での協力例として、ラオス等へ「絵本を届ける運動」や紙芝居などによる小学校支援事業、カンボディアにおける幼稚園教員の再トレーニング事業、タイの農村やスラムの子どもを対象とした「アジア子ども奨学金事業」などがある。 | ||
| (3) | 日本シルクロード倶楽部 | |
| 中国新橿ウイグル自治区からの留学生との交流に基づき設立された団体。本邦における各種の交流事業(ダンス等)に加え、ウイグル自治区等からの私費留学生の招聘や現地小学生に対する奨学金事業を実施。現地では帰国留学生が協力の窓口となっている。 | ||
| (4) | 笹川平和財団 | |
| 日本財団、モーターボート競争業界からの拠出金により、国際協力・交流に関する事業を助成。教育分野に関しては、平成13年度に「南太平洋大学法学部インターネットコースの開発」(フィジー国・南太平洋大学)に対する支援などがある。 | ||