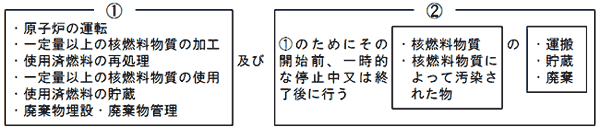|
資料5−4 主たる事業行為の終了後の損害賠償措置の合理化について(案)1.損害賠償措置規制の概要(1)原賠法上の「原子炉の運転等」 原子力事業者は、損害賠償措置を講じていなければ「原子炉の運転等」を行ってはならず(原賠法第6条)、この「原子炉の運転等」は以下の
(2)現行の損害賠償措置の問題点の見直しの方向 原賠法施行令第2条では、主たる事業行為とともに、付随行為のうちサイト内で行われるものを一体的に取り扱っており、事業行為の種類によっては、事業行為の終了後にサイト内で付随行為だけが行われる場合、賠償措置額が付随行為だけの相対的リスクに比して過大となっている。
2.事業行為終了後の損害賠償措置規制の合理化について(1)原子炉の運転熱出力が100kw(キロワット)を超える原子炉の運転については、その終了後の付随行為の賠償措置額も一律に600億円又は120億円とされているため、1.の見直しの方向性に基づき、賠償措置を合理化する余地がある。 <熱出力が1万kw(キロワット)超の原子炉の運転の場合の賠償措置額>
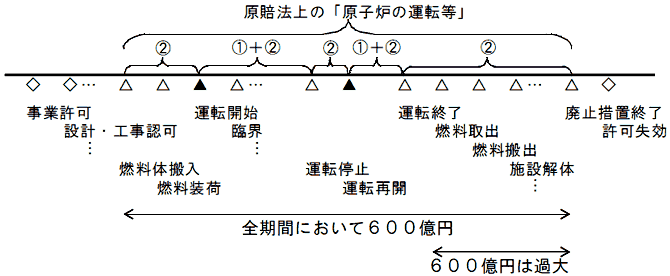 イ 使用済燃料の取出し後 原子炉の運転を終了し、炉心からすべての使用済燃料を取り出した後にサイト内で行われる付随行為は、原子炉の運転に起因するリスクはなくなる。この場合の付随行為の相対的リスクは、事業行為としての使用済燃料の貯蔵と同程度であるので、熱出力が1万kw(キロワット)を超える原子炉の運転に係る上記の付随行為については、使用済燃料の貯蔵と同額の賠償措置額を創設することが妥当である。 ロ 燃料のサイト外搬出後原子炉の運転を終了し、未使用の燃料体・使用済燃料のすべてをサイト外に搬出した後にサイト内で行われる付随行為は、核燃料物質の取扱いに伴う危険がなく、中心となる付随行為は原子炉領域の貯蔵や各種解体に伴う廃棄物の処理であり、その相対的リスクは、事業行為としての低レベル放射性廃棄物の廃棄物管理と同程度である。このため、熱出力が100kw(キロワット)を超える原子炉の運転に係る上記の付随行為については、低レベル放射性廃棄物の廃棄物管理と同額の賠償措置額を創設することが妥当である。 ハ 必要性廃止措置が行われている原子炉が複数あるほか、将来的には、供用期間が長期にわたった実用炉の運転の終了が本格化することが見込まれるため、現段階で適切に見直しを行うことが妥当である。廃止措置中の原子炉や上記の賠償措置規制の合理化の適用の見込みについては、別紙2を参照。 (2)使用一定量(5パーセント以上濃縮ウラン中のウラン235は800グラム;プルトニウムは500グラム)以上の核燃料物質の使用については、その該当行為の終了後の付随行為の賠償措置額も一律に120億円とされているため、1.の見直しの方向性に基づき、賠償措置を合理化する余地がある。 イ 一定量を超える部分の核燃料物質のサイト外搬出後一定量以上の核燃料物質の加工・使用に該当する行為を終了し、一定量以上の核燃料物質がサイト内に存在しなくなった後にサイト内で行われる付随行為は、少量の核燃料物質の貯蔵や核燃料物質によって汚染された物の保管廃棄であり、その相対的リスクは、事業行為としての低レベル放射性廃棄物の廃棄物管理と同程度である。このため、上記の付随行為については、低レベル放射性廃棄物の廃棄物管理と同額の賠償措置額を創設することが妥当である。 ロ 必要性以下の事業所については、一定量以上の核燃料物質の使用に該当する事業行為が終了しており、現段階で見直しを行うことが妥当である。
使用について120億円の賠償措置額の対象となっている事業所や上記の賠償措置額の合理化の適用の見込みについては、別紙2を参照。 (3)その他の事業加工・再処理・使用済燃料の貯蔵・廃棄物埋設・廃棄物管理については、現時点では事業行為の終了が見込まれていないため、事業行為の終了が具体化した際に適切に検討を行うことが妥当である。 (4)文部科学大臣による確認 事業行為の終了後のサイト内での付随行為について、(1)及び(2)による合理化後の賠償措置額を適用する場合には、その根拠となる使用済燃料の炉心からの取り出し等の事実を確認することが必須である。
|
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology