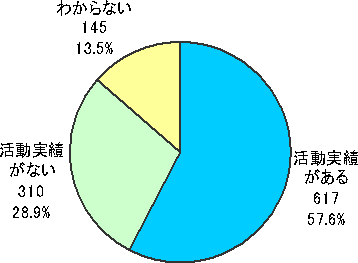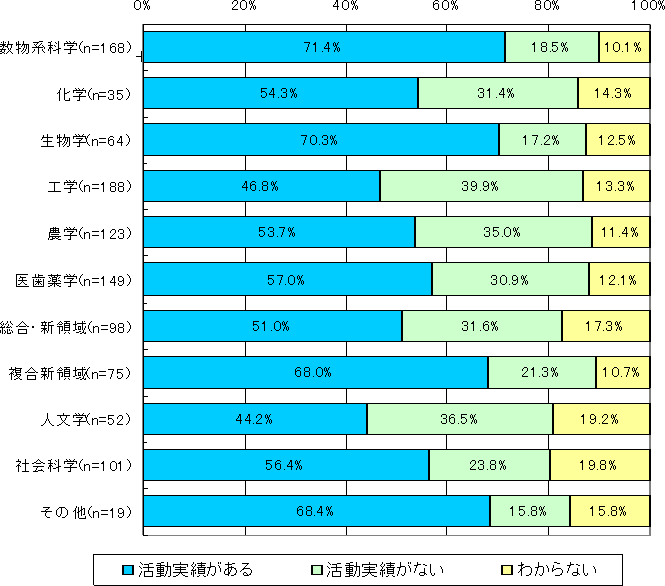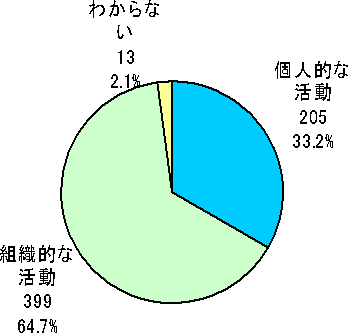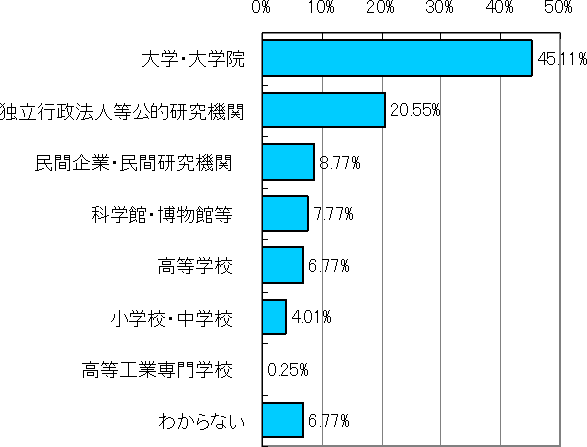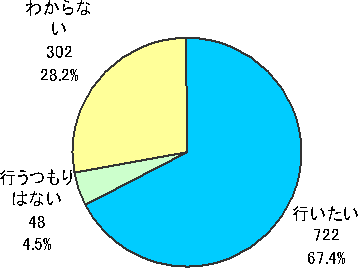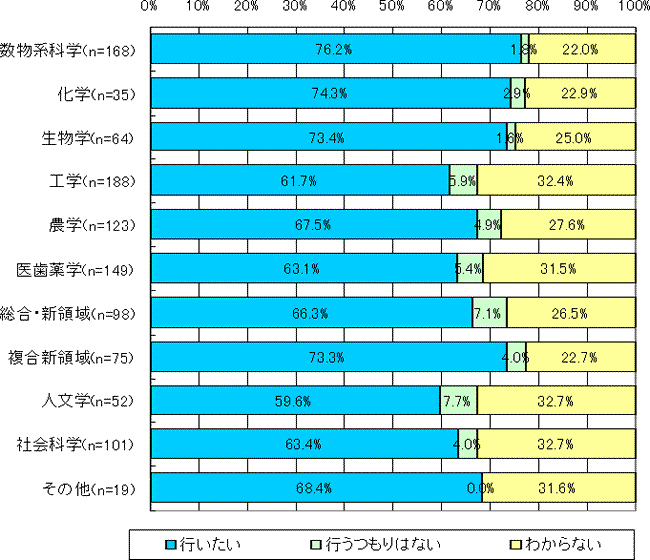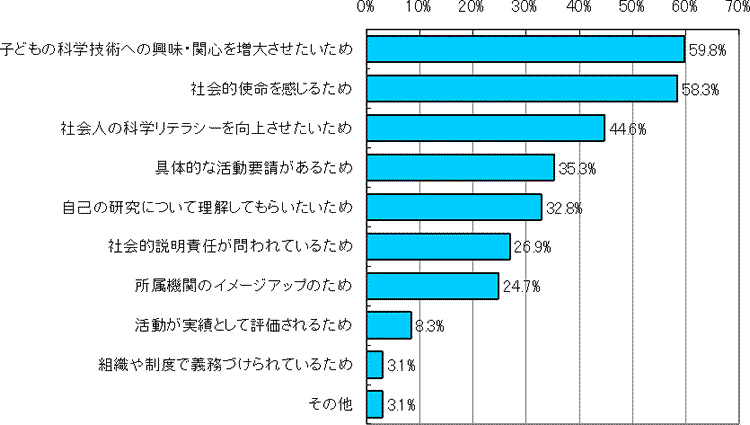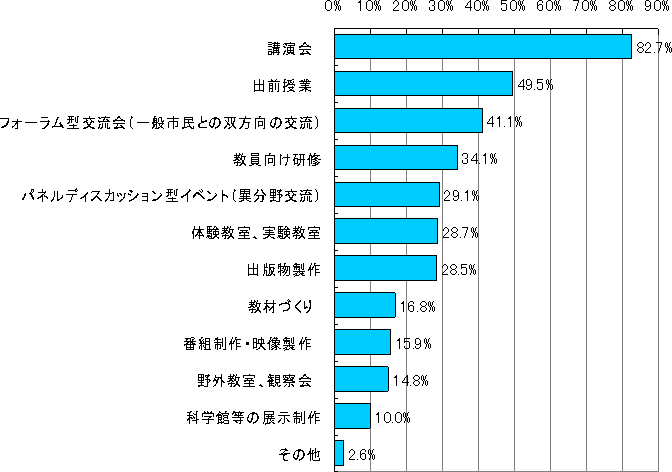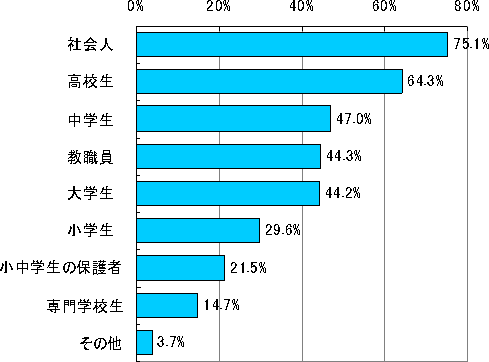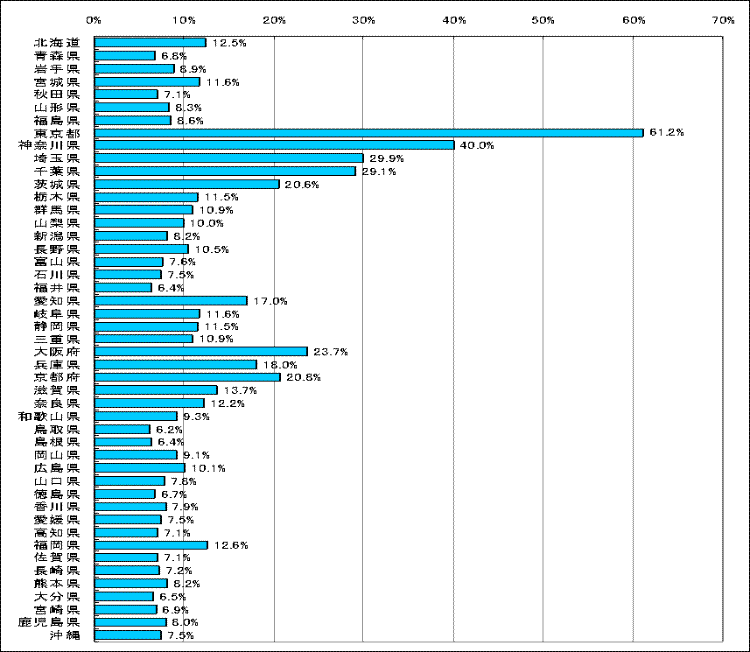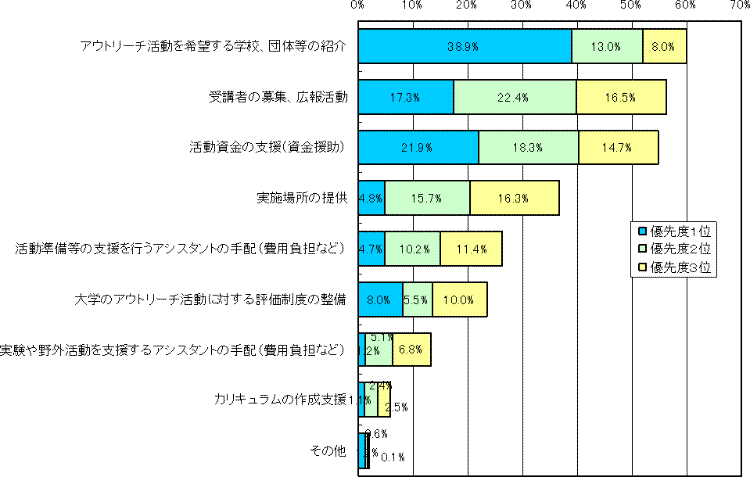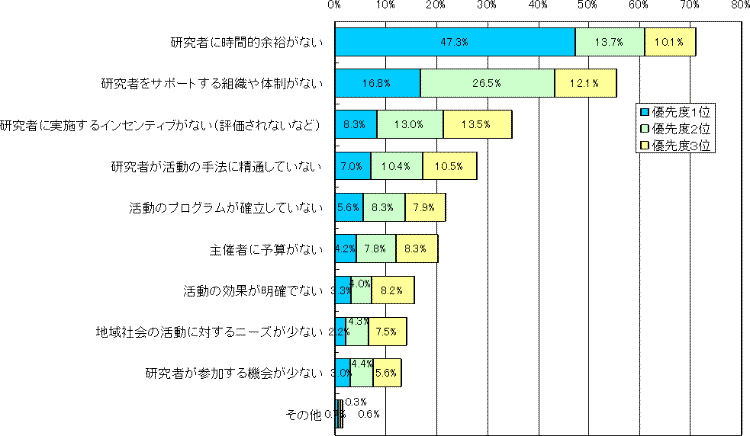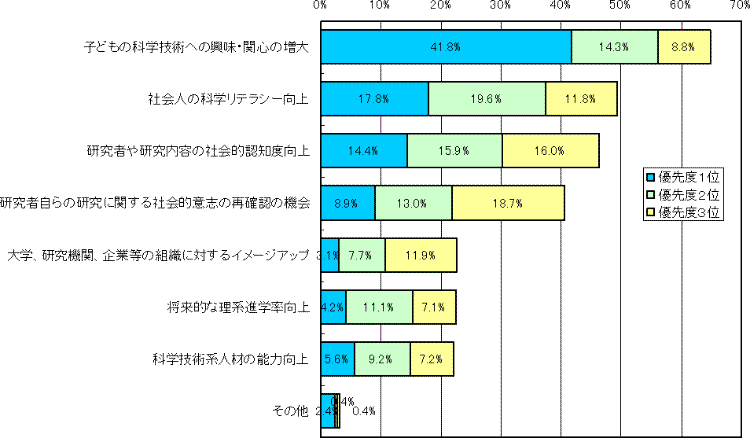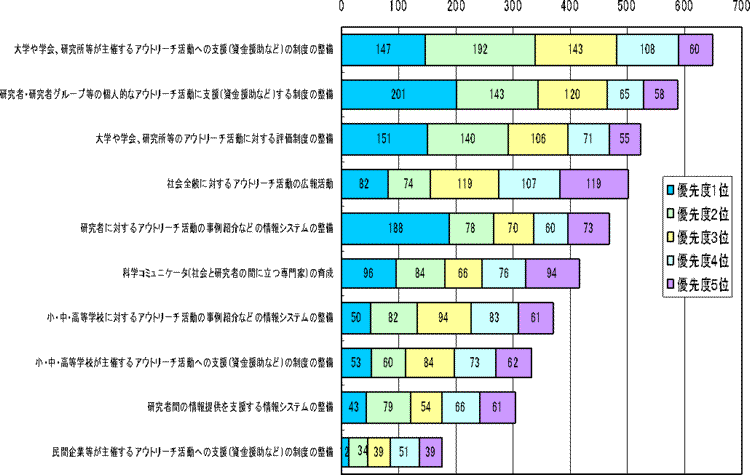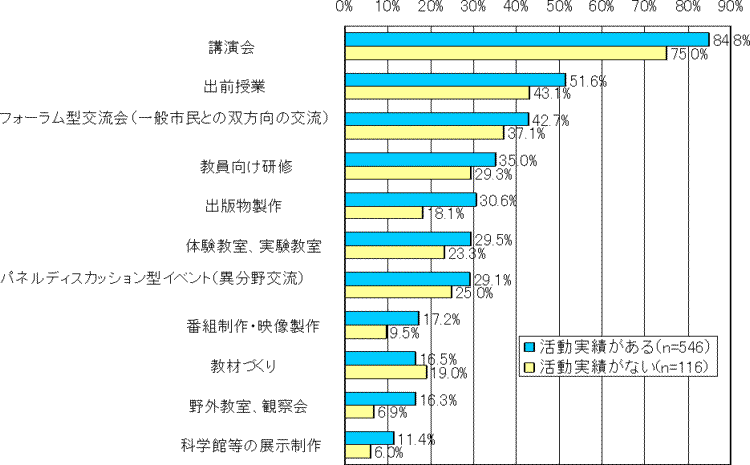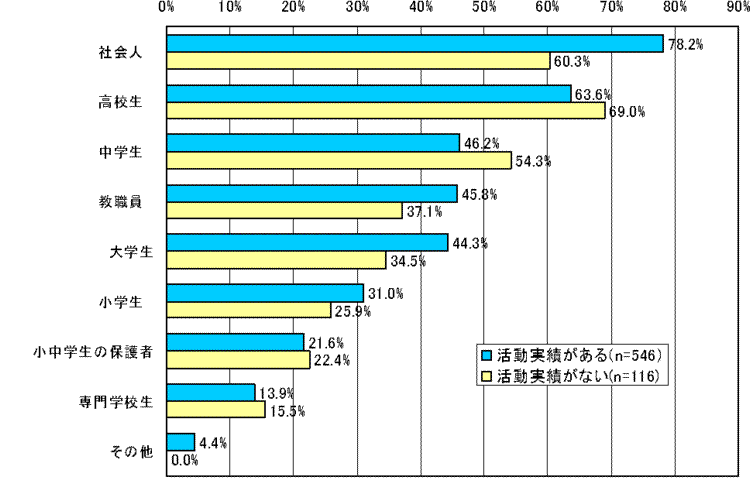| 1. |
目的 |
| |
 |
現状の研究者・技術者のアウトリーチ活動の実態や今後の実施意向を把握する |
 |
研究者・技術者の科学技術・理数教育への協力依頼のためのデータベース整備 |
|
| |
|
| 2. |
調査方法 |
| |
 |
調査対象: |
日本学術会議会員及び研究連絡会所属メンバー協力可能者1,923名(専門分野の分布は未調査) |
 |
調査期間: |
平成17年2月17日〜3月17日 |
 |
調査方法: |
Webアンケート(アクセスパスワードにより二重回答を防止) |
 |
調査項目: |
個人属性(性別、年齢、専門分野)、アウトリーチ活動実績・活動意欲・実施の要件・課題・普及策、実施可能テーマ・組織的活動例など |
|
| |
|
| 3. |
調査結果 |
| |
| (1) |
回答者 |
| |
 |
回収率55.5パーセント(1,072名。表1)、年齢層は50歳以上が約9割である(表2)。回答者が、日本学術会議会員・研連委員であることから、一般的な研究者の年齢構成に比べると、40代以下が少なく、50歳以上の研究歴の長い層に偏る傾向にある。アウトリーチ活動実績や意欲、支援策などの回答傾向への影響を考慮しておく必要がある。 |
 |
専門分野(表3)の分布は、理工系85パーセント(900名)、人文社会系15パーセント(153名)である |
|
|
| |
| (2) |
アウトリーチ活動の実態 |
| |
 |
活動実績は、回答者の約6割(617名)がある(図1) |
 |
専門分野別の活動実績率は、数物系(物理・数学等)、生物学が高く(70パーセント以上)複合新領域が続く。工学は47パーセントと最も低い(図2) |
 |
活動体制では6割以上は所属組織の活動である(図3)。所属組織は、大学・大学院45パーセント、公的研究機関21パーセント、民間企業等は9パーセント以下(図4) |
 |
活動組織の具体例360件(大学・高専108件、公的研究機関57件、科博等24件、民間10件、学協会93件) |
|
|
| |
| (3) |
今後のアウトリーチ活動の意向 |
| |
 |
参加意欲は、回答者の7割近く(722名)が有り、拒否表明は5パーセント以下(48名)(図5) |
 |
専門分野別参加意欲では、実績同様、数物系と生物学、複合新領域が高く(73パーセント以上)、化学も実績は低いが参加意欲の高さ(74パーセント)は顕著である。工学は実績同様の理工系で最も低く62パーセントにとどまる(図6) |
 |
参加理由は、子どもの科学技術への興味関心増大(60パーセント)と社会的使命感(58パーセント)が並び、社会人の科学リテラシー向上(45パーセント)が続く。研究への理解や説明責任は、30パーセント前後にとどまる(図7) |
 |
実施可能な形態は、参加希望者の8割以上が一方向的活動である講演会を挙げ、双方向活動の出前授業は、5割以下である。受講者の能動的活動である体験的な実験教室(29パーセント)や野外観察(15パーセント)を挙げているのは3割以下である(図8)。
具体的な実施可能テーマを挙げた回答者は566名(78パーセント)で、理工系テーマは472名(65パーセント)であった。主な分野は、地球環境、保健医薬、生物学、生命科学、天文・宇宙である。他防災・安全、エネルギー、火山・地震等のテーマも挙げられている。 |
 |
実施対象者は、 参加理由の傾向とやや異なり、社会人が最も高く、次いで高校生となる。実施は児童生徒より社会人向け活動が容易との判断よると考えられる。(図9) 参加理由の傾向とやや異なり、社会人が最も高く、次いで高校生となる。実施は児童生徒より社会人向け活動が容易との判断よると考えられる。(図9) |
 |
実施可能地域は、居住地や交通の便等から大都市圏は高めであるものの、低いながらも全国満遍なく実施可能と考えられる(図10) |
|
|
| |
| (4) |
アウトリーチ活動への支援や実施課題、普及策 |
| |
 |
活動支援内容には、実施対象となる学校等の紹介、受講者などの募集、活動資金支援への要望が、他に比べ20ポイント以上も高い。優先度から見ても3項目への期待度の大きさが伺える。(図11) |
 |
活動実施上の課題では、研究者の時間的な余裕が7割を越え、研究者への活動サポート体制への要望も55パーセントと高い。また、研究者の活動評価が3番目となっている点は、今後の活動推進の検討事項になろう。(図12) |
 |
活動への期待では、(3) 参加理由と同様に子どもの科学技術への関心喚起と科学リテラシー向上が高い。また、参加理由に比べると研究者や研究成果の認知度向上への期待(46パーセント)が高いことも伺える(図13) 参加理由と同様に子どもの科学技術への関心喚起と科学リテラシー向上が高い。また、参加理由に比べると研究者や研究成果の認知度向上への期待(46パーセント)が高いことも伺える(図13) |
 |
活動普及策では、活動支援同様に資金面での制度整備への期待は高い(1番目、2番目)。また、 活動実施上の課題と同様に、活動評価への期待が大きい(3番目)。さらに優先度で見ると、対象学校の紹介などの情報提供や広報活動も重視されている(図14) 活動実施上の課題と同様に、活動評価への期待が大きい(3番目)。さらに優先度で見ると、対象学校の紹介などの情報提供や広報活動も重視されている(図14) |
|
|
| |
|
| 4. |
考察 |
| |
 |
回答者のアウトリーチ活動実績は6割に達し、実施拒否が少ない点を考慮すると、潜在的な参加者は7割以上に達すると推定される。しかしながら、工学系の研究者の実績や参加意欲が低い点は、年齢層の偏りの影響等も含めて原因を検討する必要がある。 |
 |
児童生徒を対象とする意義は感じているものの、実際の活動となると難しさが伴う模様で、実績があるほど、社会人対象(図15)の活動や講演等を希望(図16)する傾向が強まるようである。 |
 |
活動支援では、活動対象の学校等の情報や活動周知等、アウトリーチ提供者(研究者)と対象者(学校、児童生徒)を繋ぐ仕組みへの期待は大きい。また、活動資金や活動評価など制度整備も一層の充実が望まれているようである。アウトリーチ活動の促進のためには、既存の支援制度(SPPなど)の周知を図るとともに、評価のあり方も早急に検討すべき課題と考えられる。 |
 |
その他、アウトリーチ普及への意見として、「アウトリーチ」の意味・定義を周知すべきとの記述が複数挙げられており、今後の対策検討も必要になろう。 |
|