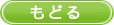
| 資料5−4 |
放射化物の扱いについて
(案)
I.現状
| (1) | 放射化物の現状 現行の放射線障害防止法では、当初から使用等を予定する放射性同位元素と放射線発生装置、また放射性同位元素によって汚染されたものが規制対象にされており、放射線の照射に伴って発生する放射化物については、明示的な規定がなされていない。 一方、放射線発生装置の性能の向上により、高エネルギーの放射線発生装置が使用されるようになり、その使用に伴い機器等が放射化されるという問題が顕在化してきた。 放射化物は、加速器の構造体である鉄、銅、アルミニウム、ステンレス、遮へい体であるコンクリート、鉄、鉛などで発生している。代表的な生成核種は、アルミニウム材中のNa-22、Be-7、鉄材中のCo-60、Mn-54、Co-56、コンクリート材中のNa-22、H-3などである。 また、表面密度4Bq/cm2、表面での線量率が3mSv/hを超える場合もある。 通常発生する放射化物については、一部事業所では、放射化した磁石、加速管等を点検し、再利用されている例もあるが、大部分は、室内に保管されている。古い加速器の解体によって発生した大量の放射化物についても、一部再利用されているものの、大部分は専用の使用施設を設置し保管されている状況である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 放射化物の取扱いに係る課長通知について 法令上、放射化物が規定されていないことから、平成10年10月30日、当時の科学技術庁が、放射化物の取扱いについて、「放射線発生装置使用施設における放射化物の取扱いについて」(科学技術庁原子力安全局放射線安全課長通知)をとりまとめ、関係事業者に対して安全管理上の留意事項を周知、徹底している。この課長通知の概要は以下のとおり。
|
II.今後の対応
| (1) | 基本方針 放射線発生装置使用施設における放射化物の取扱いについては、前述の通り、現状は、科学技術庁原子力安全局放射線安全課長通知に基づき、実態的に安全性は確保されていると考えられる。 しかしながら、課長通知は、基本的に放射化物の安全な保管管理を求めるもので、放射化物の取扱いや使用についてまで安全確保のあり方を示しているものではないこともあり、今回の法令改正の際に放射化物に係る安全確保について所要の法令整備を行うことが適当であると考えられる。 |
||||||||||||||
| (2) | 具体的な法令整備の内容案 課長通知の内容を適宜見直し、次のような方向で具体的な法令整備の内容案を検討することが適当であると考えられる。
|