 |
IAEA国際基本安全基準(BSS)
の規制免除レベル
(放射線審議会基本部会報告書「規制免除について」の概要)
平成14年11月
放射線規制室
| 1.国際基本安全基準(BSS)の規制免除レベルについて |
1−1 国際基本安全基準(BSS)とは
BSSとは、放射線被ばくに係るリスクを防ぐための放射線源の安全に対する基本要件として、IAEA理事会が1994年に承認し、1996年に刊行した基準。このBSSにおける免除レベル(規制を免除される放射性同位元素の量や濃度のレベル)の国内法への取入れ等について放射線審議会で検討が行われている。
1−2 BSSの規制免除レベルとは
ある線源について、その使用や処分に伴う全ての被ばく経路を考慮して、その被ばくが年間10μSvになるように科学的に算出された数値。約300の核種について、規制の対象外となる放射能(Bq)、濃度(Bq/g)の免除レベルを定めている。
1−3 現行規制の定義数量・濃度との比較
| |
現行 |
BSS取り入れ後 |
定
義
数
量 |
密封線源 |
3.7MBq |
核種毎に分類
(1kBq〜1TBq) |
| 非密封線源 |
核種毎に4群に分類
(3.7kBq〜3.7MBq) |
| 定義濃度 |
74Bq/g |
核種毎に分類
(1Bq/g〜1MBq/g) |
1−4 今後の課題
・BSSの国内法令への取り入れについては、利用実態等を考慮し、合理的な規制を検討
・その他の法律上の問題点も合わせて検討
国際的に整合のとれた、科学的根拠に基づく合理的な安全規制体制を構築
2−1 経緯
| (1) | IAEAは、ICRP1990年勧告を受けて、1996年に「電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準」(BSS)をとりまとめ、その中で一定の被ばくシナリオを考慮した核種毎の規制免除レベルを算出した。 |
| (2) | 放射線審議会は、1998年6月に「ICRP1990年勧告の国内制度等への取り入れについて」を意見具申し、その中で、「潜在被ばく」、「線量拘束値」及び「除外と免除」については、今後の検討課題とした。 |
| (3) | 放射線審議会基本部会でこれらについて検討した結果、「潜在被ばく」、「線量拘束値」の検討に先立って、「除外と免除」を検討することとし、1999年4月の同部会で「除外と免除ワーキンググループ」を設置し、まず免除について、基本的にはBSSの方法を参考にしながら、日本独自のシナリオとパラメータを一部取り入れ、我が国の事情を考慮した免除レベルの試算を行い、その結果を2000年12月に「規制免除についての検討中間報告」としてとりまとめた。 |
| (4) | 同中間報告は、2001年1月の省庁再編後、2001年2月の放射線審議会に報告され、同審議会は、引き続き、「除外と免除」も含めた長期的課題を検討するため、新たに基本部会を設けた。 |
| (5) | 基本部会は2002年9月10日の第9回基本部会で最終報告書をとりまとめ、10月3日の総会で報告書が了承された。 |
2−2 放射線審議会での検討経緯
| 第 8回基本部会 |
7月11日 | 報告書案の決定 |
| 意見募集 |
7月30日〜8月28日 | 報告書案についてホームページ等で意見募集 |
| シンポジウム |
8月 5日 | 利用者等からの意見聴取 |
| 第 9回基本部会 |
9月10日 | 報告書の決定 |
| 第78回総会 |
10月3日 | 報告書の了承 |
放射線審議会における規制免除の検討経過
○ワーキンググループ会合
平成11年 6月〜平成12年12月まで10回開催
○規制免除レベル計算タスクグループ会合
平成11年 7月〜平成12年 3月まで7回開催
○新放射線審議会発足
平成13年 1月 6日
省庁再編に伴い旧放射線審議会が解散
新放射線審議会発足
○放射線審議会総会
平成13年 2月14日
| ・ |
「規制免除についての検討中間報告」が報告される。 |
| ・ |
放射線審議会基本部会を設置して、継続審議することとした。 |
平成14年10月3日
| ・ |
「規制免除について-国際基本安全基準における規制免除レベルの国内法令への取り入れ検討結果-」が報告され、了承。 |
○放射線審議会基本部会
| 平成13年 8月30日 |
第1回基本部会 |
| 平成13年10月25日 |
第2回基本部会 |
| 平成13年12月17日 |
第3回基本部会 |
| 平成14年 1月17日 |
第4回基本部会 |
| 平成14年 2月17日 |
第5回基本部会 |
| 平成14年 2月27日 |
第6回基本部会 |
| 平成14年 6月21日 |
第7回基本部会 |
| 平成14年 7月11日 |
第8回基本部会 |
| 平成14年 9月10日 |
第9回基本部会 |
3−1 目次
1.はじめに
2.我が国の法令における免除レベル
3.国際機関等で検討された免除レベル
4.国際基本安全基準免除レベル
5.我が国における免除レベルの検討
6.国内の使用実態と問題点
7.海外における免除レベルの検討及び取り入れ状況
8.国際基本安全基準免除レベルの国内法令への取り入れ
9.今後の課題
10.おわりに
以下、上記構成に沿って、報告書の概要を示す。
3−2 我が国の法令における免除レベル
我が国では、以下に示す法令、規則等において、放射性物質の濃度及び数量の範囲を定め、規制の対象を定義している。
「放射線障害防止法」
| | 放射線障害防止法において規制される放射性同位元素の濃度及び数量を表1に示す。原子力基本法に規定する核燃料物質及び核原料物質、薬事法に規定する医薬品及び医療用具、工業標準化法に規定する日本工業規格に該当する鉱工業品等のうち指定する自発光性の塗料については放射線障害防止法の適用を除外している。 |
| 「医療法」・「薬事法」、「労働安全衛生法」・「船員法」・「国家公務員法(人事院規則10-5)」、「原子炉等規制法」表1放射線障害防止法で規制される放射性同位元素の濃度及び数量 |
表1 放射線障害防止法で規制される放射性同位元素の濃度及び数量
| 区分 |
濃度 |
数量 |
| 密封されていない放射性同位元素 |
1種類 |
74 Bq/gを超えるもの(自然に賦存する放射性同位元素を含む固体は370 Bq/gを超えるもの) |
第1群3.7 kBq 第2群 37kBq 第3群370kBq 第4群 3.7MBqを超えるもの |
2種類
以 上 |
それぞれの群別区分ごとの割合の和が1を超えるもの |
| 密封された放射性同位元素 |
1個あたり3.7 MBqを超えるもの |
| 集合状態の密封された放射性同位元素 |
集合したものごとに 3.7 MBqを超えるもの |
3−3 国際機関等で検討された免除レベル
| ○ | 国際原子力機関(IAEA)
ICRP1990年勧告を踏まえ、ILO、WHO等の国際機関と共同して「電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準」(以下BSSという)を1996年に改訂し、規制免除に関する具体的な基準(以下免除レベルという)を提示した。個々の核種の濃度またはその数量のいずれかが免除レベルを下回る場合には規制から免除されること、規制当局の定める条件によっては条件付きの免除を認めてもよいこと等が示されている。 |
| ○ | 欧州委員会(CEC)
放射線規制の免除を確立するための概念と方法を示すことを目的に「欧州委員会文書(RP-65)」を発行。296核種の免除レベルを規定している。 |
| ○ | 英国放射線防護庁
1999年に報告書(以下「NRPB-R306」という)を発行。合計765核種分(787の免除レベル値)の免除レベルについて、放射能濃度と放射能が示されている。 |
3−4 国際基本安全基準免除レベル
IAEAは、免除のための個人リスクを十分に低くするための規準は、数10μSv/年のオーダーであるとし、さらに、防護の最適化については、集団線量預託が1人・Svを下回るようであれば達成できると判断。欧州委員会文書(RP-65)では、この免除の規準に基づき、表2に示す免除レベル算出のための線量規準(以下「線量規準」という)を設定。
表2 免除レベル算出のための線量規準(欧州委員会文書(RP-65)より)
| |
線量規準(mSv/年) |
| 実効線量 |
皮膚の等価線量 |
| 普通の状況(通常) |
0.01 |
50 |
| 最悪の状況(事故) |
1 |
50 |
国際基本安全基準免除レベルを算出するために対象とした行為、放射性核種等は以下のとおり。
| ○ | 対象となる行為
少量の放射性物質の産業利用及び教育、研究並びに病院などの施設での小規模な使用 |
| ○ | 検討対象とする放射性核種及び物理的形態
 | 放射性核種数
295核種を規定し、永続平衡になっている娘核種も考慮する。 |
 | 物理的形態
気体(蒸気)、液体(溶液)、飛散性固体(粉末)、非飛散性固体(薄膜・箔・密封線源・容器(カプセル)) |
|
| ○ | 評価対象者
作業者及び公衆 |
被ばく線量の評価は、最も高い線量を受けると予想される個人を考え、その個人を代表とする集団を想定し、被ばく線量計算に用いるパラメータ(以下「評価パラメータ」という)については集団の平均的な値を用いている。評価経路については、表3に示す。
表3 免除レベルの算出時に考慮された被ばく経路
| シナリオ |
放射能濃度に関する被ばく経路 |
放射能に関する被ばく経路 |
作
業
者 |
通常
使用 |
A1.1 線源取扱いによる外部被ばく
A1.2 1m3線源からの外部被ばく
A1.3 気体容器からの外部被ばく
A1.4 ダストの吸入摂取
A1.5 汚染した手からの経口摂取 |
B1.1 点線源からの外部被ばく
B1.2 線源取扱による外部被ばく |
| 事故 |
上記と同じ
ただし、被ばく時間や発生確率を考えると、通常使用時の方が被ばく線量が高くなるため、計算を行っていない。 |
〈飛散〉
B2.1 汚染した手からの外部被ばく
B2.2 汚染した顔からの外部被ばく
B2.3 汚染した床面からの外部被ばく
B2.4 汚染した手からの経口摂取
B2.5 再浮遊放射能の吸入摂取
B2.6 エアロゾル、ダスト雲からの外部被ばく |
〈火災〉
B2.7 皮膚の汚染
B2.8 ダスト、揮発物質の吸入摂取
B2.9 燃焼生成物からの外部被ばく |
公
衆 |
処分場 |
A3.1 処分場からの外部被ばく
A3.2 処分場からのダストの吸入摂取
A3.3 処分場での経口摂取 |
B3.1 処分場からの外部被ばく
B3.2 処分場からの吸入摂取
B3.3 処分場の物の取扱いによる皮膚の被ばく
B3.4 処分場での経口摂取 |
国際基本安全基準免除レベルは、以下の から から までの手順で算出されている。 までの手順で算出されている。
 |
1 Bq/gの放射能濃度または1Bqの放射能あたりの各被ばく経路における実効線量、皮膚等価線量を計算する。
|
 |
各被ばく経路の実効線量、皮膚等価線量をそれぞれ以下のグループ毎に合算する。
| ・ | 放射能濃度計算用:作業場所(通常使用)、公衆(処分場) |
| ・ | 放射能計算用:作業場所(通常使用)、作業場所(事故、飛散及び火災)、公衆(処分場) |
|
 |
個々のグループ毎の免除レベルを次式で計算する。
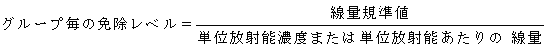
|
 |
上記で計算されたグループ毎の免除レベルのうち、最も厳しい値を採用する。
|
 |
免除レベルを3×10xから3×10x+1までの値を10x+1と端数を処理する。 |
3−5 我が国における免除レベルの検討
現行の我が国の定義数量は、米国、欧州などと違い、密封と非密封の放射性同位元素で規制の対象とする数量を区分しており、これまでの長い規制実績の中で十分機能してきた。
しかし、国際機関等で合意された免除レベルを各国が取り入れることは、放射性同位元素の貿易や輸送を円滑かつ安全に行う上でも、適切である。
したがって、国際基本安全基準に示された免除レベルを前提に、我が国の事情を考慮した免除レベルの試算を行い、我が国の国内法令への取り入れ方を検討した。
国際基本安全基準免除レベルとワーキンググループの免除レベル試算値とを比較し、評価した結果、我が国の法令に国際基本安全基準免除レベルを取り入れても、問題は無いと判断される。
3−6 国内の使用実態と問題点
定義数量以下の放射性同位元素を用いた機器
一般消費財として普及
・煙感知器(Am-241)
・グロースタータ(Pm-147, Kr-85)
・ネオンランプ(Pm-147, Ni-63) など
計測機器や分析機器
・種々の厚さ計(Sr-90, Tl-204) ・携帯型液化ガス液面レベル計(Co-60)
・γ線密度計(Co-60, Cs-137) ・RI水分・密度計(Co-60,
Cf-252) など
機器校正用線源
・測定効率決定用線源
・モニタリングポストの校正用線源
・液体シンチレーション測定装置の外部標準線源法用線源
・エリアモニタ、サーベイメータなどの機器の動作確認用線源
国際基本安全基準免除レベルを我が国の法令に導入した場合、従来と比較して厳しくなる場合と緩和される場合がある。主な核種について、表4に示す。この表によると、数量(放射能)については、非密封では緩和される核種が多いが、密封では厳しくなる核種が多い。
我が国における定義数量以下の密封された放射性同位元素の使用状況調査結果(表5)からも、現在、産業界等において利用されている機器は、国際基本安全基準免除レベルを超えているものが多い。したがって、我が国の法令に取り入れた場合、これまで自由に使用できた機器等が規制の対象となる可能性がある。
表4 国際基本安全基準免除レベルと現行法令の定義数量との比較
| |
厳しくなる核種 |
緩和される核種 |
| 濃度 |
Na-22 , Sc-46 , Mn-54 , Fe-59 , Co-60
Zn-65 , Cs-134 , Cs-137 , Ir-192 ,
Ra-226 , Am-241 , Cf-252
(その他107核種) |
H-3 , C-14 , P-32 , S-35 , Ca-45 ,
Cr-51 , Fe-55 , Ni-63 , Kr-85 ,
Sr-90 , Tc-99m , I-125 , I-131 ,
Tl-204 (その他165核種) |
放
射
能 |
密封 |
Na-22 , P-32 , Sc-46 , Mn-54 , Fe-55
Fe-59 , Co-60 , Kr-85 , Sr-90 , I-125
I-131 , Cs-134 , Cs-137 , Ra-226 ,
Am-241 , Cf-252 , Tl-204
(その他207核種) |
H-3 , C-14 , S-35 , Ca-45 , Cr-51,
Ni-63 , Tc-99 , Pm-147
(その他66核種) |
| 非密封 |
Cs-134 , Cs-137 , Ir-192 , Tl-204 ,
Ra-226 , Am-241 , Cf-252
(その他57核種) |
H-3 , C-14 , Na-22 , P-32 , S-35 ,
Ca-45 , Cr-51 , Mn-54 , Fe-55 ,
Fe-59 , Co-60 , Ni-63 , Zn-65 ,
Kr-85 , Tc-99m , I-125 , I-131 ,
Pm-147 (その他216核種) |
表5 規制対象となる可能性のある機器
| 機 器 |
使用放射性核種及び放射能 |
BSS免除
放射能 |
年間販売数* |
国内台数* |
| レーダ受信部(切替放電管) |
Am-241 |
74〜300 kBq |
10 kBq |
2,000 |
― |
| 集電式電位測定器 |
Am-241 |
326 kBq |
10 kBq |
19 |
81 |
|
エアロゾル中和器
|
Am-241 |
3.7 MBq |
10 kBq |
8 |
60 |
| 非接触厚さ計(透過型) |
Sr-90
Tl-204 |
3.5 MBq
3.5 MBq |
10 kBq
10 kBq |
―
― |
20
30 |
| 膜厚測定器(散乱型厚さ計) |
Sr-90
Tl-204 |
3.7 MBq
3.7 MBq |
10 kBq
10 kBq |
―
― |
―
― |
| 携帯型液化ガス液面レベル計 |
Co-60 |
3.7 MBq |
100 kBq |
125 |
2,855 |
| スケールチェッカー |
Co-60
Cs-137 |
3.7 MBq
3.7 MBq |
100 kBq
10 kBq |
4
― |
45
98 |
| 配管密度計 |
Co-60
Cs-137 |
3.7 MBq
3.7 MBq |
100 kBq
10 kBq |
―
― |
―
― |
| オンライン密度計 |
Co-60
Cs-137 |
3.7 MBq
3.7 MBq |
100 kBq
10 kBq |
20 |
600 |
| コア密度計 |
Co-60
Cs-137 |
3.7 MBq
3.7 MBq |
100 kBq
10 kBq |
2 |
4 |
| γ線密度計 |
Co-60
Cs-137 |
3.7 MBq
3.7 MBq |
100 kBq
10 kBq |
8
0 |
232
60 |
| バルブ開閉探知機 |
Cs-137 |
3.7 MBq |
10 kBq |
0 |
14 |
| RI水分密度計 |
Co-60 +
Cf-252 |
2.59 MBq
1.11 MBq |
100 kBq
10 kBq |
37 |
945 |
| 水分計 |
Cf-252 |
1.11 MBq |
10 kBq |
2 |
12 |
| 間隙測定器 |
Cf-252 |
1.11 MBq |
10 kBq |
0 |
1 |
| 産業用計測機器校正用線源 |
Co-60
Cs-137 |
3.7 MBq
3.7 MBq |
100 kBq
10 kBq |
25
12 |
―
― |
| 有毒ガス検出器 |
Am-241 |
3.7 MBq |
10 kBq |
― |
200 |
| 計測機器校正用線源 |
Co-60
Cs-137
他 |
3.7 MBq以下 |
100 kBq
10 kBq
― |
169
77
― |
―
―
― |
*:平成11年度現在の概数である。「−」印は販売数や国内台数が不明である。
3−7 海外における免除レベルの検討及び取り入れ状況
| ○ | 英国
電離放射線規則(IRR1999)において、国際基本安全基準免除レベル295核種及びNRPB-R306で算出された470核種について免除レベルを導入。一般消費財についての型式承認や条件付き免除も関係の規則により規定。 |
| ○ | ドイツ
2001年7月の放射線防護法令の改正により、英国と同様に国際基本安全基準免除レベル295核種及びNRPB-R306で算出された470核種について免除レベルを導入。密封線源については、IAEAで規定している条件付き免除の制度を、免除レベルの10倍までという制限などを追加して、型式承認の制度として採用。 |
| ○ | 米国
2002年3月現在、国際基本安全基準免除レベルの導入は行っていない。 |
| ○ | カナダ
2002年3月現在、国際基本安全基準免除レベルの導入は行っていない。 |
3−8 国際基本安全基準免除レベルの国内法令への取り入れ
放射線障害防止法における定義数量は、これまで安全確保に十分な役割を果たしてきた。一方、IAEA等は、ICRPが提唱する放射線防護の基本的考え方に基づき、科学的、社会的により進歩した考え方、数値を、免除レベルとして提案。欧州を中心として、その取り入れの検討が進められ、一部の国では既に国内法令に取り入れ済み。
これらの状況に鑑み、我が国としても基本的にはこれを取り入れることが適切である。
国内法令に免除レベルを取り入れるにあたっては、
| ・ | 各国の取り入れ状況や検討状況 |
| ・ | 引続き国際機関等で議論が深められている事項 |
| ・ | 過去40数年間にわたる現行の定義数量に基づく国内の規制対象及び規制対象外の放射性同位元素の使用実態 |
を考慮し、規制の仕組みも併せて十分考慮することが重要。
国内法令への取り入れに係わる主要事項は、以下のとおり
| ○ |
国際基本安全基準免除レベルに示されていない核種の取扱い
現在までにBSSと同じ方法で算出されている免除レベルは、NRPB-R306にある765核種である。放射線障害防止法の数量告示に記載されている核種で、NRPB-R306で規定されていないものが存在する(主に放射線発生装置で生成される半減期の短い核種)。
必要に応じ、γ・β線放出核種とα線放出核種というように、放出する放射線やその核種の半減期等により、グループ分けして免除レベルを設定することが考えられる。
|
| ○ |
密封線源の取扱い
国際基本安全基準免除レベルは、線源の密封・非密封による区別をしていない。我が国の法令に取り入れる場合、原則的には密封・非密封の区別を行わないものの、規制対象の線源については、密封・非密封のそれぞれの特性に対応した被ばく管理や処分が行われるように、従来から行われている密封・非密封を区別した規制方法の導入が望まれる。
現行法令において定義数量以下で用いられている密封線源については、新たに規制対象になるものも多いと考えられる。安全性を確保しつつ簡便性及び移動使用の特性を考慮した規制方法の検討が望まれる。
また、日本工業規格(JIS)(Z4821)を参考にして今後、密封線源の定義や密封性の担保に係る基準について検討する必要がある。
|
| ○ |
条件付き免除の仕組み
BSSでは以下の要件を満たす機器について、条件付き規制免除の規定を設けている。
 |
規制当局によって認可された型式であること。 |
 |
放射性物質が密封線源の形態であること。 |
 |
人が触れる装置表面から0.1mの距離における線量率が1μSv/時を超えないこと。 |
 |
処分に必要な条件を規制当局が定めていること。 |
この条件付き免除の取り入れについてドイツを例にとると、放射能が免除レベルの10倍までという条件を加え、条件付規制免除を行っている。これは、我が国の放射性同位元素装備機器で用いられている機構確認の概念とは異なっている。
新たに規制対象になる密封線源や放射性同位元素装備機器については、今までの機構確認制度とともに、この条件付き規制免除による規制の仕組みの検討が望まれる。
|
| ○ |
免除された複数の線源の規制
免除レベルの算出のシナリオでは、一個の線源による被ばく線量を評価しているが、実際には免除された線源を複数個取り扱うことが考えられる。複数個の線源を同じ場所で同時に取り扱う作業については、線源全体を集合体としてとらえて、免除の考え方が適用し得ることを確認すべき。現行の放射線障害防止法の定義数量における密封線源の集合体としての取扱(表1参照)との整合性も考慮して、複数個の免除された線源を取り扱う場合の規制方法について、検討することが必要。
|
| ○ |
教育、医療等の分野における規制
欧州委員会文書(RP-65)における免除レベル算出の際に、放射線の性質を説明するための教育上の使用、研究用実験室における生化学トレーサー、病院におけるラジオイムノアッセイなど少量の放射能を扱うものについては、規制を免除されるべきものとして示されている。このような利用は、安全が担保されることを前提に、放射性同位元素を利用する環境が整備されることを考慮されてもよい。また、それぞれの使用状況を考慮して、条件付き規制免除などを導入することも考えられる。
|
| ○ |
クリアランスレベルとの整合性
規制免除レベルと類似の概念としてクリアランスレベルの概念がある。これら2つの概念は放射線影響が無視できるほど小さいという線量規準を用いる点では共通しているが、
| ・ | クリアランスの対象物量(医療廃棄物から原子力施設解体廃棄物まで広範囲) |
| ・ |
クリアランスレベルと免除レベル算出のための評価経路や評価パラメータなどの差(同一核種に対する数値の不一致) |
という問題点がある。
IAEAではBSSにおいて、「規制当局は、クリアランスレベルについて、規制免除レベルより高くならないように決める」と規定。今後の我が国における放射性同位元素等使用施設についてのクリアランスレベルを検討する際に、以上に述べたクリアランスレベルと規制免除レベルとの整合性について考慮する必要がある。 |
3−9 今後の課題
放射線審議会基本部会での今後の検討課題として、以下を挙げている。
| ○ |
自然放射性物質の扱い
リン酸鉱石産業や鉱物砂加工業などの産業においては、自然と比べ高い放射能濃度のU-238、Th-232(自然起源の放射性物質(NaturallyOccurringRadioactiveMaterials(以下「NORM」という)))を含む鉱物資源が原料として使用されている。これらの産業において、生産規模が大きい場合、従業員、最も近隣の住民等の被ばくが高くなる可能性がある。
|
| ○ |
正当化されない行為についての規制
BSSでは、免除要件を満たすものは基本的には免除してよいが、正当化ができないと考えられる行為に対しては、免除を認めてはならないと規定。行為が正当化されるか否かは、基本的に社会的、経済的要因等を考慮して判断されるものと示されている。
|
| ○ |
放射線を発生する装置の規制
BSSでは、放射線発生装置に関する免除レベルとして、規制当局による認可を受けた型で、発生する放射線の最大エネルギーが5keVを超えないものと規定。
我が国においては、労働安全衛生法、医療法及び薬事法等で、定格管電圧が10kV以上のエックス線装置を規制対象としている。一方、放射線障害防止法では、装置表面から10cmにおける線量率が600nSv/時を超えないか、1MeVを超えないエネルギーを有する電子線及びエックス線を発生する装置を規制対象外としている。
BSSが規定する放射線を発生する装置における規制の免除要件の国内法令への取り入れについては、その妥当性や国内での利用実態を考慮して検討する必要がある。 |
ページの先頭へ
|
 |