2 現行の日本語教育能力検定試験の概要
外国人に日本語を教える日本語教員の専門性の確立と日本語教育の水準の向上に資するため,日本語教員となるために学習している者,日本語教員として教育に携わる者等を対象として,その知識及び能力が日本語教育の専門家として必要とされる水準に達しているかどうかを審査し,これを証明することを目的として財団法人日本国際教育協会が実施している。
(1)平成12年度実施実績
| 受験資格 | 学歴は問わない。但し,受験年度の4月1日における年齢が満20歳以上であること。 | ||
| 受験レベル | 試験の内容・水準は,日本語教員として最低限必要な専門的知識・能力を習得させることを目的とする大学の学部における日本語教員養成副専攻課程と同等程度とする。 | ||
| 試験期日 | 平成13年1月28日(日) | ||
| 試験会場 | 北海道地区 :北海学園大学豊平校舎 | ||
| 東京地区 :獨協大学,聖徳大学,明海大学浦安キャンパス | |||
| 近畿地区 :大阪大学豊中地区,神戸大学国際文化学部キャンパス | |||
| 九州地区 :九州大学六本松地区 | |||
| 試験結果 | 合否の結果は,3月下旬に通知するとともに,合格者には合格証書を交付する。 |
(2)日本語教育能力検定試験の受験者数等の推移
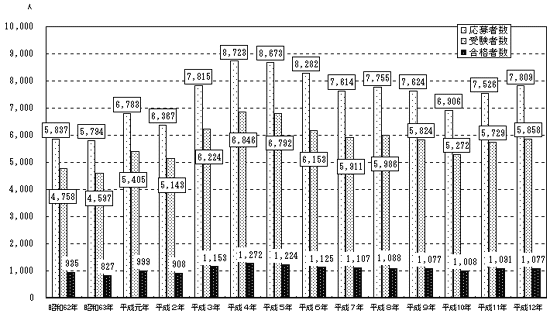
| 区 分 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 |
| 応募者数 | 5,837 | 5,794 | 6,783 | 6,367 | 7,815 | 8,723 | 8,673 | 8,282 | 7,614 | 7,755 | 7,624 | 6,906 | 7,526 | 7,809 |
| 受験者数 | 4,758 | 4,597 | 5,405 | 5,143 | 6,224 | 6,846 | 6,792 | 6,153 | 5,911 | 5,986 | 5,824 | 5,272 | 5,729 | 5,858 |
| 合格者数 | 935 | 827 | 999 | 908 | 1,153 | 1,272 | 1,224 | 1,125 | 1,107 | 1,088 | 1,077 | 1,008 | 1,091 | 1,077 |
| 合格率 | 19.65% | 17.99% | 18.48% | 17.66% | 18.53% | 18.58% | 18.02% | 18.28% | 18.73% | 18.18% | 18.49% | 19.12% | 19.04% | 18.39% |
(財)日本国際教育協会調査
(3)出 題 範 囲
次のとおりとする。ただし全範囲にわたって出題されるとは限らない。
| 領 域 | 主 要 項 目 | |
| 1-1 日本語の構造に関する体系的、具体的な知識 | ||
| 日本語学 | 概論 | 1.世界の中の日本語 |
| 2.日本語の特質 | ||
| 音声、語彙・意味、文法・文体、文字・表記、 | ||
| 言語生活等について | ||
| (1)対照言語学的に見た特質 | ||
| (2)社会言語学的に見た特質 | ||
| 音声 | 1.音声器官と発音 | |
| 名称と機能 | ||
| 調音法、調音点、調音者 | ||
| 2.単音レベル | ||
| 音素と異音 | ||
| 異音の分布 | ||
| 音素記号と音声記号 | ||
| 母音の分類 | ||
| 半母音 | ||
| 子音の分類 | ||
| 五十音図とその拡大表 | ||
| 3.音節レベル | ||
| 音節構造 | ||
| 音節(拍) | ||
| 特殊音節 | ||
| 4.単語レベル | ||
| 母音の無声化、その他環境による音声変化 | ||
| アクセントの感覚・規則・表記 | ||
| 縮約形など、話し言葉の語形 | ||
| 5.文レベル・談話レベル | ||
| イントネーション | ||
| プロミネンス(卓立) | ||
| ポーズ | ||
| 速さ | ||
| 語彙・意味 | 語彙 | 1.基本語彙と基礎語彙 |
| 2.語彙の類別 | ||
| 使用者別・場面別・語種別・言語活動別・ | ||
| 分野別・音声的特徴別・文法的機能別等 | ||
| 3.語構成 | ||
| 4.辞書 | ||
| 意味 | 1.語の意味 | |
| 2.句の意味 | ||
| 3.文の意味 | ||
| 4.文章・談話の意味 | ||
| 文法・文体 | 1.語・文節のレベル | |
| (1)品詞 | ||
| 名詞、動詞、形容詞、副詞、(助詞、助動詞、複合助辞、その他) | ||
| (2)活用などの変化形式とその用法 | ||
| 名詞、動詞、形容詞 | ||
| (3)文節の構成 | ||
| 2.文のレベル | ||
| (1)文の種類 | ||
| (2)文の成分 | ||
| (3)単文の構成 | ||
| (4)複文の構成 | ||
| (5)構文と意味 | ||
| 3.文章・談話のレベル | ||
| (1)旧情報、新情報等 | ||
| (2)話者の視点 | ||
| (3)話法 | ||
| (4)文章・談話における文の選択 | ||
| 4.言語生活と文体 | ||
| (1)敬体と常体 | ||
| (2)書き言葉、話し言葉 | ||
| (3)男性語、女性語 | ||
| (4)地域語と共通語 | ||
| (5)フォーマル、インフォーマル | ||
| 文字・表記 | 1.文字・記号の種類 | |
| 2.文字・記号の使い方 | ||
| (1)漢字仮名まじり文 | ||
| (2)仮名遣い | ||
| (3)送り仮名 | ||
| (4)外来語の表記 | ||
| (5)漢字の書き方 | ||
| (6)漢字の読み方 | ||
| (7)記号の使い方 | ||
| (8)辞書の使い方 | ||
| 3.文字表記の選択 | ||
| 4.文章の表記 | ||
| 1-2 その他日本語に関する知識 | ||
| 言語生活 | 1.コミュニケーション | |
| (1)パーソナル・コミュニケーションの場面、条件、様式、媒体等 | ||
| (2)マス・コミュニケーションの形態、媒体等 | ||
| 2.技能 | ||
| (1)聞く | ||
| (2)話す | ||
| (3)読む | ||
| (4)書く | ||
| 3.第二言語としての言語生活 | ||
| (1)母語による言語生活との比較 | ||
| (2)バイリンガリズム・マルチリンガリズム | ||
| 日本語史 | 1.古代語と近・現代語 | |
| 2.近・現代語の成立 | ||
| (1)近代語 | ||
| (2)現代語 | ||
| 2 日本事情(古典と文芸を含む。) | ||
| 1.日本の歴史・地理 | ||
| (1)日本の歴史 | ||
| (2)日本の地理 | ||
| 2.現代日本事情 | ||
| (1)現代日本の政治・社会 | ||
| (2)現代日本の文化 | ||
| 3 言語学的知識・能力 | ||
| 言語学概論 | 1.言語の本質 | |
| 2.言語能力と言語運用 | ||
| 3.言語の普遍性と個別性(類型論を含む。) | ||
| 4.言語学と関連領域 | ||
| 5.世界の言語 | ||
| 6.各論 | ||
| (1)文法論 | ||
| (2)意味論 | ||
| (3)音韻論 | ||
| (4)語彙論 | ||
| (5)文字・表記論 | ||
| 社会言語学 | 1.言語変種 | |
| (1)階層言語 | ||
| (2)地域言語 | ||
| (3)言語変化 | ||
| 2.場面と言語 | ||
| (1)敬語と非敬語 | ||
| (2)男性語、女性語 | ||
| (3)フォーマル、インフォーマル | ||
| 3.媒体 | ||
| (1)手紙、電話、書き言葉と話し言葉 | ||
| (2)マス・コミュニケーション、パーソナルコミュニケーション | ||
| 4.言語使用・言語生活 | ||
| 5.言語政策・言語教育 | ||
| 対照言語学 | 1.比較言語学・歴史言語学と対照言語学 | |
| 2.言語体系と運用の対照 | ||
| 音声、語彙・意味、文法・文体、文字・表記 | ||
| 言語生活等について | ||
| (1)類似点と相異点 | ||
| (2)母語の干渉、誤用分析 | ||
| 3.言語行動・言語生活の対照 | ||
| 日本語学史・日本語教育史 | 1.日本語学史 | |
| (1)明治以前の研究の概略 | ||
| (2)明治以後の研究の概略 | ||
| 2.日本語教育史 | ||
| (1)戦前の教育史の概略 | ||
| (2)戦後の教育史 | ||
| (3)日本語教育と国語教育 | ||
| 4 日本語の教授に関する知識・能力 | ||
| 教授法 | 1.日本語教育の目的・方法 | |
| 2.言語教育と言語研究の関心(心理言語学的観点を含む。) | ||
| 3.外国語教授法 | ||
| 4.日本語教育の基本語彙・基本漢字・基本文型 | ||
| 5.習得過程 | ||
| 6.指導手順・カリキュラム作成 | ||
| 7.練習指導技術 | ||
| 8.技能別指導法 | ||
| 9.対象別・母語別指導法 | ||
| 10.能力差・クラスサイズに対応する教授法 | ||
| 11.学習段階による指導法 | ||
| 12.添削技術 | ||
| 教育教材・教具論 | 1.教材教具概論 | |
| (1)目的 | ||
| (2)期間 | ||
| (3)場面 | ||
| (4)レディネス | ||
| (5)カリキュラム | ||
| 2.教材の具体的使用法 | ||
| (1)教材 | ||
| (2)教育条件 | ||
| (3)環境 | ||
| 3.教育機器・教具 | ||
| 評価法 | 1.評価の対象 | |
| 2.評価の目的と効果 | ||
| 3.テストの作り方 | ||
| 4.評価の方法 | ||
| 5.結果の分析 | ||
| 実習 | 1.コース・デザイン | |
| 2.教案作成と教材選定 | ||
| (1)教壇実習に備えての教案作成 | ||
| (2)具体的指導案の作成 | ||