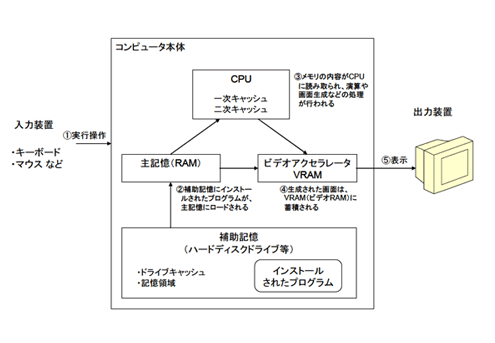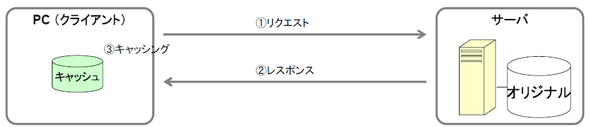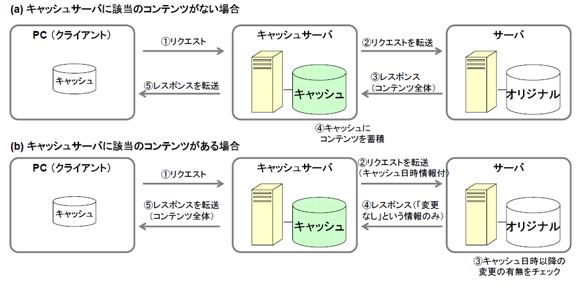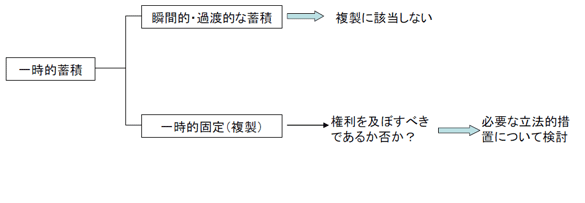|
第3節 デジタル対応ワーキングチーム 1 はじめに 本ワーキングチームの検討項目は, 2 機器利用時・通信過程における一時的固定について (1) 問題の所在 デジタル化,ネットワーク化の進展に伴い,コンピュータの機器内部における蓄積,ネットワーク上の中継サーバなどにおける蓄積など,機器の使用・利用に伴う,瞬間的かつ過渡的なものを含め,プログラムの著作物及びその他の著作物に関する電子データを一時的に固定する利用形態が広く用いられている。例えば,コンピュータにおいては,プログラムの実行にあたって,ハードディスクドライブ(HDD)等の補助記憶にインストールされたプログラムが,主記憶(RAM(注19))に蓄積される。CPU(注20)においては,RAMのメモリ内容を読み込んで,演算や画面生成などの処理が行われる。生成された画面はVRAM(注21)(ビデオRAM)に蓄積されモニタ画面に表示される。これらの蓄積は,基本的には,転送速度が遅い媒体から転送速度が速い媒体にデータを一時的に固定しておくことにより,処理の高速化を図るのが目的である。
デジタル視聴覚機器においても,機器内でデータを伝達する過程において,バッファ(Buffer)(注22),RAMへの一時的な固定を行い,処理速度の異なる装置間の調整や,音飛び防止やデータ放送用画面の表示等の特定機能を実行している。 インターネットの閲覧に当たっては,受信したWeb情報は,利用者のコンピュータ内にキャッシング(一時的に保存)され,再度同じWebサイトを閲覧する際には,サーバにアクセスせずに,コンピュータ内に保存されているデータを表示するように設定されている。また,ネットワークの経路においても,中継サーバ(キャッシュサーバ)において,中継したWeb情報を一時的に保存しておくことにより,他の利用者から同じWebサイトのアクセスがあった場合に,キャッシュサーバに保存されているWeb情報を提供することが行われている。これらの一時的な固定の目的は,特定のサーバに負荷が集中することを防ぎ,データ送信の効率化を図ることにある。
著作権審議会においては,これまでも著作権法上の複製権の対象となる「複製」の範囲について検討が行われており,例えば,昭和48年6月の同審議会第2小委員会(コンピューター関係)報告書では,「(コンピュータの)内部記憶装置における著作物の貯蔵は,瞬間的かつ過渡的で直ちに消え去るものであるため,著作物を内部記憶装置へたくわえる行為を著作物の『複製』に該当すると解することはできない。」としていた。 これらを受けて,一般的には,RAMへの蓄積(電源を切れば消去される蓄積)などのいわゆる「一時的蓄積」は,著作権法上の複製権の対象となる「複製」ではないと解されてきた。 「一時的蓄積」を複製権の対象とすべきかという点について,文化審議会著作権分科会は,平成13年12月の「審議経過の概要」において,「実際に支障,損害が生じていないのではないか」,「公衆送信権等既存の権利で対応できるのではないか」,「著作権法第113条に規定する『みなし侵害』の拡大により対応すべきではないか」等の意見もあったが,「RAMへの常時蓄積など,複製権の対象とすることが適当な場合もある」と指摘した。しかし,「法改正の必要性については,実際に法制面での対応が必要な具体的な状況の有無,関連するビジネスの動き,国際的な場における検討の状況等を引き続き注視しつつ,必要に応じ,検討する」こととした。 著作権法においては,「複製」は「有形的に再製すること」と定義(注23)されており,規定の文言上は,有形的な再製であるが「一時的」なものであれば複製には該当しないとはされていない。そのため,いわゆる「一時的蓄積」であっても,複製に該当すると解することができないではない。 しかしながら,いわゆる「一時的蓄積」を「複製」に当たるとする方向で解する場合には,機器内部や通信過程の技術的プロセスにおいて不可欠なものなどについては,機器の使用や円滑な通信に支障が生じるおそれもあることから,権利を及ぼすことが適当ではないため,立法的措置の必要性について検討すべきである。
(2)過去の国際的議論及び各国の法制度 平成8年12月のWIPO外交会議において採択された「WIPO著作権条約に関する合意声明」(注24)においては,「保護を受ける著作物をデジタル形式により電子的媒体に蓄積することは,ベルヌ条約第9条が意味する複製に当たると解するものとする。」としつつ,WIPO事務局より,瞬間的・技術的な蓄積についての議論の際に,「蓄積」については各国に異なる解釈の可能性がある旨指摘(注25)されている。 欧州においては,EU著作権ディレクティブ(注26)において,「一時的(temporary)」な複製を権利の対象としつつ,過渡的又は付随的(transient or incidental)で技術的プロセスの不可欠で主要な部分であり,媒介者による第三者間のネットワークにおける配信又は適法な使用を可能にするための,独自の経済的重要性を持たない一時的複製行為を複製権の例外としている。これを受け,イギリス(注27),ドイツ(注28),イタリア(注29)において同旨の立法が行われている。 米国においては,複製物とは著作物が固定された有体物であり,通過的期間を超える期間(a period of more than transitory duration)にわたって著作物を覚知し,再製し又はその他の方法で伝達することが可能な程度に永続的又は安定的に複製物に含められているときに,著作物は「固定」される(注30)としている。また,RAMへのプログラムの蓄積を複製とした判例(MAI判決(注31)等)があり,1995年9月の「知的財産権と全米情報基盤」ホワイトペーパー(注32)においても,この解釈を確認している。さらに,1998年の著作権法改正(注33)により,サービス・プロバイダが行う「素材の送信,転送,接続の提供又はその過程における素材の中間的かつ一時的な蓄積」,「システム・キャッシングにおける素材の中間的かつ一時的な蓄積」等の行為は,責任を問われないとしている。(注34)
(3)基本的な対応の方向性 現時点において,いわゆる「一時的蓄積」の様々な類型について,そのすべてを「複製」に当たると解すべきとする具体的な要請は見当たらないが,国際的な動向を考慮すれば,「複製」に当たると解する方向もあり得る。その場合に,どのような立法的措置が必要であるかを検討しておく必要がある。 これまでの我が国における議論を踏まえると,いわゆる「一時的蓄積」の中に「複製」に当たると解される場合があるとしても,たとえば,CDプレーヤーにおいて音楽CDを再生する場合等に機器内部で行われている瞬間的・過渡的な蓄積は,直ちに消え去るものであるため,著作権法における複製の定義(注35)に該当する行為ではないと考えられる。他方,このような瞬間的・過渡的ではないものについては,「複製」と解されることになるであろう。しかし,後者の瞬間的・過渡的な蓄積ではない一時的蓄積(一時的固定(複製))については,現に日常的に行われているような機器の通常の使用や円滑な通信に支障が生じる場合などは,権利を及ぼすべきではない場合が多いと考えられる。
なお,一時的固定(複製)の中には,現行の権利制限規定(注36)により,既に権利が制限されている行為もあると考えられるが,現行の権利制限規定が及ばない場合についても,通常の機器の利用や円滑な通信に支障が生じないよう,権利を及ぼすべきではない範囲が存在すると考えられる。 権利を及ぼすべきではない範囲に関して,立法により法文上明確化する方法としては,(a)著作権法上の「複製」の定義から除外する,(b)著作権法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を新たに設ける,という2つの方向性が考えられる。また,法文上明確にしない場合には,(c)「黙示の許諾」,「権利の濫用」等の解釈による司法判断に委ねる,という方向性も考えられる。このうち,(a)及び(b)の方向性を採る場合には,著作物の使用(視聴,受信,プログラムの実行等),又は利用(通信等)に伴い,「付随的」又は「不可避的」に生じる「一時的」固定(複製)であるものといった限定的な要件を付した上で,権利の対象から除外する必要がある。 なお,権利制限という方向性を採る場合の許容性について検証すると,権利者は一時的固定の前段階である媒体への固定やアップロード等の行為に対して権利を行使する機会があり,その時点で,その後の著作物の視聴等を予測することができるのであるから,限定的な要件を付した上で,一時的固定に関する権利制限を行ったとしても,販売機会を失うなど,権利者に現実的な経済的不利益を与えることは想定されず,権利制限の許容性を有していると考えられる。
(4)複製権を及ぼすべきではない範囲 一時的固定(複製)のうち権利を及ぼすことが適当ではないと考えられる行為として,次の
(3)において行った複製概念の整理と,上記の要件に従い,一時的な蓄積の代表的な事例について,「瞬間的・過渡的な蓄積であり,「複製」ではないもの」,「一時的固定(複製)のうち,上記 ア 瞬間的・過渡的な蓄積であり「複製」ではないもの
イ 一時的固定(複製)のうち,上記
ウ 一時的固定(複製)のうち,上記
しかし,技術の進展に伴い,様々な形態の一時的固定が出現しており,また今後も出現することが予想されるため,上記 また,通信過程におけるキャッシュなど,複製行為の主体が必ずしも明らかでない場合や,使用者の意思の有無によらず,あらかじめ一時的固定の機能が機器に組み込まれている場合など,複製主体が誰であるのかという議論もあわせて行うべきとの指摘もあった。 したがって,これらの課題については,今後の技術動向を見極める必要もあることから,現時点では緊急に立法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。しかし,法的予測可能性を高め,萎縮的効果を防止することにより,権利者や利用者が安心して著作物を流通・利用できる法制度を構築する観点から,今後も立法措置の必要性について慎重な検討を行い,平成19年を目途に結論を得るべきものとした。
3 デジタル機器の保守・修理時における一時的固定等について (1)問題の所在 近年,ハードディスクドライブ(HDD),フラッシュメモリ(注39)等の記憶装置・媒体内蔵型のデジタル機器が普及してきている。これに伴い,デジタルコンテンツの配信や視聴のサービスも多様化している。デジタルコンテンツは品質が劣化することなく複製が可能となることから,関係者間の契約や技術仕様により,デジタルコンテンツが外部に流出しないような設計がなされている。 また,携帯電話以外にも,パーソナルコンピュータ(PC),PDA(Personal Digital Assistance),デジタルテレビ,HDDレコーダーなどHDD,フラッシュメモリ等の記憶装置・媒体を内蔵するデジタル機器も普及しつつあり,これらの保守・修理についても同様の課題があると考えられる。
(2)本課題を巡る状況
携帯電話を対象とした配信事業において,デジタルコンテンツを提供する場合,関係者であるコンテンツホルダー,コンテンツプロバイダ(仲介者),キャリア(伝達者)等が契約内容や技術仕様等を決めて,ビジネスモデルを構築する。
また,近年,PCだけではなく,デジタル音楽再生機やデジタルカメラ等HDDプレーヤー又はフラッシュメモリ等の記憶装置・媒体内蔵型の機器が普及してきている。これらの機器の記憶装置・媒体が故障した際には,そのままではデータ自体を再生することができないため,まず,コンテンツなど記録されているデータを保護するためバックアップ機器に一時的に保存してから,修理し,修理後の機器にデータを復元することが必要となる。しかしながら,特にPCのHDDの故障の際に修理サービスを行う業者には中小規模事業者も多く,利用者の求めに応じて修理を行う際に,HDDに書き込まれているファイルの権利に関する情報を確かめて,個別に権利者の許諾を得ることは実際上困難である。 以上のような事情から,保守・修理等に携わる事業者や利用者からは,デジタル機器の保守・修理時における著作物の「一時的固定及び保守・修理後の機器への複製(以下「一時的固定等」という。)」について権利制限として認められるよう要望がなされている。
利用者にとっては,デジタル機器に不具合が生じた際に,著作権法上の規定による制約のため,保存されているデジタルコンテンツの継続的な使用ができなくなることは,納得し難いところである。このため,コンテンツ提供者や修理業者への不満も高まっており,平成17年3月には,携帯電話のケースを事例として,独立行政法人国民生活センターの報告書(注43)が取りまとめられている。同報告書では「携帯電話会社の給付した携帯電話端末に不具合があった以上,本来的には携帯電話会社がコンテンツを引き継げるよう諸種の手続き(コンテンツプロバイダからコンテンツの引継ぎに関する承諾を得るなど)を実施すべきである。」とし,携帯電話会社の努力義務を指摘している。更に,「本件のようなトラブルの際に,著作権法上コンテンツの引継ぎができず,結果として消費者が不利益を被る状況が生じている。(中略)消費者の不利益を解消するためにも,携帯電話端末の不具合による修理や交換の場合には,修理,交換に当たる事業者がその携帯電話端末に収納されているコンテンツの引継ぎ行為を行うことができるように著作権法を改正することが求められる。」として,著作権法の改正の必要性についても指摘している。
(3)立法的措置を講じる場合の検討
権利者は,購入されたコンテンツが利用者のデジタル機器において継続的に使用されることを,サービスの内容として認めて利用許諾を与えている。また,コンテンツビジネスにおいて著作権者等が最も懸念するのがデジタルコンテンツの無許諾な外部への流出である。機器の保守・修理時における一時的固定等は,その際のコンテンツの外部流出の防止が担保されれば,権利者に経済的な損失を全くあるいはほとんど与えないと考えられる。
デジタル機器の保守・修理時において,修理等を行う者によるコンテンツの一時的固定等を認める場合には,コンテンツが外部に流出しないための担保措置が不可欠である。そのため,デジタル機器の保守・修理を行う者は,保守・修理の作業が終了し,当該コンテンツを修理後の機器に複製した後は,バックアップしたコンテンツを消去することが求められる。そのため,本内容を著作権の「権利制限」として取り扱う場合には,デジタル機器の保守・修理の目的上「必要と認められる限度」の複製に限って認めることとし,保守・修理後に直ちにコンテンツの消去を行わない場合やバックアップ以外の用途で複製を行った場合は,権利制限の対象としないこととする必要があろう。
デジタル機器の保守・修理時における一時的固定等について,「権利制限」として認める場合に,対象となるデジタル機器の範囲としては,携帯電話,PC,デジタル音楽再生機,デジタルカメラなどが考えられるが,記憶装置・媒体を内蔵する機器としては今後も様々な新しい機器が開発されることが予想される。そのため,「権利制限」の対象となる機器は,「記憶装置,媒体内蔵型の機器」とし,法令等により具体的な機器の詳細を特定することは適当ではないと考えられる。
記憶装置・媒体内蔵型機器は,コンピュータプログラムをはじめ,音楽,映画など様々な著作物を記録することが可能であり,著作物の種別により本措置の対象とすべきか否かという取扱いを違える理由はないであろう。したがって,あらゆる種類の著作物を本措置の対象とすべきである。
デジタル機器が故障した際に,製造業者によるユーザーサポートが既に終了している場合など,利用者にとっては,やむを得ず修理ではなく買い替えを行うことは少なくないと考えられる。また,修理を行うよりも買い替えを行った方が安価である場合には,利用者は買い替えを望むであろう。しかしながら,このように機器を更新する場合についても著作権を制限するとすれば,様々な記憶装置・媒体に劣化しないコピーが半永久的に転々と保存され続けることを許容することになり,権利者にとっては将来のコンテンツの販売の機会を失うことになる。これは,保守・修理時に限定した場合と比べて,権利者の経済的な影響が非常に大きいと考えられる。このため,基本的には買い替えのように機器の更新を行う場合は本措置の対象外とすべきである。
現行制度では,著作権法第120条の2第2号において,「業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行った者」について罰則が設けられている。
(4)条約上の要請,諸外国の法制度の整理
デジタル機器の保守・修理時の一時的固定等が「権利制限」として認められるためには,著作権等関連条約のいわゆる「スリーステップテスト」(注45)の要件を充たす必要がある。すなわち「著作物の通常の利用を妨げず,著作者の正当な利益を不当に害しない特別な場合」に限り「権利の制限」が認められる。 本件の場合は,機器の保守・修理という「特別な場合」であり,配信等によるコンテンツの「通常の利用(流通)」を妨げるものでもない。また,一時的に固定した著作物は保守・修理後に消去することが法的に担保されるのであれば,「著作者の正当な利益を不当に害しない」と考えられる。したがって,「スリーステップテスト」の要件は充たされると解される。
諸外国のうち,米国とドイツにおいて,機器の保守・修理時における著作物の一時的固定等が「権利制限」として認められている。
(5)基本的な対応の方向性 以上の検討により,デジタル機器の保守・修理時の一時的固定等については,個別に許諾を得ることや事前に包括的な契約を行うこと等により解決しようとしても,権利者が膨大になるなどの理由から係者の自主的な取組では対応が困難な場合が想定され,修理業者の事業活動を萎縮させることによる国民生活への影響が大きい。一方,権利者の懸念である「デジタルコンテンツの外部への流出」については,保守・修理時(「無償」で機器を交換する場合を含む。)に限定し,作業後のコンテンツの消却を義務付けること等により,その防止を担保することが可能であり,権利者の利益が不当に害されることはないと考えられる。 したがって,デジタル機器の保守・修理の過程において,当該機器に著作物が保存されており,保守・修理により消失のおそれがある場合には,一定の条件の下,著作物を一時的に固定し,保守・修理後の機器に復元することが可能となる要件を法文上明確化すべきである。 具体的な要件を整理すると,次のようになる。
|
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology