|
資料2−1 補償金制度の論点についてのJEITAの見解平成20年7月10日 1.著作権保護技術と私的複製の関係について 当協会は、著作権保護技術が施されている場合には、当該著作物について、その保護技術が機能する範囲においては私的複製をオーバーライドし(例えば画像を写真に撮影したり、再生した音楽をマイクで拾い録音するような場合は別論)、いわば契約により法的に複製を許諾・制限しているのに等しい状況であり、当然ながら補償は不要との意見です。このことは、平成19年11月16日に公表した「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」にも詳細を述べています。関連の部分を引用すれば、以下の通りです。 著作権保護技術について、「ユーザーの複製行為が私的録音録画の範囲を超えないよう、ふたをかぶせるだけ」という意見があります。この考え方によると、私的複製として適法となる範囲は、採用される著作権保護技術が許容する複製の数によって、コピーワンスなら1個まで、ダビング10なら10個までと伸縮することになりますが、このような考え方が、法30条の解釈として相応しいものであるのか、小委員会等での学識者の意見を待ちたいと考えます。 <契約と私的複製の関係> 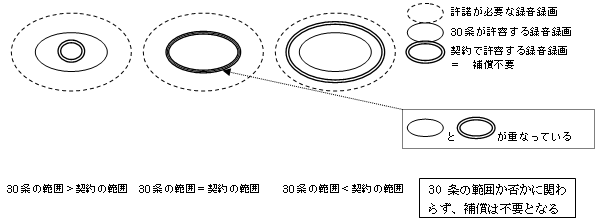
<著作権保護技術が私的複製の範囲を画定するとの考え方> 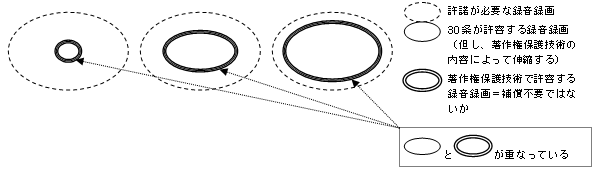
なお、当協会平成20年5月30日付見解にある「私的複製が際限なく行われること」は、著作権法30条の「私的複製」であっても、何ら技術的に抑制されない状況で行われる複製を指した表現であり、あくまで「私的複製」となる範疇で行われる複製行為について述べています。例えば、アナログ放送を受信して録画する場合には、現状では何らの技術的制約がないことから、可能性の点で、「際限なく」複製を取ることができます。すなわち、複製数を「際限なく」と表現したところで、「私的複製」である限り適法なのであって、『「私的複製が際限なく行われること」は同条の予定している範囲を超える』ことにはならないと考えます。 2.文化庁提案において縮小の道筋が明らかでないとする理由について(1)著作権保護技術と補償の関係についての整理が不分明であること文化庁提案においては、次のように表現されています。
すなわち、技術仕様策定の場において、複製数等について権利者が立場を明確にしない場合や、表明した複製数と異なる結論となった場合には、権利者の要請があったとは考えられないとの一般則が導かれることになります。今後も、設定された技術仕様策定の場において、ダビング10と同様の経緯を辿れば、権利者の要請はなく、従って、補償の必要性があるということとなるのであって、この点において、縮小するとしていることに疑義が生じます。この疑義は、平成20年7月10日配付の文化庁作成Q&Aによっても、払拭されていません。 (2)対象となる機器に関して、縮小が確実なものとはなっていないこと 携帯機器や、家庭内で用いられる機器に見るように、録音録画に供される機器は専用機器から汎用機器へと多様化してきています。将来、録音録画専用機器が存在しない状況となるとは考えませんが、明らかに機器は汎用化していくものと考えられます。
録音録画のための機器が「移行」するのであって当然に対象とすべきであると主張する意見がありますが、当協会は、これらの例については、制度の「拡大」であると考えております。これまでPC等の汎用機器を補償金対象とすべきとの主張が繰り返されてこられたことに鑑みると、「現状では」との表現を根拠に、今後、同様の主張が繰り返されることは容易に想像されます。 3.HDD内蔵レコーダー、携帯オーディオレコーダーを対象とすべきでないことについて これらの機器は、タイムシフト、プレイスシフト、あるいは契約によって提供される著作物の録音録画に用いられる機器であることから、これらを補償金の対象とする合理性はないと考えます。 また、一体型機器を対象とすることに対して第5回小委(平成19年6月5日)において当協会委員から反対を表明しているほか、今次の小委「中間整理」にて、「対象にすべきであるとする意見が大勢であった」と記述されたことに関して、第11回小委(平成19年9月5日)における反対の表明、また、平成19年11月16日意見書でも表明しているように、当協会はHDD内蔵レコーダー(HDD録画機能付テレビを含む)、携帯オーディオレコーダー等の一体型機器を対象とすることについて、一貫して疑義を唱えてきており、その点は現時点でも異なるところではありません。 なお、一体型機器の取り扱いについての「中間整理」の記述に関して、文化庁事務局は「なお、制度のあり方の問題については、先ほど亀井委員も御指摘されましたように、そう深くは議論しておりませんので、このまとめもそういう細かい点に踏み込んで問題点を整理し、かつ了承を得られたところは了承を得られた、異論があるところは異論があったという細かい議論をしておりませんので、一般論として書いているわけでございまして、確かに部分的に見れば、こういうケースはどうなるのか、ああいうケースはどうなるのかという御疑問はあると思いますけれども、現実にそこまで議論に至っていませんので、今までの議論を踏まえて整理をさせて頂いた次第でございます。」との発言をされています。「中間整理」の公表とパブリックコメントの募集以降、小委において、一体型機器の取り扱いについて、深く議論をしたという記録はありません。 4.地上デジタル放送におけるクリエーターへの適正な対価の還元について総務省情報通信審議会第四次中間答申の「基本的な考え方」の項において、その時点での「様々な場」での「コンテンツの流通の促進等に係る具体例が検討されている例」として、補償金制度も記載されているに過ぎず、補償金に限定されるとの記載は一切ありません。従来よりJEITAは以下のような疑問を持っていたところです。
今般の第五次中間答申(6月27日)において、「適正な対価の還元」等にかかる関係者の認識に相違が見られるとしつつも、補償金以外の側面から情報通信審議会において検討することとされています。JEITAとしても、上記疑問などを含め、同審議会での検討が深まっていくことを期待しています。 第五次中間答申「デジタル・コンテンツの流通の促進」(概要版)抜粋(4)以上のとおり、「適正な対価の還元」等に係る関係者の認識に相違が見られ、合成形成が困難であることが確認された後、権利者の合意として、権利者の立場から、以下の(a)(b)が提案され、ダビング10の開始期日を早期に確定することについて、委員会にて合意形成がなされたことが確認された。 (2)上記の合意の形成過程で言及された「補償金制度」は、文化審議会で検討中の事項。当審議会としてもその検討における早期の合意形成を期待するものであるが、そのあり方自体が当審議会の検討対象ではない点については、今回の審議過程でも異論はみられないところ。 5.音楽CDをソースとする場合の補償金の必要性について 音楽CDについては、著作権保護技術との関係について考察する限りでは「補償の要否」を検討する余地があると考えています。しかしながら、第4回小委(平成19年5月31日)における当協会委員の発言の通り、補償の要否を決するためには、録音によって権利者に重大な経済的不利益が生じているかどうかを吟味する必要があります。自ら購入した音楽CDをプレイスシフトすることによって再生したり、音楽配信サービスからダウンロードした音楽を再生したりすることを主目的として録音される場合には、重大な経済的不利益が生ずるとは考えられないことから、補償の必要性はないと考えています。 6.今後の検討に関して 北米のコンテンツ産業の隆盛を目の当たりにして、それが補償金制度によってではなく、資本主義社会のルールである、契約によってもたらされていることに思いを致す必要があります。例えば、北米のコンテンツホルダーを中心としたビジネスモデルにおいては、コンテンツホルダーの要望を受け、メーカーがコンテンツ保護技術を開発・提案・導入し、コンテンツホルダーに対価が還元されるビジネスモデルが構築されてきたという事実があります。 以上 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
