| 1. |
対象機器・記録媒体の範囲及び決定方法について
 |
著作権法上の定義(第30条第2項)
| ・ |
機器
デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であって政令で定めるもの
|
| ・ |
記録媒体
当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であって政令で定めるもの |
| (注) |
著作権法施行令では、対象機器・記録媒体について、録音録画機能の技術的仕様によって特定するとともに、「主として録音(録画)の用に供するもの」という要件を置いている。これは、平成10年のCD−R及びCD−RW関係機器、記録媒体の追加指定のための政令改正時に新たに挿入されたものである。
この理由であるが、補償金制度導入当初(平成5年)時点では、パソコン等による録音は技術的には可能であったが記録媒体の容量を考えると現実的には困難であったことなどから、「録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く」という規定さえしておけば、残りは専用機器になることが明白であったためである。
しかし、その後の技術発展により、録音等に使用できるパソコン等が普及してきたため、パソコンの録音録画機能は附属機器ではないので対象機器になるという疑義を払拭するための確認規定として、「主として録音(録画)の用に供するもの」という要件がおかれた。
| 例: |
著作権法施行令第1条第1項
(特定機器)
第一条 著作権法(略)第三十条第二項(略)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(略)であつて主として録音の用に供するもの(略)とする。 |
|
|
 |
具体的機器・記録媒体
| 録音 |
機器 |
DAT(デジタル・オーディオ・テープ)レコーダー |
| DCC(デジタル・コンパクト・カセット)レコーダー |
| MD(ミニ・ディスク)レコーダー |
| CD−R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)方式CDレコーダー |
| CD−RW(コンパクト・ディスク・リライタブル)方式CDレコーダー |
| 記録媒体 |
上記の機器に用いられるテープ,ディスク |
| 録画 |
機器 |
DVCR(デジタル・ビデオ・カセット・レコーダー) |
| D−VHS(データ・ビデオ・ホーム・システム) |
| MVDISC(マルチメディア・ビデオ・ディスク)レコーダー |
| DVD−RW(デジタル・バーサタイル・ディスク・リライダブル)方式DVDレコーダー |
| DVD−RAM(デジタル・バーサタイル・ディスク・ランダム・アクセス・メモリー)方式DVDレコーダー |
| 記録媒体 |
上記の機器に用いられるテープ,ディスク |
|
|
| 2. |
補償金の支払い義務者
| (1) |
支払い義務者(第30条第2項)
利用者
| |
→ |
本来は利用者が私的録音録画に際して直接権利者へ支払い |
|
| (2) |
支払いの特例(第104条の4)
| ・ |
政令指定された機器又は記録媒体の購入者は、ほとんどの場合私的録音録画に当該機器等を使用することを前提に、利用者が当該機器等を購入した時点で、指定管理団体から請求があれば一括前払いする制度。 |
| ・ |
製造業者又は輸入業者は支払いの請求及びその受領に関し協力義務を負う。 |
|
| (3) |
返還制度(第104条の4第2項)
購入した機器又は記録媒体を専ら私的録音録画以外の用途に供することの立証義務は購入者自身
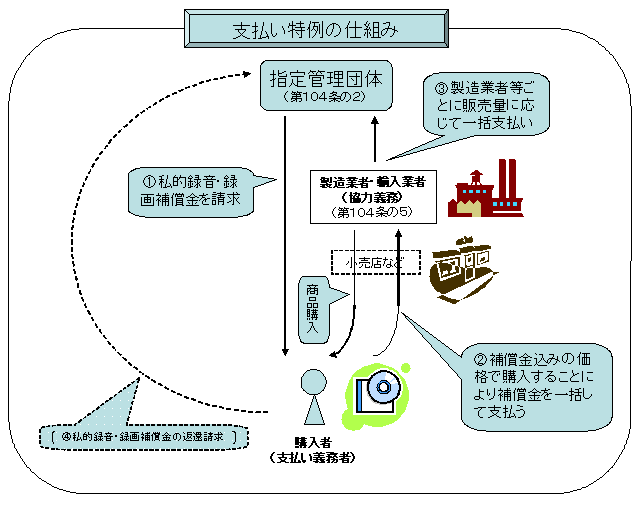 |
|
| 3. |
補償金の額の決定方法
| (1) |
補償金の額の決定方法の仕組み(第104条の6)
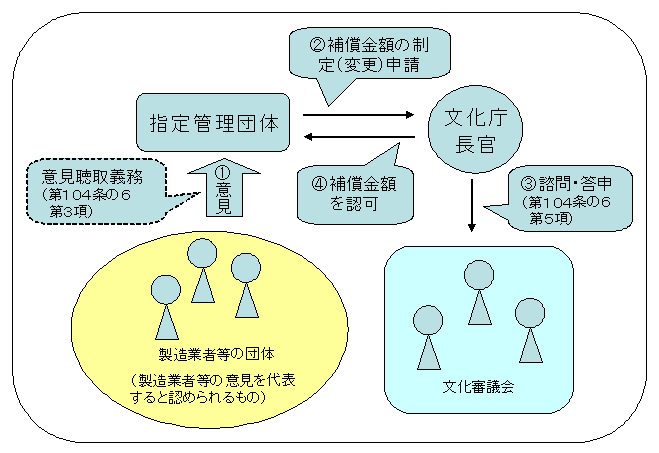
|
| (2) |
私的録音録画補償金の額
| |
特定機器 |
特定記録媒体 |
| 録音 |
基準価格(注1)の2パーセント |
基準価格(注1)の3パーセント |
| 上限: |
シングルデッキ 1,000円 |
| ダブルデッキ 1,500円 |
|
| 録画 |
基準価格(注1)の1パーセント |
基準価格(注1)の1パーセント |
| 上限:1,000円 |
| (注1) |
「基準価格」について
| ・ |
「特定機器」:最初に流通に供した価格またはカタログに表示された標準価格の一定割合(65パーセント) |
| ・ |
「特定記録媒体」:最初に流通に供した価格またはカタログに表示された標準価格の一定割合(50パーセント) |
|
|
| (3) |
私的録音録画補償金総額の推移(注2)
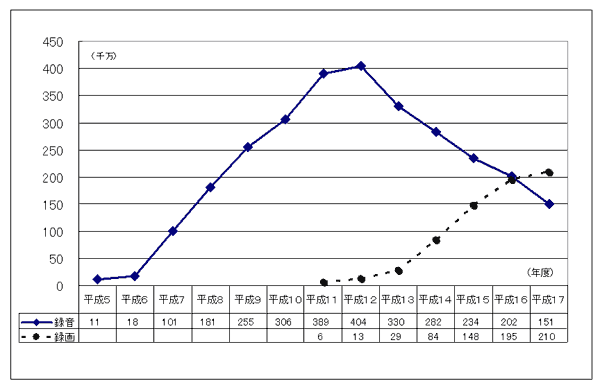
| (注2) |
金額は消費税込み。年度表示は出荷時であり、補償金収入としては翌年度の表示となる。録音の平成5年は6月〜翌3月、録画の平成11年は7月〜翌3月それ以外は4月〜翌3月。出所は、録音、録画、それぞれ私的録音補償金管理協会、私的録画補償金管理協会。 |
|
|
| 4. |
指定管理団体制度
| (1) |
文化庁長官による団体の指定(第104条の2、第104条の3)
文化庁長官は、権利者に代わって私的録音録画補償金、私的録音録画補償金を受ける権利を行使することを目的とする団体をそれぞれ1個に限り指定する。
【指定の要件】
| 1. |
民法第三十四条の規定により設立された公益法人であること |
| 2. |
権利者団体、実演家団体、レコード会社団体等であって利益を代表すると認められるものを構成員とすること。 |
| 3. |
2.の各団体がそれぞれ次の要件を備えるものであること。
| ・ |
営利を目的としないこと。 |
| ・ |
構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 |
| ・ |
構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 |
|
| 4. |
権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務を的確に遂行できる能力を有すること。 |
|
|
| (2) |
指定管理団体による補償金を受ける権利の行使(第104条の2)
| ・ |
指定管理団体がある場合、権利者は区分に応じて指定管理団体のみを通じて補償金を受ける権利を行使することができる。 |
| ・ |
指定管理団体は、権利者のために補償金を受ける権利に関して裁判上・裁判外の行為を行う権限を有する。 |
(実際に設立されている指定管理団体)
| 録音: |
社団法人私的録音補償金管理協会(sarah)
平成5年3月設立、文化庁長官指定 |
| 録画: |
社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)
平成11年3月設立、文化庁長官指定 |
|
|
| 5. |
共通目的事業
| (1) |
共通目的事業の概要(第104条の8)
指定管理団体が受け取った補償金は、原則として著作権者等に分配されるが、私的録音録画の実態は正確に把握できないところから、補償金の20パーセントに相当する額については、著作権者等全体の利益を図るために支出することとされている。
|
| (2) |
事業の内容等(対象事業の範囲は法律に明記)
 |
著作権及び著作隣接権の保護に関する事業
| ・ |
新聞・雑誌等への広告掲載 |
| ・ |
著作権教育用の小冊子・パンフレット等の作成・配付 |
| ・ |
広報誌の作成・配付 |
| ・ |
イベントへのブース出展 |
| ・ |
著作権普及啓発活動(教材開発、セミナー・シンポジウムの開催等)への助成 |
| ・ |
国際協力事業(国際セミナー、研修プログラム)への助成 |
| ・ |
著作権等に関する調査・研究事業(私的録音等実態調査、海外における侵害実態調査 等)の実施 等 |
|
 |
著作物の創作の振興及び普及に資する事業
| ・ |
コンサート、講演会等への助成 |
| ・ |
新人芸術家の育成活動(作品の公募・発表等)への助成 |
| ・ |
海外への日本音楽に関する情報の提供活動への助成 |
| ・ |
国際文化交流事業への助成 等 |
|
|
| (3) |
共通目的事業への支出額(第104条の8)
| 法律: |
私的録音録画補償金の額の2割以内 |
| 政令: |
2割 |
(参考:共通目的事業に宛てられる金額の推移)(注3)
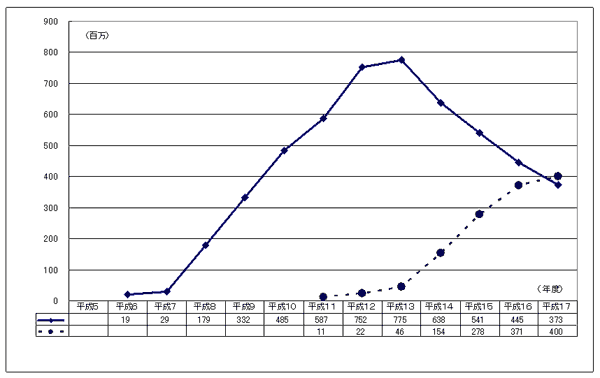
| (注3) |
金額は消費税込み。年度表示は出荷時であり共通目的基金としては翌年度の取扱となる。額については単位を百万。出所は、録音、録画、それぞれ私的録音補償金管理協会、私的録画補償金管理協会 |
|
|
| (私的使用のための複製) |
| 第三十条 |
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
| 一 |
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 |
| 二 |
技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 |
|
| 2 |
私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
|
| (私的録音録画補償金を受ける権利の行使) |
| 第百四条の二 |
第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の補償金(以下この章において「私的録音録画補償金」という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(以下この章において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章において「指定管理団体」という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することができる。
| 一 |
私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。以下この章において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金 |
| 二 |
私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。以下この章において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金 |
|
| 2 |
前項の規定による指定がされた場合には、指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
|
| (指定の基準) |
| 第百四条の三 |
文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
| 一 |
民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であること。 |
| 二 |
前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。
| イ |
私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの |
| ロ |
私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの |
| ハ |
国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。) |
| ニ |
国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。) |
|
| 三 |
前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
| イ |
営利を目的としないこと。 |
| ロ |
その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 |
| ハ |
その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 |
|
| 四 |
権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の八第一項の事業に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 |
|
| (私的録音録画補償金の支払の特例) |
| 第百四条の四 |
第三十条第二項の政令で定める機器(以下この章において「特定機器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。 |
| 2 |
前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、指定管理団体に対し、その支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。 |
| 3 |
第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第二項の規定にかかわらず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うことを要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。
|
| (製造業者等の協力義務) |
| 第百四条の五 |
前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。
|
| (私的録音録画補償金の額) |
| 第百四条の六 |
第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 2 |
前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。 |
| 3 |
指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 |
| 4 |
文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一項の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。 |
| 5 |
文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
|
| (補償金関係業務の執行に関する規程) |
| 第百四条の七 |
指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
| 2 |
前項の規程には、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。
|
| (著作権等の保護に関する事業等のための支出) |
| 第百四条の八 |
指定管理団体は、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。 |
| 2 |
文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。 |
| 3 |
文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
|
| (報告の徴収等) |
| 第百四条の九 |
文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
|
| (政令への委任) |
| 第百四条の十 |
この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。 |